
1972年6月、赤塚不二夫は『天才バカボン』『レッツラゴン』を対象作品とし、第十八回文藝春秋漫画賞を受賞。受賞記念として、「文藝春秋」にて、井上ひさしの戯曲をコミカライズした『ひさし笑劇場』(72年〜73年)の作画を受け持つことになる。
本来ならば、連載第1回目となるべきところを第1回目公演と銘打ち、劇場プログラムを意識した展開で始まるこの『ひさし笑劇場』は、文字と漫画のドッキングという新たな笑いの試みに成功。その後、赤塚は、詩人の谷川俊太郎とのコラボ『劇画詩集 自分タチ』(「月刊ポエム」76年11月号)などを発表するが、本作『大事件ON マガジン❜74』もまた、そうした系譜に連なる特別読み切りであり、『ひさし笑劇場』同様、扉ページには「(決定稿)昭和四十九年一月一日全国縦断公演 企画=一件落着の会 演出=山田一郎」と怪しげにクレジットされている。
何処ぞの旅劇団のパンフレットを模した扉から始まる本作は、1973年に耳目を集めた重大トピックを含め、八本を集めて戯画化。1ページ一コマというシンプルな構成ながらも、取り上げたこれらの話材が、今年(74年)は、どのような展開を迎えるか、予測シミュレーションした内容となっている。
では、具体的に一作、一作、1973〜74年の重大ニュースを振り返りながら、その時代背景に準じたこれらのギャグの数々を検証してみよう。
まずは、扉ページであるが、大地震に晒される市街地を風呂敷包みを担いで逃げ惑うバカボンのパパが、「今年 起こってほしい大事件をとりそろえてみましたのだ!!」の一言よりビギニング。これは、1973年6月17日に発生したマグニチュード7・4の直下型、根室半島沖地震をイメージしたカリカチュアだろう。
根室半島沖地震よる被害は、各地の太平洋沿岸にて、巨大津波が発生したほか、浸水が約三〇〇棟、負傷者二六名にも上る惨事となったものの、幸いにも一人の死者を出すことはなかった。
それ故、根室半島沖地震をテーマとしたギャグを扉ページとして扱ったのかも知れない。
「紙様は神様です!!」
ポールにピーンと張ったロープを跨ぎ、行ったり来たりのゴンのおやじとベラマッチャ。よく見ると、二人はトイレで用を足した後、ロープでお尻を拭いているではないか!!
1973年、第四次中東戦争勃発を機に原油供給の逼迫、供給量の削減等、所謂オイルショックが齎した折からの紙不足は、トイレットペーパーの買いだめ騒動が全国規模で発生するなど、我が国の物流面においても、深刻な大打撃を与えた。
消費者によるトイレットペーパーの買い占めがピークに達した11月、日本政府は「トイレットペーパーを含む紙類四品目を生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律に基づく特定物資」に指定する。
そして、翌74年1月には、トイレットペーパーも国民生活安定緊急措置法の指定品目に加わり、3月末には、買い占め騒動も沈静化。在庫量も通常レベルへとリターンした。
しかし、本作が発表された73年12月の段階においては、紙の供給不足の回復に対し、全くもって見通しが立っておらず、このようなえげつないジョークすらも、アクチュアルなパロディーとしてなり得ているのだろう。
「横井庄一 はずかしながら新商売を始めたわネ」
元陸軍軍曹で残留日本兵であった横井庄一が、グアム島のジャングルで発見され、日本に帰還したのが1972年2月、終戦から二七年経ってからのことだった。
横井の朴訥とした人柄は、世の人気を集め、耐乏生活評論家なる肩書きで全国各地で講演を開いたり、様々なイベントやテレビ出演等で引っ張りだこになるなど、横井にとって1973年は、マスコミ文化人として盤石を築いた頃った。
この一年前、横井は郷里の名古屋で家業である洋品店を引き継ぎ、「テーラー横庄」をオープン。さて、次なる横井の動向が気になる中、赤塚が予測した横井の1974年は、身の上相談ならぬ、若い女性に特化した身の穴相談。
二八年間、洞穴で生活していた経験を元に穴、女性の穴への悩みを中心にセックスカウンセリングするというもので、横井庄一役をレレレのおじさんが務めている。
いやはやなんとも、赤塚らしい下ネタ全開のギャグだ(笑)。
尚、1974年の横井庄一の動向は、グアムでのサバイバル生活を綴った著書「明日への道」を上梓し、ベストセラーとなるが、第10回参議院議員通常選挙に無所属で出馬し落選。
また、この年は、フィリピンのルパング島で、同じく残留兵の小野田寛郎少尉が戦後二九年を経て帰国し、世間の関心も横井から小野田に移り、横井人気も次第に収束していった。
「モナリザ 日本のお客に苦笑」
イタリアが生んだ天才美術家、レオナルド・ダ・ヴィンチが、1500年代初期に描いたとされる女性の肖像画「モナ・リザ」が、上野の東京国立美術館に貸し出し展示されたのが、1974年4月。場末のストリップ小屋を思わせるスポットにて、モナリザの絵を吊るしたバカボンのパパが「はいーっ!! お客さんは動かないで!! モナリザの方からお伺いしますのだ!!」と客席に訴えるものの、客は「「モナリザ」って絵だったのか フランスから来たパンダだと思ったのに」とガッカリするという落ちが付く。
当時マスコミでは、日本中が「モナ・リザ」フィーバーに湧くのではないかと予想していたが、レオナルド・ダ・ヴィンチの出自が、イタリアだかフランスだかも知らず、ただ物珍しさに野次馬的興味を引かれる庶民という見立ては、この二年前、日中国交正常化の際、友好のシンボルとして、カンカンとランランの初来日に端を発するパンダブームとその本質は変わらないといった赤塚ならではの諧謔がこの一コマに込められている。
「世紀の一戦 実現成るか!?」
1960年代から70年代に珍妙奇天烈なイベント企画を立て上げ、日本中を熱狂とパニックの渦へと落とし込んだ虚業家、国際暗黒プロデューサーの康芳夫。73年には、芥川賞作家、参議院議員であり、後に東京都知事となる石原慎太郎と組み、ネス湖に生息するとされる未確認動物「ネッシー」を捕獲し、エリザベス女王陛下に献上すると怪気炎を上げ、話題を振りまいていたが、結局、ネッシーを確認することすら出来なかった。
結局のところ、ネッシー捕獲は不発に終わったものの、1972年には、日本武道館にて、カシアス・クレイ(モハメド・アリ)対マック・フォスターというボクシング界最強のマッチメイクを実現させており、リング上で、ネッシーとウナギイヌが対戦している一コマを見ても、もし、康がネッシーを捕獲したら、クレイ対ネッシーのドリームマッチを開催していたのではないかという仮説がギャグとして描かれている。
「ウナギのように舞い イヌのように噛みますよ ワンワン」というウナギイヌの台詞は、「蝶のように舞い、蜂のように刺す」と形容されたカシアス・クレイのファイトスタイルのパロディー。
因みに、赤塚は、1971年、ニューヨークに短期遊学した際、漫画家の森田拳次、「ベニハナ」チェーンで有名な実業家のロッキー青木らの紹介により、カシアス・クレイとは知遇を得ていた。
また、康とも古くから親しい間柄であり、康の述懐によれば、1979年、康が「アントニオ猪木対食人アミン大統領、レフリー、モハメド・アリ」という企画を立ち上げた際、赤塚から「これが実現するなら、僕は直ちに漫画家辞めます。一筆入れます」と宣言したという。
結局のところ、この色物企画はバラシになり、赤塚の漫画家引退も幻に終わったわけだが、赤塚にとって、「猪木VSアミン大統領」などは、後年、自身のスランプの理由として語っていた、バーチャルな漫画の中での絵空事が現実世界で起こり得るようになってしまった悲劇そのものであったに違いない。
「ハイジャックと豆の木」
ドバイ日航機ハイジャック事件に材を採った一作。
手榴弾、自動小銃を武器にした日本赤軍とパレスチナ解放人民戦線(PFLP)の混成部隊による犯行で、パリ発アムステルダム、アンカレジ経由羽田行きの日本航空404便がハイジャックされたのが、1973年7月20日のことで、犯行グループは、前年のテルアビブ空港乱射事件で逮捕された岡本公三の解放と、現金五〇〇万ドル及び身代金四〇億円、収監されている日本赤軍メンバー二名の釈放を、それぞれ、イスラエル政府、日本政府に求めたが、日本政府側は、諸般の事情によりこれを拒否。また、PFLP側が求めたベイルート、もしくはダマスカスへの着陸も、国際問題に発展することを恐れたレバノン、シリア両国に拒否される。
結果、イスラエル政府は、岡本の解放を不承知するとともに、アラブ首長国連邦のドバイ国際空港へハイジャック機を着陸させた。
その後、ハイジャック機は、ドバイ国際空港に三日間駐機した後離陸。、シリアのダマスカス空港で燃料を補給した後、リビアのベニナ空港へと向かった。
ベニナ空港にて、犯行グループは、乗員乗客全一五〇名を解放した後、ハイジャック機を爆破し、リビア当局に投降。ムアンマル・アル=カッガーフィー大佐が統括するリビア政府の援助の下、その友好国へと国外逃亡を計ることになるが、身代金の授受に関しては、イスラエル政府、日本政府ともに非公開のため、未だ不明である。
我が国における最初のハイジャック事件は、1970年に発生したよど号事件であるが、事件より僅か三年の歳月を経ただけにも拘わらず、飛行機の機体もろとも爆破するといった暴挙さえ辞さなくなるとは、ハイジャック犯の過激化は、その後も非可逆的な展開を迎えるのではないかと、国内外において深刻な懸念が余儀なくされていたことに得心が行く。
本作では、ハイジャックに成功したニャロメが同志ケムンバスとともに、事前に撒いておいたゲリラ豆が大きくなり、ジャックの豆の木宜しく、天まで届く茎を這って逃亡を計るという内容だが、海外の政治情勢までも知り尽くした政治犯の暗躍は、一層巧妙且つ凶悪に進むものだという赤塚独自の警鐘が、ギャグというオブラートに包まれながら促されている。
「糸山英太郎 流行歌手に挑戦!!」
大阪証券取引所を舞台に、1971年から72年に掛け、中山製鋼所の株を巡り、近藤紡績所を向こうに回し、仕手戦を展開。見事勝利を収め、青年実業家として一躍名を成した新日本観光株式会社代表取締役の糸山英太郎。かてねより政界進出を希望していた糸山は、選挙に出馬するためのアクセサリーの一環として『怪物商法』や『太陽への挑戦』といった二冊の著作を上梓。特に、『太陽への挑戦』は、人気歌手・にしきのあきらの歌唱によってレコード化されるなど、広く衆目を集めた。
また、結局は頓挫したものの、ブリッティシュバンド、ローリング・ストーンズの来日公演を企画するなど、話題に事欠くことがなかった反面、厚顔無恥とも呼べるそのラディカルなキャラクターに批判が集中していたのも事実であった。
本作は、バカボン扮する糸山英太郎が、当時の浅丘めぐみのヒット曲「わたしの彼は左きき」のパロディー、「わったしの太陽〜〜〜左まきィ〜〜〜」とステージで熱唱しているというものだが、そうした糸山へのバッシングを軽妙なシニシズムへと昇華するその試みは、この上なく痛快であり、パロディスト赤塚不二夫の面目躍如といったところだろう。
さて、1974年の糸山の動向はといえば、当時、田中政権下で通産産業大臣だった中曽根康弘の私設秘書となり、石原慎太郎の強力な後ろ盾により、自由民主党から第10回参議院議員通常選挙に全国区で出馬。初当選を果たすものの、当選直後に甚大な選挙違反が発覚する。
選対本部長を含め、一四二人もの逮捕者を出したこの事件により、糸山の地位は失墜。続けて、作家の豊田行二から『怪物商法』『太陽への挑戦』『日本青年革命』の三冊のゴーストライトを務めていたことを暴露されるなど、今でいう炎上系のお騒がせ人物へと成り下がってしまった。
しかし、赤塚の糸山への関心は高く、本作以降も『ギャグゲリラ』「どうしてですか?」(「週刊文春」/74年9月16日号)や『天才バカボン』「かわいい人の本官なのだ」(「週刊少年マガジン」/74年39号)等で、糸山スキャンダルをギャグの一環として取り上げている。
また、「特集『劇画のヒーローたち』」「赤塚マンガはアンチ・ヒーロー主義」(「潮」74年11月号)と題されたエッセイで、赤塚は糸山を皮肉った、次のような文言を残している。
「最近の赤塚マンガ的英雄といったら、何といっても糸山英太郎センセイ。あの人は英雄です。『太陽への挑戦』なんてのは、まさに英雄的行為の最たるもの。あそこまでやられるとマンガ以上にマンガで、もうマンガでは描けない。」
「ポルノ解禁 ただし……」
1972年、雑誌「面白半分」の編集長を務めていた作家の野坂昭如が、1917(大正6)年、永井荷風が「文明」に発表した小説『四畳半襖の下張り』を同誌7月号に掲載した際、性的道義観念に反し、刑法175条に反するものとして、警視庁より猥褻文書販売の罪に問われるという刑事事件に発展。後に「四畳半襖の下張事件」と呼ばれた本件は、「徒に性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」と、東京高裁判事の栗本一夫は本件をこう断罪。猥褻文書に該当するものと判断した。
本作では、『四畳半の下張り』の生原稿に書かれた真面目な描写部分を伏字にしたとたん、露骨なまでの卑猥な言葉が浮かび上がり、それを見た目ん玉つながりが興奮を抑え切れないという落ちが組み込まれているが、あらゆる官能表現を猥褻として定義付け、法に裁きを委ねんとする国家権力の恣意的感情にこそ、本件を複雑化している最大の要因があるという、赤塚独特の諧謔的観点をここでも見て取ることが出来る。
本作は、1973年に起きた重大ニュースを赤塚独自の見解によりパロディー化せしめたコント集といった位置付けになろうが、こうしたその一年の重大ニュースを複数組み込んだ作品の元祖的な一編は、『天才バカボン』「重大ニュースの漫画ですのだ」(「週刊少年マガジン」73年2号)である。
本作でも取り上げられている横井庄一の帰還から札幌オリンピック開幕と笠谷幸生の金メダル獲得、飛鳥時代の壁画の発見(高松塚古墳)、ノーベル文学賞受賞作家・川端康成のガス自殺、テルアビブ空港乱射事件、第1次田中角栄内閣成立、ジャイアントパンダ・ランランとカンカンの初来日、ポール中岡ハイジャック事件といった出来事がギャグ仕立てによりダイジェストに綴られている。
このようなテーマは、赤塚にとって大層お気に入りだったと見え、『ギャグゲリラ』においても、1977年から連載終了となる82年まで、その年末に重大ニュースをテーマとして作品を連続して発表している。
いずれも、短いスペースの中で、ナンセンスと社会風刺によって染め上げられた笑いが矢継ぎ早に連打される傑作群だ。














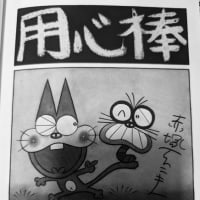
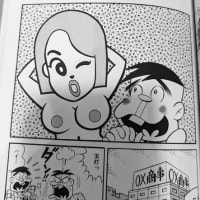
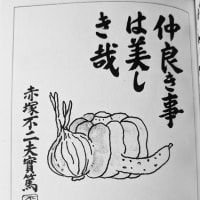
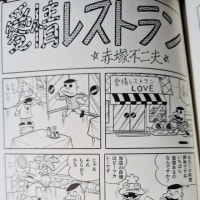

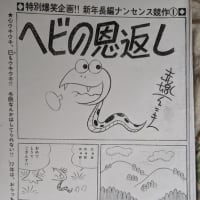
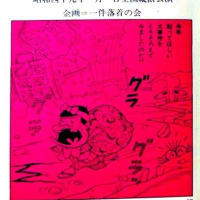
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます