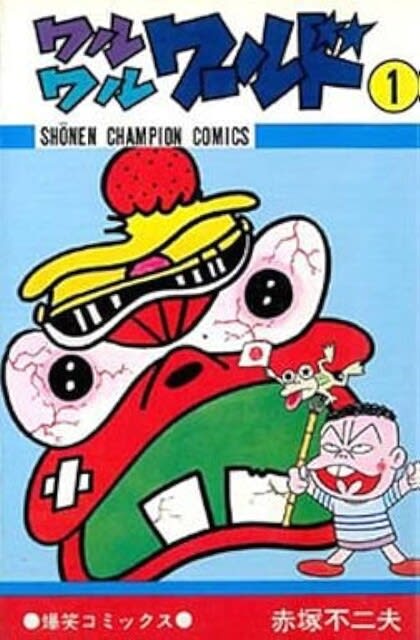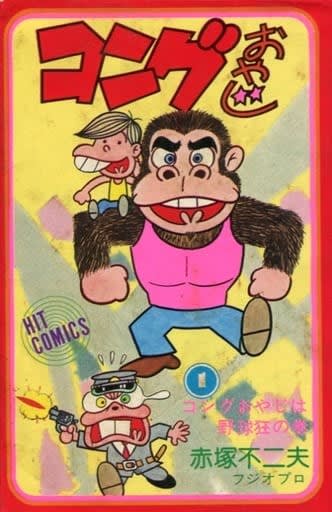1974年は、『レッツラゴン』終了後の赤塚にとって、一つの転換期とも言える年であり、無敵の進軍を誇っていた赤塚ギャグに、最大の対抗勢力となる作品が誕生する。
後に、「週刊少年チャンピオン」の部数増大の立役者の一つとなる、山上たつひこの『がきデカ』である。
主人公が日本初の少年警察官という設定そのものに、取り立てて新奇性はないものの、劇画調の絵で繰り出されるアブノーマルな笑いの数々、わかりやすいアクションを前面に押し出した混乱劇は、リアルな快楽原則に基づくエンジョイメントを放っており、山上はこの作品一本で、赤塚ギャグ以降、新たな跳躍を示し得なかった笑いのレトリックを、更に発展、鋭角化させることに成功した。
こうして、『がきデカ』は、赤塚漫画に変わり、時代の先端を行くトップ人気のギャグ漫画となり、その勢力図は大きく変貌を遂げる。
『がきデカ』のヒットは、ギャグ漫画の新たな表顕スタイルを生み出す誘発効果となり、以後、秋本治(代表作『こちら葛飾区亀有公園前派出所』)、小林よしのり(『東大一直線』、『おぼっちゃまくん』)、鴨川つばめ(『マカロニほうれん荘』)、江口寿史(『すすめ‼パイレーツ』、『ストップひばりくん』)といったフレッシュな才能が続々とデビューを果たし、山上の台頭に後続した。
そして、ギャグ漫画というジャンルは、赤塚ギャグという潮流から遠く離れ、読者が漫画に求める笑いの趣味嗜好もまた、より細分化してゆく。
赤塚が、長らく主力作家を務めていた「少年サンデー」、「少年マガジン」、そしてレギュラー執筆していた「少年キング」から撤退し、赤塚ギャグの象徴的タイトルとも言うべき『天才バカボン』の連載が終了した1978年、80年代~90年代の少年漫画界をリードするツートップが、華々しくデビューを飾る。
鳥山明(代表作『Dr.スランプ』、『ドラゴンボール』)と高橋留美子(『うる星やつら』、『めぞん一刻』)である。
この78年、79年という時代は、ファッションや音楽を含め、あらゆる若者文化が大きく組み換えられるターニング地点でもあった。
*
70年代中盤、イギリス本土で発生したパンク・ムーブメント以降、ミュージックシーンの潮流は、目まぐるしく移り変わり、78年公開の映画『サタデー・ナイト・フィーバー』の大ヒットによって、電子音楽を駆使したディスコサウンドが世界的なブームを巻き起こす。
雑誌『POPEYE』を読み耽る若者達は、アメリカのウエストコースト・カルチャーを意識した最先端のファッションや遊びに夢中になり、街のゲームセンターからは、インベーダーゲームの電子音が鳴り響く。
我が国のモータリゼーションも、77年のスーパーカー・ブーム以降、益々の拍車が掛かり、若者達を中心に、スポーツカー需要が急激に拡大してゆくなど、70年代でありながらも、世の中からは、70年代的な泥臭さが加速度的に淘汰されてゆく、そんな時代であった。
そして、軽薄短小の80年代を前に、流通社会が一気に発展的飛躍を遂げ、子供達が抱く日常での夢や憧れも、世のミッドストリーム指向の蔓延とともに、平準化してゆく。
それは、確実という概念が希薄になってゆく時代相を如実に反映した空虚感が、軽佻浮薄な風潮と重なり、子供社会全般にも影響を及ぼしてきた結果だろう。
『機動戦士ガンダム』の放映開始により、アニメメディアに新たな夜明けが訪れたのもこの頃だった。
赤塚の週刊少年誌からの退陣と、鳥山、高橋留美子のデビューが奇しくも同時期であることが、全てをシンボライズしているように、戦後ギャグ漫画の父・赤塚不二夫の才能を受け継ぐ遺伝子は、画力水準を底上げするとともに、更なる進化を遂げ、それによる少年漫画の新たな波も、皮肉なことに、赤塚の手の届かぬところへと行ってしまった。
こうして、迎えた80年代、ギャグ漫画の系譜は、ラブコメへと組み込まれ、それもまた、一つの類概念として定着する。
そして、生活ギャグやスラップスティックを身上としたナンセンスギャグは、前近代的なレッテルを帯び、いつしか戦後漫画文化の歴史の一断面として語られるだけのジャンルになってしまった。
*
漫画評論家の米沢嘉博は、70年代後半以降、赤塚漫画の人気が低迷の一途を辿った最大の要因に、その世界観に具体性が欠落していたことを挙げていたが、この指摘に限っていえば、強ち間違いでもなく、分裂生成した笑いをより不条理なギャグへと抽象化してゆく赤塚のナンセンス路線が、記号化されたその単純なタッチも含め、この時期、読者の嗜好から大きくズレ始めていたのは確かだった。
つまり、前述したような、ラブコメに見られる距離感の近い理想的世界や、精巧なメカが活躍するスピーディー且つアクロバティックな興奮、即物的な妄想を享楽的な笑いへと挿げ替えてゆくカタルシスといった、新世代の読者が漫画に求めるエッセンスを、赤塚の絵柄や発想では、具体的に示すことが出来なかったのだ。
1960年代から70年代半ばに掛け、旧世代漫画の最終形態であり、立体的なディテールとは無縁の概念を持つ赤塚作品が、時代を牽引し得たのは、いずれのギャグにも、従来の漫画表現の境界域をぶち破って余りある、圧倒的な起爆力が備わっていたからにほかならない。
だが、視覚的なリアリズムを重視したエンターテイメントが、コミックシーンの主流として台頭してきた時代にあって、そのアバンギャルドな先鋭性は、具体性が欠落しているが故、完全にコマーシャリズムとの接合点を喪失し、遂に赤塚漫画は、進化の袋小路へと陥ってしまったのだ。
ただ、21世紀を迎えた今、ギャグ漫画という分野に限り、その歴史を振り返ってみて、『がきデカ』の影響下にある一過性の人気を呼んだ諸作品と、それ以前に社会現象を巻き起こした赤塚ギャグを比較した際、様々な復刻本が出て読み継がれたり、その特異なキャラクターが、広告や商品に使われたりするなど、どちらが永遠の生命を持ち得たのか、それはもう言うまでもないだろう。
山上たつひこ、鴨川つばめは、比較的早い時期に漫画家を引退し、江口寿史は漫画家を廃業。現在も現役で執筆中の小林よしのりは、ベストセラー作家ではあるものの、もはや純然たるギャグ漫画家とは呼べないし、秋本治の長期に渡る不調は、かつてのファンからしたら、いたたまれない気持ちでいっぱいだ。
そういう意味では、拙著『赤塚不二夫大先生を読む』のインタビューで、藤子不二雄Ⓐが語っていたように、有為転変はあったものの、トータルして圧倒的な質と量を誇り、ギャグ漫画家というスタンスを、三〇年以上に渡って貫き通した赤塚を凌駕する才能は、今後もギャグ漫画界から現れることは一切ないと言っても過言ではない。
最後に、赤塚がテレビで発したこの言葉を引用し、第六章を締めたいと思う。
1970年代、赤塚がギャグ漫画の傑作、快作を大量執筆し、怒涛の勢いで、時代を駆け抜けて行った作家魂がこの言葉から零れている。
「現在、僕の仕事は、週刊誌四本に、月刊誌、新聞、その上、月刊漫画雑誌「まんが№1」の編集、発行をやっている。常識的に考えても、体力的にも、量的にも、限界にきている。これでは、ろくな作品を描けないと思いつつも、僕はこの限界を越えて行ってみようと思う。大量の仕事をやめられない激情が僕を突き上げてくる。それが一体何かということは分からない。不平不満ということもあるだろう。しかし、その真実は、とことん作品を描き尽くしてみるまでは、分からない筈だ。だから、僕の全てをぶつけた作品を、今後も大量に描き続けていくことを、読者諸君にここで宣言致します!」
(『私のつくった番組 マイテレビジョン』「赤塚不二夫の激情№1」73年1月25日放送)