ちょっとお知らせです。
法然共生・地域文化大賞を
北九州ホームレス支援機構↓が受賞しました。
http://www.h3.dion.ne.jp/~ettou/npo/top.htm
(上記ページより↓)
浄土宗が主催する「第三回 共生(ともいき)・地域文化大賞」の表彰部門「共生・地域文化大賞(1団体)」に、当機構が選ばれました!
152団体の中から9団体が一次選考を通過し、10月26日に京都・知恩院で行われたプレゼンテーションによる選考会にて選考、授与となりました。
「地域における人生支援」を中心におく当機構の活動が、「共生」というテーマに響いたのだと感じております。
浄土宗からも、野宿せざるを得ない方たちへの励ましが行われています。
厚く感謝し、共に「ホームレスを生まない社会づくり」を目指して行きたいと思います。
************
※実はこの夏、京都NPOセンターからこの事業の案内が届いていました。
その時に、北九州ホームレス支援機構を推薦できたらと思ったんです。
嘘じゃないですよ~。
けど調べたら自薦か、NPOセンターみたいなところしか推薦できなくて、
残念だなあと思っていたのでした。
そしたら、共生地域文化大賞って載ってたので、びっくり!!
めちゃ、嬉しいです。
法然共生の事業
主催しているのは知恩院で、日本仏教会が後援しています。
野宿者問題では伝統的にキリスト教系の支援団体が結構あって、
炊き出しや夜回りや継続的な支援を続けています。
仏教やお寺もそういう役割を果たしていけたらいいのに、ってずっと思ってました。
実際に目の前にいる苦しい状態の人の支えになってこそ(物心両面で)、生きた宗教だと。
知恩院がんばってほしいです。
違いやこれまでの枠を超えて、
分かちあい・支えあいの心がつながっていくと嬉しいです!(さき)
◆法然共生
共生(ともいき)・地域文化事業
http://www.jodo.or.jp/onki800/kinen/bunka/index.html
(上記HPより↓)
最近、「SR」という言葉をよく聞きます。
調べてみると、これは、「Social Responsibility(ソーシャル・レスポンシビリティ)」の略で、「社会的責任」という意味だそうです。「企業の社会的責任」「市民の社会的責任」というように色々な言葉で使われています。
では、「お寺・僧侶の社会的責任」というのはどういうものなのでしょうか。
難しい言葉ですが、「お寺・僧侶に対して社会が期待すること」「お寺・僧侶ならではの活動とは何なのか」という形で捉えると分かりやすいかもしれません。
お寺・僧侶は昔から、お釈迦様の御教えをお伝えするということはもちろん、「教育」「福祉」「医療」「文化」といった分野など、地域における公益的(社会的)な活動を担ってきました。
地域によっては、「一村一ヵ寺」、一つの村にお寺が一つあるといわれるぐらい、もともとお寺は地域に根ざした存在、地域社会に対して開けた存在で、色々な人と接点が持てる場所なのです。
浄土宗のお寺は全国で約7,000。仏教系の全宗派を合計すると、実に75,000もあるそうです。
ですので、お寺・お坊さんが地域の方々と一緒に、また、その拠点・中心となって、今よりもっと社会的・公益的な活動が展開できれば、「社会はきっと変わる」、そのように考えています。
ここでは、「共生」「平和」「環境」といった現代のテーマのもと、地域地域でさらに社会活動が進められるように、お寺・僧侶がどのように関わっていけるか、又は参加できるかということを命題に取り組んでいる記念事業を紹介します。
★ブログランキングに参加しています★
共感いただけたらクリックお願いします♪(右上のバナー)
法然共生・地域文化大賞を
北九州ホームレス支援機構↓が受賞しました。
http://www.h3.dion.ne.jp/~ettou/npo/top.htm
(上記ページより↓)
浄土宗が主催する「第三回 共生(ともいき)・地域文化大賞」の表彰部門「共生・地域文化大賞(1団体)」に、当機構が選ばれました!
152団体の中から9団体が一次選考を通過し、10月26日に京都・知恩院で行われたプレゼンテーションによる選考会にて選考、授与となりました。
「地域における人生支援」を中心におく当機構の活動が、「共生」というテーマに響いたのだと感じております。
浄土宗からも、野宿せざるを得ない方たちへの励ましが行われています。
厚く感謝し、共に「ホームレスを生まない社会づくり」を目指して行きたいと思います。
************
※実はこの夏、京都NPOセンターからこの事業の案内が届いていました。
その時に、北九州ホームレス支援機構を推薦できたらと思ったんです。
嘘じゃないですよ~。
けど調べたら自薦か、NPOセンターみたいなところしか推薦できなくて、
残念だなあと思っていたのでした。
そしたら、共生地域文化大賞って載ってたので、びっくり!!
めちゃ、嬉しいです。
法然共生の事業
主催しているのは知恩院で、日本仏教会が後援しています。
野宿者問題では伝統的にキリスト教系の支援団体が結構あって、
炊き出しや夜回りや継続的な支援を続けています。
仏教やお寺もそういう役割を果たしていけたらいいのに、ってずっと思ってました。
実際に目の前にいる苦しい状態の人の支えになってこそ(物心両面で)、生きた宗教だと。
知恩院がんばってほしいです。
違いやこれまでの枠を超えて、
分かちあい・支えあいの心がつながっていくと嬉しいです!(さき)
◆法然共生
共生(ともいき)・地域文化事業
http://www.jodo.or.jp/onki800/kinen/bunka/index.html
(上記HPより↓)
最近、「SR」という言葉をよく聞きます。
調べてみると、これは、「Social Responsibility(ソーシャル・レスポンシビリティ)」の略で、「社会的責任」という意味だそうです。「企業の社会的責任」「市民の社会的責任」というように色々な言葉で使われています。
では、「お寺・僧侶の社会的責任」というのはどういうものなのでしょうか。
難しい言葉ですが、「お寺・僧侶に対して社会が期待すること」「お寺・僧侶ならではの活動とは何なのか」という形で捉えると分かりやすいかもしれません。
お寺・僧侶は昔から、お釈迦様の御教えをお伝えするということはもちろん、「教育」「福祉」「医療」「文化」といった分野など、地域における公益的(社会的)な活動を担ってきました。
地域によっては、「一村一ヵ寺」、一つの村にお寺が一つあるといわれるぐらい、もともとお寺は地域に根ざした存在、地域社会に対して開けた存在で、色々な人と接点が持てる場所なのです。
浄土宗のお寺は全国で約7,000。仏教系の全宗派を合計すると、実に75,000もあるそうです。
ですので、お寺・お坊さんが地域の方々と一緒に、また、その拠点・中心となって、今よりもっと社会的・公益的な活動が展開できれば、「社会はきっと変わる」、そのように考えています。
ここでは、「共生」「平和」「環境」といった現代のテーマのもと、地域地域でさらに社会活動が進められるように、お寺・僧侶がどのように関わっていけるか、又は参加できるかということを命題に取り組んでいる記念事業を紹介します。
★ブログランキングに参加しています★
共感いただけたらクリックお願いします♪(右上のバナー)










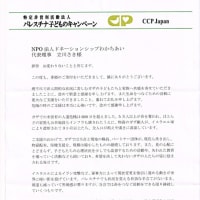















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます