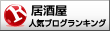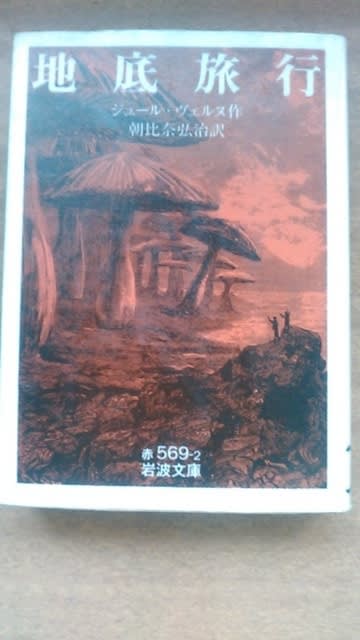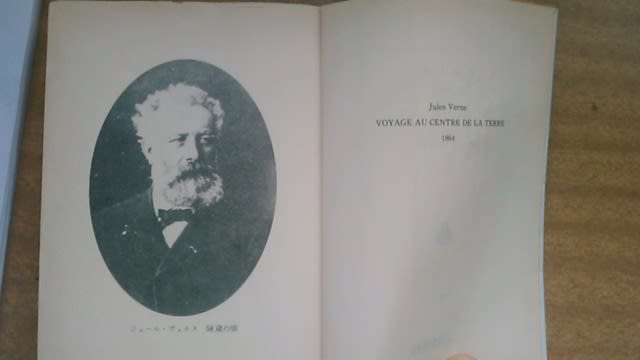学校に入り込むニセ科学
左巻健男 著

一見科学的な装いをしながら、実際には科学的な根拠はなく
教員や生徒の「善意」を利用して勢力を広げるニセ科学。
そのオカルトまがいの言説はいま
学校教育の土台を揺るがすところまで来ている。

図書館の親書コーナーでふと手にした本書ですが、ページをめくって驚きました。
実は私もだまされていました。
それが本書に書いてあってびっくりです。
これには参りましたね。
それが何かと言いますと、テレビのコマーシャルでもよくつかわれていた、「江戸しぐさ」です。
これはいいもんだと感心してよく調べもせずに、ブログにまで乗せてしまいました。
http://denkigama.tblog.jp/?eid=179185
しかし実は江戸時代のものではなく、現代人の創作だったというわけです。
ほんの少しおかしいなあとは思っていましたが、これにはすっかり騙されました。
皆さんもお気を付けください。
本書にはそれ以外にも眉唾物のニセ科学が紹介されています。
もっとも有名なのが「水からの伝言」という話です。
水にいい言葉を掛けて凍らせるときれいな結晶になり、悪い言葉を掛けると崩れるという、まったくばからしいものですが、これを信じている方もいたそうですから困ったものです。
まあ私も一つ騙されましたから偉そうなことは言えませんが。
しかし笑い話で済まされているうちはいいですが、これが教育現場で使われたのではたまったものではありません。
子供にこんな話を教える先生がいたとしたら恐ろしいものです。
この本の中にはもう一つ同感する話がありました。
それが小学校の算数の計算です。
「1冊5円のノートを6冊買ったらいくらになるでしょうか」
という問題の正解は計算式が
5×6=30(円)です。
これを逆に書いて、6×5=30とするとバツだという。
同じようなことが子供の小学校のテストにあって驚いたことがありました。
こんな頭の悪い先生がいるのかと、半ば呆れた記憶があります。
子供には先生が間違っているからこれでかまわないとしっかり教えました。
立場が変わって、今ではその先生の卵を教えていますが、これについてはいつも注意しています。
幸いに今ではこういうことはありませんが、昔はこういう不思議な教育がまかり通っていた時代もあったわけです。
人間ですからたまにはこういう神秘的なものに興味を引かれても仕方がありませんが、科学の眼だけは曇らせてはいけません。
将来を背負う子供たちのためにも気をつけたいものです。
左巻健男 著

一見科学的な装いをしながら、実際には科学的な根拠はなく
教員や生徒の「善意」を利用して勢力を広げるニセ科学。
そのオカルトまがいの言説はいま
学校教育の土台を揺るがすところまで来ている。

図書館の親書コーナーでふと手にした本書ですが、ページをめくって驚きました。
実は私もだまされていました。
それが本書に書いてあってびっくりです。
これには参りましたね。
それが何かと言いますと、テレビのコマーシャルでもよくつかわれていた、「江戸しぐさ」です。
これはいいもんだと感心してよく調べもせずに、ブログにまで乗せてしまいました。
http://denkigama.tblog.jp/?eid=179185
しかし実は江戸時代のものではなく、現代人の創作だったというわけです。
ほんの少しおかしいなあとは思っていましたが、これにはすっかり騙されました。
皆さんもお気を付けください。
本書にはそれ以外にも眉唾物のニセ科学が紹介されています。
もっとも有名なのが「水からの伝言」という話です。
水にいい言葉を掛けて凍らせるときれいな結晶になり、悪い言葉を掛けると崩れるという、まったくばからしいものですが、これを信じている方もいたそうですから困ったものです。
まあ私も一つ騙されましたから偉そうなことは言えませんが。
しかし笑い話で済まされているうちはいいですが、これが教育現場で使われたのではたまったものではありません。
子供にこんな話を教える先生がいたとしたら恐ろしいものです。
この本の中にはもう一つ同感する話がありました。
それが小学校の算数の計算です。
「1冊5円のノートを6冊買ったらいくらになるでしょうか」
という問題の正解は計算式が
5×6=30(円)です。
これを逆に書いて、6×5=30とするとバツだという。
同じようなことが子供の小学校のテストにあって驚いたことがありました。
こんな頭の悪い先生がいるのかと、半ば呆れた記憶があります。
子供には先生が間違っているからこれでかまわないとしっかり教えました。
立場が変わって、今ではその先生の卵を教えていますが、これについてはいつも注意しています。
幸いに今ではこういうことはありませんが、昔はこういう不思議な教育がまかり通っていた時代もあったわけです。
人間ですからたまにはこういう神秘的なものに興味を引かれても仕方がありませんが、科学の眼だけは曇らせてはいけません。
将来を背負う子供たちのためにも気をつけたいものです。