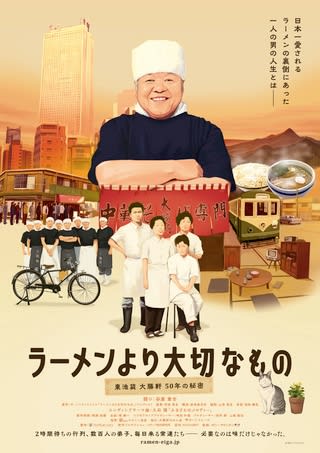2017年、日本映画
監督:月川翔
原作:住野よる
脚本:吉田智子
<キャスト>
浜辺美波:山内桜良
北村匠海:志賀春樹(学生時代)
小栗旬:志賀春樹(現在)
大友花恋:恭子(学生時代)
北川景子:恭子(現在)
矢本悠馬:ガム君
桜田通:委員長

青春モノです。
不治の病のヒロインと、根暗のヒーロー。
ありがちな設定ですが、50代半ばの私は引き込まれて最後まで見入ってしまいました。
天真爛漫に見える桜良(さくら)は、病名はわからないけど膵臓を患い(インスリンを使っていた)、先は長くない様子。
明るく振る舞う彼女は人一倍繊細な面も持ち合わせており、周りに心配をかけないよう、親友にもひたすら病気のことを隠し続ける日々。
偶然彼女の病気を知ることになった春樹は、他人に興味がなく、本が友達。
彼は過度に気を遣うわけでもなく、ふつうにつき合ってくれる。
それが彼女には新鮮でうれしかった。
桜良に振り回される春樹は、少しずつ心を開いていく。
孤独を愛してきた彼が、人と関わる喜びを感じ始める。
悲しい結末だけど、不思議な余韻を残してくれました。
印象的だったのは、夜の病院で行われたトランプゲーム「真実と挑戦」の場面。
春樹が「君は僕のことを・・・いや、気には生きることをどう考えているの?」と聞くと、
桜良はしばらく考えた末に「人と心を通い合わせること」と答えました。
「人と出会い、仲良くなり、すれ違い、好きだけど嫌い、楽しいけどうっとうしい・・・自分だけでは生きている実感がないけど、周りの人と心を通わせることで生きてるって感じるの」
それは、自分の殻に閉じこもることで自分を守ってきた春樹には衝撃的な答えでした。
古来、繰り返し議論されてきたテーマです。
ヘルマンヘッセが「知と愛」(ナルシスとゴルトムント)で描き、
初期の村上春樹が書いたデタッチメントと現在の村上春樹が書いているアタッチメント。
どこにスタンスを置くかは、その人次第。
私は、春樹寄りかな。
桜良は「人に悪く思われようとよく思われようと、僕はかまわない」と言い放つ春樹を「強い」と感じました。
両極端の二人が、お互いの存在を認め、あこがれる関係。
「青春の恋愛ストーリー」にとどまらない魅力を放つポイントはここかな。。
一見、桜良が主役ですが、原作・監督が描きたかった真の主役は春樹ではないでしょうか。
以上、青春モノも悪くないな、と久々に思わせてくれた映画でした。
<解説>
タイトルとストーリーのギャップで話題を集めた住野よるの同名ベストセラー小説を実写映画化した青春ドラマ。高校時代のクラスメイト・山内桜良の言葉をきっかけに教師となった“僕”は、教え子の栗山と話すうちに、桜良と過ごした数カ月間の思い出をよみがえらせていく。
高校時代の“僕”は、膵臓の病を抱える桜良の秘密の闘病日記を見つけたことをきっかけに、桜良と一緒に過ごすようになる。そして桜良の死から12年後、彼女の親友だった恭子もまた、結婚を目前に控え、桜良と過ごした日々を思い出していた。
大人になった“僕”役を小栗旬、恭子役を北川景子がそれぞれ演じる。「黒崎くんの言いなりになんてならない」などの新鋭・月川翔監督がメガホンをとり、「ホットロード」「アオハライド」など青春映画に定評のある吉田智子が脚本を担当。
★ 5点満点で5点。
40年前の青春時代を懐かしく思い出しました。
高校時代の春樹役の北村匠海のしゃべり方、立松和平さんに似てますね。
それから、何度も出てくるサン・テグジュペリの「星の王子様」。
この映画のヒントが隠されていそうで、ちょっと検索してみたらこちらがヒットしました。
なるほど、なるほど。
■ 【ネタバレ有】映画「君の膵臓をたべたい」 感想・考察と7つの疑問点を徹底解説!/泣ける!原作を超える完成度でした!【キミスイ】
監督:月川翔
原作:住野よる
脚本:吉田智子
<キャスト>
浜辺美波:山内桜良
北村匠海:志賀春樹(学生時代)
小栗旬:志賀春樹(現在)
大友花恋:恭子(学生時代)
北川景子:恭子(現在)
矢本悠馬:ガム君
桜田通:委員長

青春モノです。
不治の病のヒロインと、根暗のヒーロー。
ありがちな設定ですが、50代半ばの私は引き込まれて最後まで見入ってしまいました。
天真爛漫に見える桜良(さくら)は、病名はわからないけど膵臓を患い(インスリンを使っていた)、先は長くない様子。
明るく振る舞う彼女は人一倍繊細な面も持ち合わせており、周りに心配をかけないよう、親友にもひたすら病気のことを隠し続ける日々。
偶然彼女の病気を知ることになった春樹は、他人に興味がなく、本が友達。
彼は過度に気を遣うわけでもなく、ふつうにつき合ってくれる。
それが彼女には新鮮でうれしかった。
桜良に振り回される春樹は、少しずつ心を開いていく。
孤独を愛してきた彼が、人と関わる喜びを感じ始める。
悲しい結末だけど、不思議な余韻を残してくれました。
印象的だったのは、夜の病院で行われたトランプゲーム「真実と挑戦」の場面。
春樹が「君は僕のことを・・・いや、気には生きることをどう考えているの?」と聞くと、
桜良はしばらく考えた末に「人と心を通い合わせること」と答えました。
「人と出会い、仲良くなり、すれ違い、好きだけど嫌い、楽しいけどうっとうしい・・・自分だけでは生きている実感がないけど、周りの人と心を通わせることで生きてるって感じるの」
それは、自分の殻に閉じこもることで自分を守ってきた春樹には衝撃的な答えでした。
古来、繰り返し議論されてきたテーマです。
ヘルマンヘッセが「知と愛」(ナルシスとゴルトムント)で描き、
初期の村上春樹が書いたデタッチメントと現在の村上春樹が書いているアタッチメント。
どこにスタンスを置くかは、その人次第。
私は、春樹寄りかな。
桜良は「人に悪く思われようとよく思われようと、僕はかまわない」と言い放つ春樹を「強い」と感じました。
両極端の二人が、お互いの存在を認め、あこがれる関係。
「青春の恋愛ストーリー」にとどまらない魅力を放つポイントはここかな。。
一見、桜良が主役ですが、原作・監督が描きたかった真の主役は春樹ではないでしょうか。
以上、青春モノも悪くないな、と久々に思わせてくれた映画でした。
<解説>
タイトルとストーリーのギャップで話題を集めた住野よるの同名ベストセラー小説を実写映画化した青春ドラマ。高校時代のクラスメイト・山内桜良の言葉をきっかけに教師となった“僕”は、教え子の栗山と話すうちに、桜良と過ごした数カ月間の思い出をよみがえらせていく。
高校時代の“僕”は、膵臓の病を抱える桜良の秘密の闘病日記を見つけたことをきっかけに、桜良と一緒に過ごすようになる。そして桜良の死から12年後、彼女の親友だった恭子もまた、結婚を目前に控え、桜良と過ごした日々を思い出していた。
大人になった“僕”役を小栗旬、恭子役を北川景子がそれぞれ演じる。「黒崎くんの言いなりになんてならない」などの新鋭・月川翔監督がメガホンをとり、「ホットロード」「アオハライド」など青春映画に定評のある吉田智子が脚本を担当。
★ 5点満点で5点。
40年前の青春時代を懐かしく思い出しました。
高校時代の春樹役の北村匠海のしゃべり方、立松和平さんに似てますね。
それから、何度も出てくるサン・テグジュペリの「星の王子様」。
この映画のヒントが隠されていそうで、ちょっと検索してみたらこちらがヒットしました。
なるほど、なるほど。
■ 【ネタバレ有】映画「君の膵臓をたべたい」 感想・考察と7つの疑問点を徹底解説!/泣ける!原作を超える完成度でした!【キミスイ】