



光あれば影あり。意味不明ですが、「悪の読書術」は存在するのでしょうか。
不良のための読書術
「本を読んで不良になろう!」という読書術。といっても「ドラックをやりながら本を読め!!」とか、「本屋さんで喝上げをしろ!!」、「ナイフで本のページをめくれ!!」と言っている訳ではありません(それはそれでドキドキするが)。
筆者は世の中の不幸の大半はマジメな良い子がおこすと言っています。純粋培養な良い子は何も考えません。大多数に付和雷同した方が安易な道だからです。そんな安易な道へ到らない為に良い子の反対「不良」になれと主張しています。
本には毒があり、いろんな本を読んでいるといままで、真理だと思っていたものが、嘘・偽りと分かります。我々は毒まみれになる必要があるのではないかとの事です。
その為、本をたくさん読む必要がありますが、今や出版の大洪水。読んでおくべきを見つける前に溺れそうです。そのために筆者がお勧めしているのが、「ゴダール式読書法」なる読書術。本はテキトーなところを20~30ページ読めば良いそうです。
人は貧乏性でつい本を買ったら、全部読んでしまいますが、そうすると他の本が読めなくなってしまいます。フランスの映画監督ゴダールは毎日映画館をはしごしており、1本の映画を20分程度しか見て、次の映画館に行き、さらに20分たったらその次の映画館に行ったそうです。これにならって読書するという訳です。
これまでのマジメな読書法ではその本の1部を読んだだけでは、読書というのか?という疑問がありますが、筆者は「読んだことにならなくてもいいもんね」というもんね的な不良の答えをしています。
目の前にラーメンと寿司とカツ丼があったら、すべて3分の1ずつ食べて後は捨ててしまうという贅沢な読書法。といっても真面目に3分の1ずつ読む必要もなく、不良らしくタマには最後まで読んでしまう事もいいそうです。その他、「擬似速読術」や「ゴダール式減感療法」などで、ゴダール式読書法をマスターする方法を説いています。
ここまでで、2章までの話で、本の探し方・本の流通・書店・図書館・古本屋等の話や「みんなが読んでいる本は死んでもよむもんか!」「必殺!本の時間差攻撃」等の話がありますが、ゴダール式にここまでにします。
ある程度の読書した方はほど良く毒に染まって、ベストセラーについて馬鹿にする傾向があると思います。しかし、あえてベストセラーに毒毒な書評を書いている方もいます。それが、斎藤美奈子女史の「趣味は読書」(略してシュミドク)。
斎藤女史は「ベストセラーなど読みたくない」、「読まなくてもわかる」とうそぶく読者を「邪悪な読者」、読書初心者を「善良な読者」と定義しています。邪悪な読者は嫌見たらしい美食家みたいな同類という自覚を持つこと、善良な読書家はメディア・リテラシーを養った方がいいと言っています。そして、お互いの文化を知ることこと平和的共存だと。
読書族はさらに細かくすると「偏食型」・「読書原理主義者」・「過食型(読書依存症)」・「善良な読者」に分類し、世の読書族のほとんどは「善良な読者」だと仮定しています。善良な読者は感動しろといわれれば「感動し」、泣けといわれれば「泣く」といったように素朴すぎるのが欠点との事。
自ら「邪悪な読者」と名乗るように、話題となったベストセラーについて、邪悪というか愉快な感想と分析を語っています。毒書家がどのようにベストセラー本を見ているか考察するのにちょうどいい1冊と思います。
悪といえば、その名もずばり「悪の読書術」。社交としての読書論及び作家ガイドといったところでしょうか。ここで言う悪とは自分の無垢さ、善良さを前提とする甘えを抜け、より意識的・戦略的に振舞うためのモラルとの事です。若い女性向けの雑誌に掲載された原稿を元にしているため、若い女性受けしそうな作家を例に論じられています。
どんな本を愛読書として人に示すかというのは、どんな人間に見られたいか、どんな人間になりたいかをという問いに直結しており、自分はこの本が好きだから読むではなく、自分をつくり向上させるために何を読むべきかを戦略的にすべきと言っています。ようするにTPOをわきまえよと。
もう少し過激な話を期待していましたが、どうも悪というほどの話ではないような気がします。ちなみに斎藤女史の本は、文芸における男性社会的な権威主義に対して、きわめて犀利な振るっており、「この頃の若い子は歯ごたえがない」というオジさんをたばかるのに、かなり有効なアイテムとの事です。
読書術ではありませんが、人生を狂わせる読んではいけない本として、東大教授(仏文化)石井洋二郎氏の「毒書案内」なんていう本もあります。そんな事いわれると読みたくなりのですが。読書経験が少なく、精神的にまいっているときに読んだら影響があるかもいれません。7章あり5冊ずつ紹介しています。
1章 死の誘惑・2章 異界の迷宮・3章 揺らぐ自我・4章 迷走する狂気・5章 性と暴力・6章 官能の深淵・7章 背徳と倒錯
石井氏は「星の王子さま」の訳者でもあります。あら。
フランス系の本が多いです。秋木はこのリストの本は20冊くらいは読んでいます。すでに耐性がついてしまったのか、秋木にとってはあんまり毒とも思えません。むしろ楽しく読むくらいで。ちょいと読んでみたい作品もいくつかありました。
すでに毒に染まりすぎ、アナキン・スカイウォーカー(Anakin Skywalker)並にダークサイトに堕ちているようです。コーホ。こんなに裏表がない男はいないと思うのですが(裏だけですが)。
コーホー、コーホ
コーホー、コーホー
コーホー、コーホー
コーホー、コーホー
コーホー、コーホー
コーホー、コーホー
・・・・・・
・・・
・



















 祈りつつ、ラーメン。
祈りつつ、ラーメン。

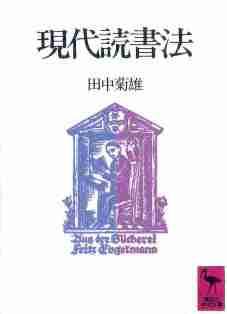
 )。
)。 。調べたかぎりでも少なくとも読書術の本は200冊以上はありますし、読書関連に関して言えば数えきれません。何だかどんどん読む本が増えています。読書術がいつまでたっても止まりそうにありません
。調べたかぎりでも少なくとも読書術の本は200冊以上はありますし、読書関連に関して言えば数えきれません。何だかどんどん読む本が増えています。読書術がいつまでたっても止まりそうにありません 。
。







 。
。











