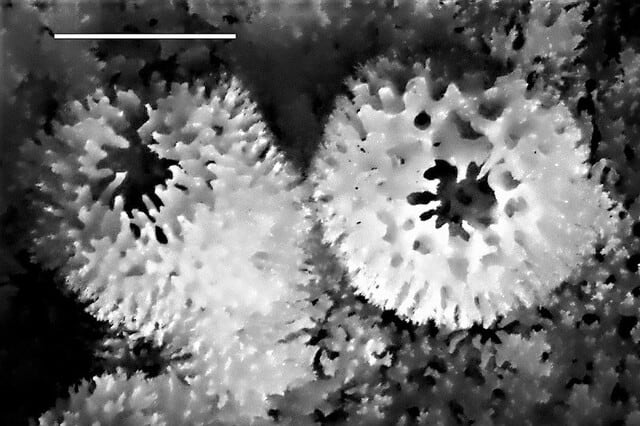旅行は終活の一環である。
数年前から体に自信が持てなくなってしまった。そのため、「体がまだ動く内に”やりたいこと”をやっておかないと」、という強迫観念を持つようになった。
旅行は”やりたいこと”の1つである。特に行っておきたい目的地は国内では2つある。1つは幼少期を過ごした北海道千歳市付近の変貌ぶりを見とどけること。三つ子の魂ではないが、当地では幼稚園と小学校低学年時代を過ごし、その大地に今へと続く私の基本的な自然観というものが醸成されたように思う。そして、当地を離れたて以来、もう60年近く再訪していない。あのどこまでも続く地平線と、印象的なフランスベッドのポツンとした看板はどうなったであろうか。
他の1つは、国内では自然景観が最も美しいとされる上高地である。1度は自分の目で見ておきたい。という次第で数日前に彼の地を訪れた。
しかしながら上高地は遠い。家がある本州最果て・最南端の地から500km、車で7時間かかる。たぶん2度と行かないであろうから、ついでに憧れの白川郷も訪問地に含めた。日程は2泊3日、初日が白川郷、2日目は西穂ミニ登山、3日目は上高地散策をそれぞれ各日のメインに据えた、なかなかの欲張り強行軍。当初、車のルートは距離が短い名古屋経由を予定していたが、新名神と湾岸が工事で渋滞が予想されたため、行きは大阪経由を選んだ。
日程
○1日目(2025年5月13日) 快晴
(自宅-白川郷:520km、6時間40分、燃費20.6km。散策歩数19000)
03:42 自宅出発、05:28 紀ノ川SA、07:42 多賀SA、10:25 白川郷、13:28 高山到着・散策、15:00 KAjette入宿、晩食は麺屋真菜で高山ラーメン



白川郷。凝縮された映像で見ていたほどではないが、それなりに良い。



高山市内。上段は飛騨地方のお守りであるさるぼぼ。お団子が名物とのことで、昼はみたらし団子、五平餅、高山牛饅を食べ歩いた。当地の観光は、それ用に整備された観光店街を歩くことになるが、興をそそられない。それよりも、川を挟んだ反対の通りが静かで、祭り関係の店や家屋が並び趣がある。下段の画像はそんな中にあった床屋。強い昭和感を放っていた。

愛車となった新型ギア。よく走り、かつとても運転しやすい。この車を買わなければ、飛騨・信州旅行は思いつかなかった。今回は1000kmを走り、平均燃費は22km/ℓもあった。