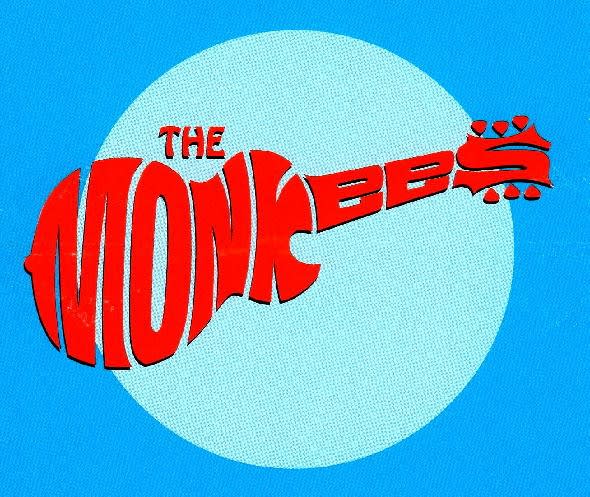少し前にコモンサンゴ類の中で最も古い種はMontipora foliosa (Pallas, 1766)で、この学名にはこれまでウスコモンサンゴの和名が充てられていたが、この和名を担う種は別にいて、それには新しい学名が与えられるかもしれないと述べた。
本日、葉状群体を形成するコモンサンゴ類の整理が一通り済んだ。これまで記載された種のチェックも行ったのであるが、ありました、ありました、ウスコモンサンゴと確実に実体を共有する学名が。それも3つ。それらは、
①Montipora pulcherima Bernard, 1897(Macclesfield, South China Sea)
②Montipora undans Crossland, 1952(Great Barrier Reef)
③Montipora sulcata Crossland, 1952(GBR)
従って、ウスコモンサンゴに対応する学名は最も提唱年の古い①ということになる。しかしながら、コモンサンゴ類分類の父であるバーナード博士はさすがである。ちゃんと、M. foliosaとウスコモンサンゴを識別し、記載してくれていた。一方、クロスランド博士はロンドン自然史博物館にあるバーナード博士の標本を調べたはずであるが、本種の形態変異に幻惑されてしまったようである。
ところで、ベロン博士とワレス博士はグレートバリアリーフのモノグラフ(Veron & Wallace, 1984)の中で、ウスコモンサンゴに対しM. foliosaの学名を用いる見解を最初に示したのであるが、その記載の中で上記の3学名を含めた15もの学名をシノニム(同物異名)として扱った。ただし、これらの多くは有効名として復活されるべきものであり、なんとも荒っぽい仕事であったことか。しかも、この中には敬愛するバーナード博士に作られたものが7つもある。いつか、日の目を見させてあげたい。

Montipora pulcherima Bernard, 1897(ウスコモンサンゴ)のタイプ標本:Bernard(1897)の図版を複写

Montipora pulcherima Bernard, 1897(ウスコモンサンゴ)のタイプ標本:タイプ標本を実写

Montipora undans Crossland, 1952:Crossland(1952)の図版を複写

Montipora sulcata Crossland, 1952:Crossland(1952)の図版を複写
本日、葉状群体を形成するコモンサンゴ類の整理が一通り済んだ。これまで記載された種のチェックも行ったのであるが、ありました、ありました、ウスコモンサンゴと確実に実体を共有する学名が。それも3つ。それらは、
①Montipora pulcherima Bernard, 1897(Macclesfield, South China Sea)
②Montipora undans Crossland, 1952(Great Barrier Reef)
③Montipora sulcata Crossland, 1952(GBR)
従って、ウスコモンサンゴに対応する学名は最も提唱年の古い①ということになる。しかしながら、コモンサンゴ類分類の父であるバーナード博士はさすがである。ちゃんと、M. foliosaとウスコモンサンゴを識別し、記載してくれていた。一方、クロスランド博士はロンドン自然史博物館にあるバーナード博士の標本を調べたはずであるが、本種の形態変異に幻惑されてしまったようである。
ところで、ベロン博士とワレス博士はグレートバリアリーフのモノグラフ(Veron & Wallace, 1984)の中で、ウスコモンサンゴに対しM. foliosaの学名を用いる見解を最初に示したのであるが、その記載の中で上記の3学名を含めた15もの学名をシノニム(同物異名)として扱った。ただし、これらの多くは有効名として復活されるべきものであり、なんとも荒っぽい仕事であったことか。しかも、この中には敬愛するバーナード博士に作られたものが7つもある。いつか、日の目を見させてあげたい。

Montipora pulcherima Bernard, 1897(ウスコモンサンゴ)のタイプ標本:Bernard(1897)の図版を複写

Montipora pulcherima Bernard, 1897(ウスコモンサンゴ)のタイプ標本:タイプ標本を実写

Montipora undans Crossland, 1952:Crossland(1952)の図版を複写

Montipora sulcata Crossland, 1952:Crossland(1952)の図版を複写