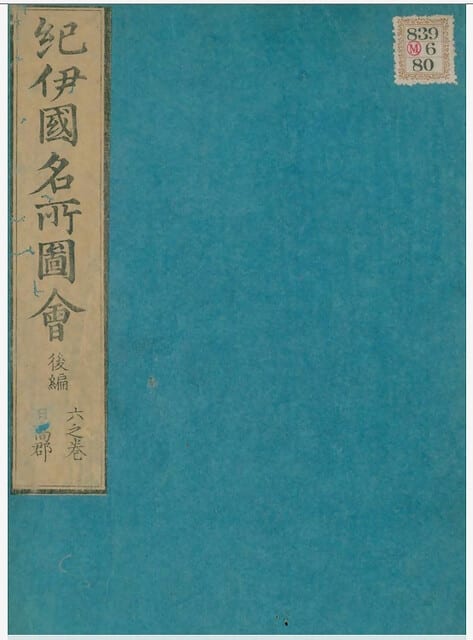兄が紀伊半島を旅行したいというので、龍神、洞川(どろがわ)、十津川の3銘泉巡りを計画し宿を取っていたのであるが、都合によりキャンセルとなった。そのため、旅行に出る意味は無くなってしまったが、洞川はまだ行ったことがなかったので、ここだけ妻と行ってきた。
洞川温泉は紀伊半島中央、奈良県に位置する。半島南端にある我が家からはいくつかルートがあるが、北山・大台ルートは閉鎖されており、また、山越えは難路ばかりであるので、無難に和歌山市から京奈和道を利用した。途中かつらぎ町で下り、道の駅をリレーしてつまみ食いを楽しみながら赴いた。
洞川は標高800m程の、洞川沿いの高地にポツンと集まった山里にある。そのルーツは、1300年も前に近くの大峰山を開山した役行者にあり、爾来、山伏の修行の聖地として、また、役行者を崇拝する大峰講の信者の宿場町として発展を遂げた。そのため、旅館街は昭和以前の古い面影や大峰講との関わりを色濃く残しており、この異色さが当該温泉街の特徴となっている。ちなみに、洞川周辺の地質は主に石灰岩より成り、そのため大小様々な鍾乳洞のあるカルスト地形が形成されている。洞川の名は「鍾乳洞から出流る川」に由来する。
当該温泉街の特色は上述したが、さらに特異なものがある。それは、各家々が提灯等でノスタルジックに電飾を施すことである。その幻想的な美しさこそ、この街の最大の売りであり、ここに泊まらなければその良さは分からない。全ての物が消え去るのが定めのこの世にあって、この異世界は末永く残って欲しいと思った。

洞川集落




洞川温泉街の昼の顔





洞川温泉街の夜の顔




山伏の持薬として古来より伝わる伝統胃腸薬「陀羅尼助丸」専門の店が何軒もある。漢方薬の類いである。さすがは、歴史ある大峰講の里。さっそく買い求めたので、適宜試してみたい。

自動販売機で売られているステッカー。パクリだがほほえましい。

近くにある鍾乳洞「蟷螂の岩屋」。山伏の修行地となっている。

山伏の根本道場。早朝に散歩していたら、ホラ貝とドラが鳴り響いてきた。今も山岳信仰が残っていることを実感した。

さすがは吉野杉の産地。枝打ちが行き届いている。