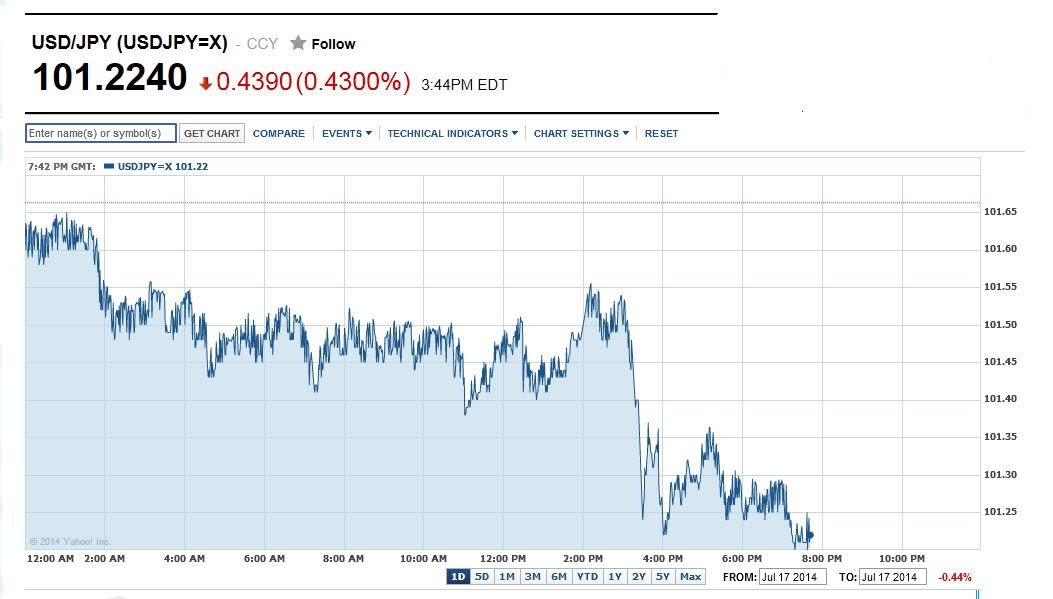米労働統計局のデータに基づきCareerCastが行った調査では、2022年までに姿を消す可能性の高い職業が明らかになった。
今は誰もがお世話になっているおなじみの職業だが、近いうちになくなるかもしれないものを順にご紹介しよう。
第1位:郵便配達員 2022年の推定雇用率:-28%
Eメールやオンライン請求の普及で郵便物が激減しているため、必要とされる郵便作業員も減る見込み。
第2位:農家 2022年の推定雇用率:-19%
技術の進歩により、少ない人員での作業が可能になったため。
第2位:メーターの計測係 2022年の推定雇用率:-19%
電気、ガス、水道各社は電子計測器の導入を進め、わざわざメーターを見に行かずともデータが送られるようになる。
第3位:新聞記者 2022年の推定雇用率:-13%
オンラインニュースの台頭により、新聞購読者が減り、購読料、広告料共に激減。新聞社が多くの記者を雇うことができなくなる。
第4位:旅行代理店の社員 2022年の推定雇用率:-12%
旅行代理店に行かなくても、ネットで旅行の手配ができるようになったため。
第5位:木材伐採人 2022年の推定雇用率:-9%
技術の進歩のおかげで必要な人材が減ったため。またデジタル化に伴い“紙”の需要が減り、木材パルプの需要も減る一方。
第6位:フライトアテンダント 2022年の推定雇用率:-7%
近年航空会社の経費削減、合併の影響をまともに食らっているのがこの仕事。今後の見通しも暗い。
第7位:ドリル作業員 2022年の推定雇用率:-6%
技術の進歩により、従来より少ないドリルでより多くの作業が可能に。製造業での人員削減が進むとみられる。
第8位:印刷業者 2022年の推定雇用率:-5%
デジタル化により紙製品は減る一方。
第9位:税務調査官及び収税吏 2022年の推定雇用率:-4%
技術の進歩に伴い企業の効率化が進み、税の調査や徴収業務の必要性も減る。
今は誰もがお世話になっているおなじみの職業だが、近いうちになくなるかもしれないものを順にご紹介しよう。
第1位:郵便配達員 2022年の推定雇用率:-28%
Eメールやオンライン請求の普及で郵便物が激減しているため、必要とされる郵便作業員も減る見込み。
第2位:農家 2022年の推定雇用率:-19%
技術の進歩により、少ない人員での作業が可能になったため。
第2位:メーターの計測係 2022年の推定雇用率:-19%
電気、ガス、水道各社は電子計測器の導入を進め、わざわざメーターを見に行かずともデータが送られるようになる。
第3位:新聞記者 2022年の推定雇用率:-13%
オンラインニュースの台頭により、新聞購読者が減り、購読料、広告料共に激減。新聞社が多くの記者を雇うことができなくなる。
第4位:旅行代理店の社員 2022年の推定雇用率:-12%
旅行代理店に行かなくても、ネットで旅行の手配ができるようになったため。
第5位:木材伐採人 2022年の推定雇用率:-9%
技術の進歩のおかげで必要な人材が減ったため。またデジタル化に伴い“紙”の需要が減り、木材パルプの需要も減る一方。
第6位:フライトアテンダント 2022年の推定雇用率:-7%
近年航空会社の経費削減、合併の影響をまともに食らっているのがこの仕事。今後の見通しも暗い。
第7位:ドリル作業員 2022年の推定雇用率:-6%
技術の進歩により、従来より少ないドリルでより多くの作業が可能に。製造業での人員削減が進むとみられる。
第8位:印刷業者 2022年の推定雇用率:-5%
デジタル化により紙製品は減る一方。
第9位:税務調査官及び収税吏 2022年の推定雇用率:-4%
技術の進歩に伴い企業の効率化が進み、税の調査や徴収業務の必要性も減る。