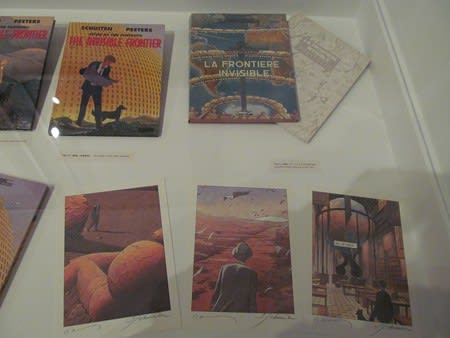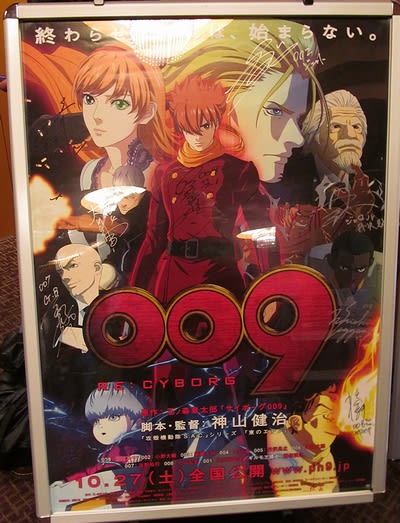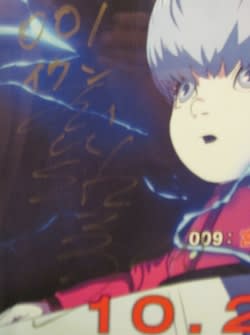昨年は行けなかったので、個人的には2年ぶりのSFセミナーに参加してきました。
本会の企画についてざっくりとしたメモをとってきましたので、参考までにご紹介します。
1. Gene,Meme,Hacking-藤井太洋インタビュウ
個人による電子書籍で出版され、好評を受けて改稿・書籍化を果たした『Gene Mapper』の作者である
藤井太洋さんに、作家でありSF考証等でも知られる堺三保さんがインタビュー。
藤井さんの経歴がかなりユニークで、劇団の舞台美術づくりからMacによるセットデザインを行った後、
食えないのでMacが使えるDTP業に転職、プログラムを書きつつソフトのセールスで世界を飛び回り、
アメリカ出張では大規模農業と環境の問題に触れるといった様々な経験をされています。
まずセルフ電子出版という形態を選んだのも「経験的にできることがわかっていたから」とのことで、
お話の端々に学者や科学ライターなどとは違う「現場経験を積んだエンジニアの気概」を感じました。
好きな作家はクラークやセーガンで、『楽園の泉』や『コンタクト』を愛読したそうですが、これは堺さんの
藤井作品に対する「バチガルピやストロスのペシミズムに対して、地に足のついたオプティミズムを感じる」
との評にも通じるような気がします。
SF作品の話に留まらず、アバターによるコミュニケーションやソフトのオープンソース化による改良などを
早くから予見していたこと、いまの株取引はマイクロセカンドの遅れが致命的なので、回線のソケットに
プログラムを仕込んで売買の自動実行をさせていること(生物の脊髄反射に近いですな)、誰でも知ってる
有名なWebサービスのソースコードに「人間が書いたとは思えない部分がある」といった、実に興味深い話も
聞かせていただきました。
我々の知らない現実は既に存在していて、一握りの人間だけがその現実を見ているのかもしれない。
そんな現実を我々にも可視化してくれるのが、藤井さんの作品なのかも。
昼休みには藤井さんと、はるこんのゲストで来日されたジョー・ホールドマンさんのサイン会が開催されました。
(福武書店版『ヘミングウェイごっこ』を持っていったら、同じ本を持ってる人が何人もいて苦笑い)
2. シスターフッドの時代に
2011年のセンス・オブ・ジェンダー賞受賞作、特に新設のシスターフッド賞についてのパネル対談。
シスターフッドとは女性同士の友情や連帯を指す言葉で、こうした視点から受賞作に選ばれたのが
『終わり続ける世界の中で』と『魔法少女まどか☆マギカ』の2作だそうです。
登壇者はジェンダーSF研幹事の小谷真理さん、選考委員の水島希さん、高世えり子さん、そして受賞作
『終わり続ける世界の中で』の作者である粕谷知世さん。司会はジェンダーSF研の柏崎玲央奈さんです。
両作品の共通点である「まじめな女の子が真剣に物事を考える作品」「女の子同士の友情の物語」について
話が進みましたが、総体としては「まどマギをどう評価すべきか」という議論に集約されてしまう感じもあり。
あとは戦う少女の人工性とメイクアップの関係、力を得た女性が私欲よりも世のために活動する話が多いこと、
少女に戦いを背負わせる社会の束縛感や、戦いとは自分の力で何かを得るための行動では?との指摘など。
今回の企画では『終わり続ける・・・』の作者でありかつての大賞受賞者、そして選考委員も勤めたことのある
粕谷さんが登壇しましたが、まどマギ側の登壇者はなし。
そうした中で両受賞作を比較するのは、欠席裁判ぽくてあんまりいい感じではないなーとも思いました。
特に登壇者のひとりが『終わり続ける・・・』との対比で主に否定的な見解を述べていたのは、一ファンとして
かなり辛かったです。(他の方はまどマギに対し、おおむね好感を持たれていたようですが・・・。)
これなら粕谷さんにじっくりと自作を語ってもらったほうが、気持ちのいい企画になったかもしれない。
シスターフッド賞という名目であれば、作中に登場するまどかの母や女性担任の立場も踏まえたうえで、
女性を生贄とし続ける世界すべてへの異議申し立てという見方まで踏み込んで評価して欲しかった・・・。
さらには魂なき肉体という見地から『接続された女』との類似性を考えるとか、作品を語るための題材は
ほかにもいろいろあると思ってますけどね。
でも小谷真理さんの「なぜ作り手は女の子の関係性をここまでよく知ってるのか?」という指摘には、
思わずヒザを打ちました。
これは虚淵脚本を考える上で、重要なヒントになり得るかもしれない。
余談ですが、今回のセミナーに来場したジョー・ホールドマンさんの『擬態』も、2007年の海外部門で
センス・オブ・ジェンダー賞の候補に挙がってますが、この時の受賞作が『ようこそ女たちの王国へ』・・・。
はっきり言って、私はこの受賞作が苦手です。
だって父権主義を女性版に裏返ししただけの冒険ロマンスで、制度自体の問題点は温存したままに見えるから。
たとえば男子の純潔が重んじられるのも、女性の処女性に置き換えただけであって、純潔性に対する固定観念に
直接切り込もうとする鋭さは見えません。つまりは世界を変えようとする意志が感じられない。
でも娯楽小説のフォーマット上「主人公男子が最後に得た特権性を肯定する」ためには、世界の仕組みなんて
変わらないほうがいいんでしょうねぇ。もし変わってしまえば、彼の得たものも無になっちゃうから。
選評では『大奥』と比較されてるけど、男女逆転が社会制度を変革し、他方では合理的に制度が温存される
『大奥』の巧みな構成と比較するのは・・・おっと、イベントのレポートと関係ない話になっちゃいました。
まあ男の目線から見た上でのたわごとなので、あんまり気にしないでください(^^;
3. 海中ロボットの現在と未来-鉄腕アトムは海から生まれる
世界的ベストセラー『深海のYrr』にも登場する自律型海中ロボットの生みの親である浦環先生が、
海中ロボットの現在から未来までを熱く語る企画。
ザトウクジラの歌を聞きわけて自動的に追跡するロボット、水中で一定の位置をキープしながら移動して
対象物の周囲を自動観察するロボットなど、すごいメカが次々に紹介されました。
浦さんの弁舌も歯切れよく、研究者としての理想と現実的な開発理念の対比もおもしろかったです。
「研究者に必要なのは、実際にやって見せること」
「有線ロボットなんてつまらない」
「自分は全自動ロボしか研究しないし、学生にもそれしか研究させない!」
「ロボットの価値は人間の役に立つかで決まる」など、数々の名言も披露。
そして浦さんの夢は、深海で海中資源を採掘し供給する人間不可侵の「ロボット帝国」を樹立すること・・・。
これを聞いて「天馬博士でもお茶の水博士でもなく、ララーシュタイン博士だったのか!」と思ったのは、
私だけでしょうか(^^;
4. ライブ版SFスキャナー・ダークリー
翻訳家・アンソロジストとして勇名をはせる中村融さんに、SFとの出会いから同人誌の製作、さらには
翻訳技術からアンソロジーの編み方までをうかがうもの。
聞き手はSFレビュアーにして中村門下の翻訳者としてもデビュー予定の橋本輝幸さんと、法政大学で
「一人SF研究会」として気を吐く茅野隼也さんです。
これは比較的まめにメモをとってきましたが、話の内容がいくつかに分かれるので、簡単に整理してご紹介。
中村さんのブログ「SFスキャナー・ダークリー」に記事があるものは、一部リンクを張っておきます。
【ファンタジーと同人誌】
SFマガジンで「夢みる都」を読んでエルリックにハマったものの、2作だけで続きが出なかったので
コナンからトールキンへと手を伸ばし、やがてファンタジー同人誌の名門「ローラリアス」に入会。
しかし原稿を送ってもなかなか掲載されず、しびれを切らして初の個人誌を作ってしまった。
(橋本さんが質問した自作小説やムーングラムのコスプレ疑惑については「別人でしょ!」と全力で否定)
【原書と翻訳】
翻訳SFファンは原書に憧れるので、シルヴァーバーグ編のアンソロジー(Alpha 5)を買った。
高校時代の3年かけて読めなかったが、3年目にライバーのYesterday houseが読めてしまった。
最初に読みきった長編は、コルム三部作の合本版。
ファン出版のTHATTA文庫でヴァンスの短編(五つの月が昇るとき)を訳したのがきっかけで、
白石朗さんから浅倉久志さんへとつながって翻訳者デビューできた。すべてはヴァンスのおかげ。
翻訳を仕事にすると日本語の話や小説は読まなくなって、主にノンフィクションを読んでいる。
翻訳は自己表現。やればやるほどうまくなるので、楽しくなる。
他人に誇れる翻訳は『ブラッドベリ年代記』。
(橋本さんから「一人称の訳し方は?」)読み始めは単なるI(アイ)でも、進めていくうちにだんだんと
人称が決まってくる。それでもブレが出てきてしまうときは、訳すときに人称を全部とってしまうこともある。
翻訳中に主語や語尾の表記を軌道修正する場合もあるが、まれに直し損ねた部分が残ってしまうことも。
【ホラーSFアンソロジー『影が行く』】
90年代は翻訳アンソロジーが出ない、出せない時期。
それをなんとかしたかったので、翻訳者として実績ができたころに東京創元社の小浜さんに相談したら
企画を任せてくれた。
名作ではないが読みたい、復活させたい作品として「影が行く」と「ヨー・ヴォムビスの地下墓地」を軸に、
ホラーなので13編に絞るまで5倍ほどの作品を検討した。
(ここで中学生時代から現在までつけているという、「読書ノート」の映像が登場。初出年、話の長さ、
5点評価のデータが書かれている。)
読書ノートで4点以上の作品を選べばすぐに作品が集まるが、いま読み返すと3プラスや3Aがついている、
「点数だけでなく何かひっかかりを感じた作品」のほうに残るものがある。
読書ノートは小説、雑誌、海外を合わせると、全部で30冊ほど。
SFホラーとしてマイクル・シェイの「検視」と、マーティンの「サンドキングズ」も収録したかったが、
版権の都合で収録できず。
代わりに収録したのが巻末のオールディス「唾の樹」だが、これが好評だった。(私も大好きです。)
ナイトの「仮面」は、わざとテーマから外して選んだ変化球。
これは作者の註入り版を使って訳したが、優秀な作家の考え方がわかって勉強になった。
アンソロジーを編むとき、傑作ばかり選ぶとべったりしておもしろくない。
(茅野さんから「引き立て役はシオドア・L・トーマスの「群体」ですか?」)そのとおり。
アンソロジーにはでこぼこが必要で、並び順が最も重要。並び順に命を懸けているとも言える。
【翻訳者兼アンソロジストとして】
ウォルハイム&カーの年刊傑作選が好き。頑固オヤジと尖った若造の両極端な組み合わせがいい。
いまやってみたいのは、ドゾワ&ダンによるアンソロジーの日本版。扶桑社から邦訳がいくつか出ているが、
意識しているのは「ALIENS!」と「ALIEN AMONG US」。
他のアンソロジーを読むと対抗心が湧く。
退化文化の話が好き。ハワードのキング・カルは暗い話だが、マッケンのピクト人論に影響を受けていると思う。
原書を読んでいい作品に当たる打率は、10本に1本ぐらい。
(橋本さん「原書のジャケ買いは?」)たまにするけど、まず失敗する。
アル・サラントニオ編の「MOONBANE」は表紙でワクワクしたけど、中味は想像以上にくだらない話だった。
今後の仕事としては、まず創元推理文庫の新訂版コナン全集が完結する。
創元SF文庫からは『時の娘』の続編的な時間SFアンソロジー『時を生きる種族』が出る予定。
これにはムアコックの表題作に加えて、T・L・シャーレッドの隠れた名作「努力」や、ヤングの中篇
「真鍮の都」を収録する。
ウルトラQが好きで、大伴昌司編の『世界SF名作集』を入口にSFを読み始め、SFマガジンは74年の
2月号から購読、次の号でティプトリーの初邦訳に接するといった流れは、ある世代のSFファンにとって
共感する部分も多かったはず。
そうした歴史を若手SF者として期待されるお二人が聞く・・・という図式も楽しかったです。
まるで世代を超えるSF魂の伝授式のようにも見えて、なんだかぐっとくるものもありました。
本会企画はこれにて終了。自分の好きなジャンルは海外SFですが、企画全体に発見や驚きがありました。
一部釈然としない部分についても、自分なりに考えるネタにはなりましたし(^^;
この後は合宿に舞台を移しての延長戦や場外戦もありましたが、それはまたの機会に。
本会の企画についてざっくりとしたメモをとってきましたので、参考までにご紹介します。
1. Gene,Meme,Hacking-藤井太洋インタビュウ
個人による電子書籍で出版され、好評を受けて改稿・書籍化を果たした『Gene Mapper』の作者である
藤井太洋さんに、作家でありSF考証等でも知られる堺三保さんがインタビュー。
藤井さんの経歴がかなりユニークで、劇団の舞台美術づくりからMacによるセットデザインを行った後、
食えないのでMacが使えるDTP業に転職、プログラムを書きつつソフトのセールスで世界を飛び回り、
アメリカ出張では大規模農業と環境の問題に触れるといった様々な経験をされています。
まずセルフ電子出版という形態を選んだのも「経験的にできることがわかっていたから」とのことで、
お話の端々に学者や科学ライターなどとは違う「現場経験を積んだエンジニアの気概」を感じました。
好きな作家はクラークやセーガンで、『楽園の泉』や『コンタクト』を愛読したそうですが、これは堺さんの
藤井作品に対する「バチガルピやストロスのペシミズムに対して、地に足のついたオプティミズムを感じる」
との評にも通じるような気がします。
SF作品の話に留まらず、アバターによるコミュニケーションやソフトのオープンソース化による改良などを
早くから予見していたこと、いまの株取引はマイクロセカンドの遅れが致命的なので、回線のソケットに
プログラムを仕込んで売買の自動実行をさせていること(生物の脊髄反射に近いですな)、誰でも知ってる
有名なWebサービスのソースコードに「人間が書いたとは思えない部分がある」といった、実に興味深い話も
聞かせていただきました。
我々の知らない現実は既に存在していて、一握りの人間だけがその現実を見ているのかもしれない。
そんな現実を我々にも可視化してくれるのが、藤井さんの作品なのかも。
昼休みには藤井さんと、はるこんのゲストで来日されたジョー・ホールドマンさんのサイン会が開催されました。
(福武書店版『ヘミングウェイごっこ』を持っていったら、同じ本を持ってる人が何人もいて苦笑い)
2. シスターフッドの時代に
2011年のセンス・オブ・ジェンダー賞受賞作、特に新設のシスターフッド賞についてのパネル対談。
シスターフッドとは女性同士の友情や連帯を指す言葉で、こうした視点から受賞作に選ばれたのが
『終わり続ける世界の中で』と『魔法少女まどか☆マギカ』の2作だそうです。
登壇者はジェンダーSF研幹事の小谷真理さん、選考委員の水島希さん、高世えり子さん、そして受賞作
『終わり続ける世界の中で』の作者である粕谷知世さん。司会はジェンダーSF研の柏崎玲央奈さんです。
両作品の共通点である「まじめな女の子が真剣に物事を考える作品」「女の子同士の友情の物語」について
話が進みましたが、総体としては「まどマギをどう評価すべきか」という議論に集約されてしまう感じもあり。
あとは戦う少女の人工性とメイクアップの関係、力を得た女性が私欲よりも世のために活動する話が多いこと、
少女に戦いを背負わせる社会の束縛感や、戦いとは自分の力で何かを得るための行動では?との指摘など。
今回の企画では『終わり続ける・・・』の作者でありかつての大賞受賞者、そして選考委員も勤めたことのある
粕谷さんが登壇しましたが、まどマギ側の登壇者はなし。
そうした中で両受賞作を比較するのは、欠席裁判ぽくてあんまりいい感じではないなーとも思いました。
特に登壇者のひとりが『終わり続ける・・・』との対比で主に否定的な見解を述べていたのは、一ファンとして
かなり辛かったです。(他の方はまどマギに対し、おおむね好感を持たれていたようですが・・・。)
これなら粕谷さんにじっくりと自作を語ってもらったほうが、気持ちのいい企画になったかもしれない。
シスターフッド賞という名目であれば、作中に登場するまどかの母や女性担任の立場も踏まえたうえで、
女性を生贄とし続ける世界すべてへの異議申し立てという見方まで踏み込んで評価して欲しかった・・・。
さらには魂なき肉体という見地から『接続された女』との類似性を考えるとか、作品を語るための題材は
ほかにもいろいろあると思ってますけどね。
でも小谷真理さんの「なぜ作り手は女の子の関係性をここまでよく知ってるのか?」という指摘には、
思わずヒザを打ちました。
これは虚淵脚本を考える上で、重要なヒントになり得るかもしれない。
余談ですが、今回のセミナーに来場したジョー・ホールドマンさんの『擬態』も、2007年の海外部門で
センス・オブ・ジェンダー賞の候補に挙がってますが、この時の受賞作が『ようこそ女たちの王国へ』・・・。
はっきり言って、私はこの受賞作が苦手です。
だって父権主義を女性版に裏返ししただけの冒険ロマンスで、制度自体の問題点は温存したままに見えるから。
たとえば男子の純潔が重んじられるのも、女性の処女性に置き換えただけであって、純潔性に対する固定観念に
直接切り込もうとする鋭さは見えません。つまりは世界を変えようとする意志が感じられない。
でも娯楽小説のフォーマット上「主人公男子が最後に得た特権性を肯定する」ためには、世界の仕組みなんて
変わらないほうがいいんでしょうねぇ。もし変わってしまえば、彼の得たものも無になっちゃうから。
選評では『大奥』と比較されてるけど、男女逆転が社会制度を変革し、他方では合理的に制度が温存される
『大奥』の巧みな構成と比較するのは・・・おっと、イベントのレポートと関係ない話になっちゃいました。
まあ男の目線から見た上でのたわごとなので、あんまり気にしないでください(^^;
3. 海中ロボットの現在と未来-鉄腕アトムは海から生まれる
世界的ベストセラー『深海のYrr』にも登場する自律型海中ロボットの生みの親である浦環先生が、
海中ロボットの現在から未来までを熱く語る企画。
ザトウクジラの歌を聞きわけて自動的に追跡するロボット、水中で一定の位置をキープしながら移動して
対象物の周囲を自動観察するロボットなど、すごいメカが次々に紹介されました。
浦さんの弁舌も歯切れよく、研究者としての理想と現実的な開発理念の対比もおもしろかったです。
「研究者に必要なのは、実際にやって見せること」
「有線ロボットなんてつまらない」
「自分は全自動ロボしか研究しないし、学生にもそれしか研究させない!」
「ロボットの価値は人間の役に立つかで決まる」など、数々の名言も披露。
そして浦さんの夢は、深海で海中資源を採掘し供給する人間不可侵の「ロボット帝国」を樹立すること・・・。
これを聞いて「天馬博士でもお茶の水博士でもなく、ララーシュタイン博士だったのか!」と思ったのは、
私だけでしょうか(^^;
4. ライブ版SFスキャナー・ダークリー
翻訳家・アンソロジストとして勇名をはせる中村融さんに、SFとの出会いから同人誌の製作、さらには
翻訳技術からアンソロジーの編み方までをうかがうもの。
聞き手はSFレビュアーにして中村門下の翻訳者としてもデビュー予定の橋本輝幸さんと、法政大学で
「一人SF研究会」として気を吐く茅野隼也さんです。
これは比較的まめにメモをとってきましたが、話の内容がいくつかに分かれるので、簡単に整理してご紹介。
中村さんのブログ「SFスキャナー・ダークリー」に記事があるものは、一部リンクを張っておきます。
【ファンタジーと同人誌】
SFマガジンで「夢みる都」を読んでエルリックにハマったものの、2作だけで続きが出なかったので
コナンからトールキンへと手を伸ばし、やがてファンタジー同人誌の名門「ローラリアス」に入会。
しかし原稿を送ってもなかなか掲載されず、しびれを切らして初の個人誌を作ってしまった。
(橋本さんが質問した自作小説やムーングラムのコスプレ疑惑については「別人でしょ!」と全力で否定)
【原書と翻訳】
翻訳SFファンは原書に憧れるので、シルヴァーバーグ編のアンソロジー(Alpha 5)を買った。
高校時代の3年かけて読めなかったが、3年目にライバーのYesterday houseが読めてしまった。
最初に読みきった長編は、コルム三部作の合本版。
ファン出版のTHATTA文庫でヴァンスの短編(五つの月が昇るとき)を訳したのがきっかけで、
白石朗さんから浅倉久志さんへとつながって翻訳者デビューできた。すべてはヴァンスのおかげ。
翻訳を仕事にすると日本語の話や小説は読まなくなって、主にノンフィクションを読んでいる。
翻訳は自己表現。やればやるほどうまくなるので、楽しくなる。
他人に誇れる翻訳は『ブラッドベリ年代記』。
(橋本さんから「一人称の訳し方は?」)読み始めは単なるI(アイ)でも、進めていくうちにだんだんと
人称が決まってくる。それでもブレが出てきてしまうときは、訳すときに人称を全部とってしまうこともある。
翻訳中に主語や語尾の表記を軌道修正する場合もあるが、まれに直し損ねた部分が残ってしまうことも。
【ホラーSFアンソロジー『影が行く』】
90年代は翻訳アンソロジーが出ない、出せない時期。
それをなんとかしたかったので、翻訳者として実績ができたころに東京創元社の小浜さんに相談したら
企画を任せてくれた。
名作ではないが読みたい、復活させたい作品として「影が行く」と「ヨー・ヴォムビスの地下墓地」を軸に、
ホラーなので13編に絞るまで5倍ほどの作品を検討した。
(ここで中学生時代から現在までつけているという、「読書ノート」の映像が登場。初出年、話の長さ、
5点評価のデータが書かれている。)
読書ノートで4点以上の作品を選べばすぐに作品が集まるが、いま読み返すと3プラスや3Aがついている、
「点数だけでなく何かひっかかりを感じた作品」のほうに残るものがある。
読書ノートは小説、雑誌、海外を合わせると、全部で30冊ほど。
SFホラーとしてマイクル・シェイの「検視」と、マーティンの「サンドキングズ」も収録したかったが、
版権の都合で収録できず。
代わりに収録したのが巻末のオールディス「唾の樹」だが、これが好評だった。(私も大好きです。)
ナイトの「仮面」は、わざとテーマから外して選んだ変化球。
これは作者の註入り版を使って訳したが、優秀な作家の考え方がわかって勉強になった。
アンソロジーを編むとき、傑作ばかり選ぶとべったりしておもしろくない。
(茅野さんから「引き立て役はシオドア・L・トーマスの「群体」ですか?」)そのとおり。
アンソロジーにはでこぼこが必要で、並び順が最も重要。並び順に命を懸けているとも言える。
【翻訳者兼アンソロジストとして】
ウォルハイム&カーの年刊傑作選が好き。頑固オヤジと尖った若造の両極端な組み合わせがいい。
いまやってみたいのは、ドゾワ&ダンによるアンソロジーの日本版。扶桑社から邦訳がいくつか出ているが、
意識しているのは「ALIENS!」と「ALIEN AMONG US」。
他のアンソロジーを読むと対抗心が湧く。
退化文化の話が好き。ハワードのキング・カルは暗い話だが、マッケンのピクト人論に影響を受けていると思う。
原書を読んでいい作品に当たる打率は、10本に1本ぐらい。
(橋本さん「原書のジャケ買いは?」)たまにするけど、まず失敗する。
アル・サラントニオ編の「MOONBANE」は表紙でワクワクしたけど、中味は想像以上にくだらない話だった。
今後の仕事としては、まず創元推理文庫の新訂版コナン全集が完結する。
創元SF文庫からは『時の娘』の続編的な時間SFアンソロジー『時を生きる種族』が出る予定。
これにはムアコックの表題作に加えて、T・L・シャーレッドの隠れた名作「努力」や、ヤングの中篇
「真鍮の都」を収録する。
ウルトラQが好きで、大伴昌司編の『世界SF名作集』を入口にSFを読み始め、SFマガジンは74年の
2月号から購読、次の号でティプトリーの初邦訳に接するといった流れは、ある世代のSFファンにとって
共感する部分も多かったはず。
そうした歴史を若手SF者として期待されるお二人が聞く・・・という図式も楽しかったです。
まるで世代を超えるSF魂の伝授式のようにも見えて、なんだかぐっとくるものもありました。
本会企画はこれにて終了。自分の好きなジャンルは海外SFですが、企画全体に発見や驚きがありました。
一部釈然としない部分についても、自分なりに考えるネタにはなりましたし(^^;
この後は合宿に舞台を移しての延長戦や場外戦もありましたが、それはまたの機会に。