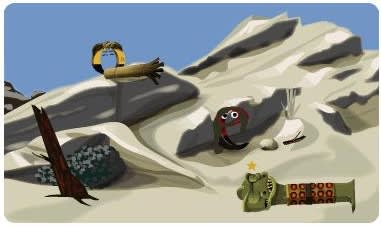六本木の森美術館で10月6日から始まった『荒木飛呂彦原画展「ジョジョ展」』を観てきました。
六本木ヒルズに着くと、偶然にも『ジョジョ展』と『リンカーン:秘密の書』の奇妙なコラボが実現中。

そういえばどちらの作品も、「吸血鬼と戦うヒーローの物語」という共通点がありました(^^;。
入場時間指定制なので、ほぼ指定どおりに到着したのですが、結局は入場待ちの行列に並ぶ羽目に。
入れ替え制ではないため、先に入った人が減ってくるまで入場制限がかかるそうです。
一緒に並んでいる人の中には、ジョジョの擬音を描きこんだストッキングを履いている女性や
ジョジョスマホを操作してる人の姿もあったりして、皆さん意気込みが半端じゃありません。
こういう人ばっかりが集まってるんだから、入場者がなかなか出てこないのも当たり前ですね。
結局エレベーターに乗るまで小一時間並び、52階に上がってからさらに20分ほど待たされて、
1時間半後にようやく展示会場に入れました。
写真を撮れるのは入口の展示タイトルと、一緒に置いてある鑑賞時の注意書きだけ。

しかしこの「ペット」、どこかで見たシルエットですが…?

展示会場には『魔少年ビーティー』『バオー来訪者』『ゴージャス・アイリン』そして『ジョジョの奇妙な冒険』
第一部から、最新作『ジョジョリオン』までのカラーイラスト、さらにルーブル展や「SPUR」で使用された
カラー原画、そしてこの展覧会のために荒木先生が描きおろした新作が飾られています。
『ジョジョ』は連載第一回のカラーページ原画がまるまる全部展示されているほか、各種のキャンペーンや
関連商品のために描かれたカラー原画も網羅しています。
さらに『ジョジョリオン』は2012年10月号掲載分まで展示されているので、荒木先生のデビュー当時から
最新の作風までを、一気に鑑賞することができるという充実ぶり。
まさに荒木先生の漫画家としての歩みを一望できる、ゴージャスでグレイトな展覧会でした。
この手の企画だと、アニメ関係の原画とか映像コーナーを入れて中だるみになる場合も多いのですが、
今回はそういうこともなく、純粋に荒木先生の原画を見せることに徹しているのが良いところ。
おかげでどっぷりと荒木ワールドの魅力に浸ることができました。
しかし生で見る原画は、やっぱりイイものですねぇ。
線の強弱や色の鮮やかさ、つぶれがちな細部の描写をよくみることができました。
印刷物よりサイズも大きいので、キャラクターやスタンドが画面から飛び出してくるような迫力で
鑑賞者に力強く迫ってきます。
会場自体のディスプレイも凝っていて、壁に擬音がプリントされていたり、物語の舞台を模した
石造りのアーチや金網などが設置されています。
さらにキャラクターの等身大フィギュアや石仮面、「ホワイトスネイク」の抜き取ったディスク、
「スティッキィ・フィンガーズ」が開けた巨大なジッパーなど、原画の鑑賞を妨げない程度で
作品世界を体験させるような趣向も凝らされており、まさにいたれりつくせりな感じ。
原画はともかく、立体物は写真撮らせてくれても良さそうなものだと思いましたが、それをやったら
ただでさえ混んでる会場が収集つかなくなるのは明らかなので、まあ仕方がないのかもしれません。
…でもステッキィ・フィンガーズの通り抜けられるジッパーだけは、記念撮影をしたかったなぁ。
備え付けのiPadでスタンドを写したり、来場者がマンガの中に入り込んだような写真が撮れる
AR体験も、なかなか面白い試みでした。
個人的には、杜王町の地図と連動させたストーリー回想がよかったと思います。
チャンスがあれば、次は仙台市内でこれを実現させて欲しいものです。
入場までは結構待ちますが、入ってしまえば結構快適に鑑賞できます。
ただし人がひっきりなしに来るので、絵をじっくりと観るのはさすがに難しいですね。
それでも作品数が多いので、見終わるまで優に2時間以上はかかると思います。
さらに入場待ちと特設ショップでの時間も含め、全体で4時間は見ておくべきでしょう。
さて、図録などを買って特設ショップを出ると、廊下もジョジョ仕様になってました。

そしてエレベーターで下に降りると、そちらのグッズショップもすっかりジョジョ仕様に。(笑)

超像可動やスタチューレジェンドがずらりと並ぶショーケースは、もう一つの見どころです。
超像可動の岸部露伴Ver.2、通常版と会場限定版が揃って飾られていました。

こちらは抽選限定購入のスワロフスキー版露伴。
まさに「ゴージャスッ!」と呼ぶにふさわしいキラキラっぷりです。

そして、2012年夏のワンフェスで販売されたゴールドエクスペリエンス。

こちらはさらにゴージャスッ!
さすがにスワロフスキー版は売ってませんが、展示されているフィギュアの一部は
こちらのショップで買うことができます。
そして帰りの電車に乗ろうとしたら、駅にも巨大な「ジョジョ展」の看板がありました。

日付のレイアウトとか、ファッションブランドの広告を意識してるようにも見えますね。
「ジョジョ展」の会期は11月4日まで。
ジョジョファンだけでなく、マンガとポップカルチャーを愛する全ての人に見て欲しい展覧会です。
ただし土・日・祝日の指定入場券は既に売り切れなので、ご注意ください。
六本木ヒルズに着くと、偶然にも『ジョジョ展』と『リンカーン:秘密の書』の奇妙なコラボが実現中。

そういえばどちらの作品も、「吸血鬼と戦うヒーローの物語」という共通点がありました(^^;。
入場時間指定制なので、ほぼ指定どおりに到着したのですが、結局は入場待ちの行列に並ぶ羽目に。
入れ替え制ではないため、先に入った人が減ってくるまで入場制限がかかるそうです。
一緒に並んでいる人の中には、ジョジョの擬音を描きこんだストッキングを履いている女性や
ジョジョスマホを操作してる人の姿もあったりして、皆さん意気込みが半端じゃありません。
こういう人ばっかりが集まってるんだから、入場者がなかなか出てこないのも当たり前ですね。
結局エレベーターに乗るまで小一時間並び、52階に上がってからさらに20分ほど待たされて、
1時間半後にようやく展示会場に入れました。
写真を撮れるのは入口の展示タイトルと、一緒に置いてある鑑賞時の注意書きだけ。

しかしこの「ペット」、どこかで見たシルエットですが…?

展示会場には『魔少年ビーティー』『バオー来訪者』『ゴージャス・アイリン』そして『ジョジョの奇妙な冒険』
第一部から、最新作『ジョジョリオン』までのカラーイラスト、さらにルーブル展や「SPUR」で使用された
カラー原画、そしてこの展覧会のために荒木先生が描きおろした新作が飾られています。
『ジョジョ』は連載第一回のカラーページ原画がまるまる全部展示されているほか、各種のキャンペーンや
関連商品のために描かれたカラー原画も網羅しています。
さらに『ジョジョリオン』は2012年10月号掲載分まで展示されているので、荒木先生のデビュー当時から
最新の作風までを、一気に鑑賞することができるという充実ぶり。
まさに荒木先生の漫画家としての歩みを一望できる、ゴージャスでグレイトな展覧会でした。
この手の企画だと、アニメ関係の原画とか映像コーナーを入れて中だるみになる場合も多いのですが、
今回はそういうこともなく、純粋に荒木先生の原画を見せることに徹しているのが良いところ。
おかげでどっぷりと荒木ワールドの魅力に浸ることができました。
しかし生で見る原画は、やっぱりイイものですねぇ。
線の強弱や色の鮮やかさ、つぶれがちな細部の描写をよくみることができました。
印刷物よりサイズも大きいので、キャラクターやスタンドが画面から飛び出してくるような迫力で
鑑賞者に力強く迫ってきます。
会場自体のディスプレイも凝っていて、壁に擬音がプリントされていたり、物語の舞台を模した
石造りのアーチや金網などが設置されています。
さらにキャラクターの等身大フィギュアや石仮面、「ホワイトスネイク」の抜き取ったディスク、
「スティッキィ・フィンガーズ」が開けた巨大なジッパーなど、原画の鑑賞を妨げない程度で
作品世界を体験させるような趣向も凝らされており、まさにいたれりつくせりな感じ。
原画はともかく、立体物は写真撮らせてくれても良さそうなものだと思いましたが、それをやったら
ただでさえ混んでる会場が収集つかなくなるのは明らかなので、まあ仕方がないのかもしれません。
…でもステッキィ・フィンガーズの通り抜けられるジッパーだけは、記念撮影をしたかったなぁ。
備え付けのiPadでスタンドを写したり、来場者がマンガの中に入り込んだような写真が撮れる
AR体験も、なかなか面白い試みでした。
個人的には、杜王町の地図と連動させたストーリー回想がよかったと思います。
チャンスがあれば、次は仙台市内でこれを実現させて欲しいものです。
入場までは結構待ちますが、入ってしまえば結構快適に鑑賞できます。
ただし人がひっきりなしに来るので、絵をじっくりと観るのはさすがに難しいですね。
それでも作品数が多いので、見終わるまで優に2時間以上はかかると思います。
さらに入場待ちと特設ショップでの時間も含め、全体で4時間は見ておくべきでしょう。
さて、図録などを買って特設ショップを出ると、廊下もジョジョ仕様になってました。

そしてエレベーターで下に降りると、そちらのグッズショップもすっかりジョジョ仕様に。(笑)

超像可動やスタチューレジェンドがずらりと並ぶショーケースは、もう一つの見どころです。
超像可動の岸部露伴Ver.2、通常版と会場限定版が揃って飾られていました。

こちらは抽選限定購入のスワロフスキー版露伴。
まさに「ゴージャスッ!」と呼ぶにふさわしいキラキラっぷりです。

そして、2012年夏のワンフェスで販売されたゴールドエクスペリエンス。

こちらはさらにゴージャスッ!
さすがにスワロフスキー版は売ってませんが、展示されているフィギュアの一部は
こちらのショップで買うことができます。
そして帰りの電車に乗ろうとしたら、駅にも巨大な「ジョジョ展」の看板がありました。

日付のレイアウトとか、ファッションブランドの広告を意識してるようにも見えますね。
「ジョジョ展」の会期は11月4日まで。
ジョジョファンだけでなく、マンガとポップカルチャーを愛する全ての人に見て欲しい展覧会です。
ただし土・日・祝日の指定入場券は既に売り切れなので、ご注意ください。