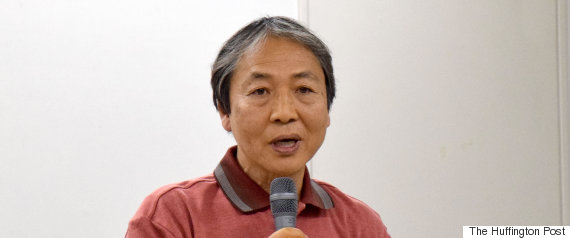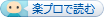投稿日: 2015年02月19日 07時49分 JST 更新: 2015年02月19日 08時49分 JST
国際ジャーナリストの後藤健二さんが過激派組織ダーイシュ(イスラム国)に殺害された事件や、フリーカメラマンの杉本祐一さんのパ スポートが返納命令を受けた問題が起きている中で、戦地を取材してきたジャーナリストらが2月17日、危険地域を取材する意義について考える緊急シンポジ ウムを都内で開催した。
自 民党の高村正彦副総裁が後藤さんについて、「どんなに使命感があったとしても、蛮勇というべきものであった」と述べるなど、戦場を取材するジャーナリスト への批判が強まるなか、シンポジウムには学生ら約140人が参加。登壇したジャーナリストらとともに、その仕事の内容や課題について活発に意見交換がなさ れた。以下にシンポジウムの様子をレポートする。

川上泰徳さん
■ジャーナリストは必要な仕事なのか
ジャーナリストの存在意義について、元朝日新聞中東アフリカ総局長の川上泰徳さんは、「現地に行かないとわからないことがある」として、2003年に起きたイラク日本人外交官射殺事件を引き合いに出した。
こ の事件は、イラクへ派遣されていた日本人外交官2人が、イラク北部のティクリートという危険な町で射殺されたというもの。川上さんによると、事件当初にア メリカ軍からもたらされた情報では、2人はこの町を自動車で走行している際に、何かしらの事情で車から降りた時に撃たれたとのことだった。
し かし現場に行ってみると、車の轍(わだち)が畑の中に一直線上に伸びており、明らかに走行中に撃たれ、そのまま畑に突っ込んだと考えられる状態だった。そ れを見た川上さんは「アメリカ軍の情報は嘘だ」と考えたと話し、政府側がもたらす情報をジャーナリズムが検証する必要性を訴えた。
川上さんはさらに、パレスチナのガザ地区を支配するハマスに、国連が接触できない例も紹介した。
「役 所とは不自由なところで、渡航禁止措置などを取ると、外交官もその地域に入れなくなってしまう。ガザ地区の代表の話では、国連はハマスとコンタクトができ ないという。国連がハマスを認めていないためだ。ジャーナリストであれば、その制限はないから、『なぜそんなことをしているのか』などと聞くことができ る」

藤原亮司さん
■「戦場にも、生活する人がいる」
パレスチナやシリアなど中東各地で取材を続けてきた藤原亮司さんは、戦場を取材する意義について、「現地で生活している人がいる。それを伝えるためだ」と強調した。
藤 原さんは後藤さんの事件を挙げ、「戦争は人がいない特別な場所で起こっているわけではなく、人がいるところで起きている。ご飯を食べたり、子供を叱ったり という生活と一緒に、戦闘がある。その生活が理不尽に奪われていることを、後藤さんは伝えるためにシリアに行ったはずなのに、その本質とは離れ、安倍政権 の対応などが議論されている。なぜ後藤さんが、シリアのような危険と呼ばれている場所に取材をしに行かなくてはいけなかったのかを考えるべきだ」と話し た。
35年に渡り戦場を取材してきたジャパンプレス代表の佐藤和孝さんは、シリアで負傷したフランス人ジャーナリストの言葉を紹介した。
「ジャーナリストが命をかけて伝えなくてはいけないものはあるでしょうかと聞いたとき、このフランス人ジャーナリストは次のように答えた。
『私はこの仕事で、起きたことを伝えていかなければならないと思っている。そうしなければ、言論の自由が消滅してしまう。独裁者がシリアのように横行し、市民を虐殺するだろう』
また、彼にこの仕事とは必要かと聞くと『絶対に必要。圧制者に対する反対勢力だから。この仕事がなくなれば、圧制者が横行するだろう。そして、民主主義が消滅する。残虐で独裁的な主導者たちがしていることを伝えるために、私たちがいる』と返ってきた」
■誤解をされるような報じ方がされている
しかし、報道によっては、ジャーナリストに対して誤解を生むような場合もある。後藤さんとも親交があったというジャーナリストの安田純平さんは、後藤さんについての報道を次のように指摘した。
「『後 藤さんは、子供や女性を取り上げており、素晴らしかったです』というような報道がされるが、彼がシリアで撮っていたのは、アサド政権の空爆の被害者だっ た。後藤さんは、誰が何をやり、誰が死んでいるのかを具体的にレポートしたのに、『女性たちは大変なんです』というような一般論でまとめられた。これは、 侮辱だと思った。
我々がやっていることは、具体的にそこに何があるのかを伝えるのが仕事であり、それを一般論にしないというのが、取材する側の大事なところだ」

安田純平さん
■「ジャーナリストが起こすミスの検証が必要」
参 加者からは、「なぜ後藤さんの事件が起ったのか、後藤さんはミスを犯さなかったのかをジャーナリスト側が検証し、それを伝えていないことにも問題がある」 との指摘が出た。企業が不祥事を起こすと報道が一斉に報じ、それによって企業側はきっちり検証する。これに対して、ジャーナリストは同業者に甘いのではな いかというのだ。
後藤さんの事件については、安田さんは「後藤さんが『イスラム国』に入った方法はイレギュラーなやり方であり、我々として はちょっと考えられないやり方だ。2億ドル積まれたってやらない。余程の背景があったんだと思う。どういう背景があって入ったのか検証すべきだ」と述べ た。
安田さんによると、「『イスラム国』は、支配地域に入った外国人をかたっぱしから捕まえる」のだという。そして、捉えた人の出身国に よって、交渉内容を変える。ダーイシュの支配地域に安全に入るには、「まるでビザを発行してもらうように」ダーイシュ側から入国許可を受けなければならな い。「現在日本人で安全に入るには、(元同志社大教授の)中田考氏のような『イスラム国』から身元保証を受けている人と一緒に入るしか、方法がないのだ」 と安田さんは話した。
安田さんは、「今回は既に、『イスラム国』に入った経験がある人が日本におり、現地の人でも中に入るのは難しいと言っ ていた。それでも後藤さんは入った。後藤さんが使ったとされる現地ガイドについても、情報を持っているジャーナリストが日本にいた。ジャーナリストの横の つながりについても、検証すべき」とした。
司会を務めた早稲田大学教授の野中章弘さんは、「ミスはゼロにできるわけではない。ロバート・キャパも、地雷を踏んで亡くなった。しかし、プロのジャーナリストは、ミスを極限まで減らそうとする。それをどこまで減らせるのかと、徹底的に検証しなくてはいけない」と話した。

野中章弘さん
■「政府は我々に判断させないようにしている」
一方で安田さんは、取材先のリスクについては、政府が判断するべきではないとして、「危険だということを一括りに扱うべきではなく、政府はもっと具体的に情報を出して、国民に判断させるべきだ」と指摘した。
「先日、イラクの北部で日本人旅行者が(ダーイシュと闘っている)クルド自治政府に拘束されたと報じられた。これに対して官房長官が『一歩間違えば大変な自体になった』などと話したというが、どこでどう捕まって、なぜ危険なのかは説明がされておらず、ただなんとなく危ないからという理由で渡航を制限している。
また、杉本さんが行きたいといっていたのは、コバニと いうところだ。朝日新聞も行った場所だが、『危ない』と批判された。コバニは『イスラム国』勢力を追い返したクルド勢力によるプレスツアーで行けるところ だ。クルド勢力は最大の護衛を付けて、ここを勝ち取ったんだとアピールしたい場所でもある。そんな場所で、どうやって『イスラム国』の人質になるのか。
リ スクは確かにゼロではないが、危険に関しては、政府は具体的な内容を出すべきだ。その内容を知れば、国民の側も危ないのか危なくないかを判断できる。国は 国民に判断させないようにしている。『全部国が決めるのだから、黙って聞きなさい』ということになっており、それでいいんじゃないのという反応も増えてい る。それが危険だと思う。
すべての国民は、自分の頭で判断し、政府がやろうとしていることが妥当かそうではないかを判断しなくてはいけない。危険だから、全て情報を取るのは国に任せてしまおうというのは、民主主義の放棄だ」
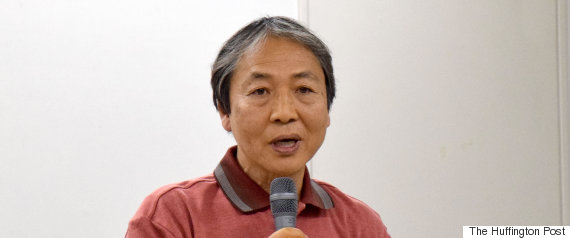
関野吉晴さん
■「もう日本の旗は、掲げられなくなった」
政策が及ぼす影響について、探検家の関野吉晴さんはコロンビアにおけるサイクリストの事例をあげて解説した。
コロンビアは自転車のロードレースが盛んな国で、海外からもたくさんのサイクリストが訪れるが、ヨーロッパのサイクリストはわざわざ自分の自転車に、アメリカ人ではないことを証明するために自国の国旗を掲げてサイクリングをするのだという。というのも、コロンビアはパナマ運河についてアメリカともめた経緯があり、国民の反米感情が強くアメリカ人に対して「何をするかわからない」のだという。
「今回の(後藤さんの)事件で、もう日本の国旗を揚げられません」

佐藤和孝さん
■「政府は見ている」
佐藤さんは政府の各種の対応に対する国民の反応を、「政府が見ている」と指摘する。
「(パスポート返納について)世間は、小さなことだと思っているかもしれない。政府はそれを見ている。迷惑がかかるからとネットの75%ぐらいの人が思っているという情報がある。政府はそれも見ている。
そして、次はこの段階、次はこの段階と(制限を)すすめ、10年後には、何も情報が見えなくなる。国民は何にも知ることができなくなる。
海外のことは、自分たちの生活に関係ないというかもしれないが、そんなことはない。外国のことだから、外のことを知らなくていいというかもしれないが、そんなことはない。政府はどんどん出国させなくなる。これは『鎖国』だ。今は、その始まりのような気がしてならない」
佐藤さんは2012年にシリアを取材中に銃撃戦に巻き込まれて亡くなったジャーナリストの山本美香さんの言葉を紹介した。
『私たちジャーナリストが何人殺されようと、残った誰かが記録して、必ず世界に伝える。全てのジャーナリストの口をふさぐことはできない。どんな強大な力を持った存在であっても、きっと誰かが立ち向かっていくだろう』