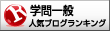皇室典範の個々の規定を個別に改正して事態を収拾しようとする政策に頭から反対するつもりはない。しかし、これは対症療法でしかなく、暫定措置的な効果が期待されるに過ぎない。天皇制(天皇家)が憲法上の制度たることをやめないかぎりは、不自由・拘束は遺憾ながら制度とともに a
付いてまわらざるをえない。(奥平康弘『萬世一系の研究』S378)
※奥平康弘氏はここまで論じ来たって、君主制(奥平氏のいわゆる「天皇制」)を、人権論や男女平等論から批判しても無力であることを悟って、結論として「天皇制(天皇家)が憲法上の制度たるをやめないかぎりは」b
「不自由・拘束は付いてまわる」と言う。この奥平康弘氏の君主制国家に対する批判において、奥平氏の示している限界は、まず第一に氏が Konstitution としての憲法しか知らず、Verfassung としての憲法を知らないことにある。こうした奥平氏の憲法観の悟性的であることの c
欠陥は、実定憲法と自然憲法の区別を必要十分に知らず、たんに「実定憲法」のみをもって「憲法」と見なすことになっている。さらに第二に、奥平氏が「不自由・拘束は付いてまわる」と述べるとき、その「自由」の実体をどのようなものとみるか、いわば氏の「自由観」における欠陥、d
もしくは弱点である。奥平氏には自由における「Liberty」と「Freedom」の区別を正しく認識されておらず、奥平氏のいわゆる「自由」が悟性的な「自由」でしかないことである。 e
では一体そもそも、「女帝」論議をひきおこす根幹である天皇制には、いかなる合理的な根拠があるのか。この論議、すなわち根底に向けてあるべき論議はどうなるのか。・・・
「戦後六〇年」の間に、天皇制に関してはたくさんの議論があった。けれども、公には、a
天皇制の合理的な根拠を真正面から問題にする機会をわれわれは持ったことがない。今こそが本当は、その好機だと思う。しかし、今度もウヤムヤに終わるだろう。「女帝」論議と違って、天皇制の合理的な根拠をめぐる議論は、道具的な意味での「合理性」が問われるのではなくて、b
憲法体系に関わる政治原理のレベルで問われるべきものであって、いわゆる「公共理性」(public reason)にもとづく討議とならざるを得ない。法制官僚的には、憲法第一条から始まり第八条にまで至る「第一章 天皇」の諸規定の存在=既成事実から出発することになるが、c
「公共理性」はそうした存在自体の根拠を問うのである。
告白すれば本書では、きちんとした形では「公共理性」からの検討がなされたわけではない。しかし制度の成立存続に関する歴史研究を遂行するに当たって、意識の背景には「公共理性」からの検討という着眼が、私なりにあるのであって、d
読者が本誌のあちらこちらでは、いくばくかでもそのことに気付いていただけたならば幸いである。(奥平康弘『萬世一系の研究』あとがき s401 )
※ここで奥平氏は 「では一体そもそも、「女帝」論議をひきおこす根幹である天皇制には、いかなる合理的な根拠があるのか。」という問いを e
自ら発して、さらに、この「合理的な根拠」を「公共理性」(public reason)と言い換え、「告白すれば本書では、きちんとした形では「公共理性」からの検討がなされたわけではない。」と言い訳しておられる。しかし、これでは話にもならない。f
いずれにせよ本書での奥平康弘氏の論考の根本的な欠陥は、ヘーゲルの歴史的な作品である『法の哲学』を検討、検証したあとがまったく見られないことである。氏のいわゆる「天皇制の合理的な根拠」「公共理性」(public reason)については、g










 review @myenzyklo
review @myenzyklo