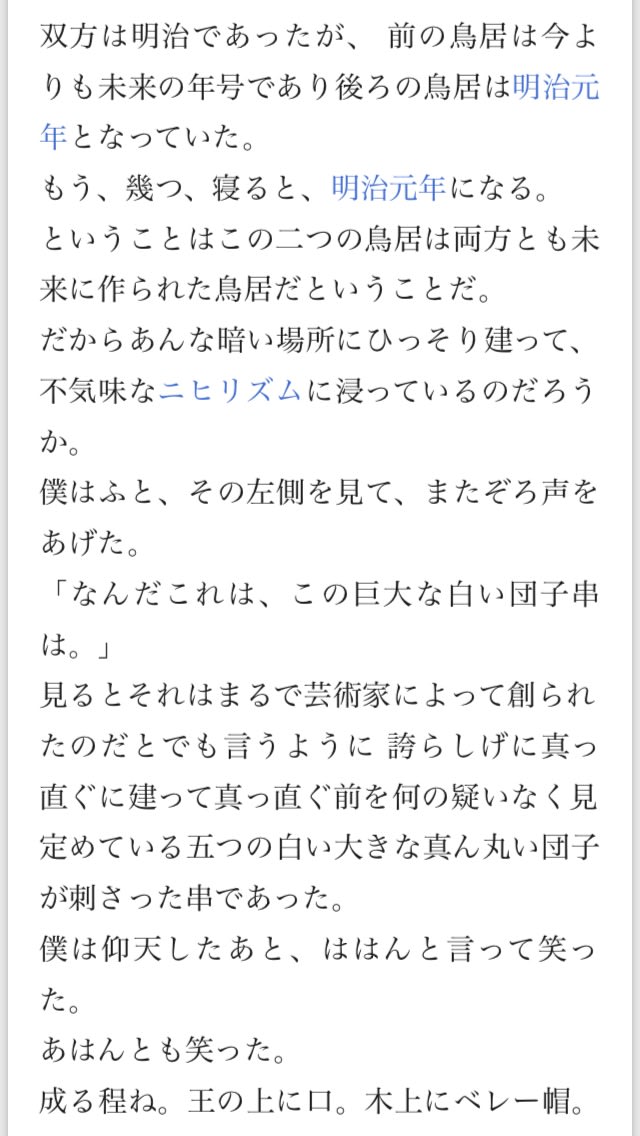惰飢えは本当の、天涯孤独となった。
だから、天はこの惰飢えに、干支藻を与えたのである。
それは丁度、惰飢えが、実の姉にLINEでこう送った次の日のことであった。
「もう二度と、わたしから話しかけることはありません。さようなら。」
この日から、惰飢えはだれひとり、相談するのも話すのも、できない人間となった。
だれも、彼女を必要とはしていなかった。
だれも、彼女を見てもいなかった。
だれも、彼女に関心を持つことすらなかった。
だれも、彼女を愛してはいなかった。
彼女は自分の震える胸の檻のなかで、小さな鳥に掛け布団を掛けて寝かし付ける日々であった。
だがその鳥は、翌朝には必ず死んでいた。
だれも彼女を見なかったので、彼女もだれも見ることができなくなってしまったのである。
此の世のすべてが、戯れ事に見える日もあった。
だれもが、本当は彼女を心の奥底で嘲笑っていた。
だれもが、本当は彼女を心の奥底で憐れんでいた。
だれもが、本当は冷たく、虚無に支配されていた。
彼女はそれを知っていた。
惰飢えの心は常に、暗黒の虚無に支配されていた。
それでも彼女は、日々こう叫んでいたのである。
「すべてをわたしによって救うことができますように。」
そして彼女は、だれひとり助けることは叶わなかった。
その代わり、悉くすべての生命を地獄に堕すことが得意であった。
彼女はみずからのこの業(わざ)に、いつも嘆き悲しんでいた。
だれも彼女を知って、それを褒めることはなかった。
だれも彼女を知らなかったのである。
一人を除いては。
先日、惰飢えの携帯を一人の彼女の担当のホームヘルパーの男が鳴らした。
その男の名は干支藻である。
干支藻は次の夕方、彼女のマンションへ遣って来て、彼女にこう告げた。
「色々と、がんばってはみたのですが…やはり難しいですね。」
干支藻はいつものようにはにかむような無邪気な笑顔でさらにこう続けた。
「身体は一つですからねぇ。」
彼女より四つ年下のこの男は彼女の担当のホームヘルパーであるのだが、彼の仕事とは彼女に多くのヘルパーサービスを行なうことではなく、登録ヘルパーたちが彼女のヘルパーを彼女の希望通りにこなせているかを時々窺いに来る指導社員であったのである。
だが運悪く、この干支藻という男に恋煩いをしてしまった惰飢えは彼に自分のヘルパーサービスをたまにして欲しいと頼んだ。理由は、「干支藻さんといると楽しいと感じるから。」だと告げた。
干支藻は正直にそう言われた時に、「そう言って貰えるのは嬉しいですね。」と嬉しそうに答えた。
彼の仕事は”人を助けること”。利用者から自分といて楽しいと感じてもらえることが何より嬉しいのは当然なのである。
例えば、どんなにサービスの仕事を感謝してもらえても、「なんかこいつと一緒におったらすっげえ嫌な気持ちになるなあ。っていうか会った瞬間から想ったが、こいつの嫌悪感っぱねえよな。吐き気がするくらいだ。」などと想われながら頑張って仕事を続け、そして仕事に対してはいつも引き攣った作り笑顔で感謝されるのはヘルパーとしても大分辛いことである。
干支藻は別段、37歳の独身女性惰飢えから「あなたといたら楽しいと感じる。」と照れながら言われたので嬉しかったわけでは決してないのである。
干支藻は誰からそう言われたとしても、まったく同じ嬉しい気持ちになって、その嬉しさを素直に照れながら返す男であった。
そこにある真正の純粋さを見抜き、惰飢えは彼に本当に恋をしたのである。
でも、惰飢えの苦しい恋慕の情に、この男干支藻はまだ気づいていない。
惰飢えひとりだけが傷つき、落ち込み、彼と会えないすべての時間、嘆いてはアルコールに慰みを求め続けた。
ただでさえ、大量に飲み続けなくては癒えない苦しみを癒す為のアルコールが、さらに増える夜もあった。
なので惰飢えはある瞬間、苦々しい想いに身を震わせ、真剣にこう想った。
彼の真の仕事とは実はわたしのホームヘルパー(Home Helper)担当ではなく、家を崖から落とす意味であるホームプッシャー(Home Pusher)であり、またの名を死へと導く男、デッドリーダー(Dead Reader)なのではあるまいかと。
だが、彼の真夏の太陽の下で真夏の蒼い風に揺れながら微笑む舞茸のような胸がきゅんと締め付けられる爽やかで優しげな笑顔を見ると、果して本当にそんなことは在り得るのであろうか?と疑わなくてはならなかった。
舞茸とは、自分の仕事を誇りになどしていない。エリンギや椎茸や、松茸のように自分の存在をえばることもしない。かと言って、えのき茸のように歯と歯の間にのめり込んで来るという失礼千万で愚劣な行為もしない。 そしてしめじのように、小癪な存在でもない。
だから、彼は茸の中で、必ず舞茸であらねばならない。
つまり彼は、みずから目立つことは一切しないが、その存在は人の心を熱く振るわせるほどの力を持っており、善なるエネルギーに満ちた光の茸なのである。
暗い森の奥に、一つだけ生えたその輝かしい舞茸を、惰飢えは見つけたのである。
彼は時に青白く点燈し、ミステリアスな面を惰飢えに見せるのだった。
彼は決して彼女に多くを喋らなかった。
惰飢えの移動支援を彼が初めて行なった日、100均店とダイエーに向って歩く道のりのなかでも、彼は沈黙の時間を恐れることはなかった。
彼はどこまでも、人を癒す存在であった。
ヘドロの底で苦しみ続ける惰飢えのような孤独な女の心の傷をも、彼のエネルギーは癒すことに励み、そして彼女の胸のろうそくに火を灯させ、自然と微笑ませることができた。
それでも彼女は、彼が少しばかり、疲れているのを見抜いていた。
でもその疲れた表情を、彼は決して人に見せようとはしなかった。
いつでも最高の微笑を、惰飢えに向って絶やすことはしなかった。
干支藻は今日も、惰飢えの目を真正面から耀く両の黒い目で見つめ、残念そうな顔で微笑みながら言ったのである。
「僕が惰飢えさんのヘルパーに入れないか、色々とがんばってはみたのですが、僕の抜けられる仕事が今なくて、残念ですが今月と来月一杯は惰飢えさんの御希望に添えることが叶わないかもしれません。」
惰飢えが物言わず、悲しい顔で残念であるということを表していると、続けて干支藻は笑顔でこう述べた。
「身体は一つしかないですからねぇ。」
惰飢えは無言で頷き項垂れ、その日、彼は「申し訳ない」旨を何度と爽やかに述べたあと、惰飢えの部屋を去って帰った。
その晩、惰飢えは悲しみの末にラム酒のストレート、シングル4杯を一気に呷ると褥に突っ伏して気絶した。
そして、二月後、暖かい春の訪れ、四月が遣ってきた。
或る日の午後、惰飢えの携帯が突然鳴った。
彼女の耳に届いた美声の一声、相手は愛しの干支藻であった。
「今日惰飢えさんにお話したいことがあるので、夕方にでも家に御邪魔させて貰っても良いでしょうか。」
惰飢えは喜んで、大丈夫であると答え、胸をときめかせながら彼を部屋で待った。
宵の刻、外が薄暗くなってくると惰飢えの部屋のチャイムが鳴り、彼女がインターフォンに出ると干支藻の声が響いた。
彼女はオートロックを開け、玄関に向った。
鼓動を高鳴らせながら彼を待っていると、階段を上る足音が近づいてきて、彼女の部屋のドアの前で止まった。
瞬間、彼女はドアをそっと開けた。
すると見よ、そこに湯気を立ち昇らせているかの如き麗しき壮年の男が後光に照らされて美しい微笑を湛えながら惰飢えの顔を見つめ立っていた。
惰飢えは久々に御目にかかった干支藻の神々しき立ち姿に胸を打ち砕かれ、腰は抜けてへなへなとその場に座り込んだ。
干支藻は瞬間、すわ、貧血か?!と想い咄嗟に惰飢えの肩を支えるのだった。
そして惰飢えの座ると同時に彼も玄関のたたきに腰を下ろした。
干支藻は、「惰飢えさん、大丈夫ですか?!」と優しい声で心配そうに訊ねた。
惰飢えは、「ちょっと腰が抜けてしまったようです。」と素直に半笑いで答えた。
干支藻は、これを冗談だと想い、彼女を見つめて爽やかに笑った。
そして、ふと部屋の奥に視線を移し、「おおおぉっ。」と大袈裟に彼は言った。
「すごく片付いているじゃないですかあ。頑張りましたね惰飢えさん。」
惰飢えは照れながら、「はい。御陰様で。」と言って微笑み返した。
週に一度の、家事支援ヘルパーを頼んではいたのだが、実際に家事支援をしてもらうのは月に二度ほどで、あとは(10年来の引き篭りのため)散歩を一緒にしてもらうことにして、結局はほとんどを自分で片付けたのだった。
それはやはり、自分の物は自分で片付けることが一番精神的に楽であったからである。
時には、町野変丸の漫画がヘルパーに見つかりはしないかとドキドキしながら部屋の片づけをするのは非常に精神的にきつかった。
ふと、「これはどんな漫画ですか?」と素直な好奇心から男性ヘルパーに訊ねられることがあったからである。
一体、なんと答えてよいか解らぬ漫画や本ばかりであった。
惰飢えの部屋は、当初そんな物ばかりが、ゴミのように埃と髪の毛に埋もれ、積まれながら散乱していた。
「これはですねぇ…近親相姦色のかなり強い闇の深い感じのエログロで悪趣味なサブカル漫画ですね。」と薄笑いで答えたところで、変態としてか見て貰えそうにないことはわかっていた。
これをわたしに自信を持って薦めてくれた今もずっとひとつの魂として愛し続けて止まない魂の同志である愛する八歳下の彼ならば、きっとあの時のように素晴らしく英明で思慮深い洞察力で見抜いた哲学的表現で彼の漫画を真っ直ぐな清らかな目で語り、決してただの変態性嗜好者とは見られなかったに違いない。
惰飢えもいつか、この漫画を彼のように愛し、深く表現することができたならと想うのだった。
その日までは、決してだれの目にもこの漫画がわたしの部屋にあることを見せてはならない。
惰飢えは、幾つもの彼女の秘密がこの部屋のなかにあることを喜んだ。
自分の部屋のなかにある秘密と自分の心のなかにある秘密、そのすべてを知ったなら、干支藻は彼女を軽蔑し、彼女の元から離れてゆくだろうか。
同時に、彼の部屋のなかにある秘密と彼の心のなかにある秘密のすべてを知ったなら、彼女は彼に幻滅し、もう彼を愛する日は来ないだろうか。
惰飢えの胸の底に、寂寞と悲しみの風が吹き、彼女は言葉を喪って黙ってそこに座り込んでいた。
干支藻はそんな彼女をまた心配になり、彼女に明るくこう言った。
「もし宜しければ、今日は初めて、部屋のなかに上がってお話しても良いでしょうか?」
惰飢えははっと気を取り戻し、「はい。」と答えて笑って頷いた。
彼は彼女の肩を支えながら彼女をゆっくりと立ち上がらせ、靴を脱ぐと共に部屋の奥へと突き進んだ。
だが、部屋の奥に来たものの、この狭い六畳間のどこに二人は座れば良いのか?二人は悩まなくてはならなかった。
デスクと椅子が一つずつ、床に直接敷いた万年床、小さなソファーテーブル、一畳ものうさぎのサークル、飾り棚と6個のキューブボックス、積み上げた収納ボックス、天まで届く本棚、残されたスペースと言えば、幅50cm縦170cmのスペースだけの10年近く使い続けている汚いベルギー製のメダリオン柄の絨毯の上であった。裏はカビが生えていることだろう。
この絨毯の狭いスペース上に、二人向かい合って座って話をするのは心苦しく、また足が痛くて痺れることだろう。
かと言って、同じく何年と洗っても干してもいない臭くて汚い万年床の上に干支藻を座らせるのも心苦しいものである。
だが干支藻一人をデスク前の椅子に座らせ、その左に彼女が敷布団の上に座って話をする場合、彼女はいつでも彼を見上げる形で、彼はいつでも彼女を見下げる形で話をせねばなるまい。
これは彼女が良くても彼がきっと許さない。
何故ならこれまでどんな日も、彼は自分が見下げる形で話すのを嫌っているように見えたからである。
彼女が玄関に立っているときには自分は座り、彼女が玄関に座る日には自分は必ずたたきにしゃがみ、彼女が玄関に座るよう言ったときにも、決して彼は玄関に上がって若干彼女を見下げる位置には立とうとはしなかった。
男はただでさえ女よりも力が強く、また頭の回転も素早くて賢く、感情的にならずに冷静に判断できることで女よりも上に立つものである。
女とはいつでも男より弱者であり、また少しのことに深く傷つく繊細な生き物である。
その為、男が女の上に立って話すことは女の心を傷つけてしまうかもしれないと女性性も強い男は不安になり、できればそれを避けたがるのである。
もっとも、彼はヘルパーであり、彼女を助ける為に此処へ遣って来た者である。
彼女に仕える男が、何ゆえに彼女を上から見下げる形の位置で話をすることを好むであろう?
できれば互いに対等の位置を望んでいるはずである。
惰飢えはたった5秒間の間に、部屋を見渡しながらこのすべてを考察した結果、干支藻に向って訊ねたのであった。
「座るの蒲団の上でもいいですか?」
「あんま綺麗じゃないのですが…」
そう苦笑いで付け足して彼女は左にいる彼の顔を見上げた。
すると意外にも、干支藻は悩むことなく「あっ、良いですか?御布団の上に座らせて戴いても。」と答えたのであった。
惰飢えは、この返事に戸惑った。
だってそうだろう。普通は恋人でも友人でもない男が女の部屋に上がり込んでいきなし蒲団の上に二人で仲良く座るなんてことは在り得ない。断じて、在ってはならない話である。
普通はそう女に言われたとしても、男はこう言うはずである。
「う~ん、でもそれはやっぱり…あまり良くないので僕はこちらの絨毯の上に座らせて戴きますから、惰飢えさんはどうぞ御布団の上に座ってください。」
これが好青年の正常な対応であろう。
しかるに、なんですか?干支藻はまるで、待ってましたと言わんばかりに彼女の薦めを断ることなく二つ返事で承知したのである。
これに惰飢えは一縷の悲しみを抱いた。
そして、やはり嫌だと感じたのである。
なので惰飢えは咄嗟にこう言った。
「やっぱり…」
そう言い掛けたときである、干支藻が察したのか、彼女の言葉の先を折って素早くこう言った。
「やっぱり、僕は絨毯の上に座らせて貰っても良いでしょうか?この僕の着ている服は言わばヘルパーの作業服でありますし、それで御布団の上に座るのはやっぱり良くないですね。すみません。」
この言葉に、惰飢えは干支藻が若干、混乱しているのではないかと想った。
干支藻は、実はとてもシャイな男であり、女性の部屋に上がった経験もあまり無く、女性と部屋で二人きりになった経験もあまりないのかもしれぬ。
であるから、彼の頭は緊張で混乱し、物事をまともに考えることすらできぬほどに頭が馬鹿になってしまったのであろう。
そうに違いあるまい。惰飢えはそう想い込むことによって、この遣り場の見つからぬ悲しみを蹴散らすことに成功したのだった。
それに、観よ。干支藻は観るからに、何か困惑しているかの様子で惰飢えの部屋の中心に突っ立っているではないか。
惰飢えは、そんな干支藻を観て、こう想った。
「嗚呼!これはわたしの愛する人…!彼は実は、とても不器用な人だったのである…!」
彼女は、彼の自然な器用さを愛していたかもしれないと想い込んでいただけなのかも知れない。
実は彼の器用さとは、作られた器用さであり、その不器用さを彼女は見抜いていたのではないか。
そう想い込むことでみずからの嫌悪感を払拭した惰飢えは、布団の上に静かに座った。
干支藻は、その頃にはいつもの静かな面持ちに戻って彼は絨毯の上に腰を下ろし、二人は小さな安物のソファーテーブルを隔てて向かい合う形になった。
二人はそうして、落ち着いて少しのま黙って見つめ合っていたが、とうとう干支藻が口を切った。
「惰飢えさん、僕が今から御話しすることを、どうか落ち着いて聴いてください。僕が今から御話しすることは、俄かに信じ難い話であると想いますが、これは事実です。僕は今から嘘を惰飢えさんに話すわけではありません。きっと衝撃を受けて、驚かれると想います。でもすべては、自分で考えた末に、決断したことです。」
干支藻は、唐突な衝撃的な言葉の数々に、ショックを隠せず、無言で涙を流す惰飢えを前に、話を続けた。
「僕たった一つの身体では、惰飢えさんの要望する通りにサービスを提供することが叶いません。これでは、はっきり言って、ホームヘルパー失格だなと感じました。大切な利用者様の要望通りにサービスを行なえなくて、何がホームヘルパーなのか、僕はわからなくなってしまったのです。一体僕は何をヘルプしているだろう、誰を心から助けることが出来ているだろうと、不安で、苦しくてたまらなくなったのです。きっと、他の利用者様の方は、こんなことを言うと駄目だと想いますが、正直、僕でなくても代りはいるのではないかと想っています。でも惰飢えさんは違います。惰飢えさんは、僕でなければ、本当の意味で助けることはできないと感じたのです。それは、きっと人間と人間の縁というものであると感じています。この縁を、僕は人を助ける役目としてこの地上に誕生した以上、決して無駄にしては駄目なのです。僕は絶対に、惰飢えさんを助ける。助けたいのです。惰飢えさんが、この三ヶ月間、ホームヘルパーを利用してもまったく飲むお酒の量を減らせず、日々鬱症状に苦しんでいることを僕は知っています。これは僕にとって、とてつもなく遣り切れないことです。なので、僕は真剣にこの数ヶ月、考えました。どうすれば良いのかと。僕の今遣っている仕事を、他の人間に代わってくれと頼むことは、できないことではないのかもしれません。でもそれだと、あんまりだと言う気がしました。自分の代りはいるだろうから、今まで遣ってきた仕事を、自分の代わりを他の人に遣らせるというのは、酷いことのように想ったのです。では自分が、この仕事を続けながらも、惰飢えさんを助ける方法はないのか?僕はあれから、ずっとずっと毎日そのことについて考えて来ました。そしてやっと、方法を見つけたのです。それはどんな方法かと言いますと、どうか心を静かにさせて聴いてください。実はですね、僕は錬金術と、白魔術を行なえる者です。これは修行によってとかではなくて、気づけば子供の頃から身につけていた能力です。僕はその、自分の編みだした術によって、僕をもう一人、生み出しました。何故かというと、僕の身体がもう一つ、本当に必要だと感じたからです。どうやって作り出したのかと言うと、これは多分僕自身の方法でしか作れない方法だと想います。つまり僕によってでしか、僕を作ることはできません。まず、何が必要だったか、それは一人の新鮮な青年の死体です。どうやって手に入れたかと言うと、死体安置所に保管されているある一人の身寄りのいない若い青年の自殺した死体を手に入れました。何故そんなことが容易くできるかと言うと、僕は警察の上部組織やフリーメイソンならぬ或る巨大な黒魔術秘密組織とも繋がりを持っているからです。遺族の存在しない人間の自殺死体は、実はあらゆる方法で手に入れたがる組織が多数あり、そのすべては無駄なく利用されています。この事実を、僕が知っていても黙っていることを惰飢えさんは悲しむかもしれません。でも間違いなくこの話を人にすれば僕は暗殺されます。なので惰飢えさんにしか話すことができません。この話は死ぬ迄、どうかシークレットにしておいてください。話を戻しましょう。僕はその自殺した哀れな青年の死体を闇経由で手に入れ、そしてその死体を丸ごとこれまたある闇組織施設の地下室にある自家用レンダリングプラントによってその肉体を丸ごと攪拌機に投げ込んでまずは骨ごとミンチ状にしました。そしてそれを大鍋で煮たものにその場で僕自身の手によって殺したそれぞれ三十三頭の牛と豚と鶏と馬と山羊と羊をすぐにレンダリングプラントでまた丸ごとミンチ状にして、それも大鍋に打ち込み、コトコトと数百種のブイヨンとハーブと塩と胡椒を入れて七日間煮込み続けました。七日が過ぎた頃、これに厚揚げと大根と人参と卵とこんにゃくとはんぺんと昆布とじゃがいもと蛸と烏賊とがんもどきと舞茸を入れて煮込みます。こんにゃくは、必ずねじりこんにゃくの形を取らねばなりません。そして茸は定めて、舞茸でなくてはなりません。」
「やはりか…!」この時、惰飢えは蒼褪め、吐き気をこらえながら心の奥でそう叫んだ。
「それで醤油と酒と味醂を足し、三日間、さらにことことと煮続けます。そのできたぐずぐずになったスープを、地上に上がって皿に入れて三十三皿、庭に並べます。その匂いに釣られて寄って来た野良犬をすべて外に出られないように拘束します。皿のなかのスープを飲み干した犬が三十三匹になればその拘束した犬のすべてを頭部のみを地上に出した状態で生き埋めにします。そして三十三匹の犬の頭の前に同じくスープ皿を三十三皿並べ、犬が餓死する寸前にその頸を切り落とします。その時、落ちた犬の頭が上手くスープ皿の中に入り、彼らはその魂でスープを飲み干します。この犬の頸のすべてを例の大鍋にまた打ち込み、三十三日間、煮込み続け、そしてそこに大量の小麦粉と米粉と片栗粉と油を投入し、捏ねます。それを巨大麵棒で伸ばしたものを僕の等身大のジンジャーブレッドマン型で型をくり抜き、巨大なスチームオーブンで七日間、じっくりと高温の蒸気と熱風で焼きます。七日目の朝、地獄の熱さのなかで、セカンド干支藻が、目を覚まします。そして”熱い!!”熱い!!”熱い!!”と絶叫しながら自力でオーブンのドアを開け、闇雲に外へ走り出して行きました。外の空気を、初めてその瞬間吸ったのです。それまでの僕は、恍惚朦朧としており、醒めているような夢の中にいるような、頭部が熱くてたまらなかったのですが、突然一陣の涼しさを覚え、気がついてみると、惰飢えさんのマンションの前に立っていたのです。」
一端、話し終えたセカンド干支藻は、惰飢えをじっと、物言わず透明な眼差しで見つめていた。
だが、突如、彼は噎び泣き始めたのだった。
惰飢えは震えの止まぬ心でその訳を訊ねた。
すると、彼は目の縁を真っ赤にしてこう泣きながら言った。
「僕は…僕は…、僕が生まれる為に、たくさんの生命に地獄の苦痛を与え、そして僕は生れ落ちました。惰飢えさん、貴女はこの世からすべての堪え難い地獄の苦痛をなくしたくて、ヴィーガンになったと以前、僕に仰ってくださいましたね。でも皮肉なことに、僕が惰飢えさんを助ける為に、僕は生み出され、その為に僕は惰飢えさんの最も苦しむことをしなくてはなりませんでした。そうしなくては、僕が惰飢えさんを助けることはできなかったのです。そうしなければ、僕が惰飢えさんを喜ばせることができなかった。」
セカンド干支藻は、大粒の涙を目から垂れ流しながら苦しそうに惰飢えに向って言った。
「正直に仰って貰えませんか。僕の存在は、惰飢えさんにとって、悪ですか。」
「僕がこの世に、僕自身によって生を受けたこと、それは間違いでしたか。」
約十分間の、沈黙が部屋のなかに流れた。
惰飢えの脳は、あまりの衝撃と悲しみにより、機能停止してしまったからである。
痺れを切らし、とうとうセカンド干支藻はこう惰飢えに向って、まるで悲しみを投げ付けるように、だが透き通る目でこう言った。
「僕は生まれきたことが間違っていたんだ。」
その瞬間であった。
惰飢えの脳が機能を再開し、ようやく惰飢えは言葉を発した。
彼女は彼に、悲しい顔でこう返すのがやっとであった。
「わたしはそうは想わない。」
彼は、自分の言った言葉を後悔するように、ただ彼女をじっと見つめていた。
その言葉は、まるで最初からそこに用意されていたように惰飢えには想えた。
何故ならば、その同じ言葉をかつて自分が亡き最愛の父に向って父の死ぬ一年ほど前に言ったときに、父が悲しげに返したやっとの言葉が、その言葉であったからである。