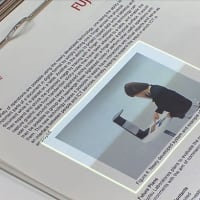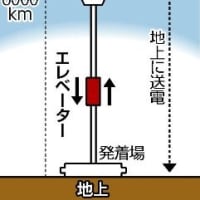http://www.yomiuri.co.jp/eco/news/20100925-OYT1T00544.htm
『首都圏の貴重な水源になっている神奈川県北西部の丹沢山地で、ニホンジカの食害などによるブナ林の荒廃が進んでいる。
再生を目指す県は2007年度以降、シカの駆除を積極的に進めてきたが、生息数は増加。害虫などにも手を焼いている。
日本百名山の一つ、丹沢山から塔ノ岳に続く尾根筋。かつてはうっそうとしたブナ林に覆われ、登山道の木立の合間から景色がわずかにのぞけるほどだった。
今ではブナの幹や枝が立ち枯れて動物の骨のような姿をさらし、斜面に残るブナ林も、根が地表にむき出しになっている所が目立つ。
県によると、ブナ林の荒廃は1980年代、東丹沢の尾根筋を中心に始まったとされる。徐々に周辺部へと広がり、草原化の恐れすらあるという。
荒廃の主な原因とされるのがニホンジカ。下草を食い荒らし、雨による土壌の流出を招いている。県の調査では、05年度末時点で、最大4500頭が生息すると推計された。
ブナなどの広葉樹が衰えると、雨水を蓄え、濾過(ろか)する機能が低下。森をすみかとする動植物への悪影響も懸念される。
県は07年度から丹沢大山自然再生計画(5年計画)に基づく本格的な保護に乗りだし、土壌流出防止策などのほか、食害防止に力を入れ、同年度はそれまでのほぼ2倍にあたる約1500頭のシカを駆除。09年度までの3年間で計約4700頭を捕獲するなどした。
ところが、県が同年度末、改めて生息数を調べたところ、推計で最大4900頭と、駆除が功を奏していない実態が浮かび上がった。県は理由を「隣県からの流入や、捕獲数を増やしたことで1頭あたりのエサが増え、生存率が高まった可能性もある」(自然環境保全課)とみて、12年度以降、駆除数をさらに増やす方向で検討している。
ただ、元凶はシカだけではない。大気汚染やブナの葉を好むブナハバチの発生、さらに登山ブームで多くの登山客が押し寄せ、植生の後退を招いているとの指摘もある。
即効性のある対策がない中で、県は「シカの駆除やブナの保護柵設置など、地道な試みを同時並行で続けていくしかない」としている。
◆丹沢山地=神奈川県相模原、秦野市、松田、山北町などにまたがる計4万ヘクタール余りの山塊。大部分が丹沢大山国定公園に指定されている。ブナ林は標高800メートル以上の山肌や尾根に広がり、ニホンカモシカやツキノワグマといった野生動物が生息する。
(2010年9月25日16時12分 読売新聞)』
シカは山を食いつくす。
捕獲により数が減っても、被害はすぐにへらない。
南アルプスでも結局、柵で保護するしかないが、山全体を囲うわけにもいかない。
何かよい方法はないものでしょうか?
『首都圏の貴重な水源になっている神奈川県北西部の丹沢山地で、ニホンジカの食害などによるブナ林の荒廃が進んでいる。
再生を目指す県は2007年度以降、シカの駆除を積極的に進めてきたが、生息数は増加。害虫などにも手を焼いている。
日本百名山の一つ、丹沢山から塔ノ岳に続く尾根筋。かつてはうっそうとしたブナ林に覆われ、登山道の木立の合間から景色がわずかにのぞけるほどだった。
今ではブナの幹や枝が立ち枯れて動物の骨のような姿をさらし、斜面に残るブナ林も、根が地表にむき出しになっている所が目立つ。
県によると、ブナ林の荒廃は1980年代、東丹沢の尾根筋を中心に始まったとされる。徐々に周辺部へと広がり、草原化の恐れすらあるという。
荒廃の主な原因とされるのがニホンジカ。下草を食い荒らし、雨による土壌の流出を招いている。県の調査では、05年度末時点で、最大4500頭が生息すると推計された。
ブナなどの広葉樹が衰えると、雨水を蓄え、濾過(ろか)する機能が低下。森をすみかとする動植物への悪影響も懸念される。
県は07年度から丹沢大山自然再生計画(5年計画)に基づく本格的な保護に乗りだし、土壌流出防止策などのほか、食害防止に力を入れ、同年度はそれまでのほぼ2倍にあたる約1500頭のシカを駆除。09年度までの3年間で計約4700頭を捕獲するなどした。
ところが、県が同年度末、改めて生息数を調べたところ、推計で最大4900頭と、駆除が功を奏していない実態が浮かび上がった。県は理由を「隣県からの流入や、捕獲数を増やしたことで1頭あたりのエサが増え、生存率が高まった可能性もある」(自然環境保全課)とみて、12年度以降、駆除数をさらに増やす方向で検討している。
ただ、元凶はシカだけではない。大気汚染やブナの葉を好むブナハバチの発生、さらに登山ブームで多くの登山客が押し寄せ、植生の後退を招いているとの指摘もある。
即効性のある対策がない中で、県は「シカの駆除やブナの保護柵設置など、地道な試みを同時並行で続けていくしかない」としている。
◆丹沢山地=神奈川県相模原、秦野市、松田、山北町などにまたがる計4万ヘクタール余りの山塊。大部分が丹沢大山国定公園に指定されている。ブナ林は標高800メートル以上の山肌や尾根に広がり、ニホンカモシカやツキノワグマといった野生動物が生息する。
(2010年9月25日16時12分 読売新聞)』
シカは山を食いつくす。
捕獲により数が減っても、被害はすぐにへらない。
南アルプスでも結局、柵で保護するしかないが、山全体を囲うわけにもいかない。
何かよい方法はないものでしょうか?