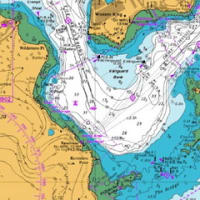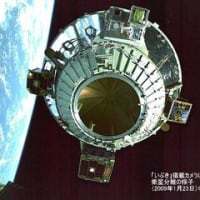航空機を操縦するのはもちろんパイロットの役目だ。しかし、パイロットが操縦桿を動かす力がそのまま動力として翼に伝わって、航空機は飛んでいるわけではない。パイロットと翼とは、Fly-by-wire(フライ・バイ・ワイヤー)というテクノロジーで繋がれている。
フライ・バイ・ワイヤーとは、日本語に訳すと「電線による飛行」ということになる。すなわち、パイロットが操縦桿に加えた力はコンピューターによって一度電気信号に置き換えられ、その電気信号がワイヤー(電線)によって翼まで伝えられ、最終的に翼に取り付けられている油圧駆動装置を作動させるという仕組みなのだ。
これは航空テクノロジーの進化によって生み出された技術で、現在開発中のほとんどの航空機で採用されている。コンピュータによる飛行制御やメンテナンスの自動化を可能にする、とても優れた技術だ。
これに対して従来の航空機では、ケーブル接続によって直接パイロットが翼の油圧駆動装置を動かしていた。すなわち、パイロットが操縦桿に加えた力がそのままケーブルを使って油圧駆動装置に伝えられ、加えた力のぶんだけ翼が動いていたのだ。これをFly-by-cable(フライ・バイ・ケーブル)方式という。
実は、僕が今インターンとして勤務しているATR社の航空機は、このフライ・バイ・ケーブルを採用し続けている航空機だ。先日ATR社の最終組立工場に行って航空機の内部を細部まで見学させてもらったのだけど、機内にはコックピットと主翼、そして、尾翼を繋ぐケーブルが張り巡らされていた。パイロットが操縦桿を左右に動かすと、その動かした量だけこのケーブルが引っ張られ、その力によって翼が動き、航空機が進路を変えたり、高度を上げたり下げたりするのだ。
ATR社がいまだにこの成熟した技術を採用しているのには理由がある。それは、成熟した技術だからこその信頼性の高さと経済性だ。もちろん、フライト・ガイドシステムとしてはコンピューターを採用しているものの、フライ・バイ・ワイヤーを導入することによって発生する新たな電子機器トラブルや追加の重量、そして、追加コストを考えれば、少なくともATR社のような地域航空輸送をターゲットにしたニッチな航空機市場にとっては、これはとても合理的な選択肢だと言える。
さらに、フライ・バイ・ケーブルという技術は、フライ・バイ・ワイヤーに比べてはるかにシンプルなオペレーションを可能にする。何か故障やトラブルがあれば、それはすぐに物理的な感覚としてパイロットの五感に伝わるし、コンピューターと人間とのミスコミュニケーションによって事故が発生するということもない。シンプルさが生み出すリスク低減効果があるのだ。
日本では新しい技術やシステムのみが世間の注目を浴び、古い技術やシステムはただ完成してから時間が経っているという理由だけで、なんとなく敬遠される傾向にあると僕は思う。技術としてただ古いことは、果たして本当にその技術の真の価値をそれほど減少させるに値する要素なのだろうか。
これを技術の進歩への否定と受けとるか、それとも、技術の本質への回帰と受けとるか、意見は人によって様々だと思う。
(写真はルフト・ハンザ航空のATR機の模型。ぜひ一台欲しい!)