
第44代アメリカ合衆国大統領にバラク・フセイン・オバマ氏が就任した。首都ワシントンで開催された就任式には全米から200万人以上の人が訪れたというから、米国における彼の人気の高さが伺える。日本で言えば政令指定都市2つ分の人口が、全て一人の人間のためだけに一箇所に集まってきたのだ。これは奇跡に近い出来事だと思う。
オバマ氏についてはいろんな人が様々な角度でコメントしているけれど、僕が一番感心させられるのは彼の「チーム・オブ・ライバル」のマネジメント能力だ。ライバル、すなわち、自分にとって競争相手である人物まで彼は味方にしてしまう能力を持っている。民主党大統領候補者の座を争ったクリントン女史をホワイトハウスの国務長官に迎え入れたのが良い例だ。クリントン女史は確か、「オバマよ、恥を知れ!」とまで言い切って彼を非難した人物だ。
トップの座に就く者はライバルさえもマネジメントしなければならない。逆に言えば、それができないような者にトップの座に就く資格などない。彼の態度はそんなことを物語っているように僕の目には映る。かつてのライバル達さえも必ず上手くマネジメントし、成果を出せるチームに仕上げてみせる、そんな自信を彼の態度に感じるのだ。
今の僕にはそんな能力があるとはとても言い切れないけれど、オバマ氏と僕との間には一つだけ共通点がある。それは、学生時代を同じ大学の同じキャンパスで過ごした経験があるということだ。米国カリフォルニア州Los AngelesにあるOccidental大学といって、彼は2年間、僕は1年間をこのリベラルアーツ・カレッジで過ごした。憲法から哲学、生命倫理学から音楽まで、人生の中で本当に大切にすべきことを僕はこのキャンパスで学んだような気がする。今振り返ってみても、本当に貴重な1年間だった。
彼の自伝によると、オバマ氏はこのキャンパスでパーティー三昧で遊びまくっていたらしい。一方の僕は、あり得ないくらいの量の英語のリーディングとレポートに追われながら、同時に、所属していた大学テニス部の練習と試合に明け暮れる生活を送っていた。週末は友人やチームメイトと本当によく遊んだし、アメリカを去る際にチームメイトから貰ったメッセージ入りのユニフォームを僕は今でも大切にしている。良い思い出はいつまで経っても色褪せない。
青春時代を同じキャンパスで過ごした者として、彼にはぜひ歴史に残るリーダーの一人になって欲しい。本当に困難な道のりはこれから始まるのだろうけれど、困難だからこそ敢えて挑戦する価値があるのだ。
■Occidental大学のバーチャル・ツアーはこちら
(写真はOccidental大学のキャンパスにあるThorne Hall。大学のHPより。)












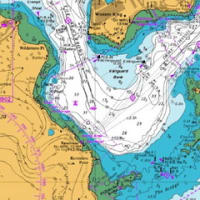



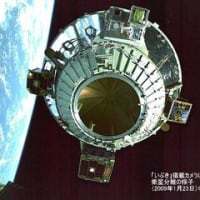


私は、なんとか2時まで起きていて、オバマ氏の演説を見てました。
確かに、アメリカも大変ですが日本の企業もかなり大変だと思います。
どんな企業が“強い企業”だと思われますか?
コメントありがとうございます。
日本もアメリカも、そして、ヨーロッパも、今は世界全体が大変な時だと思います。フランスで働いているMBA時代の友人が、航空機が急に売れなくなったと言っていました。航空会社が銀行からお金を貸してもらえない状況らしく、結果として航空機の新たな発注もほとんどない状態なのだそうです。ここしばらくは厳しい時代が続くだろうと言っていました。
「強い企業」にはいろんな定義があると思いますが、私は「不死鳥のような企業」が一番強いと思っています。言い換えれば、常に自ら生まれ変わる勇気と覚悟を持って前に進む企業です。
ご存じだと思いますが、不死鳥は一般に「死」とは無縁の鳥というイメージを持たれています。しかし、不死鳥という鳥は、絶対に死ぬことのない、「死」を超越した鳥なのではありません。フェニックスは、死を悟ると自ら火の中に飛び込んで、自らを新たな個体へと再生させるのだそうです。つまり、「死なない鳥」ではなく、自らの意思で「生まれ変わることのできる鳥」なのです。
そんな企業、強いと思いませんか?
コメントありがとう&久しぶり!
先日このブログを偶然に発見した香港在住の「弟」から連絡がありました。大学卒業以来のコンタクトにびっくりでしたが、とても嬉しかったです。夏に日本に帰ってくるそうなので、また皆で再会しましょう~!
たしかに、そんな不死鳥のような企業であったらすごく心強いです!
どこか私の考えているダーウィンのような企業(技術力の高さだけでなく、強みを活かしつつ、いかに環境に適応していくかが大事)が強い企業なのかもとどこか共通点があるような気がします。
おもしろい意見ありがとうございます。
コメントありがとうございます。
全くの偶然ですが、今日書いたブログの記事はダーウィンの進化論にちょっと関係するものです。この世で最も強い種というのは、環境に柔軟に適応できる種だと聞いたことがあります。柔よく剛を制す、ということですかね。