今回は、
(3)「反射音ピークの低減」
です。
これは、シルヴァン特有の「滑らかな”境界変化」の効能をもたらします。
一次反射という、直接音に近い時間で起こる反射は、
従来は吸音材で対処する所でした。
従来の散音材は、この反射音全体を増幅する傾向があり、
「使いすぎ注意」とされました。
サーロジックでも散音は限られた範囲(残るは単純反射面)にするよう奨めています。
もしくは、種々の音響パネルのように、吸音と散音の妥協点を探る必要がありました。
シルヴァンは、表側が細い柱で構成されており、
音波に対して緩衝効果を発揮しています。
http://www.noe.co.jp/product/pdt1/pd1_12_03.html
この配列は、特許公開「2010-189841」でも
「主に入射してくる音波に対して手前に直径が細い柱を配置し、背後には直径が太い柱を配置する。」と明記されています。
もし、逆に太い柱を前に設置してしまうと、
「より低い周波数では上述のように拡散するものの、
高い周波数の音の波面は、拡散する方向が均一でなくなり、指向性が強くなるためである。」
となり、「滑らかな”境界変化」が得られないようです。
ちなみに、「シルヴァン(製品名)」では、
「10本の円柱部分は6cm、4.5cm、3.2cmという3種類の違う太さで出来ている。」
とのこと。
http://www.phileweb.com/review/closeup/ags-sylvan/clinic/
以上の事を技術的に言うと、
「音響抵抗(インピーダンス)を緩やかに変化させ、レベルの大きな反射が柱状拡散体20の表面で起こることを回避」しているのです。
逆に言うと、「滑らかな”境界変化」を得るには、
「柱の太さ変化量/距離」をある適正値の範囲に収める必要がありそうです。
シルヴァンの「6cm、4.5cm、3.2cm」はOKでも、
同じ奥行き20cmで「10cm、6cm、3.2cm」の柱直径はダメなのだと思います。
(ちなみに、10kHzの音波の波長は、3.4cm)
んじゃあ、どういった変化割合なら「滑らかな”境界変化」なのか?
を考えると、
http://www.phileweb.com/interview/article/image.php?id=96&row=5
の図を参考にすると、
どうやら奥行き60cmタイプは
「12cm、6cm、4.5cm、3.2cm」が採用されているように見えます。
柱の太さをa(cm)、表面から柱までの距離をL(cm)とすると、
a=3.0×exp (x×L)
(定数x=0.030~0.035程度)
ということになりそうです。
定数xが大きければ、拡散帯域重視
定数xが小さければ、境界変化重視
といったところでしょうか。
実は、この「滑らかな”境界変化」という概念は以前からあって、
AA読者の方ならご存知、江川先生の【グリーンデフューザー】が該当します。
実は、同社の特許「特許公開2010-256847」では、スピーカー近傍にシルヴァンを設置している図があり、それは【グリーンデフューザー】と酷似していますね。
さらに、「SHAKTI Innovations」の「HALLOGRAPH(ホログラフ)」という商品がありました。
http://www.shakti-innovations.com/hallograph.htm
http://www.audiorefer-d.com/cgi-local/detail_view.cgi?id=00097&category=42
名前は知らずとも、その形と値段設定に驚きを覚えた方も多いはず。
これも壁面の手前に柱状拡散体を設置する事で、
(結果論として)「滑らかな”境界変化」の効能があったのかもしれません。
シルヴァンのこの特性を利用して、一次反射点やリスニングポイント近傍に設置したり、部屋全面に設置するという、従来の散音材とは異なった使い方もできるようです。
(3)「反射音ピークの低減」
です。
これは、シルヴァン特有の「滑らかな”境界変化」の効能をもたらします。
一次反射という、直接音に近い時間で起こる反射は、
従来は吸音材で対処する所でした。
従来の散音材は、この反射音全体を増幅する傾向があり、
「使いすぎ注意」とされました。
サーロジックでも散音は限られた範囲(残るは単純反射面)にするよう奨めています。
もしくは、種々の音響パネルのように、吸音と散音の妥協点を探る必要がありました。
シルヴァンは、表側が細い柱で構成されており、
音波に対して緩衝効果を発揮しています。
http://www.noe.co.jp/product/pdt1/pd1_12_03.html
この配列は、特許公開「2010-189841」でも
「主に入射してくる音波に対して手前に直径が細い柱を配置し、背後には直径が太い柱を配置する。」と明記されています。
もし、逆に太い柱を前に設置してしまうと、
「より低い周波数では上述のように拡散するものの、
高い周波数の音の波面は、拡散する方向が均一でなくなり、指向性が強くなるためである。」
となり、「滑らかな”境界変化」が得られないようです。
ちなみに、「シルヴァン(製品名)」では、
「10本の円柱部分は6cm、4.5cm、3.2cmという3種類の違う太さで出来ている。」
とのこと。
http://www.phileweb.com/review/closeup/ags-sylvan/clinic/
以上の事を技術的に言うと、
「音響抵抗(インピーダンス)を緩やかに変化させ、レベルの大きな反射が柱状拡散体20の表面で起こることを回避」しているのです。
逆に言うと、「滑らかな”境界変化」を得るには、
「柱の太さ変化量/距離」をある適正値の範囲に収める必要がありそうです。
シルヴァンの「6cm、4.5cm、3.2cm」はOKでも、
同じ奥行き20cmで「10cm、6cm、3.2cm」の柱直径はダメなのだと思います。
(ちなみに、10kHzの音波の波長は、3.4cm)
んじゃあ、どういった変化割合なら「滑らかな”境界変化」なのか?
を考えると、
http://www.phileweb.com/interview/article/image.php?id=96&row=5
の図を参考にすると、
どうやら奥行き60cmタイプは
「12cm、6cm、4.5cm、3.2cm」が採用されているように見えます。
柱の太さをa(cm)、表面から柱までの距離をL(cm)とすると、
a=3.0×exp (x×L)
(定数x=0.030~0.035程度)
ということになりそうです。
定数xが大きければ、拡散帯域重視
定数xが小さければ、境界変化重視
といったところでしょうか。
実は、この「滑らかな”境界変化」という概念は以前からあって、
AA読者の方ならご存知、江川先生の【グリーンデフューザー】が該当します。
実は、同社の特許「特許公開2010-256847」では、スピーカー近傍にシルヴァンを設置している図があり、それは【グリーンデフューザー】と酷似していますね。
さらに、「SHAKTI Innovations」の「HALLOGRAPH(ホログラフ)」という商品がありました。
http://www.shakti-innovations.com/hallograph.htm
http://www.audiorefer-d.com/cgi-local/detail_view.cgi?id=00097&category=42
名前は知らずとも、その形と値段設定に驚きを覚えた方も多いはず。
これも壁面の手前に柱状拡散体を設置する事で、
(結果論として)「滑らかな”境界変化」の効能があったのかもしれません。
シルヴァンのこの特性を利用して、一次反射点やリスニングポイント近傍に設置したり、部屋全面に設置するという、従来の散音材とは異なった使い方もできるようです。











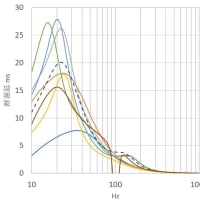
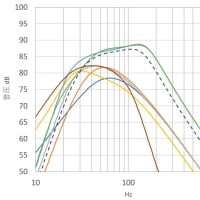

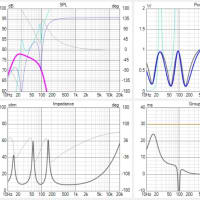

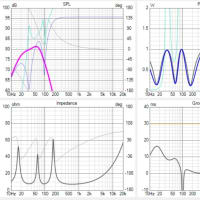
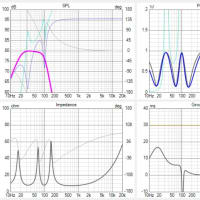









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます