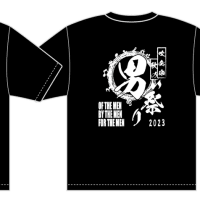「である」ことと「する」こと 第6段落 ⑳~㉔
「する」価値と「である」価値との倒錯
⑳ 〈 日本の近代の「宿命的」な混乱 〉は、〈 一方で「する」価値が猛烈な勢いで浸透しながら、他方では強靭に「である」価値が根を張り 〉、そのうえ、「する」原理を建て前とする組織が、しばしば「である」社会のモラルによって〈 セメント化 〉されてきたところに発しているわけなのです。
㉑ 伝統的な「身分」が急激に崩壊しながら、他方で自発的な集団形成と自主的なコミュニケーションの発達が妨げられ、会議と討論の社会的基礎が成熟しないときにどういうことになるか。続々とできる近代的組織や制度は、それぞれ多少とも閉鎖的な集団を形成し、そこでは「うち」のメンバーの意識と「うちらしく」の道徳が〈 大手を振って 〉通用します。しかも一歩「そと」に出れば、武士とか町人とかの「である」社会の作法はもはや通用しないような赤の他人との接触が待ち構えている。人は大小さまざまの〈 「うち」的集団 〉に関係しながら、しかもそれぞれの集団によって「する」価値の浸潤の程度はさまざまなのですから、どうしても同じ人間が「場所柄」に応じていろいろに振る舞い方を使い分けなければならなくなります。私たち日本人が「である」行動様式と「する」行動様式とのごった返しの中で多少ともノイローゼ症状を呈していることは、すでに明治末年に漱石が鋭く見抜いていたところです。
Q41「日本の近代の「宿命的」な混乱」とあるが、なぜそのように言えるのか。(90字以内)
A41 日本の近代は、市民革命を経て成立した西欧の近代とは異なり、
「である」価値が支配する精神性を残したまま表面的に取り入れたシステムにすぎず、
その混乱は必然的なものと考えられるから。
Q42「一方で『する』価値が猛烈な勢いで浸透しながら、他方では強靱に『である』価値が根を張り」は、具体的にはどのような社会状況として現れているのか。70字で抜き出せ。
A42 伝統的な「身分」が急激に崩壊しながら、他方で自発的な集団形成と自主的なコミュニケーションの発達 が妨げられ、会議と討論の社会的基礎が成熟しない
Q43「セメント化」とはどういうことのたとえか。「~化」という3文字の熟語で答えよ。
A43 硬直化 固定化
Q44 「セメント化」すると、その組織はどういうものになるのか。6字で抜き出せ。
A44 閉鎖的な集団
Q45「大手を振って」の意味を記せ。
A45 あたりをはばからず堂々と振る舞うこと。
Q46「 「うち」的集団」とはどういう集団か、本文の言葉を用いて60字以内で説明せよ。
A46 建前上は近代的組織でありながら、
「うち」意識、「うちらしく」の道徳といった「である」社会の作法が公然と求められる集団。
近代化 「西欧化」=「する」価値の浸透
「である」価値が根を張る
「である」社会のモラル
↓ セメント化
「する」原理を建て前とする組織
∥
近代的組織や制度
↓
閉鎖的な集団 「うちらしく」の道徳
「である」行動様式と「する」行動様式とのごった返し
↓
ノイローゼ症状
㉒ この矛盾は、戦前の日本では、周知のように「臣民の道」という行動様式への「帰一」によって、かろうじて弥縫されていたわけです。とすれば「国体」という支柱が取り払われ、しかもいわゆる「大衆社会」的諸相が急激に蔓延した戦後において、日本が文明開化以来抱えてきた問題性が爆発的に各所にあらわになったとしても怪しむに足りないでしょう。ここで厄介なのは、単に「前近代性」の根強さだけではありません。
㉓ むしろより厄介なのは、これまであげた政治の例が示しているように「『する』こと」の価値に基づく不断の検証が最も必要なところでは、それが著しく欠けているのに、他方〈 さほど切実な必要のない面、あるいは世界的に「する」価値のとめどない侵入が反省されようとしているような部面 〉では、かえって効用と能率原理が驚くべき速度と規模で進展しているという点なのです。
㉔ それはとくに大都市の消費文化において甚だしいのです。私たちの住居の変化――「である」原理が象徴している床の間つき客間の衰退に代わって、「使う」見地からの台所・居間の進出や家具の機能化――とか、日本式宿屋――ご承知のようにある室の客であることから食事そのほかあらゆるサービスの享受権が「流れ出」ます。なじみの客ほどそうです――がホテル化していく傾向などはまだそれなりの意味もありましょう。しかしたとえば「休日」や「閑暇」の問題になるとどうだろうか。都会の勤め人や学生にとって休日はもはや静かな憩いと安息の日ではなく、日曜大工から夜行列車のスキーまで、むしろ休日こそ恐ろしく多忙に「する」日と化しています。最近も「レジャーをいかに使うか」というアンケートをもらったことがあります。レジャーは「『する』こと」からの解放ではなくて、最も有効に時間を組織化するのに苦心する問題になったわけです。それだけではありません。学芸のあり方を見れば、そこにはすでに滔々として〈 大衆的な効果と卑近な「実用」の規準 〉が押し寄せてきている。最近もあるアメリカの知人が、アメリカでは研究者の昇進がますます論文著書の内容よりも、一定期間にいくら多くのアルバイトを出したかで決められる傾向があるという嘆きを私に語っていたことがあります。日本の大学における教授の終身制は一面ではたしかに学問的不毛の源泉であり、なんらかの実効的な検証が必要と言えます。けれども皮肉なことには、こうした日本の大学の身分的要素が、右のような形の「業績主義」の無制限な氾濫に対する防波堤にもなっているのでして、それほど文化の一般的芸能化の傾向はすさまじいと言わねばなりません。
Q47「さほど切実な必要のない面、あるいは世界的に「する」価値のとめどない侵入が反省されようとしているような部面」の具体例を、次の段落から抜き出せ。
A47 大都市の消費文化 休日 学芸
Q48「大衆的な効果と卑近な「実用」の基準」とはどういうことか。
A48 どれだけ大衆に認められたか、どれだけ実用的に機能するかという「する」価値にもとづく基準ということ。