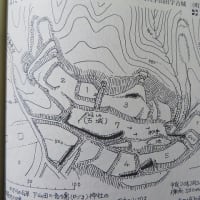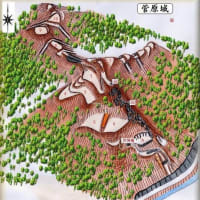産経ニュース
「赤備え」再編し直政奮迅
井伊虎松(後の直政)は、今川氏が滅亡し遠江国が徳川家康の支配下になった天正3(1575)年2月、井伊谷に戻った。御年(おんとし)15。井伊家再興を目指す直虎(次郎法師)らの働きにより家康に仕官して「万千代」と称した。
この頃の家康は武田勝頼との戦いに明け暮れていた。天正9年3月の高天神城の攻防戦では、徳川四天王である本多忠勝や榊原康政らと並び「旗本先手の将」という“家康付き”の先陣隊長に万千代は登用されている。
翌10年3月に武田氏は滅亡し、さらに織田信長が本能寺で討たれると、武田氏旧領を家康と小田原の北条氏との間で争奪戦となった。しかし、双方が争うのは得策でないため和睦交渉が始まり、その使者に抜擢(ばってき)されたのが22歳の万千代であった。この年、武田氏の旧臣ら117人を付属させ、武田軍の赤備えを再編して「井伊の赤備え」が誕生する。名も「直政」と改めた。
信長亡き後は、天下取りに邁進(まいしん)する豊臣秀吉と織田信雄・家康の連合軍が、天正12年4月の小牧・長久手で激突。この戦いは「三河中入り策」といわれ、徳川軍にとって手薄となっていた岩崎城(日進市)が、秀吉軍の猛将・池田恒興や森長可らに攻め落とされた。後を追うように家康も出陣し、従った直政も赤備えを率いて先鋒(せんぽう)を務め、見事猛将2人を討ち取った。
戦いはこれで終わったわけでなく、対立関係は2年半に及んだ。家康に救いを求めてきた信雄だったが、秀吉の攻めに疲弊し、勝手に講和を結んでしまった。三河深溝(ふこうず)の松平家忠が家康側近として仕えた約17年間を記した『家忠日記』によると、「秀吉の三河侵攻に備えて、岡崎城と周辺城郭を改造し女房衆の浜松へ疎開」とある。
天正14年になると、秀吉は作戦を変え、家康を何とか臣従させることを考えた。そして人質に母の大政所を岡崎に送った。この警衛役にあたったのが直政で、その奉仕ぶりは秀吉も感謝したと伝わる。(静岡古城研究会会長 水野茂)
「赤備え」再編し直政奮迅
井伊虎松(後の直政)は、今川氏が滅亡し遠江国が徳川家康の支配下になった天正3(1575)年2月、井伊谷に戻った。御年(おんとし)15。井伊家再興を目指す直虎(次郎法師)らの働きにより家康に仕官して「万千代」と称した。
この頃の家康は武田勝頼との戦いに明け暮れていた。天正9年3月の高天神城の攻防戦では、徳川四天王である本多忠勝や榊原康政らと並び「旗本先手の将」という“家康付き”の先陣隊長に万千代は登用されている。
翌10年3月に武田氏は滅亡し、さらに織田信長が本能寺で討たれると、武田氏旧領を家康と小田原の北条氏との間で争奪戦となった。しかし、双方が争うのは得策でないため和睦交渉が始まり、その使者に抜擢(ばってき)されたのが22歳の万千代であった。この年、武田氏の旧臣ら117人を付属させ、武田軍の赤備えを再編して「井伊の赤備え」が誕生する。名も「直政」と改めた。
信長亡き後は、天下取りに邁進(まいしん)する豊臣秀吉と織田信雄・家康の連合軍が、天正12年4月の小牧・長久手で激突。この戦いは「三河中入り策」といわれ、徳川軍にとって手薄となっていた岩崎城(日進市)が、秀吉軍の猛将・池田恒興や森長可らに攻め落とされた。後を追うように家康も出陣し、従った直政も赤備えを率いて先鋒(せんぽう)を務め、見事猛将2人を討ち取った。
戦いはこれで終わったわけでなく、対立関係は2年半に及んだ。家康に救いを求めてきた信雄だったが、秀吉の攻めに疲弊し、勝手に講和を結んでしまった。三河深溝(ふこうず)の松平家忠が家康側近として仕えた約17年間を記した『家忠日記』によると、「秀吉の三河侵攻に備えて、岡崎城と周辺城郭を改造し女房衆の浜松へ疎開」とある。
天正14年になると、秀吉は作戦を変え、家康を何とか臣従させることを考えた。そして人質に母の大政所を岡崎に送った。この警衛役にあたったのが直政で、その奉仕ぶりは秀吉も感謝したと伝わる。(静岡古城研究会会長 水野茂)