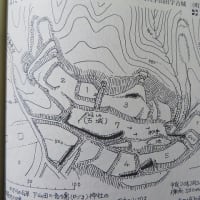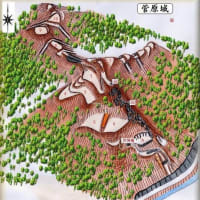男でなければ活躍しなかったかのように思われる戦国時代だが、NHK大河ドラマ『おんな城主 直虎』のように、戦国の世をたくましく生きた女性はほかにもいる。そんな女傑たちを紹介しよう。
●立花ぎん千代(たちばなぎんちよ、「ぎん」は門がまえに言、1569~1602年)
加藤清正を退却させたエリートおんな城主。立花ぎん千代は、7歳のときに父・立花道雪から立花城の城督、城領、諸道具の一切を譲り受けた。
「道雪が56歳と年を取ってからもうけた娘で、可愛がり過ぎたあまり家督を継がせた。容姿端麗で、剣術や学問などをしっかり学ぶ女性だったと伝えられています」(歴史作家で多摩大学客員教授の河合敦氏)
13歳で婿として迎えた夫・宗茂が朝鮮出兵に出ている間、秀吉がぎん千代をわが物にしようと名護屋城(佐賀県唐津市)に呼び出したことがある。このときぎん千代が長刀を構え、鉢巻・襷(たすき)がけで現われたことに、秀吉は「戦時である。立派な心構え」と苦笑いしたという。
西軍に参じた関ヶ原の戦いで夫が敗走した際は、城を明け渡すよう追ってきた東軍の猛将・加藤清正に反撃の構えを見せた。それを見て、清正が「みすみすわが兵を損ねることはあるまい」と引き返したと伝えられている。
●小松姫(こまつひめ、1573~1620年)
鎧姿の肖像画が残る「本多忠勝の娘」。昨年の大河『真田丸』で吉田羊が演じた小松姫は、真田信之の妻で無敵の武将・本多忠勝の娘である。
「小松姫の最も有名なエピソードは、関ケ原の戦い直前に真田家が徳川方と豊臣方に分かれた際、夫とともに徳川側につき、沼田城に入ろうとする豊臣方の義父・昌幸、幸村親子の計画を阻止したことです」(河合氏)
徳川四天王と讃えられた父・本多忠勝譲りの勝ち気な性格だったといわれており、鎧をまとった肖像画も残っている。●岩村御前(いわむらごぜん、生年不詳~1575年)
甥・信長に磔にされた裏切りのおんな城主。岩村御前は、歴史小説などでは「おつやの方」とも呼ばれている。織田信長の叔母にあたるが、政略結婚で東美濃(現在の岐阜県恵那市)・岩村城の城主、遠山景任(かげとう)に嫁がされた。
信長と武田信玄が対立すると、美濃・信濃国境に近い岩村城は信玄配下の秋山虎繁の軍勢に攻められる。景任は信長に援軍を要請するが無視され、城は死守したがこのときの負傷がもとで死亡。景任に跡継ぎがいなかったので、岩村御前は信長に一族を城主として送り込むよう要請したが、派遣されたのは信長の五男で当時15歳の御坊丸だったため、岩村御前が実質的城主となった。
その後も虎繁との攻防が続いたが、信長からの援軍は来ず、降伏を余儀なくされる。ここでなんと、虎繁は岩村城に入り、岩村御前を妻に迎える。それほどの美貌の持ち主だった。
ところが、天正3年(1575年)5月21日の長篠・設楽原(したらがはら)の戦いで武田勝頼が大敗すると力関係が逆転。今度は織田軍が岩村城を攻めて落城させた。虎繁と岩村御前は織田軍から「赦免する」といわれたが、それは2人をおびき出すための罠で、生け捕られた後に逆さ磔で処刑された。
「その際、岩村御前は『援軍を寄越さないから武田軍に降伏するしかなかった。叔母の私にこのような仕打ちをするのか』と壮絶な恨みの言葉を信長に向けて残しています」(河合氏)
現在、岩村城があった岐阜県岩村町では、岩村御前の肖像をラベルにした日本酒「女城主」が名産品となっている。
※週刊ポスト2017年2月3日号
●立花ぎん千代(たちばなぎんちよ、「ぎん」は門がまえに言、1569~1602年)
加藤清正を退却させたエリートおんな城主。立花ぎん千代は、7歳のときに父・立花道雪から立花城の城督、城領、諸道具の一切を譲り受けた。
「道雪が56歳と年を取ってからもうけた娘で、可愛がり過ぎたあまり家督を継がせた。容姿端麗で、剣術や学問などをしっかり学ぶ女性だったと伝えられています」(歴史作家で多摩大学客員教授の河合敦氏)
13歳で婿として迎えた夫・宗茂が朝鮮出兵に出ている間、秀吉がぎん千代をわが物にしようと名護屋城(佐賀県唐津市)に呼び出したことがある。このときぎん千代が長刀を構え、鉢巻・襷(たすき)がけで現われたことに、秀吉は「戦時である。立派な心構え」と苦笑いしたという。
西軍に参じた関ヶ原の戦いで夫が敗走した際は、城を明け渡すよう追ってきた東軍の猛将・加藤清正に反撃の構えを見せた。それを見て、清正が「みすみすわが兵を損ねることはあるまい」と引き返したと伝えられている。
●小松姫(こまつひめ、1573~1620年)
鎧姿の肖像画が残る「本多忠勝の娘」。昨年の大河『真田丸』で吉田羊が演じた小松姫は、真田信之の妻で無敵の武将・本多忠勝の娘である。
「小松姫の最も有名なエピソードは、関ケ原の戦い直前に真田家が徳川方と豊臣方に分かれた際、夫とともに徳川側につき、沼田城に入ろうとする豊臣方の義父・昌幸、幸村親子の計画を阻止したことです」(河合氏)
徳川四天王と讃えられた父・本多忠勝譲りの勝ち気な性格だったといわれており、鎧をまとった肖像画も残っている。●岩村御前(いわむらごぜん、生年不詳~1575年)
甥・信長に磔にされた裏切りのおんな城主。岩村御前は、歴史小説などでは「おつやの方」とも呼ばれている。織田信長の叔母にあたるが、政略結婚で東美濃(現在の岐阜県恵那市)・岩村城の城主、遠山景任(かげとう)に嫁がされた。
信長と武田信玄が対立すると、美濃・信濃国境に近い岩村城は信玄配下の秋山虎繁の軍勢に攻められる。景任は信長に援軍を要請するが無視され、城は死守したがこのときの負傷がもとで死亡。景任に跡継ぎがいなかったので、岩村御前は信長に一族を城主として送り込むよう要請したが、派遣されたのは信長の五男で当時15歳の御坊丸だったため、岩村御前が実質的城主となった。
その後も虎繁との攻防が続いたが、信長からの援軍は来ず、降伏を余儀なくされる。ここでなんと、虎繁は岩村城に入り、岩村御前を妻に迎える。それほどの美貌の持ち主だった。
ところが、天正3年(1575年)5月21日の長篠・設楽原(したらがはら)の戦いで武田勝頼が大敗すると力関係が逆転。今度は織田軍が岩村城を攻めて落城させた。虎繁と岩村御前は織田軍から「赦免する」といわれたが、それは2人をおびき出すための罠で、生け捕られた後に逆さ磔で処刑された。
「その際、岩村御前は『援軍を寄越さないから武田軍に降伏するしかなかった。叔母の私にこのような仕打ちをするのか』と壮絶な恨みの言葉を信長に向けて残しています」(河合氏)
現在、岩村城があった岐阜県岩村町では、岩村御前の肖像をラベルにした日本酒「女城主」が名産品となっている。
※週刊ポスト2017年2月3日号