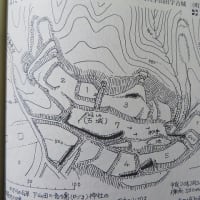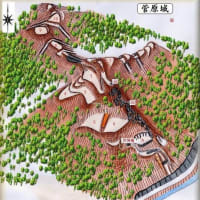ironnaというサイトに井伊直虎の記事が掲載されています。
渡邊大門(歴史学者)
2017年の大河ドラマは、「おんな城主 直虎」である。主人公は井伊直虎。男性のような名前であるが、実は女性ということで話題になっているようだ。しかも大きなポイントは、「おんな城主」というところにある。
これまで、大河ドラマでは、女性がたびたび主人公として起用されてきた。しかし、彼女たちはあくまで大名に寄り添う妻としての立場として描かれており、大名家の当主を務めていたわけではなかった。しかし、直虎はそれらの女性と一線を画しており、当主の権限を代行する役割を担っていた。
井伊直虎は生年不詳(1520年前後の生まれと推測)。父は、直盛である。井伊氏は井伊谷(浜松市北区)を本拠とする国人で、おおむね平安時代末期ごろから史料上で確認できる。ただ、中小領主の悲哀でもあるが、戦国期は今川、松平(徳川)、武田などの強大な戦国大名の狭間で翻弄された。
〔井伊家略系図〕 直平┬直宗――直盛――直虎
└直満――直親――直政(虎松・万千代)
Ads by Kiosked
直虎の祖父・直宗は、天文11年(1542)の田原城攻めで戦死。永禄3年(1560)、今川氏の配下として出陣した父・直盛は、桶狭間の戦いで戦死する。永禄6年には、直平(直虎の曽祖父)も犬居城の戦いで亡くなった。その後も、井伊家の重臣が戦いで討ち死にするなど不幸が続き、翌永禄7年に虎松(のちの直政)も三河国鳳来寺に出奔せざるを得なくなった。こうして井伊家は危機に瀕する。
ここで颯爽と登場するのが直虎である。これより以前、直虎は許嫁である一族の直親との婚約が破談に終わり、「次郎法師」と号して出家していた。しかし、一族の男たちがことごとく亡くなったため、急遽、井伊家の家督を継いだのである。
直虎の存在が特筆されるのは、自らが黒印状を認め、龍潭寺(浜松市北区)へ寺領の寄進などを行っていることである。また、直虎は寺領の寄進だけではなく、徳政令(債務を破棄すること)の発布などにも関与している。
井伊家の菩提寺、龍譚寺(同寺提供)
通常、女性の書状は消息と言われ、そのほとんどが平仮名で書かれている。内容は権利付与を伴うような重要度の高いものではなく、普通の私信が大半である。相手に近況を知らせたり、あるいは相手の様子をうかがうのが主だったのだ。
これまでの古文書学では、女性は花押(サイン)や印(黒印または朱印)を用いないとされてきた。しかし、直虎を含めた同様の例がいくつか報告されており、もはや通説は覆されている。直虎のように、権利付与を伴った文書を発給する例も確認済だ(後述)。
そのような意味で、直虎の存在はクローズアップされたのだ。なお、詳細は拙著『おんな領主 井伊直虎』(中経の文庫)をご一読いただけると幸いである。 「おんな戦国大名」の嚆矢といえば、播磨国守護・赤松政則の後妻である洞松院尼(細川勝元の娘)が有名だ。明応5年(1496)に政則が亡くなると、政則の後継者で養子の義村の後見人となった。義村がまだ幼少だったからだ。
実は、洞松院尼も黒印状を発給し、所領の安堵などを行っていた(文面は平仮名)。しかし、内容は亡き夫の政則の先例を認めるもので、必ずしも自ら新機軸を打ち出したものではない。つまり、自身が当主として家をリードするというよりも、若い後継者候補(義村)が成長するまでの「中継ぎ役」といえるであろう。その点は、直虎も「直政が成長するまで」という条件付きであったと考えられる。
その点は、今川氏親の妻・寿桂尼も同じであった。大永6年(1526)に夫の氏親が亡くなると、後継者の氏輝の後見人として今川家を引っ張っていった。寿桂尼も直虎や洞松院尼と同じく、黒印状を発給している。ただ、それは氏輝が成長するまでの「中継ぎ役」であったのは、いうまでもないところだ。
静岡市中心部に位置する谷津山の麓、龍雲寺にある今川義元の母、寿桂尼の墓。「死しても今川の守護たらん」と遺言し、駿府の鬼門(東北)にあたる同寺を墓所に選んだと伝えられる(大野正利撮影)
ただ、洞松院尼も寿桂尼も並の女性ではなかった。洞松院尼は赤松氏の危機に際し、自ら身を賭して細川氏との和睦交渉に赴いている。寿桂尼も氏輝が夭折したあとの家督争いや(花倉の乱)、武家家法の「今川仮名目録」の制定に関与した可能性があるとされている。いわゆる「女傑」だったのだ。
このように戦国時代においては、女性が当主の権限を代行することが珍しくなかった。直虎たちの例はやや極端であるが、戦国大名家における女性たちの発言権は、少なからずあったと指摘されている。
Ads by Kiosked
直虎については極端に史料が乏しく、1年を通して放映するにはかなりの想像力が必要に思う。これまでと違った「おんな戦国大名」を主人公として、どのような演出が行われるのか今から大いに期待している。
ここ数年の大河ドラマは、「ホームドラマ化」したといわれて久しい。たとえば、親子や兄弟姉妹の愛情、友達同士の麗しい友情などを含め、さまざまな教育的な配慮がなされている。身分の低い主人公が主人である大名と友達のように会話をするのは、ドラマの進行上やむをえないないのだろうか。
最近では、2011年の大河ドラマ「江〜姫たちの戦国〜」の主人公、江の演じ方があまりに斬新すぎ、いささか不興を買ったようである。かつての時代劇全盛期を知るご年配の方にとっては、いささか物足りないようだ。
戦国時代は、生きるか死ぬかの厳しい時代であり、ときに親が子を殺し、子が親を殺すような非情な時代であった。やはり、時代劇にはかつての名作のように、しびれるような重厚感や見応えがほしいところである。
直虎は、きっと男以上の高い才覚を持っていたのだろう。とにかく「おんな城主 直虎」には、大いに期待したいところだ。
渡邊大門(歴史学者)
2017年の大河ドラマは、「おんな城主 直虎」である。主人公は井伊直虎。男性のような名前であるが、実は女性ということで話題になっているようだ。しかも大きなポイントは、「おんな城主」というところにある。
これまで、大河ドラマでは、女性がたびたび主人公として起用されてきた。しかし、彼女たちはあくまで大名に寄り添う妻としての立場として描かれており、大名家の当主を務めていたわけではなかった。しかし、直虎はそれらの女性と一線を画しており、当主の権限を代行する役割を担っていた。
井伊直虎は生年不詳(1520年前後の生まれと推測)。父は、直盛である。井伊氏は井伊谷(浜松市北区)を本拠とする国人で、おおむね平安時代末期ごろから史料上で確認できる。ただ、中小領主の悲哀でもあるが、戦国期は今川、松平(徳川)、武田などの強大な戦国大名の狭間で翻弄された。
〔井伊家略系図〕 直平┬直宗――直盛――直虎
└直満――直親――直政(虎松・万千代)
Ads by Kiosked
直虎の祖父・直宗は、天文11年(1542)の田原城攻めで戦死。永禄3年(1560)、今川氏の配下として出陣した父・直盛は、桶狭間の戦いで戦死する。永禄6年には、直平(直虎の曽祖父)も犬居城の戦いで亡くなった。その後も、井伊家の重臣が戦いで討ち死にするなど不幸が続き、翌永禄7年に虎松(のちの直政)も三河国鳳来寺に出奔せざるを得なくなった。こうして井伊家は危機に瀕する。
ここで颯爽と登場するのが直虎である。これより以前、直虎は許嫁である一族の直親との婚約が破談に終わり、「次郎法師」と号して出家していた。しかし、一族の男たちがことごとく亡くなったため、急遽、井伊家の家督を継いだのである。
直虎の存在が特筆されるのは、自らが黒印状を認め、龍潭寺(浜松市北区)へ寺領の寄進などを行っていることである。また、直虎は寺領の寄進だけではなく、徳政令(債務を破棄すること)の発布などにも関与している。
井伊家の菩提寺、龍譚寺(同寺提供)
通常、女性の書状は消息と言われ、そのほとんどが平仮名で書かれている。内容は権利付与を伴うような重要度の高いものではなく、普通の私信が大半である。相手に近況を知らせたり、あるいは相手の様子をうかがうのが主だったのだ。
これまでの古文書学では、女性は花押(サイン)や印(黒印または朱印)を用いないとされてきた。しかし、直虎を含めた同様の例がいくつか報告されており、もはや通説は覆されている。直虎のように、権利付与を伴った文書を発給する例も確認済だ(後述)。
そのような意味で、直虎の存在はクローズアップされたのだ。なお、詳細は拙著『おんな領主 井伊直虎』(中経の文庫)をご一読いただけると幸いである。 「おんな戦国大名」の嚆矢といえば、播磨国守護・赤松政則の後妻である洞松院尼(細川勝元の娘)が有名だ。明応5年(1496)に政則が亡くなると、政則の後継者で養子の義村の後見人となった。義村がまだ幼少だったからだ。
実は、洞松院尼も黒印状を発給し、所領の安堵などを行っていた(文面は平仮名)。しかし、内容は亡き夫の政則の先例を認めるもので、必ずしも自ら新機軸を打ち出したものではない。つまり、自身が当主として家をリードするというよりも、若い後継者候補(義村)が成長するまでの「中継ぎ役」といえるであろう。その点は、直虎も「直政が成長するまで」という条件付きであったと考えられる。
その点は、今川氏親の妻・寿桂尼も同じであった。大永6年(1526)に夫の氏親が亡くなると、後継者の氏輝の後見人として今川家を引っ張っていった。寿桂尼も直虎や洞松院尼と同じく、黒印状を発給している。ただ、それは氏輝が成長するまでの「中継ぎ役」であったのは、いうまでもないところだ。
静岡市中心部に位置する谷津山の麓、龍雲寺にある今川義元の母、寿桂尼の墓。「死しても今川の守護たらん」と遺言し、駿府の鬼門(東北)にあたる同寺を墓所に選んだと伝えられる(大野正利撮影)
ただ、洞松院尼も寿桂尼も並の女性ではなかった。洞松院尼は赤松氏の危機に際し、自ら身を賭して細川氏との和睦交渉に赴いている。寿桂尼も氏輝が夭折したあとの家督争いや(花倉の乱)、武家家法の「今川仮名目録」の制定に関与した可能性があるとされている。いわゆる「女傑」だったのだ。
このように戦国時代においては、女性が当主の権限を代行することが珍しくなかった。直虎たちの例はやや極端であるが、戦国大名家における女性たちの発言権は、少なからずあったと指摘されている。
Ads by Kiosked
直虎については極端に史料が乏しく、1年を通して放映するにはかなりの想像力が必要に思う。これまでと違った「おんな戦国大名」を主人公として、どのような演出が行われるのか今から大いに期待している。
ここ数年の大河ドラマは、「ホームドラマ化」したといわれて久しい。たとえば、親子や兄弟姉妹の愛情、友達同士の麗しい友情などを含め、さまざまな教育的な配慮がなされている。身分の低い主人公が主人である大名と友達のように会話をするのは、ドラマの進行上やむをえないないのだろうか。
最近では、2011年の大河ドラマ「江〜姫たちの戦国〜」の主人公、江の演じ方があまりに斬新すぎ、いささか不興を買ったようである。かつての時代劇全盛期を知るご年配の方にとっては、いささか物足りないようだ。
戦国時代は、生きるか死ぬかの厳しい時代であり、ときに親が子を殺し、子が親を殺すような非情な時代であった。やはり、時代劇にはかつての名作のように、しびれるような重厚感や見応えがほしいところである。
直虎は、きっと男以上の高い才覚を持っていたのだろう。とにかく「おんな城主 直虎」には、大いに期待したいところだ。