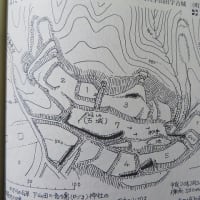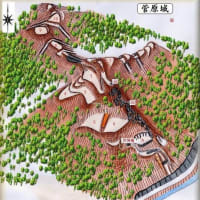石田三成の愛刀
そんな三成の愛刀は、「石田正宗」。棟(むね)や鎬(しのぎ)、茎棟(なかごむね)の刀身部分に深い切り込み瑕(きず)が二つあるところから「石田切込正宗」ともいわれている。鎌倉末期から南北朝時代初めに、相模国鎌倉で活躍した天才刀工・正宗の作刀で、刀身は2尺2寸7分(68.8センチ)。正宗は日本刀剣史上もっとも著名な刀工のひとりで、「相州伝」と称される作風を確立し、多くの弟子を育成した。正宗の刀剣は現在も、国宝、重要文化財級のものが多く、美術品としても大変高い評価を受けている。
『享保名物帳』(本阿弥光忠が編纂し幕府に提出した名刀リスト)に、元は毛利若狭守が所持していたところ、宇喜多秀家が400貫で買い取り、秀家から三成に贈られたと記されている。
三成は秀吉亡きあと「五奉行」のトップとして君臨するが、家康に匹敵する勢力を持っていた大老前田利家が病死すると、家康や他の奉行と対立。武断派の加藤清正、福島正則、黒田長政らの七将が、三成の大坂屋敷を襲撃する事件(石田三成襲撃事件)がおきる。伏見城内に逃れていた三成は、敵対する家康に保護を求めるという奇策をうち世間を驚かせた。関ケ原の戦いで敗れ、六条河原で処刑された末路はあまりにも有名だ。その事件後、帰城する三成を警護したのが家康の次男である結城秀康。三成は感謝の印として秀康に「石田正宗」を贈り、秀康死後は子孫の津山松平家に代々伝えられた。
「秀康は三成と親交があり、秀康は三成のことを兄・信康と重ね合わせて見ていたようです。単に刀をもらった以上の感情があったはずです」と石田三成の15代目の子孫・石田秀雄さん。
「石田正宗」は実戦力と機能美、あるいは芸術性と強靭性が見事に融合している点が独創的だ。鎌倉期独特の多様な刃紋の美しさは刀剣美の極致、と言っていい。
「実は石田家には前田大名家から賜った刀が昭和20年8月まであったんです。しかし、空襲で焼失してしまいました。私は直接見たことはないのですが、名刀だったことは間違いありません」(同)
新潟・妙高にあった石田家は東京・八王子に転居。その際に前田公からの刀をはじめ石田家伝来の文物を同時に移していたのだ。
三成は武将ではあるが、刀剣を持って積極的に戦うタイプではなく、刀についてもあまり執着がなかったのではと石田さんは話す。
「前田大名家から賜った刀がなくなったのが残念ですが、平和を願った三成のことを考えると、刀が必要ない世の中をきっと望んでいたはずです」(同)(ライター・植草信和、本誌・鮎川哲也)
※週刊朝日 2017年2月3日号
そんな三成の愛刀は、「石田正宗」。棟(むね)や鎬(しのぎ)、茎棟(なかごむね)の刀身部分に深い切り込み瑕(きず)が二つあるところから「石田切込正宗」ともいわれている。鎌倉末期から南北朝時代初めに、相模国鎌倉で活躍した天才刀工・正宗の作刀で、刀身は2尺2寸7分(68.8センチ)。正宗は日本刀剣史上もっとも著名な刀工のひとりで、「相州伝」と称される作風を確立し、多くの弟子を育成した。正宗の刀剣は現在も、国宝、重要文化財級のものが多く、美術品としても大変高い評価を受けている。
『享保名物帳』(本阿弥光忠が編纂し幕府に提出した名刀リスト)に、元は毛利若狭守が所持していたところ、宇喜多秀家が400貫で買い取り、秀家から三成に贈られたと記されている。
三成は秀吉亡きあと「五奉行」のトップとして君臨するが、家康に匹敵する勢力を持っていた大老前田利家が病死すると、家康や他の奉行と対立。武断派の加藤清正、福島正則、黒田長政らの七将が、三成の大坂屋敷を襲撃する事件(石田三成襲撃事件)がおきる。伏見城内に逃れていた三成は、敵対する家康に保護を求めるという奇策をうち世間を驚かせた。関ケ原の戦いで敗れ、六条河原で処刑された末路はあまりにも有名だ。その事件後、帰城する三成を警護したのが家康の次男である結城秀康。三成は感謝の印として秀康に「石田正宗」を贈り、秀康死後は子孫の津山松平家に代々伝えられた。
「秀康は三成と親交があり、秀康は三成のことを兄・信康と重ね合わせて見ていたようです。単に刀をもらった以上の感情があったはずです」と石田三成の15代目の子孫・石田秀雄さん。
「石田正宗」は実戦力と機能美、あるいは芸術性と強靭性が見事に融合している点が独創的だ。鎌倉期独特の多様な刃紋の美しさは刀剣美の極致、と言っていい。
「実は石田家には前田大名家から賜った刀が昭和20年8月まであったんです。しかし、空襲で焼失してしまいました。私は直接見たことはないのですが、名刀だったことは間違いありません」(同)
新潟・妙高にあった石田家は東京・八王子に転居。その際に前田公からの刀をはじめ石田家伝来の文物を同時に移していたのだ。
三成は武将ではあるが、刀剣を持って積極的に戦うタイプではなく、刀についてもあまり執着がなかったのではと石田さんは話す。
「前田大名家から賜った刀がなくなったのが残念ですが、平和を願った三成のことを考えると、刀が必要ない世の中をきっと望んでいたはずです」(同)(ライター・植草信和、本誌・鮎川哲也)
※週刊朝日 2017年2月3日号