
(つづき)
「長丘五丁目」バス停。

どうでもいい話だが、「上長尾」と「下長尾」の間ではあるものの、「中長尾」ではない。
また、「長丘」と付くものの、「長丘~高宮循環バス」のルートからは外れている。
バスが走る道路(県道桧原比恵線)が区境であり、



北行き(都心行き)は城南区側(時刻表には「快速57-1番」の前身である「快速56番」があり)、



南行き(郊外行き)は南区側に立つ。


北行きと南行きのバス停の間で「大池通り」(西は「福大通り」、東は「きよみ通り」にそれぞれ接続)が横切っており、「大池通り」上には「長尾変電所前」バス停があり。


「県道桧原比恵線」と「大池通り」の交差点の名称は、「長丘五丁目」でも「長尾変電所前」でも(「中長尾」でも)なく、「樋井川三丁目」。
交差点の四隅の町名が、「長尾三丁目」「樋井川三丁目」「西長住一丁目」「長丘五丁目」と、丁目の数字だけでなく町名も全て異なるため、交差点の名称として、どれを付けてもいまいちしっくりこない感があり(あくまで個人的な感覚ですが。また、「渡辺通一丁目」のように、他の3隅と比較して圧倒的な優位性がある場合は話は別なのかもしれません)。
こういう場合は、「脇山口」「早良口」「~小学校前」「~公園前」のように、「面」ではなく「点」をあらわす名称のほうが効果を発揮しそうである。
「県道桧原比恵線」に「大池通り」が交わり、「大池通り」にもバスが通り始めた時点で、西鉄が、交差点周辺のバス停に「長尾四つ角」などの名前をもし付けていたならば、それが交差点の名称にも採用されて、一般にも広く使われるようになっていた可能性があるのでは?…などと、どうでもいいことをたまに考える。
(つづく)
「長丘五丁目」バス停。

どうでもいい話だが、「上長尾」と「下長尾」の間ではあるものの、「中長尾」ではない。
また、「長丘」と付くものの、「長丘~高宮循環バス」のルートからは外れている。
バスが走る道路(県道桧原比恵線)が区境であり、



北行き(都心行き)は城南区側(時刻表には「快速57-1番」の前身である「快速56番」があり)、



南行き(郊外行き)は南区側に立つ。


北行きと南行きのバス停の間で「大池通り」(西は「福大通り」、東は「きよみ通り」にそれぞれ接続)が横切っており、「大池通り」上には「長尾変電所前」バス停があり。


「県道桧原比恵線」と「大池通り」の交差点の名称は、「長丘五丁目」でも「長尾変電所前」でも(「中長尾」でも)なく、「樋井川三丁目」。
交差点の四隅の町名が、「長尾三丁目」「樋井川三丁目」「西長住一丁目」「長丘五丁目」と、丁目の数字だけでなく町名も全て異なるため、交差点の名称として、どれを付けてもいまいちしっくりこない感があり(あくまで個人的な感覚ですが。また、「渡辺通一丁目」のように、他の3隅と比較して圧倒的な優位性がある場合は話は別なのかもしれません)。
こういう場合は、「脇山口」「早良口」「~小学校前」「~公園前」のように、「面」ではなく「点」をあらわす名称のほうが効果を発揮しそうである。
「県道桧原比恵線」に「大池通り」が交わり、「大池通り」にもバスが通り始めた時点で、西鉄が、交差点周辺のバス停に「長尾四つ角」などの名前をもし付けていたならば、それが交差点の名称にも採用されて、一般にも広く使われるようになっていた可能性があるのでは?…などと、どうでもいいことをたまに考える。
(つづく)


















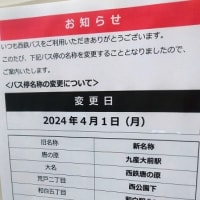


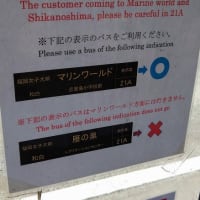










































昭和50年代前半には既に「下長尾」「長丘五丁目」「上長尾」の並びになっていたと思いますが、soramameさんに同じく、子供心に、
“なんで間に「長丘」をはさんでいるんだろう”
と、親の車に乗って眺める車窓にどうでもいいことを考えていた記憶があります。
今でこそ「県道檜原比恵線」で城南区と南区が分かれていますが、もとは道の両側が下長尾・上長尾という地名だったそうで、その真ん中を通るルートのバス停名もそれに倣ったのではないかと思います。
また、「長丘」「(西)長住」「樋井川」はいずれも町名改正で生まれた地名(もっと言えば「樋井川」は福岡市に合併する前の村の名前でもあった)だそうです。
昔の地図や航空写真を確認すると、いまの「上長尾」バス停付近と「下長尾」バス停付近の間はほぼ一面田んぼだけ(大池通りもなかった)だったようです。
ここをバスがいつ走り始めたかは知りませんが、「長丘五丁目」バス停はあとから設けられたのではと推測できますよね?
>昭和50年代前半には既に「下長尾」「長丘五丁目」「上長尾」の並びになっていたと思いますが、soramameさんに同じく、子供心に、
>“なんで間に「長丘」をはさんでいるんだろう”
>と、親の車に乗って眺める車窓にどうでもいいことを考えていた記憶があります。
親の車に乗って…というのも含め、全て同感です(笑)。
南行きについては、特に「長丘」が不自然な感じがあります。
手元にある昭和30年代の地図では、北から下長尾、上長尾という町名になっていて、バス停の記載はないのですが、地名に沿ってバス停の名前を付けて、「長丘五丁目」は後から付けたというのは、私もその通りだと思います。
その地図では、野間大池から先の大池通りもまだなく、穴観音から神松寺方面に抜ける道しかありません。
私の幼い頃でも、大池通りの西端の先、片江一丁目~小松ヶ丘間とか、油山観光道路の友泉団地~六本松西間とか、未開通だったことを考えると(当然、外環状道路とか地下鉄3号線なんて夢の夢だと思っていました)、道路整備が進んだものだなぁということを実感します。
その少し前に自動車学校の路上教習でその近辺を走り回っていましたが、「長尾」の地名に相当する部分だけが、ややのどかな感じのする地域だったという印象をもっています。
>手許にある、昭和53年6月の「福岡市内西鉄バス路線ご案内図」を見ると、たしかに「下長尾」、「長丘五丁目」、「上長尾」と並んでおり、すでに「長丘五丁目」が入っていますね。
下長尾と上長尾の間にあり、その2つと比較すると新しそうな響きもする「長丘五丁目」ですが、たしかに意外と古いんですよね。
下長尾、上長尾よりも後からできたことは正しいと思うのですが。
「長丘五丁目」を付けるにあたっては、一丁目から数えて大きな数字であることから、長丘の外れ…とまでは言わないまでも、「長丘の中心部ではない」というニュアンスを入れたつもりだった…という考え方ができるのかもしれませんね。
>その少し前に自動車学校の路上教習でその近辺を走り回っていましたが、「長尾」の地名に相当する部分だけが、ややのどかな感じのする地域だったという印象をもっています。
長住や長丘は、長尾をベースに付けられた「町」の名前でしょうから、「町」となった部分以外の、「長尾」として残っていた部分が長閑だったのは、合点がいく気がします。