1月6日にシャロン首相の脳出血に関する記載をした.いろいろ詮索するのは悪趣味かなとも思うのだが,先日のPFOに関する話題のみならず,色々な面で示唆に富み,勉強になるケースだと思われるので,再度,考察してみたい.
症例;77歳男性,BMI 約40.高血圧なし(推定).
経過; 12/18/05. TIA (transient aphasia)を主訴に来院.たぶんTEEでPFO without ASAの診断.
1/2/06. PFOに対する閉鎖術を1/5に行うと発表.
1/4/06. 大量の脳出血(右).第1回手術.術後,バルビツレート療法開始.
1/6/06. 脳出血再発.第2回手術.
1/8/06. 頭部CT改善傾向.
1/9/06. バルビツレート減量開始.自発呼吸出現.痛み刺激に反応.
1/9/06. 血圧低下から回復傾向.
1/14/06. バルビツレート中止.
1/15/06. 気管切開術.
1/16/06. 意識戻らず.
1/21/06. 人工呼吸器離脱検討.
さて最初の問題は「なぜTIA後に脳出血を起こしたか?」まず自然経過でTIA後に脳出血を来たした可能性はきわめて低い.個人的には当初,1/4/06にまず脳塞栓を発症し,3hを越えた時点でt-PAを使用したため,結果としてparenchymal hemorrhage (PH),ないしextraischemic hematomaを来たしたのではないかと考えた.少し聞き慣れない言葉かもしれないが,両者はt-PA使用後の脳出血のパターンとして,NINDSやECASS 1 & 2で使用されている言葉なので,覚えておいても損はない(注1).病態的にはischemic vasculopathyが進行し,血管がt-PA使用後の再灌流圧に耐えられず破綻した状態といえる.
もうひとつの可能性は,もともとアミロイドアンギオパチーが存在した可能性だ.つまりPFOの診断の後,(下肢深部静脈血栓の有無は不明だが)主治医はワーファリンを開始し,2週間が経過していた.そしてアミロイドアンギオパチーが存在したため,結果として脳葉型出血を引き起こした可能性が考えられる(個人的にはこの説のほうが信憑性が高いと考えている).アミロイドアンギオパチーによる脳内出血は高血圧の有無に関係なく,70才以上の高齢者に多く,大脳皮質に多発性に発生し,しかも再発率がいわゆる高血圧性脳内出血と比較して非常に高い.血腫除去術後の再出血の頻度も高い.教科書的には確定診断は剖検であるが,微小出血を繰り返すのでMRIのGREシークエンス(T2*)で疑うことはできたかもしれない(2005年11月5日の記事を参照).GREは今後の脳卒中診療ではきちんと使いこなせねばならない.
ここでは後者の仮説で話を進める(他の可能性があるようなら,コメントください).つぎに主治医が考えねばならないことはなんだろうか?当然,ワーファリンがしっかり効いているので,易出血の状態を回復し,さらに脳出血が大きい場合,手術の適応があるのか考えるということである.
次回,ワーファリンが効きすぎている症例に対してどういう治療を行うべきか,最新の治療について考えてみたい.
注1;基本的に3パターンに分けられていて,梗塞巣内に点状出血を来たすhemorrhagic infarct (HI),大きくmass effectを伴うPH,多発性に出現するextraischemic hematomaである.このなかでHIのみは予後に影響をしない.薬剤使用のルール違反はPH出現の危険因子である.またアミロイドアンギオパチー症例にt-PAを使用するとextraischemic hematomaになる頻度が高いと言われている.
注2;相変わらず好き勝手なことを書いておりますので,どうぞ批判的に読んでください.
症例;77歳男性,BMI 約40.高血圧なし(推定).
経過; 12/18/05. TIA (transient aphasia)を主訴に来院.たぶんTEEでPFO without ASAの診断.
1/2/06. PFOに対する閉鎖術を1/5に行うと発表.
1/4/06. 大量の脳出血(右).第1回手術.術後,バルビツレート療法開始.
1/6/06. 脳出血再発.第2回手術.
1/8/06. 頭部CT改善傾向.
1/9/06. バルビツレート減量開始.自発呼吸出現.痛み刺激に反応.
1/9/06. 血圧低下から回復傾向.
1/14/06. バルビツレート中止.
1/15/06. 気管切開術.
1/16/06. 意識戻らず.
1/21/06. 人工呼吸器離脱検討.
さて最初の問題は「なぜTIA後に脳出血を起こしたか?」まず自然経過でTIA後に脳出血を来たした可能性はきわめて低い.個人的には当初,1/4/06にまず脳塞栓を発症し,3hを越えた時点でt-PAを使用したため,結果としてparenchymal hemorrhage (PH),ないしextraischemic hematomaを来たしたのではないかと考えた.少し聞き慣れない言葉かもしれないが,両者はt-PA使用後の脳出血のパターンとして,NINDSやECASS 1 & 2で使用されている言葉なので,覚えておいても損はない(注1).病態的にはischemic vasculopathyが進行し,血管がt-PA使用後の再灌流圧に耐えられず破綻した状態といえる.
もうひとつの可能性は,もともとアミロイドアンギオパチーが存在した可能性だ.つまりPFOの診断の後,(下肢深部静脈血栓の有無は不明だが)主治医はワーファリンを開始し,2週間が経過していた.そしてアミロイドアンギオパチーが存在したため,結果として脳葉型出血を引き起こした可能性が考えられる(個人的にはこの説のほうが信憑性が高いと考えている).アミロイドアンギオパチーによる脳内出血は高血圧の有無に関係なく,70才以上の高齢者に多く,大脳皮質に多発性に発生し,しかも再発率がいわゆる高血圧性脳内出血と比較して非常に高い.血腫除去術後の再出血の頻度も高い.教科書的には確定診断は剖検であるが,微小出血を繰り返すのでMRIのGREシークエンス(T2*)で疑うことはできたかもしれない(2005年11月5日の記事を参照).GREは今後の脳卒中診療ではきちんと使いこなせねばならない.
ここでは後者の仮説で話を進める(他の可能性があるようなら,コメントください).つぎに主治医が考えねばならないことはなんだろうか?当然,ワーファリンがしっかり効いているので,易出血の状態を回復し,さらに脳出血が大きい場合,手術の適応があるのか考えるということである.
次回,ワーファリンが効きすぎている症例に対してどういう治療を行うべきか,最新の治療について考えてみたい.
注1;基本的に3パターンに分けられていて,梗塞巣内に点状出血を来たすhemorrhagic infarct (HI),大きくmass effectを伴うPH,多発性に出現するextraischemic hematomaである.このなかでHIのみは予後に影響をしない.薬剤使用のルール違反はPH出現の危険因子である.またアミロイドアンギオパチー症例にt-PAを使用するとextraischemic hematomaになる頻度が高いと言われている.
注2;相変わらず好き勝手なことを書いておりますので,どうぞ批判的に読んでください.

















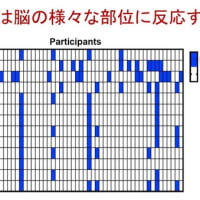








HIさん.ご指摘の通りです.次回,fFVIIa(ノボセブン)のことを中心にまとめるつもりです.