◇『もっと言ってはいけない』
著者:橘 玲 新潮社 刊 (新著新書)

前回『言ってはいけない』をご紹介したが、その続編である本書は「もっと
不愉快な本に違いない」と思ってはいけない。それは誤解で、
「言ってはいけない」ことをもっとちゃんと考えてみようという意味で、本書
では「私たち日本人は何者で、どのような世界に生きているのか」について書
いている(と筆者はまえがきで書いている)。
「遺伝決定論」を批判する人たちは、どのような困難も本人の努力や親の子
育て、あるいは周囲の大人たちの善意で乗り越えていけるはずだと頑強な信念
を持っている。だが本人がどれほど努力しても改善しない場合はその結論は決
まっている。努力しているつもりになっているだけで、努力が足りないのだ。
なぜなら困難は意志の力で乗り越えられるはずなのだから。
なるほどごもっともである。だが待てよ。努力をすればもう少しは成績が良
くなるかもしれないと、一縷の望みを頼りに努力をして、わずかながら結果が
見えて安堵する人もいるだろうから遺伝決定論をもって全否定することには無
理があると私は思う。
「行動遺伝学」では遺伝の影響は身体的特徴だけでなく、「こころ」にも及
んでいるとする。
ということで、プロローグでのっけから日本人の3分の1は日本語が読めな
いという統計的事実を示され驚かされる。OECDのPIAAC(Programme for the
International Assessment of Adult Competencies)の国際調査で、読解力、数的
思考力、ITを活用した問題解決能力の3分野のスキルの習熟度測定結果である。
またAIを用いて全国2万5千人の中高生の「基礎的読解力」を調査したとこ
ろ3人に1人が簡単な問題文が読めないことが分かった(新井紀子氏の調査)。
そこで筆者は言う。日本人の3割は、「むかしから教科書が読めない子ども
たち」だった。そんな中高生が長じて「日本語が読めない大人」になるのは当
然なのだ。
世の中に「氏より育ち」という見方がある。「氏」はもちろん生まれである。
行動遺伝学では「育ち」の方を共有環境と非共有環境に分ける。在野の心理学
者ジュディス・リッチ・ハリスは「共有環境」を「子育て」、「非共有環境」
を「友たち関係」と分類し、「遺伝」、「子育て」、「友だち関係」によって
「私」がどう作られるか考えた。
その結果殆どの領域で共有環境(子育て)の影響が計測できないほど小さく、
音楽や数学、スポーツなどの才能だけでなく外向性、協調性などの性格でも共
有環境の寄与度はゼロだったという。
行動遺伝学が発見したこうした「不都合な真実」は何を示すか。どんな子ど
もも、親が「正しい教育」をすれば輝けるなら、子どもが輝けないのは親の責
任で、子どもが犯罪者になるのは子育てが悪かった親の責任だということにな
る。(これは今では「言ってはいけないこと」になったので「社会が悪い」こ
とになった。)
自己家畜化
遺伝決定論によってユダヤ人が知的優位にあることが縷々説明されている。
東アジア系人種は中国人、朝鮮人、日本人とも遺伝子に大きな違いがない。明
治維新以降の日本の急速な経済発展は偶然のもたらしたもので日本人の優性を
示すものではないと筆者は言う。
東アジア系人種は旧石器時代に出現した打製石器に次いで農耕というイノベ
ーションによって狩猟採集生活から集団生活に移行した。そして農耕社会では
獰猛勇敢さが有用だった狩猟採集社会とは逆に温厚な気性が選択的に優遇され
たとみるのである。
人口稠密なムラ社会である東アジアでは農耕社会に最適化する気質・性格に進
化させてきたと見るのである。
人格評価上ビッグファイブと呼ばれる開放性、真面目さ、外向性、協調性、
精神的安定性の経済的成功との関係を見ると、人種的に顕著な違いがある。
東アジア人種の方が成功者が多いのである。
発達心理学者ジェローム・ケーガンの実験による刺激に対する高反応(内向
的脳)と低反応(外向的脳)に分けた場合、日本人は高反応系(刺激に敏感)
で生得的にセロトニン運搬遺伝子が少なく鬱病質であり、メランコリー親和型
(精神医学者手連・バッハ提唱)である。
日本人は、花でいえばたくましいタンポポより、適した環境では大輪の花を
咲かせるが環境が合わないととたんに萎れてしま うひ弱なランだというのが筆
者の比喩である。
かつて野球界で何かと脚光を浴びるN氏を向日葵に、それに引き換え能力が
ありながら日蔭者にある我が身を月見草に譬えた某氏もいたが…。
(以上この項終わり)
最新の画像[もっと見る]
-
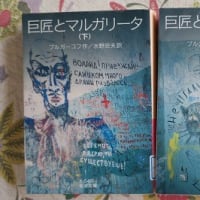 ブルガーコフの『巨匠とマルガリータ(上)』
1週間前
ブルガーコフの『巨匠とマルガリータ(上)』
1週間前
-
 令和6年のトマト栽培ー2ー
3週間前
令和6年のトマト栽培ー2ー
3週間前
-
 令和6年のトマト栽培ー2ー
3週間前
令和6年のトマト栽培ー2ー
3週間前
-
 令和6年のトマト栽培ー2ー
3週間前
令和6年のトマト栽培ー2ー
3週間前
-
 令和6年のトマト栽培ー2ー
3週間前
令和6年のトマト栽培ー2ー
3週間前
-
 令和6年のトマト栽培ー2ー
3週間前
令和6年のトマト栽培ー2ー
3週間前
-
 令和6年のトマト栽培ー2ー
3週間前
令和6年のトマト栽培ー2ー
3週間前
-
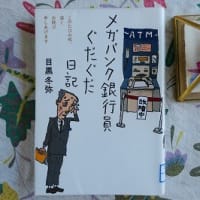 目黒冬弥の『メガ銀行銀行員ぐだぐだ日記』
4週間前
目黒冬弥の『メガ銀行銀行員ぐだぐだ日記』
4週間前
-
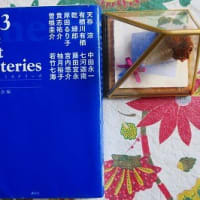 2013The Best Mysteries(ザ・ベストミストリーズ:推理小説年鑑)
1ヶ月前
2013The Best Mysteries(ザ・ベストミストリーズ:推理小説年鑑)
1ヶ月前
-
 令和6年のトマト栽培ーⅠー
1ヶ月前
令和6年のトマト栽培ーⅠー
1ヶ月前















