NHK教育TVで「日めくり万葉集」第2弾が始まりました。
平日の午前中ということで 勤めの方は ご覧になれません。
そこで ここで取り上げて 訳し・「みじかものがたり」を 掲載したく思います。
ご覧下さい。
【四月七日】放映分
★見れど飽かぬ 吉野の河の 常滑の 絶ゆることなく また還り見む
《見飽けへん 吉野の川に また来たい またまた来たい ずうっとずっと》
―柿本人麻呂―(巻一・三七)
【万葉歌みじかものがたり】《見れど飽かむ》

持統天皇の治世も ようやく 安定を見たころ
天皇は 思い起していた
(吉野
夫大海人と 越えた雪の峰 氷雨ふる山路 父天智との確執の後 手に入れた 地位
ああ 吉野が恋しい そうじゃ 離宮を作ろう 宮滝に離宮を)
風光明媚な 吉野宮滝
立派に 成った離宮
持統女帝の 吉野行幸が 重なる
行幸の 従駕人
そこには 必ず 人麻呂の姿があった
帝への 捧げ歌 人麻呂は詠う
やすみしし わご大君の 聞し食す 天の下に
国はしも 多にあれども 山川の 清き河内と
御心を 吉野の国の 花散らふ 秋津の野辺に 宮柱 太敷きませば
《天皇の お治めなさる 国々は 仰山あるが
山川の 綺麗なとこと 気に入りの 吉野の国の 秋津野に 宮殿作り おわしまし》
百磯城の 大宮人は 船並めて 朝川渡り 舟競ひ 夕河渡る
《お連れの人は 朝となく 夕となしに 船遊び》
この川の 絶ゆることなく この山の いや高知らす
水激つ 滝の都は 見れど飽かぬかも
《流れ続ける 川水と 高う高うに 茂る山 その滝の宮 見飽けへん》
―柿本人麻呂―(巻一・三六)
《見飽けへん 吉野の川に また来たい またまた来たい ずうっとずっと》
―柿本人麻呂―(巻一・三七)
見れど飽かぬ 吉野の河の 常滑の 絶ゆることなく また還り見む
人麻呂は 得心した
(これぞ 神の宮 寿ぎの歌)
――――――――――――――――――――
【新しい試みです】
「歌心関西訳」の作成過程をご覧ください。
これなら あなたも 訳せますよ。
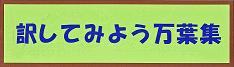 <訳してみよう万葉集>へ
<訳してみよう万葉集>へ
【万葉歌みじか物語】はこちら

<万葉歌みじかものがたり>へ
■リンク先






平日の午前中ということで 勤めの方は ご覧になれません。
そこで ここで取り上げて 訳し・「みじかものがたり」を 掲載したく思います。
ご覧下さい。
【四月七日】放映分
★見れど飽かぬ 吉野の河の 常滑の 絶ゆることなく また還り見む
《見飽けへん 吉野の川に また来たい またまた来たい ずうっとずっと》
―柿本人麻呂―(巻一・三七)
【万葉歌みじかものがたり】《見れど飽かむ》
【宮滝の激湍】

持統天皇の治世も ようやく 安定を見たころ
天皇は 思い起していた
(吉野
夫大海人と 越えた雪の峰 氷雨ふる山路 父天智との確執の後 手に入れた 地位
ああ 吉野が恋しい そうじゃ 離宮を作ろう 宮滝に離宮を)
風光明媚な 吉野宮滝
立派に 成った離宮
持統女帝の 吉野行幸が 重なる
行幸の 従駕人
そこには 必ず 人麻呂の姿があった
帝への 捧げ歌 人麻呂は詠う
やすみしし わご大君の 聞し食す 天の下に
国はしも 多にあれども 山川の 清き河内と
御心を 吉野の国の 花散らふ 秋津の野辺に 宮柱 太敷きませば
《天皇の お治めなさる 国々は 仰山あるが
山川の 綺麗なとこと 気に入りの 吉野の国の 秋津野に 宮殿作り おわしまし》
百磯城の 大宮人は 船並めて 朝川渡り 舟競ひ 夕河渡る
《お連れの人は 朝となく 夕となしに 船遊び》
この川の 絶ゆることなく この山の いや高知らす
水激つ 滝の都は 見れど飽かぬかも
《流れ続ける 川水と 高う高うに 茂る山 その滝の宮 見飽けへん》
―柿本人麻呂―(巻一・三六)
《見飽けへん 吉野の川に また来たい またまた来たい ずうっとずっと》
―柿本人麻呂―(巻一・三七)
見れど飽かぬ 吉野の河の 常滑の 絶ゆることなく また還り見む
人麻呂は 得心した
(これぞ 神の宮 寿ぎの歌)
――――――――――――――――――――
【新しい試みです】
「歌心関西訳」の作成過程をご覧ください。
これなら あなたも 訳せますよ。
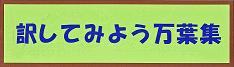 <訳してみよう万葉集>へ
<訳してみよう万葉集>へ【万葉歌みじか物語】はこちら

<万葉歌みじかものがたり>へ
■リンク先
















