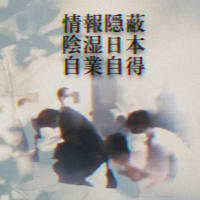[画像]長妻昭さん、2013年5月29日(水)、衆・厚労委、衆議院インターネット審議中継から。
【衆・厚労委 2013年5月29日(水)】
岡田内閣の官房長官候補と言えば、「昔北橋、今長妻」。北橋健治さんは北九州市長に転出してしまいましたが、今国会で長妻昭さんの存在感が飛躍的に増しています。
衆・厚労委は「戦後最大の改正」と言われる、生活保護法の改正法案(183閣法70号)と生活困窮者自立支援法案(71号)の審議に入りました。
生活保護行政を巡っては、政府自民党と厚労省が参院選後に「3年間で生活扶助を6・5%下げろ」と自治体(法定受託者)に通達する見通し。受給者の0・1%の不正受給者が問題視されるなかで、99・9%の受給者の手当が下げられてしまうという、自民党の十八番「論理のすり替え」。そもそも、アベノミクスで、2年間で年2%ずつ物価を上昇させているので、実質の下げはより大きく、まさに自民党政治ここにきわまる、としか言いようがありません。
この日の委員会では、長妻さんが登場するやいなや、「生活保護法の改正法案の24条を削除せよ」と迫りました。

[画像]生活保護法の改正案(上)と現在の法律(下)、厚生労働省、第183回国会提出法案のホームページから。筆者貼り合わせ。
このように、改正法案の第24条には「保護の開始の申請は」「申請書を保護の実施機関に提出しなければならない」とあります。
我が国はひらがな、カタカナ、漢字があるのに、識字率99%以上。でも、生活保護の申請書を書けない人はいっぱいいますし、正直、そういう方ほど生活保護が必要な場合が多々見られるのは言わずもがな。
長妻質問に先立ち、長年厚生労働委員をつとめる、公明党の古屋範子さんも「申請書を書き込むのが困難な人もいるます。現在は口頭による申請など柔軟な運用がなされています。生活保護の申請を書面で提出することについて、大臣は心配を払拭してください」と語りました。
[画像]答弁する田村憲久・厚生労働大臣。
田村憲久厚労相は「24条については、(自治体の)職員が(申請者からたずねて)書き込んでもOKで、調査をしっかり厳格化することが目的の条文です。そのためには申請の時点で何か書くことが必要なので、内閣法制局と相談のうえ、入れました」と答弁。「運用面では、今と何も変わりありません」と語りました。
長妻さんは、この24条について、村木厚子・厚労省「社会・援護局長」(昭和53年労働省)が民主党部門会議で、「内閣法制局のアドバイスで、『審査を厳格化するのなら法案の中に入れた方がよい』と言われ、加えたものだ」と語ったとしました。長妻さんは「生活保護は最後のセーフティーネットであって、(法定受託した自治体が窓口で申請者を追い返すことで生活保護費を浮かす)水際作戦を強化するための条文だ」として、「24条をとってください。削除してください」と迫りました。
[画像]答弁する村木厚子・厚生労働省社会・援護局長。
田村厚労相は「なぜとれないのか。それは国会に提出したからです」として、「実際には運用は変わりません。政府の情報発信が不十分でご迷惑をおかけしました。おわびしたい」と詫びました。
なお、閣法の修正は、衆院通過前ならば、本会議での承諾で可能。民主党政権3年3ヶ月のうち、衆参ねじれの2年5ヶ月間で、多用した手法です。が、今国会の流行からすると、民主党などの議員修正により、24条は修正され、事実上削除される見通しだと、私はみています。
話は変わりますが、「24条」。
ほぼ1年前の衆・社会保障と税の一体改革特別委では、児童福祉法24条の改正条文の解釈をめぐって、岡田克也副総理(昭和51年通産省)が山本庸幸・内閣法制局長官(昭和48年通産省)を叱る場面がありました。
(参考エントリー保育の最終責任者はだれ? 児童福祉法24条改正で答弁混乱 岡田副総理、法制局長官を叱責)
これは、2012年5月22日の委員会で、野党・自民党の田村憲久委員が児童福祉法24条について「市町村は保育しなければならない、とある条文を改正すると、市町村からあっせんされた私立の保育所で、事故があった場合、保育所の運営主体が倒産した場合、国家賠償請求を受けられないのではないか」との趣旨の質問をしました。これに対して、山本法制局長官が「改正の前と後とでどちらが重いかということはなかなか一概に比較することはできない」と答弁したところ、田村さんが法案の問題点だと一方的に論を進めた国会審議です。これについて、昼休みに岡田副総理が山本長官に答弁内容を問いただしました。岡田さんは「私も気になって、法制局長官にその後、確認をいたしましたが」「これはいわば当たり前の話であって」「やや誤解を招きやすい法制局長官の答弁だった」と語っています。つまり三世議員で、議運・国対の経験を蓄えた田村さんのペースに引き込まれてしまった法制局長官の官僚答弁をたしなめることで、自民党ペースから手綱を引き戻した出来事で、消費税増税法成立につながりました。
[画像]答弁する山本庸幸・内閣法制局長官。
この1年前の「児童福祉法24条事件」と、今回の「生活保護法24条事件」とは、登場人物がよく似ています。
まず、田村さんが昨年は野党議員として、今回は厚生労働大臣として登場しています。
そして、答弁者である山本・法制局長官は昨年も今年も同じ。
この法案の担当だった村木厚子・内閣府局長(共生社会担当政策統括官)は、今は厚労省社会・援護局長。
昨年は6月から修正実務者として登場した長妻昭さんは、今回も差し替えながら重要な指摘をしました。
この場にいないのは、落選してしまった小宮山洋子・厚労相(兼)内閣府担当相と、岡田副総理です。
では、なぜ、岡田さんは、初当選のときから所属した厚生労働委員会からいなくなってしまったのか。
国家公務員法100条は「国家公務員の守秘義務」、地方自治法100条は「地方議会の調査権限」を定めており、「100条」には重要な規定が多い傾向があります。この経緯は知りませんが、これは法案を書いた自治省など旧内務省系の官僚たちの志が行間からにじみ出ているように感じます。
それに引き替え、厚労省は、1本で済みそうな法案を2、3本に分けて出したり、毎通常国会に、「健康保険法の一部を改正する法律案」、「国民年金法の一部を改正する法律案」、「厚生年金法の一部を改正する法律案」など、一見すると何をどう変えるか分からない法案を平然と出すなど政治センスが極めて低い役所です。一体改革を実現した閣僚経験者も「財務省が必死に一体改革を実現させても、厚労省は使うことばかり考えて、まったく汗をかかない」と批判しています。この閣僚経験者が首相官邸首脳を務めている際には、厚労事務次官経験者が人事院総裁から更迭されました。
こうやってうんざりして厚労委員をやめる議員はあとをたちません。その中で、長く委員を務める公明党の古屋さんや、民主党の山井和則さん、そして、さしかえで登場してくる長妻昭さんの根気は日本を支えています。
労働省採用の村木さんが社会・援護局長をやっていることは、余人を以て代え難い、ということなのでしょう。このエントリーでは詳述しませんが、靖國神社にA級戦犯が合祀されてしまった経緯にも、社会・援護局をめぐる利権の波に官僚が流されたからです。村木さんはぜひ、事務次官もやって、その後は、宮内庁長官になって、厚生省や宮内庁を立て直してください。旧労働官僚が厚生省を乗っ取るぐらいでなければいけません。
2年連続で「24条問題」をおこした厚労省は別として、第183通常国会は、法案の修正と附帯決議をつくれる国会議員が中心になってきました。7月21日の第23回参院選で自民党が衆参とも単独過半数をとれば、その後の3年間は、政府が提出した法案が無修正で法律となり、各省が政令・施行令・通達ですべてを済ます政治になるでしょう。
残り28日間、志ある国会議員、それは自民党政府外議員も含めてですが、最後のチャンスと心得て、命がけで法律を修正し、附帯決議を付けて、前を見すえるべし。
[お知らせ1]
会員制ブログで今後の政治日程とそのポイントを解説しています。
今後の政治日程 by 下町の太陽
最初の1ヶ月は無料で試し読みできます。取材資金にもなりますので、ぜひご協力下さい。
[お知らせ2]
「国会傍聴取材支援基金」を設けました。他メディアにはない国会審議を中心とした政治の流れをこのブログで伝えていきます。質素倹約に努めていますが、交通費などがかかります。
「国会傍聴取材支援基金」の創設とご協力のお願い
ご協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
[お知らせおわり]