
6月からスタートした社内外勉強会は8月最終水曜日の本日をもって終了です。
毎回1時間という短い時間でしたが、皆さんの熱心さに支えられて勉強することができました。
まずは参加者の皆さまに御礼申し上げます。
最終回は、「24年介護保険改訂に向けての提言」でした。
といっても1時間という短い時間で提言ができるわけはありません。
様々な団体が提出している提言他を見ながら、各自の意見を述べました。
ポイントは、地域包括だからこそ提言できることは何かでした。
2点に絞りました。
1つ目は、要支援と要介護という棲み分けの是非です。
例えば、要支援1、要支援2、要介護1という区分けは必要なのかということです。
もちろん、給付制限という点では意味があるでしょうが、評価できることはありません。
大多数の人にとっては給付限度額に達することもできない仕組みになっています。
「現在のような機械的給付制限から、担当者会議での詳細決定へと変更すべし」
「現在のような細かな区分は必要ない。3段階でよい」
二つ目は、地域包括業務から予防給付を外すべきかということです。
これは意見が分かれました。
社会福祉士会は、相談業務を中心にし、介護予防ケアマネ業務、予防給付業務は外すべきだという考えで
主に社会福祉士にはこの意見の方が多い。
一方、所内のケアマネの方は、介護保険を直接扱うことのない地域包括は、ケアマネやサービス事業者から
相談相手として認められないのではないか、という意見です。
私は、予防給付業務を持つこと、具体的には要支援の方の顔を知っていることの意味はとても大きい。
このことが、地域包括の力の源であるということを話した。
社会資源である居宅やサービス事業所の人々とともに仕事をしていることは大きな財産であると思っている。
企業の中で、仕事をしてきた者にとって、顧客の大切さ以上のものはなかった。
これは骨身に染みていた。
しかし、このことが当たり前と思わないのがこの業界のようだ。
私は社会福祉士会の要望は間違っていると考えている。
この後は、少し煮詰めて「提言」として送りたい。
A4 1枚程度で十分でしょう。















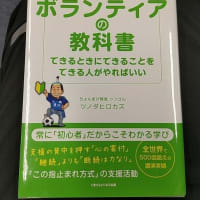




また、最後の予防対象者への考え方も、
私は居宅介護支援の立場から、
帳票類を介護・予防を一本化し
予防対象者を居宅に戻し、
地域包括の本来業務を行いやすく・・・、
という流れは、なんか違うんじゃない?
と感じていましたが、
今、求められいるアウトリーチの手段というは、
まさに、その通りと、感心しました。
私が地域包括の方とお話する機会はほとんど無く、
数少ない、会う機会に、それとなく探りをいれるのですが、
地域包括支援センターから、
このところの危機感を感じることは出来ないです。
コメントありがとうございます。
危機感のなさは、ご指摘通りです。
残念ながら仕事は与えられるものという姿勢ですね。
そして、「地域包括の業務は重要である」という意見に安住している。
そのことが危機感のなさに繋がっているのでしょう。
足元に深い穴が開いているにも関わらずです。
もしかすると来年度地域包括支援センターを委託するかもしれないとすると(もしかですが)、すでにその動きの計画をしなくてはならないように、人から離れての相談・ニーズの導きなどありえないと個人的に思っています。
コメントありがとうございます。
地域包括が相談業務中心になることは
私は現実的ではないと思います。
結城氏の提案が間違がって採用されることが
あれば可能性は零ではないでしょう。
しかし現在の予防の給付管理費がそのまま居宅に受け入れられることも考えられません。
厚労省は維持したいでしょうね。