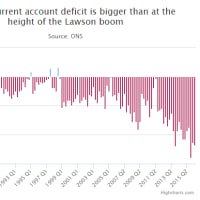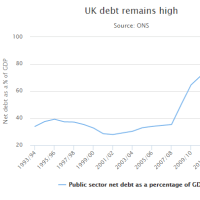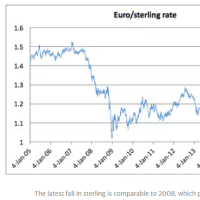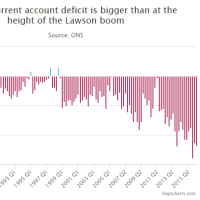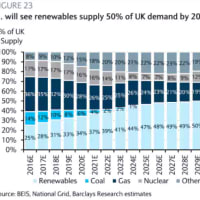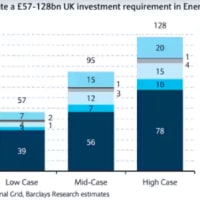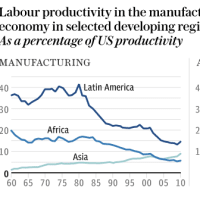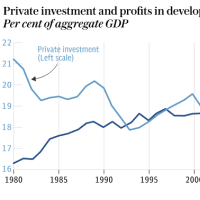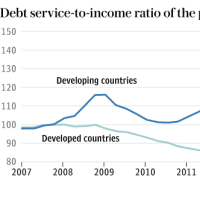Towards a radical new theory of Anglo-American slavery, and vindication of free markets
(ラジカルな新アングロ・アメリカン奴隷理論と自由市場証明への動き)
By Ambrose Evans-Pritchard
Telegraph: 7:53PM BST 07 Aug 2013


(ラジカルな新アングロ・アメリカン奴隷理論と自由市場証明への動き)
By Ambrose Evans-Pritchard
Telegraph: 7:53PM BST 07 Aug 2013
New evidence coming to light in the National Archives and the Bodleian Library may soon change our entire view of the British slave trade, and the roots of institutional plantation slavery in the Americas.
国立公文書館とボデリアン図書館で発見された新たな証拠は、英国の奴隷貿易の見解や米国のプランテーション奴隷制度のルーツを間もなく覆すかもしれません。
With luck it will help to vindicate the fathers of liberal government and the free market in the 17th and 18th Centuries, falsely accused until now of abetting - or promoting - the great crime of race-based African slavery.
運が味方してくれれば、17世紀と18世紀の自由政府と自由市場の父達は、人種に基づくアフリカ人奴隷制度という大犯罪を幇助(または推進)した、という濡れ衣を着せられていたと証明出来るでしょう。
For academic orthodoxy holds that John Locke and the great Whig thinkers of the Glorious Revolution (1688) helped to design and foster the economic system of hereditary slavery that shaped Atlantic capitalism for a century and a half.
学術的な通説は、ジョン・ロックと1688年名誉革命のホイッグ党の大思想家が、大西洋資本主義を1世紀半に亘って形作った世襲的奴隷制度の経済システムの設計と育成を助けたとしています。
From that it is but a step to dismiss the moral claims of liberalism as so much humbug, to write off all the talk of justice, natural rights, inviolable contracts and government by consent as the self-interested catechism of oppressors. As Samuel Johnson said acidly: "How is it we hear the loudest yelps for liberty among the drivers of negroes?"
その通説から一歩でも進めば、自由主義の道徳的主張など戯言だと却下し、正義、自然権、破ってはならない契約、合意による政府など、抑圧者の利己的な公共要理だと切り捨てることになります。
サミュエル・ジョンソン博士が辛辣に言い放った通りですね。
「二グロの親方が一番やかましく自由を喚き散らすとは何事だ?」
Except that this established version of events is not true. It is a near complete inversion of what happened, and this matters in all kinds of ways since the debate over slavery refuses to subside, even though the trade was abolished in 1808 and Empire slaves were freed in 1833.
この確立された事態の説明を除き、全ては本当ではありません。
実際に起こったことのほぼ真逆であり、これはあらゆる意味において重要です。
何故なら、奴隷貿易が1808年に廃止され、帝国の奴隷は1833年に解放されたにも拘らず、奴隷制度を巡る議論は沈静化を拒んでいます。
Indeed, it is coming to the boil again. The Caribbean states, CARICOM, are filing a lawsuit against Britain, Spain, France, Holland and Portugal for slavery reparations. Apologies are not enough, says Ralph Gonsalves, premier of Saint Vincent. "We have to have appropriate recompense."
そう、事態は再び白熱化しています。
カリブ海諸国で構成されるCARICOMは英国、スペイン、フランス、オランダ、ポルトガルを相手取って、奴隷賠償請求を行っています。
謝罪だけでは不十分だ、とセント・ビンセントのラルフ・ゴンサルヴェス首相は言います。
「我々は適切な償いを得なければならない」
It matters too because liberal democracy has been on the back foot in large parts of the world for a decade. China is bidding for global leadership with radically different claims - with allies in Moscow, and followers from Bangkok to Caracas. It seizes eagerly on anything that punctures the moral claims of the West.
また、自由民主主義がこの十年間、世界の大半で劣勢になっているため、これは重要なのです。
中国は抜本的に異なる主張を掲げ、モスクワの仲間と共にバンコクからカラカスまで支持者を集めて、世界覇権を争っています。
西側の道徳的主張を傷付けるものなら何でも飛び付きます。
Joshua Kurlantzick says in Democracy in Retreat that the "Washington Consensus" we have known for so long is losing ground to an ascendant "Beijing Consensus", the greatest challenge to Western Liberal values since fascism and communism in the 1920s and 1930s.
ジョシュア・カーランツィック氏は『Democracy in Retreat』の中でこう記しました。
長らく知られる「ワシントン・コンセンサス」は、台頭する「ペキン・コンセンサス」に地歩を奪われつつあり、これは1920年代、1930年代の西側の自由主義的な価値観に対するファシズムと共産主義の挑戦以来、最も大規模な脅威であると。
The banking crash of 2008-2009 has tempted some in China's Politburo to conclude that Leninist planning is superior to Anglo-Saxon markets, and prompted many in Europe to ask whether Capitalisme Sauvage is worth saving at all. They misread events of course. It was governments that caused the crisis: the West by fixing the price of credit too low, the East by amassing reserves and flooding the world with excess capital. But that is not the narrative of the web, or political discourse.
2008-2009年の銀行危機は、中国共産党政務局の一部に、レーニン主義の計画経済はアングロ・サクソンの市場に勝ると考えさせ、ヨーロッパの多くの人に、野蛮な資本主義など救う価値があるのかと思わせました。
言うまでもなく、彼らは事態を読み誤っています。
この危機を引き起こしたのは政府だったのです。
信用価格を余りにも低く固定した西側と、準備金を大量に蓄積して世界中に過剰資本を大量放出した東側の政府だったのです。
しかし、ネットの論調も政府の発表も、そう伝えません。
So let us start to set the record straight on one point at least. The archives demonstrate that the Stuart monarchs Charles II and James II systematically drew up laws to enforce and spread hereditary slavery, mimicking the Spanish practice of the day and the "divine right" absolutism of the Habsburg empire.
ですから、少なくとも或る一点において、記録を正すところから始めましょう。
スチュアート朝のチャールズ2世とジェームス2世は、当時のスペインの慣行とハプスブルク帝国の「神権」を真似て、世襲的奴隷制度を実施、拡大するために体系的に法律を策定した、と公文書は示しています。
They did so with relentless focus, stacking the courts to ensure favourable rulings, and carrying out police state sedition trials against opponents, not least because revenues from tobacco and sugar plantations became the chief source of wealth for the crown.
また、煙草と砂糖のプランテーションからの収入が王室の主な財源になったこともあり、わき目も振らずにこれを推し進め、裁判所に好意的判決を下させるようにし、反対者に対して警察国家的な見世物裁判を実施しました。
Professor Holly Brewer from the University of Maryland says Charles II was so enamoured with the Royal African Company that he engraved its symbols of elephant and castle on one side of his golden Guinea. "The Stuarts envisaged monarchy and slavery as, literally, two sides of the same coin," she said.
メリーランド大学のホリー・ブリューワー教授によれば、チャールズ2世は、ギニー金貨に同社の象と城のシンボルを彫刻するほど、王立アフリカ会社を愛していたそうです。
「スチュアート朝は君主制と奴隷制度を、文字通り、コインの裏表だと考えていた」と教授は言います。
Slavery had not been hereditary in British possessions before. There were African slaves, just as there were indentured white workers, but it was fluid, in a legal grey zone, and judges could not be counted on to enforce the recapture of runaways.
英国の奴隷制度はそれまで世襲的ではありませんでした。
白人の契約労働者と同様に、アフリカ人奴隷はいましたが、流動的であり、法律的グレーゾーンにあり、脱走者の奪還を裁判官に頼ることは出来ませんでした。
Prof Brewer said the findings she has uncovered in the archives show that Locke fought tooth and nail to reverse this new hereditary structure while on the Board of Trade in the 1690s under William of Orange.
ブリューワー教授は、公文書からの発見事項は、ロックがオレンジ公ウィリアム統治下の1690年代に商務省に属している間、この世襲的奴隷制度構造を覆さんと死に物狂いで闘ったことを示していると言います。
Locke sought the stop linking land grants to the number of imported slaves - 50 acres per head - a "strangely perverted "practice, in his words, intended to ensure a plantation aristocracy built on slaves. He urged that the children of blacks should be "baptized, catechized and bred Christians" so that they could not be denied their civil liberties so lightly.
ロックは、公有地の供与と輸入した奴隷の人数(50エーカー/人)の関連付け、つまり奴隷を基盤とする農園貴族を守るための、「奇妙に倒錯した」行為と彼が呼ぶものを阻止しようとしました。
彼は黒人の子供達が市民的自由を易々と否定されないよう、彼らは「洗礼され、キリスト教を学び、キリスト教徒として育てられる」べきだと強く主張しました。
Locke had been compromised earlier in the 1660s as a young man working for the Stuarts but later became an exile and rebel in Holland. "When he had a position of real power, he tried to undercut the development of slavery in comprehensive ways," she said.
ロックは1660年代初頭、若い頃はスチュアート朝のために働きながら、後にオランダに追放され反逆者となり、失脚しました。
「真の権力者だった頃、彼は包括的に奴隷制度の発展を阻止しようとした」と教授は言います。
His was the outlook of most liberal thinkers who shaped the American Revolution. It was the view too of Adam Smith, the free market theorist writing later in the 18th Century, also accused of promoting slavery. Smith, in fact, argued that slaverly stifled economic growth and innovation. "It appears from the experience of all ages and nations, I believe, that the work done by freemen comes cheaper in the end than that performed by slaves," he wrote in Wealth of Nations. William Wilberforce cited Smith approvingly to buttress the abolition case.
彼の物の見方は、アメリカ独立戦争を形作った自由主義思想家と同じです。
アダム・スミスとも共通する見解で、この18世紀後半に執筆活動を行った自由市場主義者もまた、奴隷制度推進を批判しました。
実のところ、スミスは奴隷制度は経済成長と技術革新を阻害すると論じていました。
「全ての時代や国の経験から考えるに、自由民によって行われる労働は奴隷によって行われる労働よりも最終的に安価となると考える」とスミスは『国富論』に記しました。
ウィリアム・ウィルバーフォースは奴隷制度廃止論を強化すべく、スミスを肯定的に採り上げました。
Locke's efforts to undo Stuart damage came too late. Vested interests were too powerful. Hereditary slavery had become embedded in the economic system of the American and Caribbean colonies. Britain would acquire the notorious "Asiento" at the Treaty of Utrecht in 1713, giving the South Sea Company the contract to supply the Spanish Empire with slaves. The cancer then metastasized.
スチュアート朝のダメージを回復しようとするロックの努力は手遅れでした。
既得権益が強過ぎたのです。
世襲的奴隷制度はアメリカとカリブの植民地の経済システムに植え付けられました。
英国は1713年のユトレヒト条約で悪名高い「特権」を獲得して、スペイン帝国に奴隷を供給する契約を南海会社に与えました。
その後、この癌は転移しました。
In my view, the British are a little too cavalier about this saga, thinking the nation absolved because the practice was far away and not on island soil.
僕が思うに、英国勢はこの物語において余りにも紳士的であり、これがブリテン島ではなく余りにも遠くで行われているがために、自国は無罪だと考えたのでしょう。
We tend not to be aware that King George III actively perpetuated the slave trade in the late 18th Century, vetoing laws by Virginia and other states trying to deter the inflow by raising import taxes on slaves. It is why Thomas Jefferson's original draft of the US Declaration of Independence contained a clause saying the king "has waged cruel war against human nature itself, violating its most sacred rights of life and liberty in the persons of a distant people who never offended him, captivating and carrying them into slavery in another hemisphere or to incur miserable death in their transportation thither. Determined to keep open a market where men should be bought and sold, he has prostituted his negative for suppressing every legislative attempt to prohibit or restrain this execrable commerce. And that this assemblage of horrors might want no fact of distinguished die, he is now exciting those very people to rise in arms among us."
ジョージ3世が18世紀後半、奴隷の輸入税を引き上げて流入を防ごうとするバージニア州などの法律を拒否して、奴隷制度を積極的に存続させたことは余り知られていません。
だからこそトマス・ジェファーソンの米国独立宣言のオリジナルには、国王は「人類そのものに残忍な戦いを遂行し、一度も彼を攻撃したことのない遠方の人々の生命と自由という最も神聖な権利を侵害し、彼らを捕まえて奴隷にしては地球の裏側へ連れて行き、その輸送過程で悲惨な死を遂げさせた。人が売買される市場を存続させることを決意して、国王はこの嫌悪すべき商売を禁じ、抑制しようとする法的試みを弾圧すべく拒否権を発動した。また、このような恐怖の集合体は事実をあげつらわれることを望まないかもしれないが、国王は今や我々の中にいる正にその人々に武器を取って立たせるほど刺激している」というパラグラフが含まれていたのです。
And no, Jefferson was not a hyprocrite because he owned slaves. They were mortgaged, due to his family's crushing debts left from monetary deflation after the Seven Years War. They could not legally be freed.
そして、そうです、ジェファーソンは奴隷を所有していたのですから、偽善者ではありませんでした。
七年戦争の後のデフレで莫大な債務をジェファーソン家は背負ったため、奴隷は抵当に入れられていました。
合法的に解放することは出来なかったのです。
America puts its own gloss on events. Simon Scharma argues in Rough Crossing that "theirs was a revolution, first and foremost, mobilized to protect slavery". His point is that the "Somerset" ruling of 1772 in England - "the state of slavery is so odious, that nothing can be suffered to support it: the black must be discharged" - set off ferment in the colonies, and the Dunsmore Proclamation in 1775 offering freedom to slaves who fought on the British side rallied planters to the revolution. Yet this can be pushed too far. The intellectual leaders of the American Revolution were Lockeans through and through, almost all tormented by slavery.
アメリカは事態を誤魔化しています。
サイモン・シャーマ氏は『Rough Crossing』の中で、「彼らのそれは第一に、奴隷制度を護るために立ち上がった革命だった」と主張しました。
彼が言いたいのは、1772年に英国で下された「サマーセット」判決、つまり「奴隷制度は極めて醜悪で、何物もそれを支持出来ない。黒人は解放されなければならない」という判決は植民地で混乱を引き起こし、英国のために戦った奴隷を解放するという1775年のダンモア卿の宣言は、大農園主を革命に駆り立てました。
とはいえ、これも言い過ぎかもしれません。
アメリカ独立戦争の知的指導者達は根っからのロック哲学の信奉者で、ほぼ全員が奴隷制に苦しめられていました。
As Britain prepares to defend itself against the Caricom suit - so soon after settling torture claims from Mao Mao victims in Kenya - it is scarcely helps perhaps to argue that the slave system was built by monarchical tyranny, rather than by private citizens beyond control, as we like to think. It is worse, in some ways, if it was a state endeavour.
英国がカリブ諸国の訴えに対する抗弁を準備している時に(ついこの間、ケニアでのマオマオ被害者からの拷問の訴えを解決したばかりなのに…)、奴隷制度は、僕らがそう思いたいと思っているような暴走民間人ではなく、暴君によって作られたのだと論じることは殆ど助けになりません。
或る意味、それが国家的努力だったとすれば、もっとひどいことになります。
Yet it should be some comfort that Parliament and liberal government may be absolved, at least in part. Slavery was excresence of absolutism, not free commerce. We cannot hold our own in the world's bare-knuckled battle of ideas if we concede this cardinal point of history.
とはいえ、議会と自由主義政府が、少なくとも部分的には、無罪とされるかもしれないというのは、若干の助けでしょう。
奴隷制度は自由商業ではなく絶対主義の生成物でした。
僕らがこの歴史の枢要点を譲歩すれば、世界のなりふり構わぬ思想闘争で闘うことは出来ないのです。