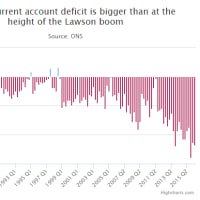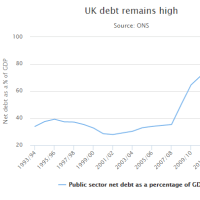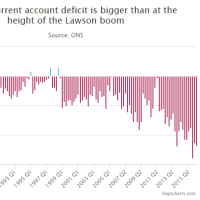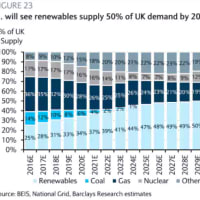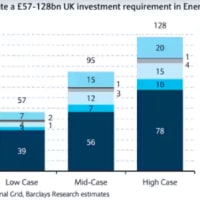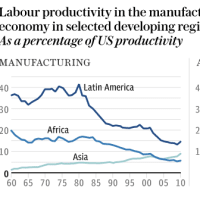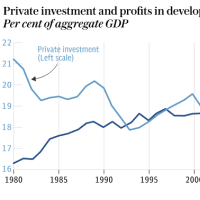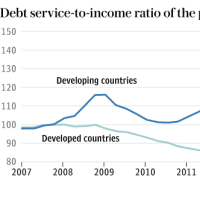Let us be honest: UK withdrawal would be traumatic, altering the political chemistry of Europe in unpredictable ways. While it is possible that a cluster of like-minded states on the Atlantic and Nordic rim would eventually retreat with us into a free-trade bloc, it would be rash statecraft to bet on it.
正直に言わせてもらおう。
英国の脱退はトラウマ的事件になって、予想も出来ない形でヨーロッパの政治的形勢を変えてしまうだろう。
大西洋に面した国や北欧の国の中で、同じような考えを持つ国々が、英国と一緒に自由貿易圏へと逃げ込む可能性はあるよ。
でも、それに賭けるのは焦り過ぎと言うものだろう。
Those that tend to align with Britain inside the EU as a counterweight to Rhineland domination – Scandinavians, Dutch, Balts, Slavs, and Spain (on-off) – would have to trim, tucking in obediently behind Paris and Berlin.
EUの中で、ラインラント勢力への対抗勢力として(北欧勢、オランダ、バルト諸国、スラヴ勢、そして(出たり入ったりの)スペイン)英国と手を握りそうな国は当たり障りなく、仏独コンビの後ろに従順に引っ込まなければならないだろう。
Britain would risk creating the sort of monolithic Habsburg Europe we wish to avoid, violating the balancing principle of our diplomacy in Europe since Elizabeth I. One wonders how that shrewd, equivocating, steely queen would have played the EU.
英国は、僕等が避けたいと願う、或る種の石頭ハプスブルク・ヨーロッパを生み出し、エリザベス1世以来のヨーロッパにおける我が国の外交原則、平衡原則を犯す危険がある。
かの鋭敏で、名言を避け、冷徹な女王ならどうしただろう、と思わずにはいられない。
Yet to accept that exit would be a high-risk gamble does not settle the argument. Ultra-federalists might scream, hurl abuse, and attempt to shut Perfidious Albion from EU markets, but the Dutch, Danes, Swedes and others would want to heal the rift.
しかし、脱退はリスクの大きいギャンブルだと認めたところで、この議論にケリはつかない。
超連邦主義者は金切り声を上げて罵りまくり、EU市場から「Perfidious Albion(不実な英国)」を締め出そうとするかもしれない。
だが、オランダ、デンマーク、スウェーデンなどが、仲直りしたがるだろう。
If Brussels pushed too hard for Carthaginian terms, it would risk setting off unstable combustion in the residual EU. As Breugel says, the legitimacy of the EU is already badly eroded.
欧州委員会がカルタゴ的条件をゴリ押しすれば、残りのEUに不安定な動揺を引き起こしかねない。
ブリューゲルが言う通り、EUの正当性は既にズタボロなのだ。
This great question might have been left unresolved, finessed by English pragmatism, had the EU not taken a dangerously authoritarian course by ramming through the European Constitution – renamed Lisbon – after it had been rejected by voters in France and Holland in 2005, and would have been rejected by half Europe had the fiasco continued. This manoeuvre is altogether different from the euro-creep tactics of EU father Jean Monnet, who handled democratic sensibilities with greater care.
2005年に仏蘭の有権者に拒絶された後、EUが(リスボン条約と改称された)欧州憲章を力ずくで押し通して危険な独裁主義路線を突っ走っていなければ、この大問題は英国の現実主義に巧みに操られ、宙ぶらりんになっていたかもしれない。
また、あの騒動が続いていれば、欧州の半分に憲章は拒絶されただろう。
この動きは、民主主義的な傷つき易さを大変慎重に扱った、EUの父ジャン・モネのユーロじわじわ浸透戦術とは全く別物だ。
Clearly it never occurred to those behind this heavy-handed move – Angela Merkel and Nicolas Sarkozy – that Irish voters would then reject the text in the one country allowed to vote. Perhaps the Irish can be cajoled in their weakened state into voting “Yes” next month. But a delicate line has been crossed. The EU project is usurping power, even if the forms of parliamentary ratification have been preserved.
明らかに、この強攻策の背後にいる連中(アンゲラ・メルケルとニコラス・サルコジ)は、アイルランドの有権者がどこかの国がOKした文書を蹴っ飛ばすなどと、思いもよらなかったのだろう。
そのアイルランド人も、来月にはボロボロに疲弊した国で丸め込まれ、「YES」に投票させられるかもしれない。
だが、デリケートなラインは越えられた。
議会による批准プロセスが維持されているにせよ、EUプロジェクトは権威を侵害しているのだ。
Critics call the Lisbon Treaty a “federalist blueprint”. That muddies the issue. It in fact concentrates power in a unitary state, giving the European Court jurisdiction for the first time over the whole gamut of EU affairs (all three pillars, in EU jargon – the Community pillar, the common foreign and security policy pillar and the pillar devoted to police and judicial cooperation in criminal matters). It will adjudicate over the Charter of Rights. Euro-judges will have power to reshape British society by court ruling if they so wish, just as the activist Warren Court reshaped America.
批判者はリスボン条約を「連邦主義者の青写真」と呼ぶ。
が、それでは問題がごちゃごちゃになる。
これは、実は、単一国家に権力を集中させ、欧州裁判所に初めて、EU問題のありとあらゆることに対する管轄権を与えているのだ。
ありとあらゆること、とはEU業界語で言うところの三本柱全部、つまり超国家的共同体、共通外交・安全保障政策、そして司法内政分野における政府間協力の全部、ということである。
これは欧州基本憲章を超越して裁くものだ。
ユーロ裁判官は、ウォレン・コートが米国を作り変えたように、そう望めば、英国社会を判決で作り変える力を握るのだ。
By creating a full-time EU president and by giving Euro-MPs the power of the purse, it mimics nationhood. Yet it should be obvious that Europe cannot ape the institutions of the historic nation states in this way. Shifting power from London, Madrid, or Copenhagen to the EU core does not transfer democratic accountability: it breaks the lines of accountability. Strasbourg’s Babel house has no unifying language or political culture. It answers to no coherent demos, and cannot do so because none exists at a European level. Italians read Italian newspapers about Italian politics, just as we read British newspapers about British politics. It is surreal that this should be happening when the EU is in crisis.
常任のEU大統領を創設し、欧州議会議員に財布の紐を握らせることで、EUは独立国家のフリをする。
しかし、ヨーロッパがこのような方法で、歴史ある独立国家の制度を猿真似することなど、不可能なのは明白だ。
ロンドン、マドリッド、またはコペンハーゲンからEU中枢へ権力を移動させたところで、民主主義的説明責任は移転されない。
責任系統を断絶させるだけだ。
ストラスブールのバベルの塔では、言語もバラバラなら、政治文化もバラバラだ。
一致団結したデモには対応することはなく、ヨーロッパ・レベル団結したデモなど存在しないのだから、そもそも対応しようがない。
イタリア人はイタリアの政治についてイタリアの新聞を読む。
そう、僕等が英国の政治について英国の新聞を読むのと同じだ。
EUが危機にある時に、こんなことが起こっているなんて非現実的だ。
We are confronted by a venture that is using anti-democratic means to establish an anti-democratic power structure, to no useful end for the people of these isles. It fair to say that this breaches the Burkean principle of “settled practice”, dear to readers of The Daily Telegraph. Since this unwelcome revolution is being forced upon us, perhaps it is time to end the long taboo and ask whether we must inevitably go along with it.
僕等は、この島々に住む人間にとってなんの利益にもならない、反民主主義的権力構造を確立するために、反民主主義的手口を利用する連中と対峙している。
デイリー・テレグラフ紙の読者にとって大切な、バーク主義的「定着した慣行」原則を破るものだ、と言って良いだろう。
招かれざる革命が僕等に強いられている以上、長きタブーを破り、僕等はどうしてもこれに付き合わねばならないのか、と問い質す時なのかもしれない。

別に思いつきでくっつけたわけじゃない。
今、諦めてやけっぱちになっちゃいけない理由が書いてある。
柔らか頭で柔らかアプローチ。
駄目なら止めれば良いじゃない、ってことで。