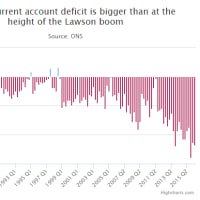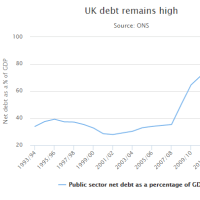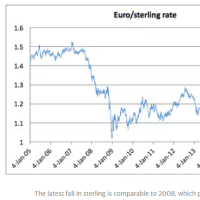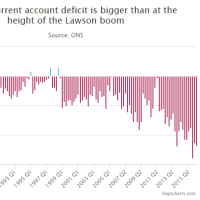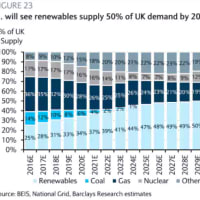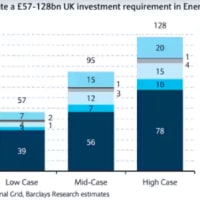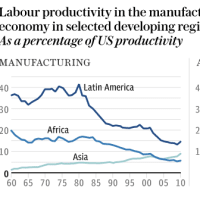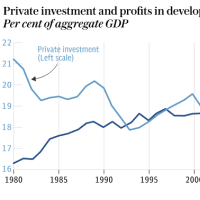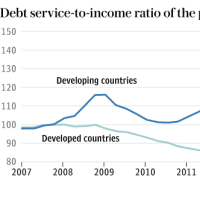There is life after Europe, but let us stop the triumphalism
(脱ヨーロッパにも未来はありますが、勝ち誇るのは止めましょう)
By Ambrose Evans-Pritchard Economics
Telegraph: Last updated: June 10th, 2014


(脱ヨーロッパにも未来はありますが、勝ち誇るのは止めましょう)
By Ambrose Evans-Pritchard Economics
Telegraph: Last updated: June 10th, 2014
The case for British withdrawal from the EU - if you are so inclined - is to ensure the Parliamentary self-government of these islands.
英国のEU離脱の正当性は(これに前向きな方の場合ですが)、この島国の議会による自治の確保することにあります。
It is to uphold democracy at its natural and optimal level, in a nation state forged over the centuries by wars, shared institutions, and the ancestral chords of memory, with a single dominant language.
何世紀にも亘る戦争、共通制度、先祖代々の記憶、単一言語によって作られた国家において、民主主義を自然かつ最適な水準に維持するためなのです。
It is to advance by Burkean steps - or as Confucians would say, by crossing the river through feeling the stones - and to resist vaulting leaps towards Hegelian or Utopian structures that usually end in horror.
バーク的ステップを踏んで前進する(また儒学者なら川底を確かめつつ川を渡ると評するでしょう)ため、おしなべて恐ろしい結末を迎えるヘーゲル主義者や夢想家的な構造への跳躍に抵抗するためなのです。
It is to protect the English Common Law and the broad principle that anything is permitted unless specifically forbidden (the rest regulated by the constraints of custom and manners), in contrast to a Napoleonic code that loosely starts from the opposite premise and is alien to our way of living.
その反対から始まり僕たちの生き方とは相容れないナポレオン法典とは対照的に、英コモン・ローと、特別に禁じられない限りあらゆることは認められる(その他は慣習と礼儀の縛りで規制されています)という広範な原理原則を護るためなのです。
It is to protect Habeas Corpus against political magistrates. It is to keep the political judges of the European Court at a very safe distance.
政治的リーダーに対する人身保護令状を護るためなのです。
欧州司法裁判所の政治的な判事達と極めて安全な距離を保つためなのです。
Brexit should not be reduced to squalid arguments about a pound of flesh, or quibbling over British payments into the EU budget. Net flows to Brussels are £7bn to £8bn a year, or about 0.5pc of GDP. This is an irritant. One does not cheerfully pay the salaries of EU officials, as well as their tax-free hardship allowances, and the university fees for their children until the age of 26 (unless it has changed since my wife's day, when she worked for the Commission). But it is not central.
ブレギジットを、返済を求める借金に関するくだらない論争や、EU予算への英国の支払いを巡る小競り合いに貶めてはならないのです。
欧州委員会への純支出額は年間70-80億ポンド、GDPの0.5%程度に上ります。
これは腹立たしいことです。
EUの役人共の給料や、この役人共の非課税の困難手当や26歳以下の彼らの子供達の大学授業料などを大喜びで払う人はいません(僕の妻が欧州委員会で働いていた頃と変わっていない限りこの様です)。
でも、それが大事なことではないのです。
Nor should Brexit be about the alleged suffocation of Britain by EU regulation. As the Centre for European Reform argues in its new report, this is greatly overblown. These rules have not yet prevented Britain from retaining some of the developed world's least regulated product and labour markets on the OECD index, just as Anglo-Saxon in this respect as the US, Australia, or Canada.
また、ブレギジットの要点をEU規制による英国の窒息とやらにしてもいけないのです。
欧州改革センターが最新レポートで論じているように、これは非常に大袈裟に言われています。
これらの規則によってこれまで英国が、この意味合いにおいて米国、オーストラリア、カナダのアングロ・サクソンのように、OECDのランキングで極めて規制の緩やかな製品、労働市場を維持出来なくなったことはないのです。
Nor has it prevented Sweden from being one of the world's most successful economies, nor prevented Germany from conquering global markets with panache (helped of course by an undervalued currency).
更に、スウェーデンが世界屈指の経済大国たるのを妨害したこともなければ、ドイツが(言うまでもなく安過ぎる通貨に後押しされて)華々しく国際市場を征服するのを邪魔したこともありません。
Many of Britain's regulations are tougher than the EU benchmark. The UK's bank ratios are far stricter. Britain's land use rules are among the least free-market in the world, and are the key reason why half as many houses are built today as in the 1960s and why great numbers of people live in broom cupboards. It is why British transport infrastructure is always struggling to catch up.
英国の規制の多くはEUのベンチマークよりも厳しいのです。
この国の銀行自己資本比率規則は遥かに厳しいものです。
英国の土地利用規則は世界でも屈指の厳格なものであり、それこそが現在は1960年代の半分も家が建たない主要因であり、非常に多くの人がウサギ小屋に住んでいる主な理由なのです。
だからこそ、英国の交通インフラは常にキャッチアップに悪戦苦闘しているのです。
As the CER argues, Britain would not be emancipated from the dead hand of the Acquis Communautaire on leaving the EU, if it wished to carry on trading broadly as before. Switzerland drafts its laws with one eye constantly on compliance with EU norms. "The regulatory sovereignty that would supposedly flow from leaving would be largely illusory," it said.
欧州改革センターが主張するように、これまで通り幅広い取引をしたいと望むのなら、英国がEU離脱でアキ・コミュノテールの死の手から解放されることはないでしょう。
スイスは常にEUの規範に即しているかどうか確かめつつ法案をまとめています。
「離脱で規制の主権が取り戻されるだろうという考えはほぼ幻想だ」とのことです。
There would be no bonfire of the diktats unless Britain were willing to withdraw to scorched-earth defensive lines, a minimalist WTO trade status with 15pc average tariffs that would kill foreign investment in the UK overnight.
英国が焦土作戦の防御線まで引き上げるつもり、つまり海外からの対英投資を一晩にして枯渇させる平均関税率15%というミニマリストWTO加盟国とならない限り、絶対命令が燃え尽きることはありません。
Britain would not inherit the EU's trading treaties with China, the US, Brazil, Russia, Turkey, or anywhere else by some kind of natural right - quite apart from our trading treaty with the EU itself. Each one would have to be negotiated again, from a position of relative weakness.
英国はEUとの通商協定を除き、EUが中国、米国、ブラジル、ロシア、トルコその他ある種の自然権による国々と結んだ通商協定を引き継がないでしょう。
それぞれ、相対的に弱い立場から、再交渉しなければならなくなります。
So let us stop this triumphalism and disregard for what Brexit might entail. Britain has let itself become deeply enmeshed in the European system. If the British people wish to embark on such a drastic course of action, they must not delude themselves about the implications.
そのようなわけで、このような勝ち誇った態度や、ブレギジットがもたらすかもしれないものに対する無関心は止めましょう。
英国は自分からヨーロッパのシステムに深入りしたのです。
英国人がそのようなドラスティックな行動に乗り出そうとするなら、その意味合いについて自分を誤魔化してはなりません。
Some readers have taken umbrage at the headline on my news piece last night. The term Wise Men has prompted fury.
僕が昨夜アップした記事の見出しに怒った読者もいるでしょう。
賢人委員会という表現が怒りを招いたんですね。
Just to be clear, the report was written under the guidance of a commission that included Sir Nigel Wicks from the British Bankers' Association, Simon Walker from the IoD, ex-MPC member Kate Barker, Prof Kevin O'Rourke from Oxford, Prof Wendy Carlin from UCL, Profs Nicholas Crafts and Andrew Oswald from Warwick University, Profs Paul De Grauwe and John Paulson from the LSE, Blackstone's chief Gerard Errera, BT chairman Sir Michael Rake, and Jonathan Portes from NIESR, among others.
誤解をはっきりさせるために申し上げますと、
あの記事は、英国銀行協会のサー・ナイジェル・ウィックス、IoDのサイモン・ウォーカー氏、元イングランド銀行政策委員会委員のケイト・ベーカー氏、オックスフォード大学のケヴィン・オローク教授、ユニバーシティ・カレッジ・オブ・ロンドンのウェンディ・カーリン教授、ウォリック大学のニコラス・クラフツ教授とアンドリュー・オズウォルド教授、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスのポール・デ・グラウェ教授とジョン・ポールソン教授、ブラックストーンのジェラルド・エレーラ代表、ブリティッシュ・テレコム代表のサー・マイケル・レイク、そしてNIESRのジョナサン・ポーツ氏などによる委員会のガイダンスに従って書かれたものです。
As for my own view, I am broadly in favour of the Brexit as matters currently stand. This is on the grounds that the EU has slipped its democratic leash and cannot be trusted after repeatedly overriding the verdict of voters, culminating in the suppression of the Dutch and French No votes on the European Constitution and the repackaging of the same text as the Lisbon Treaty (which I regard as illegitimate, to be defied on principle).
僕の見解としては、現状のままであるのならブレギジットに概ね賛成です。
その理由は、EUがオランダとフランスの欧州憲法に関する投票結果をもみ消し、全く同じものをリスボン条約と看板を掛け変えて出してくるという、民主主義の紐を断ち切って、繰り返し有権者の判断を無視した後はもはや信用ならないから、というものです(ちなみに僕は、リスボン条約は違法であり原則に基づいて否定されるべきものだと思っています)。
Monetary union has put the EU and Britain on irreconcilable paths. The logic of EMU is further fiscal union that must acquire the features of a unitary European state over time if it is to hold together. There is no conceivable place for Britain in this destiny, so the sooner we clear this up the better.
通貨同盟はEUと英国が相容れない状況に追い込みました。
ユーロの理屈は財政同盟の推進であり、ユーロを維持するならいずれ欧州統合政府という形を取らざるを得ないでしょう。
この運命において英国の場所はありませんから、解決は早い方が良いわけです。
Yet let there be no mistake, withdrawal from the EU would be traumatic and fraught with risk, though just how traumatic would depend on the civility and statesmanship of British leaders at the time, and the tone of Parliament and the press in this country. Do we leave in sorrow and a hope of friendship, or do we leave in anger amid a mood of tub-thumping, beer hall, nationalist hysteria? Therein lies a great difference.
とはいえ、間違いのないようにしましょう。
EU離脱はトラウマ的でありリスク一杯です。
しかしどれほどのトラウマになるかは、時の英国首脳陣の礼節と政治的手腕、そしてこの国の議会やメディアの論調次第です。
悲しみと友好の希望を以って離脱するのか、酒場で見られるような民族主義ヒステリーの熱気の中で怒って離脱するのか。
そこには大きな違いがあります。
It can be done, but it means acquiring a new business model. Much of the FDI investment flowing into Britain is contingent on EU market access. The Japanese and European car factories in Britain are designed to supply the European market, and even fixed plants are more footloose than you may think.
離脱は可能ですが、それは新たなビジネス・モデルの構築を要します。
海外からの対英投資大半はEU市場へのアクセスを条件としています。
英国にある日系、欧州系の自動車工場は欧州市場への供給を意図したものであり、固定された工場ですら皆が思うほど固定されていないのです。
The City flourishes in part because global banks and funds can use London as a regional hub to branch out across Europe. There is a long list of great financial centres that have disappeared almost overnight due to political error, like Antwerp in the 1550s.
シティは或る意味、国際的な銀行やファンドがロンドンをヨーロッパへのアクセスのハブとして利用出来るため潤っているのです。
1550年代のアントワープのように、政治的なミスのせいでほぼ一夜にして消滅した大金融センターは枚挙にいとまがありません。
The question for the City is whether Brexit is the greater risk, or whether it is even worse to stay in the EU as it seizes on the Lehman aftermath to force through a much more restrictive regime for the future.
シティの問題は、ブレギジットがより大きなリスクであるのか否か、またはリーマン破綻を期に将来に向けて遥かに厳格な規制を押し通そうとするEUに残留するよりも悪いのか否かということです。
It is an article of faith in Europe's political circles that "speculators" caused the EMU debt debacle. This is of course a canard. The origin of the crisis lies in massive current account imbalances and an EMU-induced flood of capital into southern Europe, all made worse by contractionary policies ever since. But that is what they believe.
「投機家」がユーロ債務危機の引鉄を引いたのは、ヨーロッパ政界への揺るぎない信頼である。
これは言うまでもなくデマです。
かの危機の原因は、巨大な経常収支不均衡であり、ユーロ発足がきっかけとなった南部欧州への資本大流入であり、これはその後も緊縮政策によって一層酷いことになっています。
とはいえ、彼らはそう(信頼のせいだと)信じているのです。
The CER report glosses over the systematic assault on areas of the City, an attack launched under the guise of making finance safer. It began with rules for hedge funds that are almost entirely based in London (80pc of the EU total) and which were falsely blamed for causing the crisis.
欧州改革センターのレポートは、ファイナンスをより安全にするというお題目で開始されたシティへの総攻撃を誤魔化しています。
ほぼ全部がロンドンを拠点としており(EU全体の80%)、件の危機の犯人だという濡れ衣を着せられたヘッジファンドへの規制が始まりでした。
Three new bodies have been created to control banking, securities, and insurance. They have powers to overrule a national veto when push comes to shove, ending 300 years of British control over the City. We are suddenly in a new dispensation.
銀行、証券、保険を管理する3つの新機関が創設されました。
これらの機関には、300年間に及ぶ英国のシティ統治を終焉させる、いざとなれば加盟国の拒否権を覆せるという権限が与えられました。
僕らは突如として新たな制度に放り込まれたのです。
The attacks on the City violate the long-established rules of the game in EU affairs, that no country is ever overruled on an industry where it has a dominant stake and is Europe's leader, whether cars for Germany, farms for France, or finance for Britain.
シティ攻撃は、ドイツの自動車、フランスの農業、英国の金融のように、いかなる国もその主要産業であり欧州において主導的な産業を支配されることはない、というEU問題における昔ながらのルールを侵害したのです。
The CER argues that the City is intricately woven into EMU bond markets and the mechanics of monetary union, and therefore has as strong interest in remaining in the EU. But this is double-edged. If you think that EMU is a trap that must ultimately drive debt ratios through the roof and lead to a chain of sovereign defaults on a colossal scale, then the sooner the City extricates itself, the better.
欧州改革センターは、シティはユーロの債券市場と通貨同盟の仕組に複雑に折り込まれているため、EU残留に大きな利益関係を持っていると論じています。
とはいえ、これは諸刃の剣です。
ユーロをいずれ債務比率を劇的に上昇させて物凄いスケールで数々の破綻を来たすトラップだと考えるのなら、シティは早く離脱した方が良いのです。
There is no doubt that Brexit would amount to a trade shock. The UK would be in chaos until the dust settled. Yet this cannot be the end of the matter. Nations have to take a large view of events. It is surely not the beyond wit of a future UK government to sort out Britain's trading relations with North America and the biggest economies of Asia within a couple of years.
ブレギジットがトレード・ショックになるのは間違いありません。
英国は事態が収まるまでカオスとなるでしょう。
しかしこれで終わりではありません。
国は事態を俯瞰しなければなりません。
将来の英国政府には2年以内に、北米やアジア屈指の経済大国との通商関係を解決出来るだけの知恵はあります。
"If we left the EU we would be like Canada or New Zealand or any other trading country. The idea that we have to be locked into the EU because we are geographically close is absurd," said Tim Congdon from International Monetary Research.
「EUを離脱するとカナダやニュージーランドなどの貿易国みたいになるだろう。地理的に近いのだから僕らはEUにしがみ付いていなければならないという考えは馬鹿げている」とインターナショナル・マネタリー・リサーチのティム・コングドン氏は言います。
The EU might be vindictive but it strikes me that pro-Europeans are on a losing wicket hinting at any such behaviour, for that is to argue from fear. The more likely outcome is that they would strive to minimise the damage and avoid any course of action that might push a string of Northern states closer to the exit.
EUは報復するかもしれませんが、そのような振る舞いをほのめかす、恐怖に訴えようとするなど、欧州シンパは終わっていると僕には思えます。
より考えられるのは、EUがダメージを最小化しようとして、北部欧州を次々に離脱へ追い込むかもしれない行動を避けようとするということです。
My chief objection to the CER report is the implicit assumption that the EU would carry on as before after Britain left, as if nothing had happened. This is implausible. The EU is already in existential crisis. The Front National won the French elections with calls for an immediate restoration of the franc and a referendum on Frexit. The Franco-German axis that has held the project together for 50 years has broken down.
欧州改革センターのレポートに対して僕が主に反対するのは、EUは英国が離脱した後も何事もなかったかのように平常運転を続けるだろうという暗黙の前提です。
これはあり得ません。
EUは既に存在の危機にあります。
国民戦線はフランス・フランの即時復活とフレギジット国民投票の実施を掲げ、フランスで選挙に勝利しました。
このプロジェクトを50年間維持してきた仏独枢軸は崩壊したのです。
By launching the euro before the EMU states were ready or able to withstand the rigours of monetary union, and then letting the North-South chasm widen each year, they have led the region into depression and mass unemployment. There is no way out of this under any of the policies being advanced. The Fiscal Compact ensures that it will go on for another decade or more. This is an intolerable situation. Italy's Matteo Renzi is already spoiling for a fight.
加盟国が通貨同盟の厳格さに耐える準備が出来る、または耐えられるようになる前にユーロを発足させて、南北格差を毎年広がるままに放置することで、彼らはこの地域を不況と大量失業に追い込みました。
今進められているような政策の下で、これから脱出することはありません。
財政協定は、これがあと十年以上続くことを確実にしています。
これは耐え難い状況です。
マッテオ・レンツィ伊首相は既に闘いたくてうずうずしています。
It is far from clear what the EU will look like in 2017 when Britain holds its referendum (unless Labour wins). By then the global cycle of economic expansion might be over, with Europe back in another deep recession before it had ever really shaken off the last one.
英国が国民投票を実施する2017年(労働党が勝たなければの話ですが)に、EUがどうなっているかわかりません。
その頃までには、世界的な景気拡張サイクルは終わっているかもしれませんし、ヨーロッパは前回の不況から脱出する前に次の深刻な不況に再び投げ込まれるかもしれません。
British withdrawal would not only puncture the EU Project's aura of historic inevitability but would also change the internal chemistry of the Union. Germany would be placed in a position of hegemony that it does not want, and that would subvert EU cohesion. It would make France's subordination even harder to endure, and embolden the Souverainiste camp to look for other solutions. The pro-market states of northern and eastern Europe that tuck in behind Britain would lose their footing.
英国のEU離脱はEUプロジェクトの歴史的運命というオーラに穴を開けるだけでなく、域内のケミストリーも変えるでしょう。
ドイツは望んでもいない覇権国の立場に断たされ、EUの団結を崩すでしょう。
フランスの従属関係を一層耐え難いものにして、勢い付いた主権主義陣営に他の解決策を模索させるでしょう。
英国の影に隠れたヨーロッパ北部と東部の自由市場推進派諸国は足場を失うでしょう。
The whole enterprise would become even more unstable at a time when it has already lost its charisma as a motivating idea for the European peoples. I reject the premise that the EU would be calling the political shots in such circumstances, or that Britain would necessarily be a supplicant pleading for terms. The residual EU would be in such crisis that it too would have to tread with extreme care, assuming it was able to come up any coherent terms at all.
欧州の人々にとってモチベーションをもたらす構想としてのカリスマを既に失えば、全てが一層不安定になるでしょう。
僕は、EUはそのような状況でも政治的主導権を握り、英国は必然的にお願いする立場になるだろうなどという予測を却下します。
残りのEUは余りの危機に、なんらかの一貫した条件を考え付けるとしてですが、やはり極めて慎重に動かなければならなくなるでしょう。
If Britain were to throw open its commercial borders and relaunch itself as a free-trade island with no tariffs against anybody, the tables might be turned over time. It might even be the catalyst for a great national renewal over the next quarter century.
英国が通商障壁を取り除いて、いずれの国に対しても一切関税をかけない自由貿易国として再出発したら、時間とともに形勢は逆転するかもしれません。
次の四半世紀の偉大なる国家再生のカタリストになることすらあり得ます。
When the Tudors lost Calais in 1558 and finally relinquished all claims on their French possessions six years later at the Treaty of Troyes, it was viewed as an English calamity. It proved to be a Godsend.
チューダー王家が1558年にカレーで敗北し、その6年後にトロア条約でフランスの領土を全て放棄した時、これは英国にとっての大災難だと考えられました。
実は天からの贈り物だったのです。
The English people ceased to waste their energies on endless entanglements in Europe and embarked on an entirely different course as a seafaring nation with trading ties across the world. The 1570s and 1580s saw an explosion of worldwide expansion by Raleigh, Drake, Gilbert, and Frobisher. Of course there is life after Europe.
英国人はヨーロッパとの無限のもつれにエネルギーを浪費するのを止め、世界と交易関係を有する海洋国家として全く新しい路線に乗り出しました。
1570年代と1580年代には、ラリー、ドレイク、ギルバート、フロービシャーによって世界的拡大を遂げました。
言うまでもなく、ヨーロッパ離脱後の世界は存在するのです。