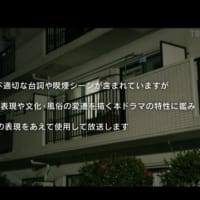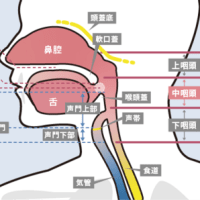桜田義孝文部科学副大臣が、10月5日、
高濃度の放射性物質を含む焼却灰の処理をめぐり
「人の住めなくなった福島に置けばいい」と発言。
福島の人々を傷つける心ない発言ではあるが、
実は表面上曖昧な姿勢をとり続ける政府内の本音と
言えるのかも知れない。
東京電力福島第一発電所近隣の地域の現状は
一体どうなっているのか?
日本のマスコミは正確に伝えようとしないが、
海外メディアはどう捉えているのだろうか?
Japan's Nuclear Refugees, Still Stuck in Limbo 日本の原発難民、いまだ曖昧な状況に縛られる
福島近くでは人的な難局が静かに展開されている:原子力発電所周囲の最も大きな被害を受けた地域から退去した83,000人の避難民は、災害から2年半が経った今も自宅に戻れないままである。
By MARTIN FACKLER
福島県双葉郡浪江町発:毎月、ワタベヒロコさんは、運命に対して彼女自身の小さいながらも果敢な抵抗を見せるため損壊した福島原発近くの放置された自宅に数時間戻っている。彼女は外科用マスクを着け、頸のまわりに2つの放射線測定装置をぶら下げ、しゃがみこんで雑草を抜く。
彼女は自分の家を見捨てたのではないことを証明するために自宅の小さな庭をきれいにしておきたいと考えている。彼女とその家族はマグニチュード9.0の地震と津波が5マイル離れた原子力発電所を壊滅させた後、その自宅から退去した。必ずしも彼女の近所の人たちすべてが進んで危険を冒そうとしているわけではない。かつてはきちんとしていた家の出入口も今では胸の高さまである雑草が塞いでいる。
「心の中では、もう二度とここに住めることはないとわかっています」ワタベさんは言う。彼女は夫とともに郡山市から車でやって来た。彼女らは一時間ほど離れたその町に災害以来住んでいる。「しかし、こうすることで私たちに目標がもたらされるのです。ここがまだ自分たちの家なのだと言えるのです」毎日数百トンの汚染水が太平洋に流れ込むなど福島第一原子力発電所で今も続く環境的災害が世界のトップ記事を飾っている一方で人的な難局が静かに繰り広げられている。同発電所が日本の東北地方に放射性汚染物質を放出してから2年半が経つが、最も大きな被害を受けた地域から退去した83,000人の原発難民は今も自宅に戻れないままだ。仕方なく転居した人もいるが、政府がいつかは戻れるとの期待を持たせる中、何万人かの人たちは法的にも感情的にも曖昧な状況に留められている。
待つにつれ、多くの人たちには辛さが増している。ほとんどの人たちは、町を除染することによって中には何代にもわたって住んできた家に人々が戻れるようにするという当局の目標を支持してきた。しかし、今、より多くの独立した専門家たちの声が警告してきたように、見込みより何十年も先ということはないまでも、かつて例を見ない除染が何年もかかるということを政府は承知している一方で、日本の他の原発を再稼働させる計画が頓挫するのを恐れてそれを認めようとしないのではないかと彼らは疑うようになっている。
そういったことで、浪江町の人々をはじめ、立ち退きとなっている他の10の町の多くの人たちは正しい選択がほとんどできない状態に追い込まれた。彼らは窮屈な仮の住居に住み住み続け、政府からの比較的乏しい月々の補償を受けとることができる。あるいはどこか別の地に新しい生活を築こうと試みるものの、政府が敗北を認め彼らの失われた家や生活の十分な補償をしない限りにおいて、多くの人たちにとってそれはほとんど不可能に近い。
「政府は私たちに戻るよう指示するものの、その一方でただ待ち続けるよう命じるのです」とババタモツ氏は言う。彼は、爆発が原発を揺るがし始めたとき大急ぎで退去させられた2万人のこの町の町長である。「役人たちは起こったことすべての責任をとることを避けたいと思っており、私たち一般人が犠牲を払うことになるのです」
浪江町の住民にとって、政府の不明確な態度は何も新たに生じたものではない。彼らが退避したその日、東京の役人たちは、コンピューターモデリングに基づいて、彼らが向かっている方向が危険な可能性があることを知っていたが、パニックを生ずることを恐れて通告しなかった。町民は北に向かったが、それは目に見えない放射性汚染物質の中に直行していたのである。
あの災害の前までは、浪江町は山地と太平洋の間に広がる静かな農業と漁業の地域だった。最近では、個々の地域でどれほど汚染されているか、さらに限られた日中だけの訪問で住民がどれだけ長く滞在できるかを示す色分けされた区域に同町は分けられている。彼らは区域に入るときに線量計を支給され、出てくるときに検査される。検問所の隣には、脱出する農民らが解放して以来、自由に徘徊している野生化した乳牛について警告する標識がある。
検問所より先では、浪江町は残骸や雑草で雑然とした人気のない通りのゴーストタウンとなっており、これはかつて非常にきちんとしていた日本においては例を見ないものだ。伝統的な木造の農家の一部は今回の地震で残ったが、放置状態には耐えることはできない。雨が降り込むことで、古くからの木の梁を腐らせ倒壊した。瓦屋根は道路に落下している。
埃にまみれた店のウインドウごしに地震で棚から落下した商品がまだ床に散乱しているのが見える。町役場ではカレンダーは災害が襲った2011年3月のままとなっている。
町当局は帰町準備室として庁舎の一角の利用を再開したが、これまでの彼らの成果はポータブルトイレの設置と略奪を防止するための警備員の配備だけだった。政府は、最終的には何トンもの汚染土をかき集めるためにここに大勢の労働者を配備したいと考えている。しかし、町当局は障害にぶち当たっている:汚染土を貯蔵できる場所が49ヶ所必要なのに、町はわずかに2ヶ所しか確保できていないのである。
先月、政府は、そのような問題により11町のうち8町で修正できないほどスケジュールの遅れが出ていることを認めた。当初は来年3月までに除染できると見込まれていたのである。また、除染が始まっている場所でも、別の問題が表面化している。土を取り除く作業では放射線レベルの低下に限られた有効性しか得られなかったのである。雨によって近隣の山々からさらなる汚染がもたらされることもこの一因となっている。
浪江町を含めた8町の除染の完了は先延ばしとされ、新たな期限は決まっていないと現環境大臣は述べている。
浪江町では、町役場の調査で、住民の30%が町での生活を取り戻すことを断念。30%は断念していないが、40%はいまだに迷っているということが明らかとなった。
ワタベさんの訪問は気持ちの上で切ないだけでなく、怖いことでもある。彼女の夫が経営する自動車の販売特約店は盗難にあったという。家の庭は危険なイノシシに荒らされており、彼女が何とか追い払った。彼女は出入り口の除草は大変危険なことと考えており、通常であれば避難を余儀なくされるレベルの2.5倍の測定値を示している彼女の線量計を提示して、手伝いを申し出てくれる来訪者を断っている。
彼女はかつて結束の強かった自分たちの地域社会を思い出す。当地ではお茶を飲みながらのゆったりとしたおしゃべりのために近所の人たちが立ち寄ってくれていた。彼女は当地で4人の子供を育て、10人の孫がよく訪れていた。今、彼らの動物のぬいぐるみや赤ちゃんのおもちゃが、販売特約店の床に残骸とともに転がっている。
その家に同居し家業を継ごうとしていた彼女の一番下の息子は二度と戻らないと決めた。そうして彼は東京郊外に転居したが、浪江町と関係があるという評判だけで、二人の若い娘らが広島や長崎の原爆生存者と同じ種類の差別に直面することになるのではないかと心配した。
「若い人たちはすでに浪江町をあきらめています」とワタベさんは言う。「戻りたいと思っているのは年を取った人たちだけです」
「そして、私たちでさえまもなくあきらめなければならなくなるでしょう」夫のマサズミさんは付け加えて言う。
彼らが戻れるチャンスは低いように思われるが、同町の山あいにある西側半分では、かつての隣人たちが近いうちに戻れる可能性はさらに低い。ワタベ家の自宅は中間レベルの放射線を示すオレンジゾーンに位置するが、西側の大部分は最も大きな被害を受けたレッドゾーンとなっている。
中心街から、急流が音を立てる狭い山峡に向かう道路は、最近の訪問の際、放射線測定装置の測定音を除けば、のどかに思われた。山腹全体を削ってきれいにしようとすることの困難さからこの地の除染は一層難しいと以前から見られてきた。
彼女の築300年になる農家の入り口の近くで、84才になるオガワジュンさんは、立ち退いたときに入ってきたネズミの糞を箒できれいにした。彼女はこの日、恒例となっている法事を行うために戻ってきており、地震の前に亡くなった夫の墓を磨くのである。
ワタベ家と違って、彼女は既に転居を決めており東京郊外に息子と住んでいるが、その一方で彼女が決別しようとしている過去を大切にするために戻ってくるのである。彼女が戻るたびに、たとえ屋内に留まっていても1回ないし2回分の胸部レントゲンに匹敵する放射線量を受けるのだと彼女は言う。箒を突き出し元通りにできていないものを指し示す。階段状になった水田は草に覆われており、家の太い木の梁は近所のそれより長く持ちこたえてはいるが、それらもまた腐り始めている。
「この辺りを一目見れば、戻れる可能性がないことがすぐにおわかりになるでしょう」と彼女は言う。
曖昧にされていることに対して私たちは
真実を強く求めようとはせず、
つい見て見ぬふりをしてしまってはいないだろうか。
一方、福島の自宅への帰還を願う被災者たちは、
その曖昧な情報ゆえに大きな苦悩を背負わされている。
国民の中で、
福島第一原子力発電所が本当にコントロールできていると
心の底から信じている人はほとんどいないはずである。
垂れ流される汚染水の問題、
遅々として進まない除染作業の問題、
これらについて政府は
真実をきちんと公表すべきではないだろうか。