明けましておめでとうございます。
2008 年は本当にひどい一年だったので、
今年こそは明るい年となってもらいたいものである。
あ
さて、おおみそかの夜は
皆様どのように過ごされただろうか…
MrK は地上波番組に見切りをつけ、BS 朝日でやっていた、
『インサイド9・11完全版~同時多発テロの真実』を見た。
2001 年に起こった米・同時多発テロから7年以上が経過し、
当時の記憶もかなり薄れてきていたのだが、
この特集を見てあらためて事件の悲惨さ、
テロの問題の根深さに衝撃を受けた。
あ
一方、先月 27 日に始まったイスラエル、ハマスの間の
攻撃の応酬は一向に収束する気配が見られない。
多くの負傷者が出ている模様のガザ地区だが、
イスラエルに補給路を絶たれているため、
医療の対応が困難な状況にあり、
また食糧の不足も危惧されている。
いくらハマス掃討を目的としているとはいえ、
完全に民間人を巻き込んでしまっているイスラエルの作戦は
行き過ぎといえるだろう。
アメリカはイスラエルを擁護する構えだが、
EU諸国は停戦に向け積極的な行動を起こしているようだ。
で、日本は一体何をするつもりなのか。
中曽根外相は、イスラエルの女性の外相に電話で自制を
促したそうだが、誰からかわからぬ迷惑電話くらいにしか
思われていないことだろう。
あ
さて、そんな混沌とした世界情勢の中、
2009 年、日本は何を目標に進んでゆくことになるのだろう?
政治家が右往左往している状況では、
国民がその目標を見定められないのは当然だ。
今こそ、政治家は目標を国民の前に強く掲げるべき時にあると思う。
財政が立ち行かんから、2011 年度から消費税増税します、
それまでは景気対策に力を注ぎます、では
何ら目標が示されたことにはならない。
あ
話は転ずるが、
50 年前、国民総結集を感じさせるシンボルが建てられた。
東京タワーである。
昭和 32 年に着工。同 33 年に竣工。世界一の高さを誇る建造物。
まだ物資が十分にない時代に、思い切った決断をしたものである。
しかし 50 年が経った今、東京タワーは
東京、そして日本国民のシンボルとしての役割を
十分果たしてきたと思われる。
これに関して、米国紙にも記事が出ていたので紹介する。
Beacon of Japan's Future, Sparkling With Nostalgia
かつての日本の行く末の航路標識、今、懐古とともに輝く
(ちょっと訳に無理がある?)あ
あ
それは、まだ戦争の傷跡が残る町の、かつて古い仏教の寺院のあった場所に、解体したアメリカ製戦車の鋼鉄を用いて建築された。
1958 年に完成した時、東京タワーは、明るい未来への方向性を示すことで日本の今後についての想像力をしっかりかき立てた。エッフェル塔に似ているが、オレンジと白のストライプの 1,093 フィート(333 メートル)の建築物は世界で最も高い自立式鉄塔で、このタイトルは今も保持している。
さらに、カラー・テレビの幕開けとなる放送がこのタワーで開始されたという事実は、またたく間に、技術に秀でたいという、平和な時代における日本の羨望の象徴となった。パリのエッフェル塔や自由の女神のように世界的に認知はされなかったが、現在まで、豊かで壮大な都市の象徴であり続けている。
しかし半世紀が経ち、老朽化したタワーはかつてのように際立つことはなく、感動的でもなくなってしまった。東京タワーは懐古的な国内メディアによる報道の高まりの中、先週 50 周年を迎えた。
テレビ・ニュースでは、東京タワーを伝える粒子の粗い白黒フィルムを流し、日本の新幹線や 1964 年の東京オリンピックなどとともにすばらしい成果を残した過去の時代の産物として紹介した。実際、このタワーは今回、国民の意識の中で、セピア色の過去の記念建造物という新たな地位を得たように思われる。
こうした変化が起こったのは、日本が総じて、その未来に自信を失ったように見え、ついにはゆっくりとした衰退に甘んじるようになった時期に一致する。こういった変化はさらに広い見方を強調していると言える。すなわち、時代の流れがどのようにして国民の象徴の意味を変えることとなったのか―東京タワーほどの大きなものでさえ―という視点である。
「東京タワーは未来の夢を表していましたが、その夢は過ぎ去ったのです」と、一橋大学歴史学の名誉教授 Masanori Nakamura 氏は言う。
「日本が夢を持っていないのと同じように、東京タワーはもはや夢を提供しないのです」近年、一層大胆なデザインのガラス張りの超高層ビルの増加によって東京タワーは目立たなくなってきた。
この都市で最も高い構造物としての地位を長年保持してきたが、この地位を 2011 年には新しいテレビ塔に譲ることになる。
それは、東京スカイ・ツリーというちょっと変わった名前のタワーで、2,003 フィート(611 メートル)の高さがあり、東京タワーの約2倍である。そうは言っても、東京タワーは、開業以来、約1億 5,700 万人もの観光客を招き入れ、この都市の想像力を保持し続けてきた。
先週火曜日、約 20,000 人が 50 周年の記念日に参加し、タワーの2ヶ所の展望台のうちの一つへ上がるエレベーターに乗ろうとして数時間も列に並んだ。所有者である Nippon Television City は7色の 276 台の照明器具を配備した新しい夜間照明計画 the Diamond Veil ダイヤモンド・ヴェールに 650 万ドルの改修費を拠出した。
タワーを訪れた人たちや近隣の住民は、その魅力を愛情のこもった言葉で説明し、驚異的な社会と経済の変革の数十年を自分たちとともに見守ってきた古い友人のように語った。
「私の父親の世代では、東京タワーは、自分たちが作り上げようとする新しい東京のシンボルでした」と、東京タワーの近くでカメラ屋を営む Midori Tajima さん(60才)は言う。
「しかし、私たちの世代にとっては、すべてが変化してゆくように思えるような 50 年の間、唯一変わらずに私たちを見守ってきてくれたように思えるのです」小学校4年生で東京タワーの建築を見ていた Tajima さんは、自分の店に古い写真を展示して記念の日を祝った。
その中には密集する木造の家々から立ち上がるタワーや、今はなくなっているケーブル・カーが写っている 1958 年の写真もある。完成当時、東京でそれまで最も高かった国会議事堂より約 900 フィートも上回った。
建築中には、タワーのてっぺんからハワイが見える、という噂が巷には流れていた、と年寄りの住人は言う。このタワーの創設者である、右寄りの新聞社、産経新聞のかつてのオーナー、Hisakichi Maeda (前田久吉)氏は 1986 年に亡くなったが、生前には、このそびえ立つ建築物を“日本の建築技術の勝利”であると呼んでいた。
このタワーの建築には、当時 840 万ドルを費やし、数少ない上質の鋼鉄の調達源の一つであった韓国軍の戦車を解体して転用した。最近の懐古ブームがこのタワーの人気回復につながっている。
この 10 年以上少しずつ入場者数が減ってきていたが、過去3年の間に約 50 %増加し、昨年は 320 万人が訪れた、とNippon City は言う。この懐古ブームの一部は、このタワーを題材にした最近の小説や映画の一時的流行に影響されている。
(最初に登場したのは 1961 年の白黒映画『モスラ』で、この中で東京タワーは巨大なイモ虫によって倒された)最近の小説・映画では、高齢化の進むこの国で、この 2, 30 年の間に失われたと思われるもののメタファーとして、東京タワーが登場する。
それは、その経済的奇跡を起こす原動力となった共通の目的意識や若者の楽観主義、さらに日本が経済大国となる前の質素な生活様式を意味する。このタワーの歴史への興味が非常に高まりつつあることから、オーナーはこれを建築した作業員に引退生活から表に出てくるように要請したり、学校、旅行団体あるいは報道機関に情報を提供することを始めた。
その一人が Goro Kiryu 氏 76 才で、彼によると、タワーの鋼鉄の桁をボルトを締め付ける作業は、たとえそれが尋常でない高さでの作業であったり恐ろしい強風に見舞われることがあっても、当時はいつもと変わらない作業であると感じていたという。「当時は皆、自分たちの生活を少しでも良くしようとただ一生懸命に働いていました」と Kiryu 氏は言う。
「東京タワーが自分の人生において主要な仕事であったということが今になってわかりました」テレビジョン・ネットワークが放送をスカイ・ツリーに切り替えることを発表し始めているが、この懐古ブームが東京タワーの収益維持をささえるだろうと日本シティーは見ている。
高さでは相手にならない新たな競争相手に観光客を奪われることを恐れて、Nippon City は、歴史の視点を強調するために、同タワーで行っている古くなったアトラクションを刷新する予定であるという。「東京タワーは東京の歴史の一部です」と常務の Tatsuo Matsuzawa 氏は言う。
「さらに 50 年間生き延びてもらいたいと思っています」
東京スカイ・ツリーが、どれほど見物客を集めたとしても
東京タワーが果たしてきたかつての精神的役割を
引き継ぐことはないだろう。
昨今、後ろばかり振り返りがちな日本国民を、
なんとか前に向かせる術はないものだろうか。


















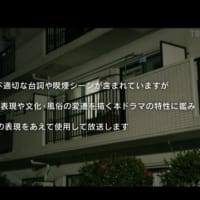

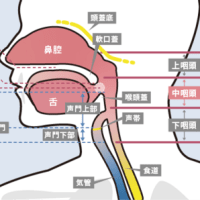





あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたしますm( _ _ )m
元旦早々から各地大雪になりましたが、Mr.K様はいかがお過ごしでしょうか?
さてさて今年一番最初のニュースが東京タワーですか。
しかしNew York Timesもなかなか鋭いところを突いてますね。
しかしどの文明にも、発展期があれば衰退期があるのも事実です(衰退期というより爛熟期といったほうがいいのかな?)
はっきり言って、アメリカ合衆国でも「9.11」以降は衰退期に入っているように思えるのですが。
たしかにこのような状態のときは、政治主導で(官僚主導でなく)国の将来を見出さないといけないのでしょうが、今の政治家にそれを求めても、無理なような気がします。
今の二世・三世が主体の政治家に期待しろというほうが無理なのでしょう(あまりにひ弱すぎるし、下々のことが理解できていない)。
そこで思ったのですが、議員の世襲制は禁止するような法案を誰か提出してくれないでしょうか。
無理かな・・・
明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。
当地は山間部ということもあり、18cmの積雪となっています。
ところで、さすが Black Nurse さん。
『爛熟』という言葉、まさに今の日本にぴったりの言い方かと思います。さしずめあのお方はこの漢字を「えんじゅく」とでも読むのかな?(笑)
ワタクシの高校時代の同級生があの方の派閥の議員なのですが、「あの人をマイナスの一面だけで判断しないでくれ」といまだに擁護しております。すでに「全面お手上げ状態」だというのに…。確かに、下の面倒見はいいようで若手議員からは人気があったようですが、国民の心情を理解することができず、漫画ばかり読んで勉強もしない、また、身を投げ打ってでも初志を貫き通すという覚悟もない…。
できることなら世襲制、禁止にしていただきたいとワタクシも思います。(カップラーメンの値段や漢字の読みを問う候補者選定試験なるものを実施してはいかがだろう…)
同級生の方に国会議員の方が居られるなんて(しかもかの方の派閥!)、Mr.K様の交友関係にはびっくり!です。
で、かの方が以前本を出されておられまして、『とてつもない日本』という題名で、読ませていただきました。
良いことが書いてあります。高齢化社会・若者のニートの問題・格差社会問題等の解決方法(?)。
でも総理総裁になられた今、そのことを活かしておられない。
Mr.K様が言われるように、ここはひとつ本を書かれたころの初心に帰って、初志を貫くよう頑張っていただきたいものですが。
無理かな?やっぱ無理?・・・(-.-;)=フゥ
ちなみに本は新潮新書から2007年6月に出版されてます(宣伝ではありません^^;)
新書なら廉価でしょうから、総理在職期間中にはその『とてつもない日本』、読んでみようと思います、って、もう時間がない?(汗)
さて、件の議員とは交友関係といえるほどの付き合いはありません。わずかな支援金は出しました、が、その礼はなかった(怒)。(この前、解散要求決議案の採決で、与党席でぽつんと一人立った人の隣の隣で笑っているのが映っていた←あんたも立てよっ!)
ぜひ賞味期限(?)が切れるまでにどうぞ
賞味期限切れになって読まれた場合の補償はいたしかねます(笑)
本日早速書店で探してみましたが、あ○う氏の著書は全く見当たりませんでした。
まさか売れ過ぎて品切れということはないでしょうから、やはりすでに賞味期限が切れてしまっているのでしょか…トホホ。