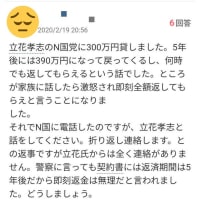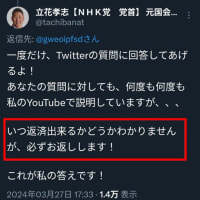脊髄損傷で下半身が麻痺! 「二度と再生しないと」いわれてきた中枢神経系の再生能力を引き出す臨床研究〈dot.〉
6/18(木) 17:00配信
AERA dot.
(イラスト/タナカ基地)
損傷した皮膚や神経などの機能を再生させられるのではないかと期待され、研究が続けられているiPS細胞。脊髄損傷により、からだが麻痺した患者にも治療の兆しがみえてきた。週刊朝日ムック『新「名医」の最新治療2020』では、10年以上研究を続ける、慶応義塾大学医学部生理学教室の岡野栄之医師に話を聞いた。
* * *
脊髄とは、脳から背骨の後ろ側を通る中枢神経系で、脳からの指示を伝えてからだを動かす重要な役割を担っている。神経の本幹であり、脊髄から首や肩、腕へと枝分かれしている。
事故などで背骨を骨折したり脱臼したりすることで脊髄が圧迫されて起こるのが、脊髄損傷だ。頸椎後縦靱帯骨化症や頸椎症などを患っている人が、何かの衝撃によって起こすこともある。日本では新規患者が年に約5千人いて、累積患者数は10万人以上いる。
主な症状は、損傷部より下部に起こる麻痺だ。呼吸障害や排尿・排便障害が起こるケースもある。下半身が全く動かなくなってほぼ無感覚になる完全麻痺と、一部が損傷して動きや知覚に障害が出る不全麻痺の2種類がある。からだだけでなく、車いすでの生活になれば精神的なダメージも大きい。
現在の主な治療は、背骨の固定やリハビリテーションだ。劇的に麻痺を回復させる薬物療法は確立されていない。ロボット技術や電気刺激を使ったリハビリテーションもおこなわれているが、失った機能の回復を目指すのではなく、残った機能を使って日常生活の動作を獲得するために実施される。
不全麻痺の急性期で圧迫が残っていれば、それを取り除く手術や薬物療法を実施する場合もある。
再生医療では、2014年から慶応義塾大学で急性期の患者を対象に、細胞の再生を促す働きがあるHGF(肝細胞増殖因子)というタンパク質からつくった薬を腰から注射する臨床試験がおこなわれ、約半数で改善がみられた。現在、創薬ベンチャーのクリングルファーマがHGFの製剤の臨床開発を進めている。
一方で、損傷後2~4週間の亜急性期の完全麻痺の患者を対象にしている臨床研究が、他人由来のiPS細胞を使った治療だ。これを進めているのも慶応義塾大学で、岡野栄之医師らが中心になっている。この研究のはじまりは、1998年にさかのぼる。岡野医師らが神経細胞(ニューロン)を新しくつくり続けうる「神経幹細胞」を世界で初めて見つけたのだ。その後も、脳梗塞で傷ついた脳であっても神経幹細胞から新しいニューロンが生まれることや、機能を回復させるためには大量の神経幹細胞が要ることなどを突き止めた。
「それまで中枢神経系は損傷したら二度と再生しないといわれていましたが、実は再生能力を引き出せるとわかったのです」(岡野医師)
当初は胎児由来の神経幹細胞を使う計画だったが、06年にiPS細胞が作製されて以降はiPS細胞由来の神経幹細胞に切り替え、10年以上研究を続けてきた。
iPS細胞由来であれば、大量に増やして用意できるうえに、凍結保存しておけば必要なときに解凍でき、移植までの時間もかからない。iPS細胞をつくるには3カ月かかり、それを神経幹細胞へと分化させるとさらに3カ月かかってしまう。岡野医師はiPS細胞を分化誘導し神経幹細胞に調整している。
岡野医師に、対象が亜急性期の患者になっている理由を尋ねた。
「脊髄損傷は直後1~2週間の急性期には炎症でニューロンが生まれません。また、6カ月以降の慢性期になると、瘢痕組織というかさぶた状のものができ、これも神経の線維の再生を邪魔します。その間の亜急性期に神経幹細胞を移植するのが最適だと考えました」
■チェックが終わり次第移植が始まる見込み
移植では、背中から皮膚を切開し、椎骨(背骨の一部)を切除してよけて、硬膜を切って脊髄の損傷部を露出し、中心部に直接注射する。見た目では少なくとも、そのなかには安全性が確認された量である約200万個の神経幹細胞が入っているという。移植するとニューロンがつくられ、失われた細胞の補充が期待できる。
これらの計画は19年2月に厚生労働省に臨床研究の開始が承認された。
「細胞はつくり終えていて、今は品質チェックの最終段階。チェックが終わり次第、実際の移植が始まる見込みです」(同)
リスクは少なからずある。他人由来の細胞を利用するため、半年ほど免疫抑制剤を使うことだ。健常時の脊髄には免疫系の細胞はなかなか入ってこない。脊髄損傷の直後には入ってくるが、他臓器より免疫抑制剤の使用量や使用期間は軽度で済むと考えられている。
またリスクとして腫瘍化の可能性も否定できないが、ないであろうことがさまざまな方法で確認されている。岡野医師は、万一腫瘍化すれば手術で摘出するか、免疫抑制剤の使用をやめて免疫細胞にアタックさせるか、放射線治療をするかの3パターンを考えている。
「今後は脊髄損傷の慢性期や脳梗塞などにも応用したいです。これまで慢性期の患者さんには有効な治療法がありませんでしたが、我々の実験では成功し、論文で発表しています。準備には時間がかかりますが、2年後くらいにできたらいいなと。当院だけではなく、日本全国や世界中でできる治療法にしていきたいです」(同)
(文・小久保よしの)
≪取材協力≫
慶応義塾大学 医学部生理学教室 岡野栄之医師

6/18(木) 17:00配信
AERA dot.
(イラスト/タナカ基地)
損傷した皮膚や神経などの機能を再生させられるのではないかと期待され、研究が続けられているiPS細胞。脊髄損傷により、からだが麻痺した患者にも治療の兆しがみえてきた。週刊朝日ムック『新「名医」の最新治療2020』では、10年以上研究を続ける、慶応義塾大学医学部生理学教室の岡野栄之医師に話を聞いた。
* * *
脊髄とは、脳から背骨の後ろ側を通る中枢神経系で、脳からの指示を伝えてからだを動かす重要な役割を担っている。神経の本幹であり、脊髄から首や肩、腕へと枝分かれしている。
事故などで背骨を骨折したり脱臼したりすることで脊髄が圧迫されて起こるのが、脊髄損傷だ。頸椎後縦靱帯骨化症や頸椎症などを患っている人が、何かの衝撃によって起こすこともある。日本では新規患者が年に約5千人いて、累積患者数は10万人以上いる。
主な症状は、損傷部より下部に起こる麻痺だ。呼吸障害や排尿・排便障害が起こるケースもある。下半身が全く動かなくなってほぼ無感覚になる完全麻痺と、一部が損傷して動きや知覚に障害が出る不全麻痺の2種類がある。からだだけでなく、車いすでの生活になれば精神的なダメージも大きい。
現在の主な治療は、背骨の固定やリハビリテーションだ。劇的に麻痺を回復させる薬物療法は確立されていない。ロボット技術や電気刺激を使ったリハビリテーションもおこなわれているが、失った機能の回復を目指すのではなく、残った機能を使って日常生活の動作を獲得するために実施される。
不全麻痺の急性期で圧迫が残っていれば、それを取り除く手術や薬物療法を実施する場合もある。
再生医療では、2014年から慶応義塾大学で急性期の患者を対象に、細胞の再生を促す働きがあるHGF(肝細胞増殖因子)というタンパク質からつくった薬を腰から注射する臨床試験がおこなわれ、約半数で改善がみられた。現在、創薬ベンチャーのクリングルファーマがHGFの製剤の臨床開発を進めている。
一方で、損傷後2~4週間の亜急性期の完全麻痺の患者を対象にしている臨床研究が、他人由来のiPS細胞を使った治療だ。これを進めているのも慶応義塾大学で、岡野栄之医師らが中心になっている。この研究のはじまりは、1998年にさかのぼる。岡野医師らが神経細胞(ニューロン)を新しくつくり続けうる「神経幹細胞」を世界で初めて見つけたのだ。その後も、脳梗塞で傷ついた脳であっても神経幹細胞から新しいニューロンが生まれることや、機能を回復させるためには大量の神経幹細胞が要ることなどを突き止めた。
「それまで中枢神経系は損傷したら二度と再生しないといわれていましたが、実は再生能力を引き出せるとわかったのです」(岡野医師)
当初は胎児由来の神経幹細胞を使う計画だったが、06年にiPS細胞が作製されて以降はiPS細胞由来の神経幹細胞に切り替え、10年以上研究を続けてきた。
iPS細胞由来であれば、大量に増やして用意できるうえに、凍結保存しておけば必要なときに解凍でき、移植までの時間もかからない。iPS細胞をつくるには3カ月かかり、それを神経幹細胞へと分化させるとさらに3カ月かかってしまう。岡野医師はiPS細胞を分化誘導し神経幹細胞に調整している。
岡野医師に、対象が亜急性期の患者になっている理由を尋ねた。
「脊髄損傷は直後1~2週間の急性期には炎症でニューロンが生まれません。また、6カ月以降の慢性期になると、瘢痕組織というかさぶた状のものができ、これも神経の線維の再生を邪魔します。その間の亜急性期に神経幹細胞を移植するのが最適だと考えました」
■チェックが終わり次第移植が始まる見込み
移植では、背中から皮膚を切開し、椎骨(背骨の一部)を切除してよけて、硬膜を切って脊髄の損傷部を露出し、中心部に直接注射する。見た目では少なくとも、そのなかには安全性が確認された量である約200万個の神経幹細胞が入っているという。移植するとニューロンがつくられ、失われた細胞の補充が期待できる。
これらの計画は19年2月に厚生労働省に臨床研究の開始が承認された。
「細胞はつくり終えていて、今は品質チェックの最終段階。チェックが終わり次第、実際の移植が始まる見込みです」(同)
リスクは少なからずある。他人由来の細胞を利用するため、半年ほど免疫抑制剤を使うことだ。健常時の脊髄には免疫系の細胞はなかなか入ってこない。脊髄損傷の直後には入ってくるが、他臓器より免疫抑制剤の使用量や使用期間は軽度で済むと考えられている。
またリスクとして腫瘍化の可能性も否定できないが、ないであろうことがさまざまな方法で確認されている。岡野医師は、万一腫瘍化すれば手術で摘出するか、免疫抑制剤の使用をやめて免疫細胞にアタックさせるか、放射線治療をするかの3パターンを考えている。
「今後は脊髄損傷の慢性期や脳梗塞などにも応用したいです。これまで慢性期の患者さんには有効な治療法がありませんでしたが、我々の実験では成功し、論文で発表しています。準備には時間がかかりますが、2年後くらいにできたらいいなと。当院だけではなく、日本全国や世界中でできる治療法にしていきたいです」(同)
(文・小久保よしの)
≪取材協力≫
慶応義塾大学 医学部生理学教室 岡野栄之医師