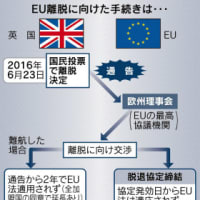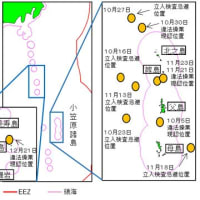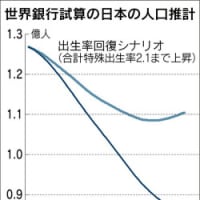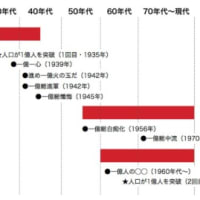掟を内面化し、自らの意思で山に親の入る母親は、息子に背負われながらも、親子の情を相対化して死に場所への“道行”を進む。これが今村作品の核にある発想であることは、昨日の記事で論じた。
『掟が内面化された「姥捨山に入る」思想~「楢山節考」の世界131002』
それと共に貧困の中での人間の欲求は、飢えを凌ぐだけでなく、営みとしての性愛、暴力にも向かうことを描く。今村はそれを動物の生態を通して、表現する。爬虫類、昆虫、獣たちの交尾、蛇がネズミを呑込み、鳥は蛙を食べる、そして蛇の出産シーンだ。野兎を追詰め、銃で撃って仕留めたが、それを鷹が上空から浚っていく。生存競争と生態系の中で生きる自然界の動物と人間は同じだ。
しかし、人間はそれだけでは生きていけない。競争、性愛、暴力もコントロールが必要なのだ。それらと掟を具体的な問題の中で適切に処理していかねばならない。自然の生態系が調整してくれるわけではないのだ。
孫が大家族の家の娘を妊娠させ、連れてきた。その娘は食料を盗んで実家へ届けた。息子は娘の帰りを待伏せ、殺そうとしたが、腹の子を思ってやめた。更にその家のものが盗みを働き、村人たちはその家を根絶やしにすることを決めた。
翌日、母親は娘に芋を持たせて実家に帰した。夜、村の男たちが押し入って、一家全員を個別に網にくるみ、予め掘っておいた穴に全員を放り込み、土をかぶせて生き埋めにした。素早い連携プレーによる作業だ。隣で観ているおじさんが「集団無責任!」と呟いたが、そうではない、「集団責任」なのだ!
息子「親子の情」と母親「掟を貫く姿勢」がぶつかる場面だ。息子・孫は「性的人間」であるが、母親は「政治的人間」なのだ。マックス・ウェーバーが『職業としての政治』の中で、ゲーテを引用して「悪魔は年をとっている。」「だから悪魔を理解するには、お前も年をとっていなければならぬ。」との言葉が浮かぶ。
孫は母親(祖母)に喰ってかかるが、強く無視される。後日、孫は腹を大きくした別の女を家に住まわしていた。性愛とはこういうものだ。
また、生き埋めは若者たちの暴力の発露の場面だ。しかし、軍隊の如く、一糸も乱れず、素早く仕上げ、余計な暴力は使わずに終わらせるのは、見事なコントロールだ。ここには「情」は一切ない。それと共に「憎悪」もない。あるのは「掟」なのだ。結局、孫もそれを理解し、母親(祖母)との関係は普通に維持される。
しかし、性愛と暴力が絡むとやっかいだ。その村では長男以外の男子は結婚を許されていない。これに対して、後家さんが毎晩、順番にその連中の相手をする場面がある。しかし、息子の弟は体臭のため、順番を外され、怒り狂って暴れる。
息子(兄)は嫁に一晩だけ相手になるように頼むが説得できない。母親は老女に頼み、弟に思いを遂げさせ、一家のバランスを取る。一方、母親は秘密の魚とりの場所を嫁に教え、嫁を自らの代わりになるように育てる。この立ち回りが家族の間を取り持っている。
更に各シーンを分析することもできるが、冗長にもなるので止めておこう。
今村が描く「おりん(母親)」の姿は、共同体の掟を自らの意思として体現する等身大の人間像である。それは理念としてではなく、姿として私たちの前に立ちあらわれ、性愛、暴力をコントロールしていることにより、納得させられるのだ。
『掟が内面化された「姥捨山に入る」思想~「楢山節考」の世界131002』
それと共に貧困の中での人間の欲求は、飢えを凌ぐだけでなく、営みとしての性愛、暴力にも向かうことを描く。今村はそれを動物の生態を通して、表現する。爬虫類、昆虫、獣たちの交尾、蛇がネズミを呑込み、鳥は蛙を食べる、そして蛇の出産シーンだ。野兎を追詰め、銃で撃って仕留めたが、それを鷹が上空から浚っていく。生存競争と生態系の中で生きる自然界の動物と人間は同じだ。
しかし、人間はそれだけでは生きていけない。競争、性愛、暴力もコントロールが必要なのだ。それらと掟を具体的な問題の中で適切に処理していかねばならない。自然の生態系が調整してくれるわけではないのだ。
孫が大家族の家の娘を妊娠させ、連れてきた。その娘は食料を盗んで実家へ届けた。息子は娘の帰りを待伏せ、殺そうとしたが、腹の子を思ってやめた。更にその家のものが盗みを働き、村人たちはその家を根絶やしにすることを決めた。
翌日、母親は娘に芋を持たせて実家に帰した。夜、村の男たちが押し入って、一家全員を個別に網にくるみ、予め掘っておいた穴に全員を放り込み、土をかぶせて生き埋めにした。素早い連携プレーによる作業だ。隣で観ているおじさんが「集団無責任!」と呟いたが、そうではない、「集団責任」なのだ!
息子「親子の情」と母親「掟を貫く姿勢」がぶつかる場面だ。息子・孫は「性的人間」であるが、母親は「政治的人間」なのだ。マックス・ウェーバーが『職業としての政治』の中で、ゲーテを引用して「悪魔は年をとっている。」「だから悪魔を理解するには、お前も年をとっていなければならぬ。」との言葉が浮かぶ。
孫は母親(祖母)に喰ってかかるが、強く無視される。後日、孫は腹を大きくした別の女を家に住まわしていた。性愛とはこういうものだ。
また、生き埋めは若者たちの暴力の発露の場面だ。しかし、軍隊の如く、一糸も乱れず、素早く仕上げ、余計な暴力は使わずに終わらせるのは、見事なコントロールだ。ここには「情」は一切ない。それと共に「憎悪」もない。あるのは「掟」なのだ。結局、孫もそれを理解し、母親(祖母)との関係は普通に維持される。
しかし、性愛と暴力が絡むとやっかいだ。その村では長男以外の男子は結婚を許されていない。これに対して、後家さんが毎晩、順番にその連中の相手をする場面がある。しかし、息子の弟は体臭のため、順番を外され、怒り狂って暴れる。
息子(兄)は嫁に一晩だけ相手になるように頼むが説得できない。母親は老女に頼み、弟に思いを遂げさせ、一家のバランスを取る。一方、母親は秘密の魚とりの場所を嫁に教え、嫁を自らの代わりになるように育てる。この立ち回りが家族の間を取り持っている。
更に各シーンを分析することもできるが、冗長にもなるので止めておこう。
今村が描く「おりん(母親)」の姿は、共同体の掟を自らの意思として体現する等身大の人間像である。それは理念としてではなく、姿として私たちの前に立ちあらわれ、性愛、暴力をコントロールしていることにより、納得させられるのだ。