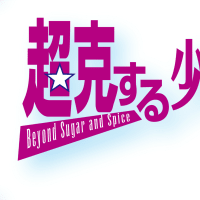そして少女はどうなったのか
インディペンテントキュレーター・美術評論 室井絵里
少女はいつまでも、少女でいるわけではないが、人の中に棲む「少女性」は失われない。少女性は女性特有のものでもないし、少年性が男性特有のものでもない。
女性性・男性性・少女性・少年性はあるいは、中性性も一人の人間の中に様々な形で共存するものだ。
80年代半ば、当時台頭した女性アーティストたち(1960年生まれが中心)を「美術の超少女たち」として、 BTが特集した。彼女たちが自分たちの意思でグループを結成したのでなく、展覧会タイトルでもなかったが、その時代を共有していた人たちには一種の華々しさとともに、ムーブメントのように扱われたのだ。「超少女」と言われた彼女たちも、当時すでに十代の「少女」ではなかったので「超少女」と名付けたのか。いずれにせよ、そこには、これから女性が華々しく、自由に、活躍していけそうな気配、アート界だけでなく「男女雇用機会均等法」などが本格的に施行されたりして、時代に開けた未来へというムードが伴っていた。
バブルや失われた20年を経て彼女たちも熟年を超えて、制作を休止している人もいるが、活動の方向や形を変えている場合も多い。今回の「超克する少女」には「超少女」から菅野由美子に参加してもらったが、菅野も当時は大きな立体作品を作っていた、しばらく沈黙ののちに現在の絵画作品へと、作品の形態は大きく変化してきている。
関西の作家では松井智恵も映像を含めたインスタレーションへと変化している。これは、一人の作家として様々な個人的な環境と同時に、時代の大きな移り変わりがメディアや方法論の変化として現れたとも考えられる。
菅野は、自宅のアトリエで旅をして買い集めてきたものたちを淡々と描いている。同じ対象を描いていても、不思議と年々変化しているし、立体作品を知るものからすると通底する構図や、流れが脈々と見える気がする。自宅に篭って絵を描く行為は、修行のようでもあり、彼女は、世界の文物を一つの画面に描くことで私なりの世界平和を願っているのと言っていて、なるほど、であるからこれらはものとしての個々のティストの限界を超えて、何か一つの大きな別の次元のものたりえているのか、従って、私の中では菅野の絵画作品は、絵画でありながらいわゆる「抽象」「具象」を超えた、絵画そのものの枠も超えた地平で論じられるべきものとしてうつるのだと気付くのである。
AKI INOMATAは、ヤドカリの「宿」を3Dプリンターで製作し、それにヤドカリに入ってもらうシリーズで注目されている。宿は世界の様々な都市を象っていて、都市を越境し、生命あるものとないものとの交換など、極めて現代的な生命科学の問題と深くリンクしてくる。
今回は、福島のあさりの成長の音をレコード化して可視化だけでなく、可聴化している。
もともとは、彼女自身が、3.11後に現れた作品に感じた違和感や、災害が人に与えるダメージが他の生物ではどうだろうという疑問をもったことからあさりの成長記録を研究している人の新聞記事を目にしたところに始まる。あさりの貝殻に成長線があり、成長線は潮の満ち引きなどでも影響を受けているのだが、 3.11以前と以降では震災よりも護岸工事後にダメージが大きかったという。二枚貝のスパイラルからその音を形状としてレコード盤にし、見せて聴かせることに結びつく。これまで、インコのワサビッチョとフランス語を習いに行く作品(ワサビッチョシルヴゥプレと、話し出す!)。または、犬の毛を自分がまとい犬が自分の毛をまとうという作品に表れていた「自己」と他の生命とのつながりを一歩超えて、その生命が人によってどう変化させられているのかということを社会的に見ようとする姿勢がうかがえる。一つの作品で、テーマを深めるタイプのアーティストとして今後この作品がどのように展開していくのか、私にとっても今回の展示は一つの過程であり、その今後をも見たい作品の一つだ。
片山真理は、自身の義足である身体をとおしてハイヒールをはきたい自分やおしゃれをしたい自分を延長するということから作品作りがはじまっていた。あいちトリエンナーレでは、義足の女の子の部屋、それは--彼女自身の部屋でもあったのだろうが--、を、作り込むという印象的な空間で、それ以降、自分を客観視するために自身の身体性を見せる意味で強調した自の像(自画像といってもいいだろう)、セルフシャッターを切る写真作品や、様々なもののコラージュや「人型・人形-ひとがた」などを作るという形で表現の幅を広げている。
いわゆる、セルフイメージというのが人からどう見えているのかという大きい葛藤を超えてきていると思うので、一般的な意味での自撮りの写真ではない。アーティストが自ら写真に入るというのとも少し位相が異なる。自己露出や記録を超えたフラジャイルなものをいわばコラージュし、息を一瞬のむかのように留めた緊張感ある作品である。「超克少女」と同時期に、国立国際美術館で小谷元彦氏のパラレルな映像画面には演者として片山の意思もみえてくるという意味でコラボレーションが成立している。また、YAMADA TAKEOが彼女の撮影を続けているが、彼の目を通して私たちの目も顕著に意識されるのか。それは彼女自身が彼女をみているのと、どのよう異なるのか。今回はじめての二人での展示となる。他者が彼女の身体を通してみようとしていることというのは、彼女がみたいことや、みせたいことと、ズレが生じてくるだろうが、その生じた先にはなにが起こってくるのだろうと考えた。
見られる自分と見せる自分、果てしない揺らぎ、誰にも固定化した自画・像などありはしないのだ。
安喜万佐子 with Melectro(Maeda Shinjiro+Yasuki Masako )の作品をみたのは、東京の安喜の個展会場の一角だ。安喜の絵画作品は、消失した都市や、網膜にうつる風景を岩絵の具や銀箔など古典的画材を使い丹念な技法で描いたものだ。風景とは、そもそも一瞬にして飛び込んでくるが、常に目の裡でみているものは消えていくので、そこ―絵の表面--に、留められているものは、どこにもあり得ない。留められないし実際にはあり得ないものを描く行為が、風景を描くということなのではないだろうか。丹念に描かれたものであるにもかかわらず、私はそれを描くではなく、留めると書いてしまったが、それは私が一種の葛藤を彼女の作品の中に、苦しみでなく美として見てきたからだ。日本や上海をロケし四季を映したMaedaの映像作品が、どこか安喜がこれまで捉えようとしてきた原風景、あるいは、留めてこようとした行為の本質のようにも見え、絵画と映像作品の互換性が素直に見てとれたコラボレーションであったのだ。今回は、さらに深めて映像作品を絵画作品に照射する。いや、見ている風景(画)に逆照射するというコラボレーションに展開する予定である。それは、どのような融合と、ズレと、幸せな分離をそこに生んでいくのか楽しみな一つである。
「超克少女」は、「超少女」が「少女」ではなかったように私の中ではもはやアーティストが女性、男性かは、あまり意味をなさない。むしろ、そういう単純な問いかけへの複雑な答えを用意するのが、常に美術のもつ意味であると思うので、答えはどんどん複雑化し、幸せな融合だけでなく、時には分離や、社会からの乖離でもあるかもしれない。
みえているものを、変えていける強さと同時に弱さを、時々に人の生きている超克途上を見たいという純粋な実験としての展覧会の場である。
(少女たちはおそらく、なにものにもならなかった。)
インディペンテントキュレーター・美術評論 室井絵里
少女はいつまでも、少女でいるわけではないが、人の中に棲む「少女性」は失われない。少女性は女性特有のものでもないし、少年性が男性特有のものでもない。
女性性・男性性・少女性・少年性はあるいは、中性性も一人の人間の中に様々な形で共存するものだ。
80年代半ば、当時台頭した女性アーティストたち(1960年生まれが中心)を「美術の超少女たち」として、 BTが特集した。彼女たちが自分たちの意思でグループを結成したのでなく、展覧会タイトルでもなかったが、その時代を共有していた人たちには一種の華々しさとともに、ムーブメントのように扱われたのだ。「超少女」と言われた彼女たちも、当時すでに十代の「少女」ではなかったので「超少女」と名付けたのか。いずれにせよ、そこには、これから女性が華々しく、自由に、活躍していけそうな気配、アート界だけでなく「男女雇用機会均等法」などが本格的に施行されたりして、時代に開けた未来へというムードが伴っていた。
バブルや失われた20年を経て彼女たちも熟年を超えて、制作を休止している人もいるが、活動の方向や形を変えている場合も多い。今回の「超克する少女」には「超少女」から菅野由美子に参加してもらったが、菅野も当時は大きな立体作品を作っていた、しばらく沈黙ののちに現在の絵画作品へと、作品の形態は大きく変化してきている。
関西の作家では松井智恵も映像を含めたインスタレーションへと変化している。これは、一人の作家として様々な個人的な環境と同時に、時代の大きな移り変わりがメディアや方法論の変化として現れたとも考えられる。
菅野は、自宅のアトリエで旅をして買い集めてきたものたちを淡々と描いている。同じ対象を描いていても、不思議と年々変化しているし、立体作品を知るものからすると通底する構図や、流れが脈々と見える気がする。自宅に篭って絵を描く行為は、修行のようでもあり、彼女は、世界の文物を一つの画面に描くことで私なりの世界平和を願っているのと言っていて、なるほど、であるからこれらはものとしての個々のティストの限界を超えて、何か一つの大きな別の次元のものたりえているのか、従って、私の中では菅野の絵画作品は、絵画でありながらいわゆる「抽象」「具象」を超えた、絵画そのものの枠も超えた地平で論じられるべきものとしてうつるのだと気付くのである。
AKI INOMATAは、ヤドカリの「宿」を3Dプリンターで製作し、それにヤドカリに入ってもらうシリーズで注目されている。宿は世界の様々な都市を象っていて、都市を越境し、生命あるものとないものとの交換など、極めて現代的な生命科学の問題と深くリンクしてくる。
今回は、福島のあさりの成長の音をレコード化して可視化だけでなく、可聴化している。
もともとは、彼女自身が、3.11後に現れた作品に感じた違和感や、災害が人に与えるダメージが他の生物ではどうだろうという疑問をもったことからあさりの成長記録を研究している人の新聞記事を目にしたところに始まる。あさりの貝殻に成長線があり、成長線は潮の満ち引きなどでも影響を受けているのだが、 3.11以前と以降では震災よりも護岸工事後にダメージが大きかったという。二枚貝のスパイラルからその音を形状としてレコード盤にし、見せて聴かせることに結びつく。これまで、インコのワサビッチョとフランス語を習いに行く作品(ワサビッチョシルヴゥプレと、話し出す!)。または、犬の毛を自分がまとい犬が自分の毛をまとうという作品に表れていた「自己」と他の生命とのつながりを一歩超えて、その生命が人によってどう変化させられているのかということを社会的に見ようとする姿勢がうかがえる。一つの作品で、テーマを深めるタイプのアーティストとして今後この作品がどのように展開していくのか、私にとっても今回の展示は一つの過程であり、その今後をも見たい作品の一つだ。
片山真理は、自身の義足である身体をとおしてハイヒールをはきたい自分やおしゃれをしたい自分を延長するということから作品作りがはじまっていた。あいちトリエンナーレでは、義足の女の子の部屋、それは--彼女自身の部屋でもあったのだろうが--、を、作り込むという印象的な空間で、それ以降、自分を客観視するために自身の身体性を見せる意味で強調した自の像(自画像といってもいいだろう)、セルフシャッターを切る写真作品や、様々なもののコラージュや「人型・人形-ひとがた」などを作るという形で表現の幅を広げている。
いわゆる、セルフイメージというのが人からどう見えているのかという大きい葛藤を超えてきていると思うので、一般的な意味での自撮りの写真ではない。アーティストが自ら写真に入るというのとも少し位相が異なる。自己露出や記録を超えたフラジャイルなものをいわばコラージュし、息を一瞬のむかのように留めた緊張感ある作品である。「超克少女」と同時期に、国立国際美術館で小谷元彦氏のパラレルな映像画面には演者として片山の意思もみえてくるという意味でコラボレーションが成立している。また、YAMADA TAKEOが彼女の撮影を続けているが、彼の目を通して私たちの目も顕著に意識されるのか。それは彼女自身が彼女をみているのと、どのよう異なるのか。今回はじめての二人での展示となる。他者が彼女の身体を通してみようとしていることというのは、彼女がみたいことや、みせたいことと、ズレが生じてくるだろうが、その生じた先にはなにが起こってくるのだろうと考えた。
見られる自分と見せる自分、果てしない揺らぎ、誰にも固定化した自画・像などありはしないのだ。
安喜万佐子 with Melectro(Maeda Shinjiro+Yasuki Masako )の作品をみたのは、東京の安喜の個展会場の一角だ。安喜の絵画作品は、消失した都市や、網膜にうつる風景を岩絵の具や銀箔など古典的画材を使い丹念な技法で描いたものだ。風景とは、そもそも一瞬にして飛び込んでくるが、常に目の裡でみているものは消えていくので、そこ―絵の表面--に、留められているものは、どこにもあり得ない。留められないし実際にはあり得ないものを描く行為が、風景を描くということなのではないだろうか。丹念に描かれたものであるにもかかわらず、私はそれを描くではなく、留めると書いてしまったが、それは私が一種の葛藤を彼女の作品の中に、苦しみでなく美として見てきたからだ。日本や上海をロケし四季を映したMaedaの映像作品が、どこか安喜がこれまで捉えようとしてきた原風景、あるいは、留めてこようとした行為の本質のようにも見え、絵画と映像作品の互換性が素直に見てとれたコラボレーションであったのだ。今回は、さらに深めて映像作品を絵画作品に照射する。いや、見ている風景(画)に逆照射するというコラボレーションに展開する予定である。それは、どのような融合と、ズレと、幸せな分離をそこに生んでいくのか楽しみな一つである。
「超克少女」は、「超少女」が「少女」ではなかったように私の中ではもはやアーティストが女性、男性かは、あまり意味をなさない。むしろ、そういう単純な問いかけへの複雑な答えを用意するのが、常に美術のもつ意味であると思うので、答えはどんどん複雑化し、幸せな融合だけでなく、時には分離や、社会からの乖離でもあるかもしれない。
みえているものを、変えていける強さと同時に弱さを、時々に人の生きている超克途上を見たいという純粋な実験としての展覧会の場である。
(少女たちはおそらく、なにものにもならなかった。)