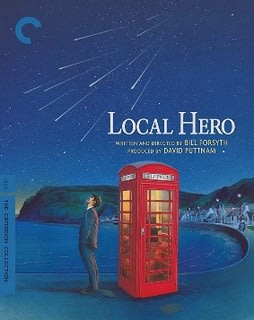(原題:ANNA)リュック・ベッソン監督によるアクション物としては、やっぱり「ニキータ」(90年)や「レオン」(94年)といった全盛期の作品よりは幾分落ちる。ならばダメな映画かというと、決してそうではない。旧作群のインパクトには及ばないということを早々に見切った上で、筋書きの面白さで勝負しようとしている。これは正解だと思う。
90年のモスクワ。市場で露店の番をしていた大学生のアナは、モデル事務所にスカウトされ、パリのファッション界でデビューする。その存在感でアッという間に売れっ子となるが、実は彼女は、KGBによって生み出された凄腕の殺し屋だった。モデルになったのも、最初から仕組まれていたに過ぎない。早速言い寄ってきた財界の要人を始末したのを皮切りに、次々と“仕事”をこなしてゆく。一方、CIAがソ連に送り込んでいた諜報部員たちがKGBに捕まって皆殺しになる事件が発生していた。CIAエージェントのレナードはソ連情報部の中枢に潜り込むべく、アナに接近する。
本作は“二重スパイとしてKGB長官の命を狙うヒロイン!”といったような売り出し方をされているようだが、実際はそう単純ではない。アナがKGBに雇われるようになった経緯や、レナードの執念、アナを憎からず思っているKGBエージェントのアレクセイの葛藤などを時制を前後させて描いており、けっこう人間ドラマとして深いところを突いてくる。
またKGB内での派閥争いの存在を匂わせるが、誰がどっちの陣営に与しているのか最後まで分からないのも高ポイントだ。背景にソ連崩壊前夜のCIAとKGBとの関係性が浮かび上がるのも興味深いモチーフで、フィクションながら実際は斯くの如しだったのだろうという説得力を持つ。
主演のモデル出身のサッシャ・ルスは、正直あまり好きなルックスではないが(ヒロインの友人を演じるレラ・アボヴァの方が可愛い ^^;)、一年かけてマーシャルアーツを習得しただけあり卓越した体術を見せる。ルーク・エヴァンスとキリアン・マーフィの男性陣も良いのだが、圧巻はKGB幹部に扮するヘレン・ミレンで、さすがの海千山千ぶりを発揮している。リュック・ベッソンの演出は今回は才気走った面は見られないが、けっこう手堅くて破綻が無い。ティエリー・アルボガストのカメラとエリック・セラの音楽も及第点だ。