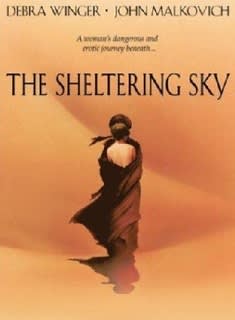主人公のような生活と人生観には到底行き着くことは出来ないが、少なくとも映画を観ている間は“こういう生き方も悪くないじゃないか”と思わせてくれる。斯様な無理筋のキャラクター設定を(一時的にでも)観る者に納得させてしまえば、映画としては成功していると言えよう。そして映像と大道具・小道具の御膳立てには抜かりは無く、鑑賞後の印象は良好だ。
初老の作家ツトムは、長野県の山奥で一人暮らし。畑で育てた野菜類や、山で採れる山菜やキノコ類を料理して自給自足の生活を送っている。彼を訪ねて時どき担当編集者の真知子が東京から訪ねてくるが、彼女はツトムの恋人でもある。だが、彼は13年前に他界した妻の遺骨を墓に納めていない。そんな中、近くに住む亡き妻の母親が逝去し、ツトムは葬式を仕切るハメになる。水上勉の料理エッセイ「土を喰う日々 わが精進十二カ月」を原案に劇映画として仕上げられた。

ツトムは典型的な世捨て人で、真知子とは仲が良いが末永く付き合おうとは思っていないようだ。彼にとって世を去った妻の存在がどれだけ大きかったのかは明示されないが、たとえ生きていたとしても俗世と距離を置いたスタンスは変わらないだろう。単身人里離れた山荘に住むツトムの生活は、常人には付いていけない。もしも何かあったら、ただちに命の危険に繋がる。
しかしながら、オーガニックな食事と共に四季の移り変わりを実感しながらマイペースに執筆活動をおこなうというのは、ある意味理想の生き方とも言える。たとえ不可抗力でそんな日々が途絶えたとしても、すべて責任を自分で背負って静かに退場するだけだ。
演出・脚本を担当した中江裕司は、快作「ナビィの恋」(99年)で日常世界を離れた一種の桃源郷を描いていたが、舞台は違うものの今回もその姿勢は一貫している。そして本作では、それを納得させるような仕掛けの上手さがある。料理研究家の土井善晴が監修した精進料理の数々は、どれもすこぶる美味そうだ。しかも、食材の採取から調理手順に至るまで丁寧に示している。松根広隆のカメラによる信州の風景は痺れるほど美しく、観ているこちらにも清々しい空気が伝わってくるようだ。
主演の沢田研二はさすがに年齢を重ねたが、決してショボクレた年寄りには見えないのは昔はスターとして鳴らした彼のキャラクターによるものだろう。真知子役に松たか子も凜とした好演だ。西田尚美に尾美としのり、檀ふみ、火野正平、奈良岡朋子などの脇の面子も手堅い。
初老の作家ツトムは、長野県の山奥で一人暮らし。畑で育てた野菜類や、山で採れる山菜やキノコ類を料理して自給自足の生活を送っている。彼を訪ねて時どき担当編集者の真知子が東京から訪ねてくるが、彼女はツトムの恋人でもある。だが、彼は13年前に他界した妻の遺骨を墓に納めていない。そんな中、近くに住む亡き妻の母親が逝去し、ツトムは葬式を仕切るハメになる。水上勉の料理エッセイ「土を喰う日々 わが精進十二カ月」を原案に劇映画として仕上げられた。

ツトムは典型的な世捨て人で、真知子とは仲が良いが末永く付き合おうとは思っていないようだ。彼にとって世を去った妻の存在がどれだけ大きかったのかは明示されないが、たとえ生きていたとしても俗世と距離を置いたスタンスは変わらないだろう。単身人里離れた山荘に住むツトムの生活は、常人には付いていけない。もしも何かあったら、ただちに命の危険に繋がる。
しかしながら、オーガニックな食事と共に四季の移り変わりを実感しながらマイペースに執筆活動をおこなうというのは、ある意味理想の生き方とも言える。たとえ不可抗力でそんな日々が途絶えたとしても、すべて責任を自分で背負って静かに退場するだけだ。
演出・脚本を担当した中江裕司は、快作「ナビィの恋」(99年)で日常世界を離れた一種の桃源郷を描いていたが、舞台は違うものの今回もその姿勢は一貫している。そして本作では、それを納得させるような仕掛けの上手さがある。料理研究家の土井善晴が監修した精進料理の数々は、どれもすこぶる美味そうだ。しかも、食材の採取から調理手順に至るまで丁寧に示している。松根広隆のカメラによる信州の風景は痺れるほど美しく、観ているこちらにも清々しい空気が伝わってくるようだ。
主演の沢田研二はさすがに年齢を重ねたが、決してショボクレた年寄りには見えないのは昔はスターとして鳴らした彼のキャラクターによるものだろう。真知子役に松たか子も凜とした好演だ。西田尚美に尾美としのり、檀ふみ、火野正平、奈良岡朋子などの脇の面子も手堅い。