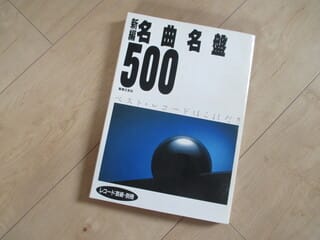(英題:CONFESSION)なかなか良くできた韓国製サスペンス劇だ。もっとも、本作は2016年製作のオリオル・パウロ監督によるスペイン映画「インビジブル・ゲスト 悪魔の証明」(私は未見)のリメイクなのだが、それでも最後まで飽きずに見せ切るだけのクォリティは確保されている。登場人物を少数に絞り込んで、それぞれ達者な演技者を振り当てていることもポイントが高い。
大手IT企業の社長であるユ・ミンホの不倫相手キム・セヒがホテルの一室で殺害された。現場は密室で外部の人間が入り込むことが困難であるため、唯一の関係者であるミンホが疑われ逮捕される。保釈された彼は、山奥の別荘で女性弁護士ヤン・シネと公判の打ち合わせをする場を設ける。再検証を進めるうちに、どうやら事件に先立って起こった交通事故が本件に関係しているらしいことが分かってくるが、目撃者が現れたことによって事態は思わぬ方向へと進んでゆく。

主な舞台を雪深い山荘(ここも一種の密室)に限定していることは、各キャラクターに逃げ場を与えないという意味で効果的だ。また、伏線は少なからぬ数が張り巡らされているが、事件の再現パートを違う視点から複数挿入することにより、それらの伏線が一応破綻なく機能していることを立証しているあたりも冷静な判断である。どこぞの三流スリラーのように、行き当たりばったりにプロットをデッチ上げる愚を犯してはいないのだ。
後半の、二転三転する展開は見ものだが、これがあざとく感じないのは、コーエン兄弟の影響を大きく受けたという監督ユン・ジョンソクの手腕によるものだと思う。ミンホ役のソ・ジソブは本国ではよく知られた俳優だが、私は初めて見た。役柄の広さを感じさせるフレキシブルな演技を披露し、人気の高さも頷ける。シネに扮するキム・ユンジンはさすがの安定感。無理筋とも思える役柄を難なくこなしている。
セヒを演じるナナは、アイドルグループの一員とは思えないほど手堅い仕事ぶり。特に、髪型一つで悪女と清純派を器用に演じ分けるあたりは感心した。また、事件のカギを握る人物に扮するチェ・グァンイルもイイ味を出している。キム・ソンジンのカメラによる、寒色系の澄んだ映像も印象深い。本国では興行収入ランキング初登場一位を記録。各国の映画祭でも好評を博しているとのこと。韓国映画の一種独特の作劇の強引さが苦手でなければ、観て損のない快作と言える。
大手IT企業の社長であるユ・ミンホの不倫相手キム・セヒがホテルの一室で殺害された。現場は密室で外部の人間が入り込むことが困難であるため、唯一の関係者であるミンホが疑われ逮捕される。保釈された彼は、山奥の別荘で女性弁護士ヤン・シネと公判の打ち合わせをする場を設ける。再検証を進めるうちに、どうやら事件に先立って起こった交通事故が本件に関係しているらしいことが分かってくるが、目撃者が現れたことによって事態は思わぬ方向へと進んでゆく。

主な舞台を雪深い山荘(ここも一種の密室)に限定していることは、各キャラクターに逃げ場を与えないという意味で効果的だ。また、伏線は少なからぬ数が張り巡らされているが、事件の再現パートを違う視点から複数挿入することにより、それらの伏線が一応破綻なく機能していることを立証しているあたりも冷静な判断である。どこぞの三流スリラーのように、行き当たりばったりにプロットをデッチ上げる愚を犯してはいないのだ。
後半の、二転三転する展開は見ものだが、これがあざとく感じないのは、コーエン兄弟の影響を大きく受けたという監督ユン・ジョンソクの手腕によるものだと思う。ミンホ役のソ・ジソブは本国ではよく知られた俳優だが、私は初めて見た。役柄の広さを感じさせるフレキシブルな演技を披露し、人気の高さも頷ける。シネに扮するキム・ユンジンはさすがの安定感。無理筋とも思える役柄を難なくこなしている。
セヒを演じるナナは、アイドルグループの一員とは思えないほど手堅い仕事ぶり。特に、髪型一つで悪女と清純派を器用に演じ分けるあたりは感心した。また、事件のカギを握る人物に扮するチェ・グァンイルもイイ味を出している。キム・ソンジンのカメラによる、寒色系の澄んだ映像も印象深い。本国では興行収入ランキング初登場一位を記録。各国の映画祭でも好評を博しているとのこと。韓国映画の一種独特の作劇の強引さが苦手でなければ、観て損のない快作と言える。