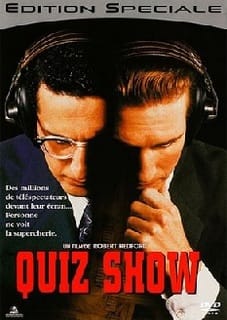説明的なセリフの多さは、通常マイナス評価に繋がるものだが、本作に限ってはそうではない。これは素材の奥深さをセリフがフォローしているという状況が現出しているためで、言葉が先行して映画を引っ張ろうとしているのではないのである。
考えてみれば、映画のテーマ(及びその扱い方)を評するのも、やはり“言葉”に頼るしかないのだ。それを捨象してしまえば、単なる“何となく良かった(あるいは悪かった)”という低レベルの“感想”に終わってしまう。そんな当たり前すぎる原初的な認識を再確認させる、この映画の玄妙さは侮れない。
漫然と大学生活を送っていた20歳の典子は、お茶を習うことを奨められる。茶道の師匠で、立ち振る舞いの洗練度が並ではない“武田のおばさん”から何かを学ばせたいという母親からの提案だった。当初は気乗りがしなかった典子だが、大いに興味を示した同い年のいとこの美智子に誘われ、2人は茶道教室に通い出す。
典子は厳格なプロトコルで構成されたお茶の世界に戸惑ったが、次第にその面白さにハマるようになり、それから20数年にわたり武田先生に師事することになる。その間、彼女は就職も恋愛も経験するが、いずれも思ったような結果に繋がらない。ただ、お茶はいつも彼女の側にあり、考えるヒントを与えてくれるのだった。森下典子のエッセイの映画化だ。
私は茶道に関しては門外漢だが、それでもこの芸事における膨大なルールと、さらにそれらを超えたところにあるアーティスティックな境地に見入ってしまう。これを平易に表現するには、なるほどセリフを敷き詰めねばならないのは当然だろう。それどころか、本作ではセリフは必要最小限に抑えられているのではないかと思ってしまう。
“考えるんじゃなく、感じるんだ”という意味の武田先生の言葉(某映画でもお馴染みだが ^^;)が、実にしっくりと収まる作劇。それまで典子が気が付かなかった音や色彩や、四季の移ろい等がヒロインの成長と共に観る者にも伝播していくという構成は、見事と言うしかない。モチーフとして出て来る、フェリーニの「道」の扱いも納得出来る。
主演の黒木華は殊更メイクなどに凝っていないにも関わらず、ちゃんと長い年月を感じさせる演技を披露しているのには感心する。さすが若手屈指のパフォーマーだ。先生役の樹木希林は、これはもう“神業”に近いのではないか。どう見たって茶道のエキスパートそのものだ。美智子に扮する多部未華子をはじめ、鶴田真由や鶴見辰吾など、脇の仕事ぶりも確かなものである。
監督の大森立嗣は出来不出来の幅がある作家だが、今回は落ち着いた演出を見せる。槇憲治の撮影、世武裕子の音楽、そして全編を彩る茶道の大道具・小道具の数々。鑑賞後の満足度は高い。