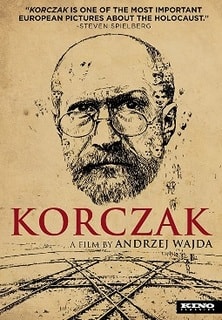昭和29年東宝作品。原作が林芙美子で監督が成瀬巳喜男という、「めし」(1951年)や「稲妻」(1952年)などに続く鉄板のコンビによるシャシンで、完成度も前2作に負けないほど高い。とにかく、力量のあるキャストと闊達な演出は、今観ても感心してしまう。この頃の日本映画の代表作だ。1954年度のキネマ旬報ベストテンでは、7位にランクインしている。
かつて売れっ子の芸者だった倉橋きんも、引退後は興味の対象は金だけになっていた。結婚はせず、口の不自由な女中の静子と二人暮しだ。昔の芸者仲間のたまえ、とみ、のぶの3人は近所に住んでいたが、いずれも貧乏暮らしで、きんに金を借りていた。そんな3人にきんは容赦なく取り立てを敢行するのだった。ある日、若い頃にきんと恋仲だった田部から会いたいという手紙を受け取る。有頂天になった彼女はめかし込んで彼と会うのだが、実は田部は単に金を借りに来たのだ。怒ったきんは、今まで持っていた彼の手紙や写真を焼き捨ててしまう。
とにかく、きんのキャラクター造型が出色だ。本当に彼女は金のことしか考えない。うっかり昔の彼氏に心を動かされるが、それを吹っ切るのも早い。その徹底ぶりは爽快感すら覚える。たまえ達はそれぞれの家庭で問題を抱えているが、きんはそれらとも完全に距離を置く。
この、開き直ったような人間性を、作者は決して批判も軽視もしていない。それまでの人生で辛い思いをしたであろう彼女にとって、信じられるものは金だけというのも、大いに納得出来る。一方でたまえ達の、それこそ“家庭的”で猥雑な環境も肯定しており、きんとの対比は平易で無理がない。たまえ達ときんの生き方を改めて強調する幕切れも鮮やかだ。
成瀬の仕事ぶりは万全で、名もなき市井の人々の“日常”をしっかりと描き出す。緻密な人間描写は相変わらずで、何気ない出来事の積み重ねが庶民の希望と達観と諦観を静かに表現しているあたりは流石と言うしかない。主演の杉村春子は絶品。明け透けのようで、その内面にある情感を密かに醸し出すパフォーマンスには舌を巻いた。細川ちか子に望月優子、沢村貞子といった他の女優陣は万全だし、上原謙や加東大介、小泉博などの男優たちも場を盛り上げる。玉井正夫のカメラによる奥深い映像。齋藤一郎の音楽も及第点だ。