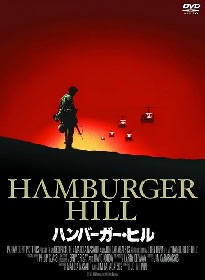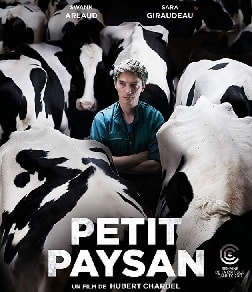(原題:PETERLOO)今まで知らなかった歴史上の事件を紹介してくれたことは、とてもありがたい。しかしながら、映画として面白いかどうかと聞かれると、あまり色好い返事は出来ない。史実をありのままに伝えようと腐心するあまり、ドラマ面での興趣がネグレクトされているような印象だ。しかも上映時間が2時間半というのは、抑揚を欠いた展開を見せつけるには、あまりにも長い。
1815年に長く続いたナポレオン戦争は終結したが、イングランドは経済状態が悪化。さらに地主や農業資本家の利益を擁護した穀物法の制定が拍車をかける。この社会の窮状は北部において顕著で、選挙権の欠如の問題と結びつき、民衆の間には政治的急進主義が広まってゆく。議会改革を訴えていたマンチェスター愛国連合は、1819年8月16日に有名な急進派の活動家であるヘンリー・ハントを招き、マンチェスターのセント・ピーターズ・フィールドで大規模な集会を決行した。しかし、地元の治安判事たちは軍当局に群衆を蹴散らすことを命じ、武装した騎兵隊が集会に乱入。多数の死傷者が発生する。
この出来事は本作を観て初めて知った。歴史家ジャクリーヌ・ライディングの協力を得て、綿密にリサーチされた史実の再現は確かに見応えがある。当時の風俗の描写にも抜かりが無い。しかし、映画としての味わいは淡白だ。
冒頭、ワーテルローの戦いと生き残ったマンチェスター出身の若者ジョセフがクローズアップされるが、以後はジョセフがドラマの中心になることは無い。北部のリベラリスト達や、彼らを押さえつけようとする当局側の者がドラマを引っ張っていくことも無い。集会の主賓はヘンリー・ハントだが、彼のプロフィールが紹介されるわけでもない。
ならば群像劇・集団劇のスタイルを取っているのかというと、それに見合う骨太なドラマ展開は用意されておらず、映画は平坦に進むだけだ。クライマックスの騒乱場面は迫力があり、ここは監督マイク・リーの実力が発揮されている。だが、この事件後どのような影響が生じたのか、英国史にどういう位置付けが成されているのか、そういうフォローは一切無い。そもそも、この事件が何年に起こったのかも映画の中で示されないのだ。
映像面で史実を表現したという次元に留まっており、映画としての求心力は弱い。マキシン・ピークにロリー・キニア、デイヴィッド・ムーストといったキャストはいずれも印象に残らず、ゲイリー・ヤーションの音楽は控え目に過ぎる。ただ、ディック・ポープによる撮影は見事だった。