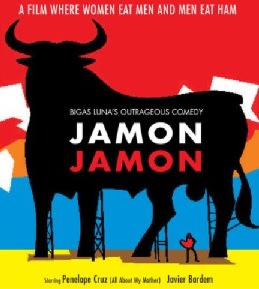88年東宝作品。吉永小百合の映画出演100本記念作品として上映されたが、正直、どうしてこのような企画が通ったのか分からない。出来の方も、さほど芳しいものではない。
もっとも、監督の市川崑はこの前年に「竹取物語」を撮ってヒットさせており、映画会社としては“むかし話の第二弾”(?)として、ある程度の興収が見込めると踏んだのだのかもしれない。だが、古典文学と民話では違うアプローチが要求されるだろうし、加えて主演に吉永を持ってこなければならない立場上、当初から無理筋の話だったのかもしれない。
民話「鶴の恩返し」の映画化で、今さらこのネタをスクリーン上で展開する必然性があったのかどうかはともかく、作劇面では工夫が足りない。その最たるものは、つるの夫となる貧しい百姓・大寿の造型だ。明らかにコメディ方面に振られたキャラクター設定で、静謐な雰囲気の創出を狙った美術や演出テンポと合っていない。演じる野田秀樹はよくやっていたと思うが、彼が頑張れば頑張るほど違和感は増すばかり。これは脚本とキャスティングの不備かと思う。
主演の吉永は美しく撮られていたとは思うが、もとより演技力に難のある女優なので、彼女が画面の真ん中に陣取るたびに白々としたムードが漂ってしまう。さらに致命的なのは、機を織る鶴の描写が呆れかえるほど稚拙なことだ。ただのハリボテではどうにもならない。いくらCGが普及していない時代の映画とはいえ、特撮映画を数多く手掛けていた東宝の作品とも思えない。
樹木希林に川谷拓三、横山道代、菅原文太、岸田今日子、常田富士男といった豪華な面子を並べているのに、大して働かせていないのもマイナスだ。ただ、上映時間が1時間半ほどである点は良かった。この調子で2時間以上も引っ張っていれば、観ているのも苦痛になっていたところだ。
私はこの映画を封切り当時に観ているのだが、映画本編よりも驚いたことがある。それは何と、劇場の天井にミラーボールが備え付けられており、場内が暗くなって映画が始まる前に起動し、劇場中に小さな光がハデに反射したことだ。どうやら鶴の羽根が舞い踊る様子を表現したかったらしいが、こういう“小細工”に頼らざるを得ないほど、映画会社は本作の興行的な難しさに(完成後に)気付いたということだろうか。なお、谷川賢作による音楽は良かった。




もっとも、監督の市川崑はこの前年に「竹取物語」を撮ってヒットさせており、映画会社としては“むかし話の第二弾”(?)として、ある程度の興収が見込めると踏んだのだのかもしれない。だが、古典文学と民話では違うアプローチが要求されるだろうし、加えて主演に吉永を持ってこなければならない立場上、当初から無理筋の話だったのかもしれない。
民話「鶴の恩返し」の映画化で、今さらこのネタをスクリーン上で展開する必然性があったのかどうかはともかく、作劇面では工夫が足りない。その最たるものは、つるの夫となる貧しい百姓・大寿の造型だ。明らかにコメディ方面に振られたキャラクター設定で、静謐な雰囲気の創出を狙った美術や演出テンポと合っていない。演じる野田秀樹はよくやっていたと思うが、彼が頑張れば頑張るほど違和感は増すばかり。これは脚本とキャスティングの不備かと思う。
主演の吉永は美しく撮られていたとは思うが、もとより演技力に難のある女優なので、彼女が画面の真ん中に陣取るたびに白々としたムードが漂ってしまう。さらに致命的なのは、機を織る鶴の描写が呆れかえるほど稚拙なことだ。ただのハリボテではどうにもならない。いくらCGが普及していない時代の映画とはいえ、特撮映画を数多く手掛けていた東宝の作品とも思えない。
樹木希林に川谷拓三、横山道代、菅原文太、岸田今日子、常田富士男といった豪華な面子を並べているのに、大して働かせていないのもマイナスだ。ただ、上映時間が1時間半ほどである点は良かった。この調子で2時間以上も引っ張っていれば、観ているのも苦痛になっていたところだ。
私はこの映画を封切り当時に観ているのだが、映画本編よりも驚いたことがある。それは何と、劇場の天井にミラーボールが備え付けられており、場内が暗くなって映画が始まる前に起動し、劇場中に小さな光がハデに反射したことだ。どうやら鶴の羽根が舞い踊る様子を表現したかったらしいが、こういう“小細工”に頼らざるを得ないほど、映画会社は本作の興行的な難しさに(完成後に)気付いたということだろうか。なお、谷川賢作による音楽は良かった。