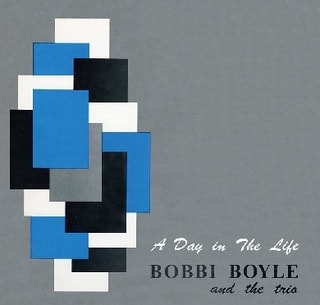(原題:BABYLON )とても評価できる内容ではない。デイミアン・チャゼル監督は自身が本当は何が得意で何をやりたいのか、まったく分かっていないようだ。彼は守備範囲が極端に狭いことを認めたくないのか、前作と前々作では場違いなネタを扱って上手くいかなかった。本作に至って少しは軌道修正したのかと思ったら、さらに酷いことになっている。アカデミー賞では主要部門にノミネートされなかったのも当然だろう。
1920年代のハリウッドを舞台に、メキシコから夢を抱いてやって来た青年マニー・トレスと、偶然彼と知り合って意気投合した駆け出しの女優ネリー・ラロイ。そして大スターのジャック・コンラッドの3人を中心に、サイレントからトーキーに移行する映画製作の現場を狂騒的に描く。

まず納得できないのは、この時代のハリウッドを描いた映画としては既に「雨に唄えば」(1952年)という傑作が存在していることを作者が理解していないことだ。“いや、それは違う。劇中にはちゃんと「雨に唄えば」が引用されているではないか”という反論が返ってくるのかもしれないが、単に存在を知っているだけでは「雨に唄えば」の価値を分かっていることにはならない。事実、本作における「雨に唄えば」の扱いは、漫然とした“場面の紹介”に終わっている。
さらに、昔のハリウッドのダークな内幕を描いた作品としては「サンセット大通り」(1950年)や「イヴの総て」(1950年)といった突出した前例があるが、本作はそれらに遠く及ばない。また、デイヴィッド・リンチ監督の「マルホランド・ドライブ」(2001年)における魔窟としてのハリウッドの描写には、この映画は比べるのも烏滸がましい。ただ、クレイジーな事物を賑やかに並べて自己満足に浸っているだけだ。
では、チャゼル監督が本当に描くべきものは何だったのかというと、それはジョバン・アデポ扮するジャズ・トランペット奏者である。映画におけるジャズ音楽の重要性、そして黒人プレイヤーとして味わう数々の辛酸、その屈託をサウンドとして叩き付けるプロセスを、得意の演奏場面で活写すればかなりの成果が上がったはずだ。それを何を勘違いしたのか、“自分はハリウッドの歴史を俯瞰的に捉える実力がある”とばかりに総花的な3時間超の“大作”に仕上げてしまった、その暴挙には呆れるしかない。
ブラッド・ピットにマーゴット・ロビー、ディエゴ・カルバ、オリヴィア・ワイルド、トビー・マグワイアなどキャストは皆熱演ながら、徒労に終わっている感がある。唯一興味深かったのが、オリヴィア・ハミルトン扮する女流監督だ。モデルはサイレント映画時代にハリウッドで唯一の女性監督だったドロシー・アーズナーらしいが、こういう人材が実在していたことを本作で初めて知った次第である。
1920年代のハリウッドを舞台に、メキシコから夢を抱いてやって来た青年マニー・トレスと、偶然彼と知り合って意気投合した駆け出しの女優ネリー・ラロイ。そして大スターのジャック・コンラッドの3人を中心に、サイレントからトーキーに移行する映画製作の現場を狂騒的に描く。

まず納得できないのは、この時代のハリウッドを描いた映画としては既に「雨に唄えば」(1952年)という傑作が存在していることを作者が理解していないことだ。“いや、それは違う。劇中にはちゃんと「雨に唄えば」が引用されているではないか”という反論が返ってくるのかもしれないが、単に存在を知っているだけでは「雨に唄えば」の価値を分かっていることにはならない。事実、本作における「雨に唄えば」の扱いは、漫然とした“場面の紹介”に終わっている。
さらに、昔のハリウッドのダークな内幕を描いた作品としては「サンセット大通り」(1950年)や「イヴの総て」(1950年)といった突出した前例があるが、本作はそれらに遠く及ばない。また、デイヴィッド・リンチ監督の「マルホランド・ドライブ」(2001年)における魔窟としてのハリウッドの描写には、この映画は比べるのも烏滸がましい。ただ、クレイジーな事物を賑やかに並べて自己満足に浸っているだけだ。
では、チャゼル監督が本当に描くべきものは何だったのかというと、それはジョバン・アデポ扮するジャズ・トランペット奏者である。映画におけるジャズ音楽の重要性、そして黒人プレイヤーとして味わう数々の辛酸、その屈託をサウンドとして叩き付けるプロセスを、得意の演奏場面で活写すればかなりの成果が上がったはずだ。それを何を勘違いしたのか、“自分はハリウッドの歴史を俯瞰的に捉える実力がある”とばかりに総花的な3時間超の“大作”に仕上げてしまった、その暴挙には呆れるしかない。
ブラッド・ピットにマーゴット・ロビー、ディエゴ・カルバ、オリヴィア・ワイルド、トビー・マグワイアなどキャストは皆熱演ながら、徒労に終わっている感がある。唯一興味深かったのが、オリヴィア・ハミルトン扮する女流監督だ。モデルはサイレント映画時代にハリウッドで唯一の女性監督だったドロシー・アーズナーらしいが、こういう人材が実在していたことを本作で初めて知った次第である。