清水寺を眺めて阿弥陀堂にと進み、熊子は屋根の裏が気に成り始めました。
元設計士の兄に昔の宮大工は釘を使わずに木を組んでお堂を作ったの?と
質問しましたらね、カエルマタ、トキョウという言葉が出てきました。
 画はサムネル画です。クリックすると大きくなります。
画はサムネル画です。クリックすると大きくなります。

あれがカエルマタ、トキョウだよと兄。う?え?あ?・・・の熊子。
 画はサムネル画です。クリックすると大きくなります。
画はサムネル画です。クリックすると大きくなります。

これが、大斗・斗拱(タイト・トキョウ)という組み方です。
 画はサムネル画です。クリックすると大きくなります。
画はサムネル画です。クリックすると大きくなります。

これが、蛙股(カエルマタ 上下の梁の飾束)と言います。
 画はサムネル画です。クリックすると大きくなります。
画はサムネル画です。クリックすると大きくなります。

三重の塔の建築様式はね、組物といい、柱の上に載って軒を支える装置の
事で、斗拱(トキョウ)とも言います。勉強になったべさ。
※お兄ちゃん、これでいいかな、間違っていたらどうしよう 。
。
日本古来の建築様式サイトです。
興味のある方はクリックしてね。
 画はサムネル画です。クリックすると大きくなります。
画はサムネル画です。クリックすると大きくなります。

清水寺を支えている柱です。この柱の梁に屋根が付いていますよね。
この屋根がね長年雨から柱を守っているので、このお寺は丈夫だそう
です。それにしても大勢の人を毎日毎日支え続ける清水寺の柱です。
開創はね、今から1,200余年前、奈良時代末だそうです。
素晴らしいですね。
 画はロールオーバーです。マウスを乗せると画が変わります。
画はロールオーバーです。マウスを乗せると画が変わります。

観音様がたくさんおいででしたが、阿弥陀様とふれ愛観音様を
載せました。ふれ愛観音様をみなさん優しく撫でてておいででした。
余談ですが、観光客の多くはアジア方面、主には中国から来て
います。ツーショットをお願いするのに苦労しました。
<<追加記事です。>>
蟇股(カエルマタ:蛙股)割り束(上梁と下梁の間の束)です。
縦の力が掛かり(軸力)、安定もあって下が開き加減。
蛙が股を開いた感じで、どんどん装飾がほどかされていく。
斗・大斗・斗拱:斗は、ます、ますの上に載る細長い肘木(肘木)、
1,2,3と組んでいく。一手先、二手先、三手先、この組み物を斗拱という。
大斗は柱の上の斗(ます)いう。
木材ですので下地は漆(腐食を防ぐ)、清水の舞台柱梁仝じ、
更に梁は上水平面、雨水を浸透させぬため片屋根をつけている。
▲法隆寺金堂の断面図
▲法隆寺金堂上層部高欄(こうらん)の細部
卍くずしの組子(くみこ)と人字形の割束(わりづか)組物(くみもの)
組物とは、柱の上に載って軒を支える装置の事で、斗拱(ときょう)とも
言います。斗拱は、斗(ます)の部分とその上に載る細長い肘木(ひじき)の
組み合わせで成り立っています。(「三手先」を参照)
▲五重塔の組物
三手先(みてさき)
組物(「組物」を参照)は、斗(ます)の部分とその上に載る細長い
肘木(ひじき)の組み合わせで成り立っています。この斗と肘木の
組み合わせが積み重なった数を手先という言葉で表し、柱から出た
肘木の上に載る斗のいくつ目に軒桁が載るかで手先の数が決まります。
奈良時代以降の仏寺の重要な建物にはこの三手先が用いられました。
なお、この三手先が主流になる以前の飛鳥様式の仏寺では、肘木に
曲線模様をつけた雲肘木(くもひじき)が使われました。
▲薬師寺東塔の三手先(みてさき)
▲雲肘木(くもひじき) 組み物の前は(斗拱)この経費木が多い
わかるかな?専門用語ばかりですが・・・三重、五重の塔は中心に
柱、高くなり、更に4本小柱梁で中央の大柱を支える
基礎はほとんど平たい面を持つ石が多い。
参考:伊勢神宮、「唯一神明造」で柱は地中に埋める(腐る)
20年毎遷宮する1300年余続けてきている。
※後日、兄より追加文が届きましたので掲載いたしました。
元設計士の兄に昔の宮大工は釘を使わずに木を組んでお堂を作ったの?と
質問しましたらね、カエルマタ、トキョウという言葉が出てきました。
 画はサムネル画です。クリックすると大きくなります。
画はサムネル画です。クリックすると大きくなります。

あれがカエルマタ、トキョウだよと兄。う?え?あ?・・・の熊子。
 画はサムネル画です。クリックすると大きくなります。
画はサムネル画です。クリックすると大きくなります。

これが、大斗・斗拱(タイト・トキョウ)という組み方です。
 画はサムネル画です。クリックすると大きくなります。
画はサムネル画です。クリックすると大きくなります。

これが、蛙股(カエルマタ 上下の梁の飾束)と言います。
 画はサムネル画です。クリックすると大きくなります。
画はサムネル画です。クリックすると大きくなります。

三重の塔の建築様式はね、組物といい、柱の上に載って軒を支える装置の
事で、斗拱(トキョウ)とも言います。勉強になったべさ。
※お兄ちゃん、これでいいかな、間違っていたらどうしよう
 。
。日本古来の建築様式サイトです。
興味のある方はクリックしてね。
 画はサムネル画です。クリックすると大きくなります。
画はサムネル画です。クリックすると大きくなります。

清水寺を支えている柱です。この柱の梁に屋根が付いていますよね。
この屋根がね長年雨から柱を守っているので、このお寺は丈夫だそう
です。それにしても大勢の人を毎日毎日支え続ける清水寺の柱です。
開創はね、今から1,200余年前、奈良時代末だそうです。
素晴らしいですね。
 画はロールオーバーです。マウスを乗せると画が変わります。
画はロールオーバーです。マウスを乗せると画が変わります。
観音様がたくさんおいででしたが、阿弥陀様とふれ愛観音様を
載せました。ふれ愛観音様をみなさん優しく撫でてておいででした。
余談ですが、観光客の多くはアジア方面、主には中国から来て
います。ツーショットをお願いするのに苦労しました。
<<追加記事です。>>
蟇股(カエルマタ:蛙股)割り束(上梁と下梁の間の束)です。
縦の力が掛かり(軸力)、安定もあって下が開き加減。
蛙が股を開いた感じで、どんどん装飾がほどかされていく。
斗・大斗・斗拱:斗は、ます、ますの上に載る細長い肘木(肘木)、
1,2,3と組んでいく。一手先、二手先、三手先、この組み物を斗拱という。
大斗は柱の上の斗(ます)いう。
木材ですので下地は漆(腐食を防ぐ)、清水の舞台柱梁仝じ、
更に梁は上水平面、雨水を浸透させぬため片屋根をつけている。
▲法隆寺金堂の断面図
▲法隆寺金堂上層部高欄(こうらん)の細部
卍くずしの組子(くみこ)と人字形の割束(わりづか)組物(くみもの)
組物とは、柱の上に載って軒を支える装置の事で、斗拱(ときょう)とも
言います。斗拱は、斗(ます)の部分とその上に載る細長い肘木(ひじき)の
組み合わせで成り立っています。(「三手先」を参照)
▲五重塔の組物
三手先(みてさき)
組物(「組物」を参照)は、斗(ます)の部分とその上に載る細長い
肘木(ひじき)の組み合わせで成り立っています。この斗と肘木の
組み合わせが積み重なった数を手先という言葉で表し、柱から出た
肘木の上に載る斗のいくつ目に軒桁が載るかで手先の数が決まります。
奈良時代以降の仏寺の重要な建物にはこの三手先が用いられました。
なお、この三手先が主流になる以前の飛鳥様式の仏寺では、肘木に
曲線模様をつけた雲肘木(くもひじき)が使われました。
▲薬師寺東塔の三手先(みてさき)
▲雲肘木(くもひじき) 組み物の前は(斗拱)この経費木が多い
わかるかな?専門用語ばかりですが・・・三重、五重の塔は中心に
柱、高くなり、更に4本小柱梁で中央の大柱を支える
基礎はほとんど平たい面を持つ石が多い。
参考:伊勢神宮、「唯一神明造」で柱は地中に埋める(腐る)
20年毎遷宮する1300年余続けてきている。
※後日、兄より追加文が届きましたので掲載いたしました。










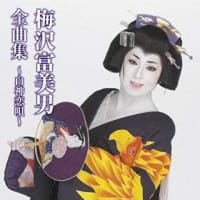









上に登るために柱を伝って行こうともくろんでいる。
錆びやすい釘を使っていないのは知ってましたが、カエルマタ(蛙股)やトキョウ(斗拱)の名は初めて知りました。見ているのにね、それがそうだとは知らなかった。
舞台を支えている柱の小さな屋根、それも知っていました。でもあれはネズミ返しだろうと思っていた。なるほど正真正銘の柱専用の屋根なのね。勉強になりました。
何度も行っている清水寺ですが釘を使っていないぐらいのことしか知りませんでした。
熊子さんが行ったのは平日ですよね?やはり清水寺へは混雑していますね。
清水寺~産寧坂~二年坂~高台寺~八坂神社~祇園へと歩くのが私のいつものコースです。歩く歩く!
清水寺手前の八つ橋の試食はお茶をいただきながら私は必ず寄って食べてきます
八つ橋の試食とお茶は必ず味わって行きましょう。
あまもりさんも良く知っているなぁ!?
私は建築様式にはまったく興味が無かったのでした。
ただただ有名な所に行く事だけが目的でした。
これから先も興味は持てそうに有りません。人それぞれ楽しみ方に違いあっても良いですよね?
私も何気なく見てるだけで、済ませていました。
で、蛙股と斗拱についての質問です。
蛙股について、広辞苑では『下方が開いて蛙の股のような形をしている』とあり、ネットで様々な蛙股を調べても、清水寺の画像のように足の出てないのは見当たりません。
画像の蛙股は、斗拱と外観が似ているようにも見え、
斗拱の装飾された物ではないでしょうか?