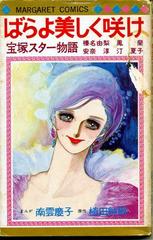「大須浅草三文オペラ」で、トリに歌われたのが超有名(と思われる)「コロッケの唄」でした。これは、「カフェーの夜」っていう演目の劇中歌として有名になったもので、面白おかしいコミックソングなんです。
浅草オペラ関係で有名な曲ではありますが、「レヴューの王様―白井鉄造と宝塚 (1983年)」」で高木史朗せんせいが語るところによると、もともとは帝劇女優劇(川上貞奴とかの提案でできた、当時の日本で珍しい、女優による現代劇の公演)で歌ってた曲のようですね。それが「カフェーの夜」で使われて再ヒットしたってことらしい。
コロッケの唄
CDキングアーカイブシリーズ「懐かしの浅草オペラ」に収録されてるのは3番まで。(たしか大須浅草三文オペラの公演でも3番までしか歌ってなかった)
****************************
1 ワイフもらってうれしかったが いつも出てくるおかずがコロッケ
きょうもコロッケ 明日もコロッケ これじゃ年がら年じゅう(ウィー)コロッケ
2 亭主もらってうれしかったが いつもちょいと出りゃ めったにゃ帰らない
きょうも帰らない 明日も帰らない これじゃ年がら年じゅう(エーッくやしい)留守居番
3 さいふ拾ってうれしかったが 開けてみたらば金貨がザクザク
株を買おうか 土地を買おうか 思案最中に(ハッハッハッハクション)目がさめた
※CDの歌詞カードから引用ですが、「アッハハハハハハハこりゃおかし」とかのコーラス部分は省略してあります。
****************************
一方、高木史朗せんせいの「レヴューの王様―白井鉄造と宝塚 (1983年)」に載ってる歌詞は7番まであって微妙にちがう!
****************************
1 ワイフ貰って、嬉しかったが、いつも出てくるおかずはコロッケー
今日もコロッケー、明日もコロッケー、是ぢゃ年から年中(ゲープ)コロッケー
2 亭主貰って、嬉しかったが、いつもチョイト出りゃめったに帰らない
今日も帰らない、明日も帰らない 是ぢゃ年がら年中(マ随分だワ)留守居番
3 夜店ひやかし、おはち買ったが たった二十銭ぢや滅法界に安い
家へ帰って、フタをとったら 安いはづだよ(アッしまった)底が無い
4 ちょいと紳士に、成ってみたいと 無理にさんだんして自動車借りて
乗るにゃ乗ったが、ぢきに止まって 仕方なくなく(皆さんすみませんが手を貸して下さいな)エンサカホイ
5 晦日近くに、財布ひろって 開けてみたらば金貨がザクザク
株を買うか、地所を買うか 思案最中に(ハクショーイ)目がさめた
6 英語習って、訳も知らずに チョイト西洋人にアイラブユーと言ったら
急に抱きつき、顔をなめられ つけた白粉が(オーきたない)むらだらけ
7 私しや洋食が好きと云ったら 直ぐに呼ばれて、出されたものは
牛の脳みそ足に尻っぽ 肝になめくじ(モウ結構です)豚の腸
****************************
高木先生が本に載せているこの歌詞、白井鐵造が持ってたコミックソングの楽譜集に載ってたもんらしいです。それをみて、高木せんせいも「コロッケの唄は7番まである」ことを知ったそうです。
まあ、浅草の小屋でかかった昔の曲なんて、いろんなパターンの歌詞あって、変化もしてそうですが・・・。それにしても、いまCDとして残されているものは、いかにも毒がないよね。7番まであるヤツのほうが、なんというか・・・浅草っぽい。(あくまでイメージですが)
それにしても、こんな貴重な資料を白井先生が持ってらしたとは。この資料、宝塚歌劇団が受け継いでいたりするんじゃないの??だとしたら、宝塚レビューの現場は、なんて恵まれているんだろう!って思ってしまった。
で、このコロッケの唄を作詞したのが益田太郎冠者ってヒトなんだけど・・・って話は次回につづきます。
★へえボタン★