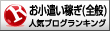宴席ではシベリアの歌や踊りも披露されました。若い男女がかわるがわる歌ったり、みなで踊ったりとマトリョーシカを歓待したのです。スターリン皇帝はますます上機嫌になり、拍手をしたり大笑いしたりとご満悦の様子でした。
「マトリョーシカ殿、どうですか。サハリンの歌でも踊りでもやってみませんか」
スターリンがそう言うので、せっかくの勧めを断るわけにはいきません。マトリョーシカは歌も得意です。彼女は立ち上がると、サハリンの民謡を歌い始めました。なかなかの美声ですが、宴席の人たちはそれよりも、彼女の愛くるしい美貌に改めて見とれている感じです。民謡を歌い終えると、万雷の拍手が巻き起こりました。
「いや素晴らしい、素晴らしい! ハラショー!」 スターリンも盛んに拍手を送りました。こうして宴会は和やかに盛り上がりましたが、やがてスターリンが言いました。
「マトリョーシカ殿、今度は愚息のピョートルを貴国に招いてくれませんか。彼も一度 サハリンをぜひ訪問したいと願っているのです」
そう言われると、もちろん断るわけにはいきません。「はい、いつでもいらっしゃってください」 マトリョーシカは“外交辞令”のように答えました。
宴会が終わると、スターリンとピョートルは彼女ににこやかに会釈して退席しました。皇帝は酒盃を重ねてほろ酔い状態でしたが、マトリョーシカには心から満足している様子でした。心の中で、彼女とピョートルが結ばれることを期待していたのです。
マトリョーシカはヤクーツクに10日ほど滞在しました。街並みを見物したり郊外に出かけるなど、マリアとゆっくりした日々を過ごしましたが、帰国の際にスターリンから豪勢な土産物をもらったのです。ツルハゲ王には立派な毛皮が、カチューシャ王妃とマトリョーシカには美しい衣類などが贈られました。
こうして、ヤクーツク滞在を楽しんだあと一行は帰路につきましたが、マトリョーシカは、あのピョートルのことがどうしても気になります。いずれ彼はサハリンにやって来るでしょう。でも・・・やはり、アレクサンドルの面影が脳裏に浮かんでくるのでした。
馬車で帰国する道すがら、マリアが話しかけてきました。
「あのスターリン皇帝は、息子とあなたを結びつけようとしているのですね」
「ええ、そうかもしれないわ。でも・・・」 マトリョーシカが口ごもると、マリアが続けます。
「あなたはそんな気持はないのでしょ? それとも、サハリン・シベリア両国にとって良いとでも考えているのかしら」
マトリョーシカは返事に窮し暫く答えませんでしたが、ついに真情を吐露しました。
「マリア、このことはまだ誰にも言わないで。私はベラの兄さんに惹かれているの」
「やっぱりそうか・・・ それなら、私からベラに話をしてもいいわ」
「いえ、まだ言わないで。今度ベラに会ったら話そうと思うの。それまで黙っていてちょうだい」
マトリョーシカは心の内をマリアに明かすと、何かほっとした気持になりました。胸につかえていたものが、取り除かれたように感じたのです。マリアに話した以上、帰国したらできるだけ早くベラに打ち明けなければなりません。旅に出ていると、意外に素直に自分の思いを明かすことができるのですね。
こうして、マトリョーシカらの一行はシベリアを後にし、来た時と同じ道をたどってノグリキへと向かいました。途中の何ヶ所かで少し“寄り道”はしましたが、ほぼ真っすぐ王宮に帰ってきたのです。
無事に元気な姿で戻ってきたマトリョーシカを見て、ツルハゲ王夫妻は大喜びでした。スターリンからの贈り物にもご満悦でしたが、ツルハゲ王はマトリョーシカの報告を聞くとこう言いました。
「そのピョートルとかいう息子を早く招待しよう。スターリンの考えていることがだいたい分かってきたな。しかし、お前はまだ若いから、あまり急ぐことはないのだぞ」
ツルハゲ王は早くも、政略結婚を思い描いているようです。マトリョーシカに“婿”を取らせるのは結構な話ですが、肝心の彼女はベラの兄・アレクサンドルを慕っていたのです。
マトリョーシカは自分の思いを王夫妻に告げる気持は全くありませんでした。それはそうでしょう。王女が一般人に恋をするなど、王夫妻は想像もできないことでしたから。それに、アレクサンドルやベラが何と思うかも分かりません。
そうこうするうちに、ツルハゲ王はシベリア側に皇帝の次男・ピョートルの招待状を出しました。これはあくまでも「答礼訪問」という形で出したのですが、王はマトリョーシカとピョートルが結ばれることを願っていたのです。もちろん、サハリン・シベリア両国の絆を強めることが狙いでした。
ところが、これはマトリョーシカにとって好都合だったのですが、シベリア帝国はちょうどその頃、西方遠征のため大わらわの状態になっていました。スターリン皇帝の長男・アレクセイも次男のピョートルも、遠征軍に加わることになったのです。その点、スターリンは息子たちを決して甘やかすことはありませんでした。このため、ピョートルのサハリン訪問は延期になったのです。
ちょうど良い機会なので、当時のユーラシア大陸の情勢について触れておきましょう。シベリア帝国がウラル山脈を越えて領土を拡張している話はしましたが、スターリンは飽くなき欲望に突き動かされ、さらに西方へと軍を進めました。彼は古今未曾有の『大帝国』を夢見ていたのです。まさにあのアッティラ大王と同じですね。いや、面積から言うとそれ以上かもしれません。
ところが、スターリンの前に恐るべき“強敵”が現われました。それは今のドイツを拠点にして勃興したゲルマン帝国のヒトラー皇帝だったのです。ゲルマン帝国は強大な軍事力によって周囲の国を次々に制覇し、ヒトラー皇帝はその触手を東方へ伸ばしてきました。こうなると西方へ進むシベリア軍は、いずれゲルマン軍と衝突せざるを得ません。両帝国の軍隊は、今の東ヨーロッパを舞台に対峙したのです。このため、スターリンはシベリア軍に総動員令を下しました。息子のアレクセイもピョートルも動員されるのは当然ですね。
こうしてピョートルがサハリンに来れなくなったのは、マトリョーシカにとって幸いでした。彼女は自分の恋を実らせようと、アレクサンドル“攻略”の手筈を練っていたのです。
マトリョーシカとマリア、ベラ、ナディアの4人の集いは相変わらず続いていました。4人は本当に仲が良いですね。マトリョーシカはベラに自分の気持を伝えようと思ったのですが、いざとなるとなかなか口に出せません。
しかし、ある日、マリアに促されたこともあって、ついにアレクサンドルに好意を抱いていることをベラに告白しました。王女が自分の兄に想いを寄せていることを知ったベラは驚きました。
「マトリョーシカ、あなたは一般の男性に好意を持って大丈夫なのかしら。兄は立派な人間です。でも、身分があまりにも違うでしょう。いろいろな問題や摩擦が出てくると思うけど、本当に大丈夫なの?」
「ええ、私は決心したのです。あなたのお兄さんは実に立派な方です。身分とか地位の違いなどは全く問題になりません。このことはシベリアへ行った帰りに、マリアにも明かしたのよ。彼女は了解してくれました。だから、あなたもぜひ分かって頂きたいの」
それからマトリョーシカは、初めてアレクサンドルに会った時の印象や、その後の自分の気持の経緯を詳しく述べました。彼女は純粋で真剣でした。ひたむきにアレクサンドルを慕っていたのです。ベラは心を強く打たれました。親友が“王女”であろうとなかろうと、これは一人の乙女の純粋な気持なのです。彼女は近いうちに、マトリョーシカの想いを兄に伝えると約束しました。もちろん、アレクサンドルがどう思うか分かりませんが、ベラは親友と兄の仲立ちをすることになったのです。
それから2日後、農作業を終えて帰宅した兄に、ベラはマトリョーシカの件を包み隠さず伝えました。アレクサンドルの驚きは大変なものでした。彼はすっかり考え込み、その話はなかったことにしてほしいと妹に頼んだのです。それもよく分かりますね。王女が一介の若い男に想いを寄せるなど、普通では考えられないことですから。しかし、ベラは兄を必死に説得しました。
「兄さんの気持も分かるけど、マトリョーシカ王女も真剣なのです。ぜひ一度、会ってみてください。あとで何か不都合なことがあれば、それは全て私が責任を負います。私も真剣なのです」
妹の必死の説得に、ついに兄も折れました。こうして、マトリョーシカとアレクサンドルは、数日後に二人きりで会うことになったのです。
HD 《 乙女の祈り / バダジェフスカ 》 軽井沢から
その日、マトリョーシカは秘かにベラの家を訪れました。いつも一緒のマリアもナディアも今日は来ません。彼女はベラの手引きでアレクサンドルの部屋に入りました。彼は緊張した面持でマトリョーシカを迎え、ベラがすぐに退席したので二人きりになったのです。
ここで、マトリョーシカとアレクサンドルの詳しいやりとりは省きます。とにかく、彼女は自分の“真心”を切々と彼に訴えました。アレクサンドルの方は終始無言で、もっぱら聞き役に回っていました。それはそうでしょう。相手は“王女”です。口を挟む余裕などはなかったのです。
しかし、最後にマトリョーシカがアレクサンドルの前にひざまずいた時、彼は仰天して叫びました。「王女様、それは止めてください! お立ちになってください! 私は一介の若者ですから」 その叫び声でマトリョーシカが立ち上がると、アレクサンドルは「ただただ名誉なことです」と述べました。
この後、どちらが言い出したか知りませんが、二人は屋外へ散策に出かけることになりました。歩いているうちに、アレクサンドルもようやく緊張感がほぐれ、田畑や小川など景色の説明を始めたのです。マトリョーシカはそれらを何度も見てきましたが、今日はどこか新鮮な印象を受けるのです。彼と初めて散歩をしているからでしょうか。
「私はこの人と終生 一緒にいたい。いや、きっと一緒にいるだろう」 マトリョーシカは自分にそう言い聞かせました。一般の男性であろうと、アレクサンドルは彼女にとって掛け替えのない人だったのです。前にも述べましたが、アレクサンドルはもちろん凜々しく美しい青年ですが、何よりも誠実で真面目な人柄でした。
それはマリアからも聞いていましたが、彼と散歩をしながら話をしていると、その人柄がにじみ出てくるようです。アレクサンドルはマトリョーシカより3歳年上の青年ですが、ベラより年下の弟もいるので、自分が彼と結ばれてもチャスラフスカ家の“跡取り”は問題がないと、マトリョーシカは勝手に考えていました。まだどうなるか分からないというのに、ずいぶん一方的な思い込みですね(笑)。
こうして二人の散歩は終わりましたが、帰宅するとベラが夕食を用意していました。今度は3人で食事ですが、マトリョーシカとベラが屈託のない会話を続けるので、緊張した雰囲気は全くなくなりました。マトリョーシカは近いうちにまた会ってほしいとアレクサンドルに告げ、彼も快く同意したのです。
それから2~3ヶ月がたちました。マトリョーシカとアレクサンドルはすっかり打ち解けた関係になり、何回も、いやそれ以上に親しく交際を続けたのです。マトリョーシカは彼に対して、女友だちと同じようにファーストネームで呼び合うよう強く求めました。始めはアレクサンドルも抵抗感がありましたが、そのうち「王女様」ではなく、気軽に「マトリョーシカ」と呼ぶようになったのです。もちろん、これは内輪の集まりや個人的に会う時だけでしたが。
チャスラフスカ家には、犬が10数匹もいました。皆が犬好きだったこともありますが、広い農地や田畑を守るには“番犬”が必要ですね。犬の種類はよく分かりませんが、マスチフやシベリアン・ハスキーのような犬だったでしょうか。こうした犬を連れて散歩に行く時、マトリョーシカもアレクサンドルも気がまぎれて楽しい気分になります。彼女も犬は大好きです。番犬の中でも、ガブリエルというのがマトリョーシカによくなついていました。
ある日、二人はガブリエルなど数匹を連れて散歩に出かけました。そろそろ寒い季節になってきました。どのくらい歩いたでしょうか・・・ 小高い丘に通じる坂道に達した時、アレクサンドルが言いました。「マトリョーシカ、僕は君が好きだ」
初めて聞く言葉に、マトリョーシカは体中に暖かい血がめぐるのを感じたのです。彼女は感謝の気持を込めて彼の両手を握り、そっと体をアレクサンドルにあずけました。彼はマトリョーシカを抱擁すると、その唇に唇を重ねました。そして、もっと強く彼女を抱き締めたのです。 アレクサンドルの息づかいが次第に激しくなり、その口づけはまるでマトリョーシカを飲み干すかのようです。彼女は天にも昇る気持になりました。
恍惚の一時が終わると、二人は来た道を戻りチャスラフスカ家へと帰ります。「アレクサンドル、ありがとう」 言葉は短くても、マトリョーシカは心からの謝意を表わしました。この帰り道だけは二人とも“無口”です。ほとんど話しをしません。どちらも、これで運命が定まったと深く思うのでした。
二人が帰宅すると、いつもと様子が違うのでベラはいぶかしく思いました。夕食を用意したのに、マトリョーシカはすぐに王宮に戻ると言うのです。ベラは何かあったかと直感しました。彼女は二人の関係がおかしくなったのではと心配したのです。しかし、それは杞憂でした。この日、マトリョーシカとアレクサンドルの心は固く結ばれたのです。
二人が交際していることは、王宮でも話題になりました。初めは侍女たちがひそひそ話をする程度でしたが、やがてツルハゲ王夫妻も知るところとなったのです。ある日、王夫妻はマトリョーシカを呼び、アレクサンドルとの交際について話をしました。
「一般の男性と二人だけで付き合っているそうだね。マトリョーシカ、お前はもうすぐ女王になる身だ。行き過ぎたことにならないよう、くれぐれも気を付けることだな」 ツルハゲ王が釘をさしたのです。
「お爺様、その人は私の友人の兄で、男友だちということです。何もやましいことはありません」 マトリョーシカはさりげなく答えましたが、内心はとうとう聞かれたかという思いでした。
「あなたは来年、二十(はたち)になるのですよ。お爺様の跡を継ぐ心構えをしなくてわね。スターリン皇帝の子息が来れば、お会いしなければならないでしょう。いつまでも“少女”のような気分でいては駄目ですよ」 カチューシャ王妃が珍しくきっぱりした口調で述べました。
「はい、分かっています。粗相(そそう)のないようにします」 マトリョーシカはそう言うのが精一杯で、今は王夫妻に余計な心配をかけてはならないという思いでした。しかし、いずれ正直に自分の気持を祖父母に伝える時が来るでしょう。マトリョーシカはそう考えながら退席しましたが、やはり気になるのがスターリンの次男ピョートルのことでした。
そのピョートルはゲルマン帝国との戦争に備え、今はシベリア軍の一員として出陣していますが、ここでシベリア・ゲルマン両国の動静について述べておきます。 シベリア軍が東ヨーロッパを舞台にゲルマン軍と対峙していることは先に話しましたが、戦線が延びてほとんど膠着状態になっていました。一部で小競り合いが起きる程度で、戦局は持久戦の様相を呈していたのです。
そうした中で、両国間に驚くべき動きが出てきました。というのは、ゲルマン帝国のヒトラー皇帝がスターリン皇帝に“特使”を派遣してきたのです。特使の名はリッベントロップと言いますが、彼はまずスターリンの重臣であるモロトフと会って、両国間で「不可侵条約」を結ぼうと提案してきたのです。その条件は、ヨーロッパの中部にあるポーランド王国を分割して占領しようというものでした。要するに、弱い王国を“餌食”にして手を結ぼうということですね。
モロトフはリッベントロップを伴って、今のモスクワの近くにあるシベリア軍の前線基地に案内しました。そこにいたスターリン皇帝はヒトラー皇帝の親書を受け取ると、すっかり上機嫌になりました。彼は満面に笑みをたたえリッベントロップに告げたのです。
「実に良いご提案だ。両国でポーランドを分割統治しましょう。不可侵条約の締結にも賛成だ。ヒトラー皇帝に伝えてほしい。ゲルマン帝国は西ヨーロッパ全部を支配し、われわれシベリア帝国は東ヨーロッパや南方地域を全部支配する。それで宜しいかと」
「私は全権を委任されてきました。それで宜しいと思います」 リッベントロップが答えました。こうして、両帝国はポーランド王国を餌食にし、侵略と支配の地域を画定したのです。やがて、両帝国が不可侵条約を結んだという知らせが伝わると、周辺諸国は大変な驚きとショックを受けました。なぜなら、不倶戴天の敵と見られていた両国が和睦したからです。これによって、ゲルマン・シベリア両国は後顧の憂えなく、安心して西方と東方へ侵略の手を伸ばすことができたのです。 スターリンはヒトラーと和睦し、すっかり余裕ができたということですね。さて次はどこを攻略しようかと、彼は想を練るようになりました。
ユーラシア大陸の情勢はともかく、サハリンでは平和な日々が続いていました。年も明け、マトリョーシカは20歳の春を迎えたのです。マリアやベラ、ナディアが、20歳一番乗りのマトリョーシカを祝福しました。
「お姉さま、誕生日おめでとうございます!」
「まあ、マリアったら。同い年じゃないの~」
マリアに“お姉さま”と言われ、むっとしたマトリョーシカが切り返すと皆が笑いました。4人は賑やかに誕生会を楽しみましたが、マリアもナディアもむろん、マトリョーシカとアレクサンドルの交際を知っています。
「その後、彼とはどうなの?」
「ええ、もちろん上手くいってるわ」
ナディアの問いかけにマトリョーシカが答えましたが、彼女は今年こそアレクサンドルとの結婚を全ての人に認めてもらおうと心に誓ったのです。