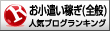16)卒業論文
冬休みに入ると、彼は遅れがちだった卒業論文の作業を進めようとしたが、まだどうも気乗りがしなかった。 そこで、近所に住む向井弘道の家へ遊びに行ったり、彼の方が行雄を訪ねてきたりして雑談を交わしていたが、向井も某石油化学会社への就職を決めていたため、将来の仕事や生活ぶりが話題の中心になった。
彼は親元を離れ、会社の独身寮に入るということが相当に嬉しいようだった。日頃は温和で控え目な性格だったが、彼は独立心のある芯の強い人間なのだろう。 行雄が「独身寮とは羨ましいね」と言うと、向井は「うん、親からいろいろ言われることもないしね」と明るい声で答えた。
彼と話していると、自分も早く親元から離れたいと思うのだが、月給3万円では都内のアパートを借りることはとても無理だ。 当分は浦和の自宅からFテレビに通うしかないが、いずれ早く独立したいと行雄は思う。向井とあれこれ話していると気が紛れて楽しかった。
そんな冬休みを送っているうちに、兄の国雄が妙なことを言ってきた。「お前、結婚するにしても、きちんと卒業してからにしろよ」 行雄は何を言っているのだと思い「結婚なんて考えていないよ」と答えた。それにしても、兄は変なことを言うではないか・・・彼はそう考えていると、百合子のことを思い出した。
兄が自分と百合子との関係を知っているのだろうか? まさか、そんなことはないだろう。行雄がそう訝っていると、ある晩、父の国義が彼を部屋に呼んだ。傍らには母もいた。「行雄、お前は中野さんという女性と付き合っているだろう。もう止めろよ。 向うのお母さんから、交際は止めてほしいというお願いがあったのだ。相手が嫌だと言うのに、無理に付き合おうとしても駄目じゃないか。とにかく、もう止めろよ。みっともないじゃないか」
父の言葉に行雄は愕然とした。 百合子との関係については、家の中では一切話していないというのに、どうしてそんなことが父の耳に入るのだろうか。兄が先日、変なことを言ったのも父から事情を聞いていたからだろう。世の中はどう動いているのかと、彼は信じられない思いがした。
「向うのお母さんの話しによると、娘も世間知らずで幼いものだから、こちらにいろいろ誤解を与えるようなことをしたかもしれない。もしそうだったら大変申し訳なくて謝りたいが、娘には交際を続けようという気持はまったくないので、宜しく取り計らってほしいというのだ。 向うが交際したくないと言っているんだぞ、行雄。だから、もう止めたらどうなんだ」
国義はそう言うと、一呼吸置いてから付け加えた。「なあ、行雄。女なんかいくらでもいるとは言わないが、中野さんという子も随分“のっぺり”した顔をしてるな」 そんなことまで知っているのか! 行雄は父の言葉に何も答えることができなかった。
唖然としたまま、どうして百合子の母から国義にそうした意思表示があったのか、どのように伝えられたのかといった疑問が湧いてくる。国義はその辺を察したらしく続けた。「向うから手紙が来たんだよ。中野さんの兄弟というのも、お前のことを調べたらしいぞ。 それにしても、お前は女の子の扱い方がえらく下手なようだな」 彼はそう言って笑い声を上げた。
行雄はおおよその事情を理解し、周囲の人間を巻き込んでいることにある種の“恥ずかしさ”を覚えた。 これ以上、双方の家族に迷惑をかけることは絶対に控えなければならない。彼は、訴えられた被告のような気持になり、「中野さんとの交際は止めるよ」と父に告げた。
百合子の母からの手紙について、もっと知りたいとも思ったが、行雄はそれ以上のことを父に聞く気にはなれず自分の部屋に戻った。 これで全てが終ったと悟ったが、何とも言えない空しさが込み上げてきて、彼はベッドの上に寝転んだ。
年が明けて昭和39年を迎えた。 行雄は卒業論文の作成作業に本格的に取り組み始めたが、中野家からの“絶縁通告”の件がまだ心に重く伸しかかり、憂うつな気分が抜けなかった。 しかし、卒論の提出期限は一ヵ月後に控えている。彼は憂いを忘れて、全力で作業に没頭するしかなかった。
「ロマン・ロランのゲーテ研究」の核心を、スピノザの汎神論としたので、若き日の両者が「エチカ」から鮮烈な影響を受けた点から書き始めた。 また、スピノザ哲学を共通項として、ロマン・ロランがゲーテから学んだもの、啓示を受けた点を中心に検証を進めていった。
ところが、テーマは定まっていたものの、ゲーテやロランの著作は極めて厖大であるため、文章の引用と検証作業は実に“骨の折れる”ものであった。 しかし、卒論を仕上げなければ卒業できないのだから、行雄は自分に鞭打つ気持で作業に全力を注いだ。
冬休みはあっという間に終った感じだったが、論文の進み具合は遅々として捗(はかど)らない。 彼は必要最低限の講義にしか出席せず、自宅で過ごす日が圧倒的に多くなったが、丁度この頃、家庭教師のアルバイトから解放されたのが幸いであった。
田端で教えていた女子中学生が私立高校を受験する時期となり、行雄は最後の授業アルバイトを済ませた。 国鉄職員のSさん一家は彼の労をねぎらい、御礼に上等なソックス3足を贈ってくれ、「Fテレビはよく見ているから、頑張って下さい」と励ましてくれたので、行雄は気持良くアルバイトを終了することができた。
彼はその直後、このアルバイトを頼まれた徳田に電話をかけて雑談したが、彼もポール・エリュアールの卒論で四苦八苦しているという。「でも、大丈夫だ。(主査の)中山教授とはいつも会っているし、よく飲んだりしているからな」 徳田らしい言い方だった。
彼は、中山教授の姪である小野恭子と仲睦まじくやっているし、教授と酒を飲む間柄だから何の心配もしていないのだろう。 話しが百合子のことに及ぶのを恐れて行雄は電話を切ったが、アルバイト終了の報告と共に、卒論でエールを交換した形となった。
1月から2月にかけて、行雄は卒論の作成作業と格闘した。原稿用紙を何十枚も書き直したり、また破棄したりと悪戦苦闘の連続だった。 正直言って、卒論の作成がこれほど大変で苛酷なものとは思わなかった。正に、学生生活の最後を飾る“戦争”だったのである。
疲れてくると、国義が持っているゴルフのパターとボールを借りてきて、カーペットの上にマッチ箱を立て、それを倒す行為を無心に続けた。そうしている間だけが、休息の時間だったのである。 書いては破り棄て、また書いては書き直す。そして、パターを手にしてマッチ箱を倒すという日々が続いた。
2月上旬、「ロマン・ロランのゲーテ研究について」はようやく完成した。94枚の原稿用紙には文字が“びっしり”と書き詰められていた。 余裕がなかったせいか、「改行」というものが一カ所もなかった。読み返してみると息苦しくなるほどだ。(これでは、主査の先生も読みにくいだろうと思ったが、後の祭りだ。)
卒論が完成した時「ああ、これで終った、終ったのだ」という実感が込み上げ、行雄は安堵と喜びで一杯になった。 彼はゴルフボールを転がして“最後”のマッチ箱倒しをやったのである。それは、これまでにない楽しい一時であった。 翌日、彼は大学の近くの製本屋に卒業論文を渡し、出来上がると担当主査のS助教授に提出した。
それから暫くして、大学生活最後の期末試験が始まった。試験となると多くの学生が集まってくる。 ある日、仏文学関係の課目が終った後、行雄は徳田、高村と連れ立ってW喫茶店に入った。大学周辺の喫茶店を訪れるのも、あと僅かだと思うと名残惜しいような気持になる。
行雄は特に喫茶店が好きだった。悲しい時も楽しい時も、いつも喫茶店にいたように思う。一人で入ると、喫茶店は彼に寛ぎや安らぎを与え、いろいろな友人、知人と入ると、談話や議論の場を提供してくれた。 全学連で活躍していた時も、百合子との関係が上手くいかなかった時も、この“オアシス”はいつも彼を温かく迎え入れてくれた。
W店もS店もT店も、他の全ての“オアシス”がそうだった。 いま、徳田や高村とブレンドのホットコーヒーを啜(すす)っていると、いろいろな思い出が甦ってくるようだ。二人は試験課目のことや社会に出た時のことなど、取留めのない話しをしている。
行雄もその話しの輪に入りながら、彼らと談話を楽しむのも残り少なくなってきたと思うと、妙に甘いメランコリックな気分になってくる。 学生時代は終ろうとしているのだ。俺の学生時代は何だったのか。少しは有意義だったとも思えるし、無残で情けなかったとも思える。
大学のキャンパスとは、あと一ヵ月ほどでお別れだ。ここを出てしまえば、俺は単なる卒業生でしかない。二度と戻ってくることはないだろう。そんなことを考えていると、高村がふいに声をかけてきた。「村上、君は中野さんともう終りということか?」 又その話しかと思い、行雄は答えなかった。
「村上君、本当に君はもう中野さんとは付き合わないということか」 今度は徳田が聞いてきたが、行雄は黙っていた。「残念だなあ。君は立派な会社に就職も決まり、彼女もフランス大使館に決まって張り切っている。 一、二年付き合っているうちに、“しこり”があっても解(ほぐ)れてくるだろうに。ここでもう一度、すっきりと考え直したらどうなんだ。最後のチャンスだよ」 徳田が真剣な面持ちで付け加えた。
「そうは行かない。いろいろあったので、仕方がないんだ」行雄はようやく重苦しい口調で答えた。彼は中野家から絶縁状が来たことは友人に話すまいと思っていた。「なぜだ。余計なお世話かもしれないが、あれほど彼女に“首ったけ”になっていたくせに、どんな理由で別れるというのだ。気持が冷めてしまったというのか」 今度は高村が追及してくる。その舌鋒が鋭かったので、行雄はまるで“尋問”を受けているような気分になった。
「僕のことだから、もう放っておいてくれ。これ以上、何を言っても無駄だよ」彼は嫌気がさして突き放すように答えた。 気まずい雰囲気になり、せっかくのコーヒーブレークを沈黙が覆う。暫くして、徳田が重々しく口を開いた。「君がそう言うのなら仕方がないね。高村も僕も期待していたんだ。 残念だな、中野さんはいい人なのに」
「もういいか、君自身の問題だからな。これ以上言っても君を困らせるだけだ。余計なお節介は止めよう」 高村が静かな口調で語ったので、行雄は安堵した。「君達には済まないね。いろいろ心配をかけてしまって・・・」彼は素直な気持に戻りコクリと頭を下げた。
「まあいいや。久しぶりに3人で飲みに行かないか、軽くだぞ。明日は試験がないから、いいじゃないか」徳田が快活な声を上げた。 「よし、行こう。村上もいいだろう?」高村の誘いに行雄もすぐに応じた。彼はFテレビの研修などで酒に慣れてきたせいか、飲酒に抵抗感はなくなっていた。
むしろ、最近はビールが旨いと思うようになり、自分は酒好きの父に似てきたのではと考えるほどだった。 3人はW喫茶店を出て高田馬場駅の方へ向かい、途中の居酒屋に入った。 この店は、徳田が中山教授と一緒によく来る所だという。以前、行雄がマル学同の“勉強会”に出席した蕎麦(そば)店のすぐ隣にあった。
それもあってか、3人でビールを飲みながら雑談していても、行雄は全学連時代の自分を思い出していた。あの巨大な安保闘争は何だったのか。いま酒を飲んでいる高村達を誘って、よくデモに行ったではないか。3年以上も前の思い出が走馬灯のように浮ぶ。高村も自分もあの頃は随分血気にはやっていた。
しかし、今の俺達にはその面影はまったくない。何か年を取ってしまったように思う。いや、事実、年を取ってしまったのだ。 卒業を目前にして、年を取った俺達は就職のことぐらいしか頭にない。3人はバラバラに離れてそれぞれの道を歩んでいく。そして俺の場合は、全学連のことも百合子のことも、全ては遠い過去の記憶の中へ去っていくのだろう。ビールの酔いもあって行雄は感傷的な気分に浸った。
期末試験も終りに近づいた頃、行雄は卒論担当主査のS助教授から呼び出しを受けた。愛称が「国連ビル」と呼ばれる文学部教員研究室の10階に彼の部屋があった。S助教授は卒論の講評を行なったのだが、それはおおむね好意的な内容だったので、行雄は結果に自信を持った。
S氏は最後に「卒論は大学に残しますか、それとも君の家に持ち帰りますか」と聞いてきたので、行雄は持ち帰ると答えた。彼は大変な苦労を重ねて仕上げた自分の卒論を、どうしても手元に置いておきたかったのだ。そして、この卒論は一生離さずに持っておこうと自分に言い聞かせた。
やがて期末試験が終了した。試験の最終日に、行雄は教室で百合子と出会ったが、当然のように無言のままで別れた。彼女の母が行雄の父に「絶縁」を伝えてきたのだから、そうするしかない。 しかし、彼はあと何回百合子と出会えるだろうかと考えた。多分、クラスのお別れコンパと卒業式の時ぐらいではないか。
そう思うと、やはり寂しい心地になってくる。しかし、そうは言っても「絶縁」されたのだから仕方がない。 加えて、行雄は百合子による束縛と重荷を感じていた。自分が社会に出ても、月給3万円で一緒に暮らしていくことは重圧でしかない。まさか、親の援助に頼るなどあってはならないことだ。
結婚・・・それは、若い自分にとっては重い責任を負うものではないか。22歳の若さで、将来の人生と運命が決まってしまうのは、余りに呆気なく“はかない”ものではないか。 自分には、まだ想像もできないような未知の人生が待っているはずだ。22歳で人生と運命が決まってしまうなんて、何と空しいことではないか。
行雄はそう考えると、今でも百合子に惹かれていようとも、結婚などはあり得ないと自分に言い聞かせた。 すると、2年以上も前から彼女に恋してきたことは何だったのかと思う。あれは本当の恋ではなかったのか。“偽りの恋”でしかなかったのか。彼女に「芯がない」と言われたのは、そういうことだったのかと思ってしまう。
俺は真実の恋を偽りの恋に変えてしまったのだ。俺はかつて、百合子に対し「僕の一生の感謝、一生の幸福になって下さい」とラブレターを書いたはずだ。 さらに「あなたの暖かい懐の中で死ねたら なんという感激!」だとか、「君は永遠に僕のものだ」とか「君の足元に 永遠にひれ伏す」などと書いたはずだ。それらは全て偽りであり嘘だったのか!?
そう考えると、行雄はやり切れない気持になってくる。 俺は彼女を裏切ったのだ。心底から愛していると言いながら、実はそれは見せ掛けだけの甘言だったのだ。彼の心にはっきりと“罪の意識”が湧き上がってきた。 俺は罪を犯した。真っ赤な嘘を言って彼女を騙したのだ。結果的にそうなったとはいえ、騙した事実には変りない。何と卑怯な仕打ちだろう。
それに比べると、徳田や会沢はそれぞれの恋人と目出たくゴールインする。二人には真実の恋があるからそうなるのだ。 もとより、恋愛関係にある全ての人達が結婚するわけではない。恋愛イコール結婚ではない。いろいろな事情で、絶縁や破局を迎えることはいくらでもある。
しかし、自分の場合は最初の頃、誰よりも強く深く真剣に相手の異性(百合子)を好きになっていたではないか。その恋慕の情は、どんな恋人のものよりも美しいと自負していたし、崇高で純粋で輝かしいものであった。 ところが、月日が経つにつれて、その恋愛感情は見るも無残に汚れ腐敗していった。最初が美しかっただけに、それは余計に醜いものとなった。
なぜ、偽りの恋になってしまったのか。行雄はその原因を考えると、自分の場合は単に「リビドー」が爆発したに過ぎないと思われた。性的エネルギーが爆発し奔出したのだ。 美しい憧れや夢想は、そのリビドーを艶やかに飾っていたに過ぎない。崇高で純粋だと思っていたものは、単なる上辺の“飾り”だったのではないか。
従って、時間が経つにつれてメッキが剥がれ、どす黒く濁った中身が表面に現われてきたのだ。それは欲情そのものだった。 俺は百合子を何度、いや何十回“オナペット”にしただろう。映画で見たモービー・ディック(白鯨)も巨大空母も、幻影の中で百合子の肢体に変っていったではないか。そのように思い返してみると、自分の恋愛というのは結局、欲情の発露でしかなかったのかと、行雄は情けない気持に襲われた。
それと同時に彼は、この2年以上にわたって悩み苦しんできたことが、非常に空しいものに思われた。自分と百合子は互いに惹かれ合いながらも、傷つけ合ってきたのだ。引力で惹かれながらも、絶えず斥力で反発し合っていたのだ。 その結果、二人は傷つき行雄は悩み苦しんだのだ。そう考えると、何と実のない馬鹿げたことをしてきたのか。
俺は呪われたのだ! 呪われた時間を過ごしたにすぎない。何と惨めな青春の一ページだったことか(でも、ある意味では有意義だったのか・・・)。 期末試験を終えて大学を去る時、彼は自分も百合子も、大学のキャンパスも全てを呪いたい気持になった。呪われたキャンパスよ、さらば! 行雄は心の中でそう叫んだ。